病気を治療することの本質は、つらい症状や死の不安を軽減し、人々をより「幸せ」な状態に導くことにあるーー平成医療福祉グループは、「じぶんを生きる を みんなのものに」という理念のもと、病気や障がいがあってもなくてもその人らしく生きられる社会の実現を目指しています。
今回ご紹介するのは、東京・足立区西新井にある、同グループの精神科病院 大内病院を中心とした取り組み。施設の老朽化対策のための建て替え構想から、精神科医療のあり方を根底から問い直すプロジェクトへと発展しました。同グループ代表・武久 敬洋さん、医療事業部部長の田村 大輔さんに、約10年におよんだプロジェクトを振り返りながら、入院医療改革と地域精神ケア構想についてお話しいただきました。
<プロフィール>
武久 敬洋(たけひさ・たかひろ)
平成医療福祉グループ代表。徳島県神山町在住。3人の子どもの父。2010年、平成医療福祉グループへ入職。以降、病院や施設の立ち上げなどに関わりながら、グループの医療・福祉の質向上に取り組む。2022年、グループ代表に就任。共同編集した著書に『慢性期医療のすべて』(2017 メジカルビュー社)がある。
田村 大輔(たむら・だいすけ)
平成医療福祉グループ 医療事業部部長。理学療法士として急性期病院に勤めたのち、大学で機械工学を学ぶ。2010年に多摩川病院に入職。同院の事務長を経て、医療事業部に配属され同グループの開設、建て替えなどを多数手掛ける。
リニューアルした大内病院をご紹介!

まずは、リニューアルを終えた現在の大内病院をご案内しましょう。

場所は、東京の西側・足立区の真ん中あたり。お大師さんで知られる下町・西新井、タコ型滑り台発祥の地とされる新西新井公園に面しています。2024年に竣工した6階建ての新しい病棟は、赤いレンガ色が印象的です。

1階の外来フロアは木材や木目調を取り入れた、あたたかく落ち着いたインテリア。


10室ある診察室は、さまざまな患者さんに対応できるように設計されています。診察室も、リラックスして過ごせるように木目調のインテリアです。

お菓子や軽食、日用品から衣類まで幅広く取り揃える売店トピアは、精神疾患当事者の人たちが働く場にもなっています。新西新井公園を挟んで向かい側にある「OUCHI」(後述)のパンの販売もあり、ご近所の方たちにも開かれています。

認知症に関するあらゆる相談を受け付ける認知症疾患医療センター、発達障害や学習、行動面の課題をサポートする発達診察室もあります。診察や検査を待っている時間を過ごしてもらう外来スペースには、一息つけるようにテーブルと椅子を置きました。病院の外には、車で通う人たちのための広い駐車場や、地域の方々と一緒に作業する畑もつくられています。
2〜5階は患者さんたちが入院する病棟です。


病室は、患者さんが安心して静かに過ごせるようプライベートに配慮。ほとんどが個室で、多床室(4人部屋)も仕切り壁を設置しています。いずれもゆったりと空間が取られており窓から公園の緑が見えるお部屋もあります。

各階に、2カ所の多目的スペースが設けられています。こちらは集団リハビリや作業活動を行う場所。日々の小さなイベントもここで開かれます。

こちらの多目的スペースは、静かにリラックスして過ごせる空間です。左手前は、座ると左右と背面の壁に守られたプライベート空間になるソファ。今は奥の本棚にいろんな本や雑誌が並んでいます。

多職種が集うスタッフステーションは、患者さんとスタッフが垣根なく、気軽にコミュニケーションを取れるように設計されました。取材の日には、オープンなカウンター越しに、患者さんがスタッフに声をかけて談笑する姿を見かけました。



6階には、東京を一望できる屋上庭園、患者さんがリハビリテーションをするトレーニングルームや作業療法室があります(冒頭の写真も屋上庭園で撮影しました)。気候がよい季節には、患者さんとスタッフがここで過ごす姿も見られます。

また、役職や職種で分けずフラットに交流できる、スタッフルームとスタッフ休憩室も。コミュニケーションが自然に生まれる空間設計は、チーム医療への良い影響も期待されています。
いかがでしょうか?あかるく開放的な病棟のようすを意外に思われた方もいるかもしれません。実は、以前の大内病院は老朽化のために全体に暗く、旧来の精神科病院によくある閉鎖的な設計で、病棟には畳敷きの多床室もありました。どのようにして、精神科病院としては日本で屈指と言っても過言ではない現在の療養環境を実現したのでしょうか。
「べてるの家」で得た感覚を建替構想に組み込む
大内病院が開院した1958年は、国が精神疾患・精神障がいのある人たちを隔離収容する政策を進めていた時代。以前の病棟には、当時の精神科医療の考え方が色濃く残っていました。リニューアルは、施設の老朽化対策だけでなく、従来の精神科医療のあり方をも問い直すプロセスでもありました。
同グループが大内病院を承継したのは2009年のこと。築50年を迎えて施設は老朽化が進んでおり、病院運営のための組織改革の必要もありました。2016年に事務長として着任した田村さんは、まずは病院運営の立て直しに取り掛かりました。一方で、当時副代表だった武久さんは、リニューアルの構想を練るために精神科医療をについてリサーチやフィールドワークをはじめていました。
なかでも大きな影響を受けたのは、1984年に北海道・浦河町に設立された「べてるの家*」。「弱さを絆に」を理念に、生きづらさや症状を仲間と共有して研究しあう「当事者研究」はよく知られています。

武久さん「べてるの家には、精神疾患に伴う幻覚や幻聴をタブー視せずに、ごくふつうに話し合える場があります。『障害は人ではなく、社会の側にある』と言いますが、社会のなかでタブーな存在とされがちな精神障がいのある人たちが、自然に受け入れられているだけでこんなに楽にいられるし、楽しいんだなと思いました。精神疾患・精神障がいのある人を特別扱いせずに受け入れられる場をつくれたら、その人らしく暮らしていける地域になっていく。大内病院が目指す方向はこっちだなと確信しました。べてるの家で得た感覚は、大内病院だけにとどまらず今のグループ全体に大きく影響していると思います」。
“べてるの家で得た感覚“は、大内病院プロジェクトにおいては、「建て替え」と「院内改革」、そして精神疾患・精神障がいのある人を地域で支える「地域精神ケア構想」という3つの柱に生きています。それぞれ、順を追って紹介していきましょう。
*べてるの家:地域のなかで当事者が人間的な営みを回復するための活動を展開する、精神障がいのある当事者のための地域活動拠点。有限会社ふくしショップべてる、社会福祉法人浦河べてるの家、NPO法人セルフサポートセンター浦河などの活動の総体として「べてる」と呼ばれ、生活、働く場、ケアという3つの性格をもつ共同体を形成している。
精神科医療が抱える”負のループ”を抜け出すために
日本の精神科医療は、いくつもの大きな課題を抱えています。下の図は、以前武久さんが作成したスライドですが、課題がつながり合って悪循環を生み出している状況が示されています。


武久さん「日本には、世界の精神科病床の約5分の1を占めるほど多くの精神科病床があります。その約9割は民間病院によって運営されており、病床を常に高稼働率で維持しなければ経営が成り立たない仕組みになっています。さらに、精神科入院の診療報酬は一般病院と比べて極端に低く、『精神科特例』 によってスタッフの配置も少なくてよいとされているため、その人数で対応できる範囲に業務が限定され、十分なケアや退院支援が難しい状況です。加えて、地域で患者を支えるリソースも極端に不足しているため、退院が進まず、長期入院が常態化しています」。
こうした制度的・社会的要因が重なり合い、長期入院が世界一多い精神科病床を支えるという負のループが生まれているのです。
武久さん「さらに、日本には家族など1名の同意があれば、事実上本人の同意を得ずとも強制的に入院させられる『医療保護入院』という制度。実に、入院患者の5割以上がこの制度によって入院しています。この制度も諸外国から批判され続けていますが、今なお廃止に至っていません」。

“負のループ”を抜け出すにはどうすればよいのかーー同グループは、「自分の暮らしに戻るための入院医療」と「生き心地のよい地域づくり」を両軸に据えて、病院も含めた地域で支える「地域精神ケア構想」を掲げました。そして、病床を344床から228床へと減らし、病棟機能も一部変更する決断をしました。
武久さん「本当は、もっと大幅に病床数を減らしたかったのです。しかし、現在の東京の状況では、大内病院だけが病床を減らしても、他の病院がその患者さんを抱え込むだけで、精神医療全体の構造を変えることはできません。だからこそ大内病院では、ある程度の病床数を維持しながら、最善の入院医療を実践し、短期間で地域に戻って暮らせる人を増やすことを目指しました。そうすることで、旧態依然とした精神医療にとどまる病院は、変化するか、淘汰されるかを迫られると考えています。東京でやるのが一番難しいけれど、足立区西新井で、べてるの家のある浦河町のように、地域であたりまえに暮らし続けられる状況に少しでも近づけたいと願っています」。
大幅な病床削減にはリスクが伴うため、田村さんは何度も試算を繰り返したそうです。最後は、グループのスケールメリットで補填することを前提に、初めのうちは赤字になることも覚悟のうえで大幅な病床を削減して、入院医療改革に乗り出すことになりました。

回復期リハビリテーション病棟での実践を応用する
大内病院の入院医療改革では、同グループの“強み”である回復期リハビリテーション(以下、回リハ)病棟の実践も応用されています。
回リハ病棟では、在宅復帰に向けたさまざまなリハビリテーションを行います。歩行や車椅子での移動、着替えや食事、排泄や入浴、のような日常生活動作(ADL)の訓練、復職に向けた訓練、自宅で生活するために家屋調査や住居改修、退院後のリハビリや介護サービスの調整などを行なっています。同グループの理念「じぶんを生きる を みんなのものに」に基づいて、病気や障がいの有無に関わらず、地域のなかでその人らしく生きられるようサポートしています。
武久さん「適切な医療を行うためには、マンパワーを増やす以外に道はありません。リハビリスタッフを回リハ並みに増やすことが経営的にも成り立たせることができる唯一の方法でした。同時に、リハビリの概念を大きく広げて『患者さんがふたたび地域に戻るために必要なあらゆるサポート』としました。リハスタッフには、患者さんと対話したり、安心感を与えたりする役割も担ってほしいと期待しています。」。
田村さん「リハビリスタッフの加配は、病床削減とセットでした。入院医療改革の柱のひとつに対話中心の治療方針を定めたものの、病院経営の立場からすると、以前のほぼ半分に減床するプランは衝撃でした。何度試算しても成り立たなかったんです」。
折りしも、2020年の診療報酬改定で、長期療養が必要な精神疾患のある人が入院する精神療養病棟について、精神科作業療法の疾患別リハビリテーションを診療報酬として算定可能になりました。さらに、2024年の診療報酬改定では、精神科病院の長期入院の解消を目的に、精神科地域包括ケア病棟を新設。精神疾患・精神障がいのある人たちの地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟です。大内病院ではいちはやく両病棟を設置し、病院経営の安定を図っています。しかし、「地域移行・地域定着」は、地域の側に支える仕組みがなければ実現できません。

田村さん「これだけ多くの病床を削減した病院は、関東ではほとんどないと思います。ある意味では、『病院で診るのではなく、地域で支えていくよ』という地域に向けての宣言みたいなものだと思っています」。
武久さん「入院中心の精神科医療から地域移行を進めるには、地域での活動への報酬が出るように制度を変える必要があります。不要な長期入院を減らし(日本の)精神科の入院ベッド数を減らすことができれば、その分の医療費を地域精神ケアに振り分けられるはずです。まずは、リハビリスタッフの病棟配置による実績やリハビリテーションの効果を研究・発表して、コンセンサスを得ることから取り組みはじめています」。
地域精神ケアの“旗”となった「OUCHI(おうち)」
大内病院の建て替えに先立って、同グループは精神障がいをもつ人たちが地域に戻るサポートをする施設「OUCHI(おうち)」を開設しました。退院後の一時的な住居としてのグループホーム、就労訓練・就労場所としてのお菓子・パン工房とカフェ、当事者研究などの各種ミーティングを行う交流スペースもあります。OUCHIの開設には地域精神ケアを進めるための布石でもありました。

武久さん「OUCHIをつくったのは、新しい精神科医療や地域精神ケアを一緒にやるスタッフを集めるためでもありました。古い精神科病院で募集をかけても、新しい取り組みに共感してくれる人材を集めるのは難しいだろうし、新しくてちょっとかっこいい建物をつくって、僕らが何をしようとしているのかを知ってもらうほうがいいと考えたんです」。
2020年には重い精神障がいを抱える人たちを生活の場で相談・支援する、ACT(Assertive Community Treatment、包括型地域生活支援プログラム)を立ち上げました。ACTでは、住み慣れた場所で自分らしく暮らせるよう、24時間365日、包括的な訪問支援を提供しています。
現在は、「地域精神ケアセンター」として退院後の患者さんが地域で安心して暮らせるようにサポートの輪を広げようとしています。住まいを確保するための調整、安心して過ごせる居場所や健康的でリーズナブルな食事と一緒に食べる場所、就労移行支援事業や新たな仕事場など。数年後の足立区西新井は、べてるの家のある浦河町のように、精神疾患・精神障がいのある人たちが暮らしやすい地域に変わりはじめているかもしれません。
大胆な改革で精神科医療を変えていく
2024年7月、冒頭でご紹介した新しい大内病院がオープンしました。それから間もなくして、大内病院は精神科病棟で常態化してきた身体拘束ゼロを一夜にして実現しました。
※平成医療福祉グループでの身体拘束をなくす取り組みについてはこちらをご覧ください。

武久さん「身体拘束ゼロは、以前の病棟では建物の構造に問題があり非常に困難でした。しかし、新しい病棟なら少しの工夫で達成可能だと思っていましたし、新しい病棟で身体拘束をしている風景に慣れてはいけないと思い、移転後2日目には実行しました」。
田村さん「代表と一緒に病棟スタッフが一部屋ずつ病室を回って、患者さんともコミュニケーションをとりながら、『この人はセンサーマットを敷いたらいいね』『超低床ベッドなら大丈夫じゃないか』などと話し合いながら解決していくんです。代表の思いがかたちになる瞬間をスタッフが目の当たりにしたのは、すごい影響力になったと思います。衝撃的でしたね」。
リニューアルオープンから1年が経ち、病院の内外に少しずつ変化の兆しが現れはじめています。
武久さん「職員は確実に変化していますし、いろんなイベントや企画が受け入れられるようになっています。たとえば、今秋はじまるアーティストの滞在企画『Oouchi Hospital Artists’ Guild(以下、O-HAG)』。10年前ならこの企画をやりたいと思っても、院内で共感を得られるのは難しかったと思うんです。でも、今はふつうに受け止められるし、手を挙げるスタッフがいるというのは大きな変化だと思います。僕自身も『あとはこの人たちに任せよう』と思えるような、思いとやる気のある人が増えているのも実感していますね」。
田村さん「精神科医療の世界の外から新たに参入した当グループが、これほど大幅な改革を進めたことは、良い意味で衝撃を与える大胆な取り組みとして受け止められている面もあるようです。精神科でこれだけリハビリテーションスタッフを手厚く配置する病院は稀であり、病床数の削減にも踏み切りました。そもそも建て替えの事例も少ない中で、私たちがどのような考え方で、どのように運営しているのかに、強い関心が寄せられています」。

O-HAG(Oouchi Hospital Artists’ Guild、おはぐ)参加アーティスト募集ポスター。「溶け合わずして、共鳴。」というコピーが右上で波打っています。
大内病院が目標として掲げている、「自分の暮らしに戻るための入院医療」と「生き心地のよい地域づくり」はまだはじまったばかりですが、確実にその歩みを進めています。来年にはO-HAGのアーティストが滞在していて、病院に新しい風が吹いているはずですし、退院して地域で暮らしはじめている患者さんも増えているでしょう。また、しばらく経つ頃にその変化についてお話を聞いてみたいと思います。
本特集では、入院医療改革、リハビリテーション、そして地域精神ケアの取り組みについてじっくり掘り下げていきます。この後に公開する記事もどうぞお楽しみに!
プロフィール

フリーライター
杉本恭子
すぎもと・きょうこ
京都在住のフリーライター。さまざまな媒体でインタビュー記事を執筆する。著書に『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)、『まちは暮らしでつくられる 神山に移り住んだ彼女たち』(晶文社)など。
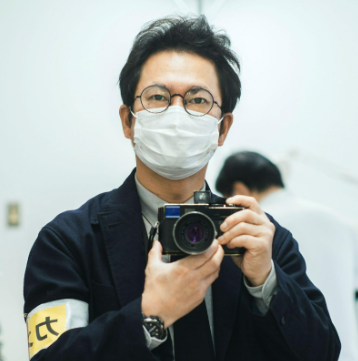
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





