病棟の建て替えを契機にはじまった大内病院の入院医療改革。精神障がいや疾患のある人が「じぶんを生きる」ために必要な治療やケアを考え、現行制度の中でできることを検討した結果、リハビリを増やしていく体制をとったというのは、これまでの記事でもご紹介したとおりです。
リハビリは、運動機能の回復を目指すものだと思われている人が多いのではないでしょうか。しかし本来は、病気や怪我で心身にさまざまな障がいが生じた人が、再び自分らしい生活を送り、社会での役割を取り戻せるよう、身体的・精神的な機能の回復、日常生活動作の改善、社会参加の支援などを包括的に行うものです。精神障がいの領域では、リハビリはその人らしく生きることの支援を意味することが多くなっています。
大内病院ではどのような方針のもと、精神科リハビリテーションの取り組みが展開されているのでしょうか。リハビリテーション部 部長の飯島直孝さんと同部 係長の松本武士さんにお話を伺いました。
<プロフィール>
飯島 直孝(いいじま・なおたか)
大内病院 リハビリテーション部 部長。理学療法士。2011年4月、平成医療福祉グループの緑成会病院に入職。2015年には印西総合病院の立ち上げに携わる。2019年3月から2020年7月まで、厚労省の医政局医事課に出向。その後、大内病院に異動し、現職
松本 武士(まつもと・たけし)
大内病院 リハビリテーション部 係長。2015年4月に大内病院に入職。2020年にはACTの立ち上げに関わり、ACTチームリーダーに。2023年4月から2025年3月まで人事部に異動し、大学院で精神科リハビリテーションについて学ぶ。4月より現場復帰し、現在は精神障がいの回復期にいる患者さんが多く入院している病棟を担当している
*ACT(Assertive Community Treatment、包括型地域生活支援プログラム)重度の精神障がいのある人たちが住み慣れた地域で安心して暮らせるように多職種の専門家チームで支援を提供するプログラム。
目の前の患者さんのことを第一に考える
大内病院がリハビリに力を入れ始めたのは、病棟の建て替えプロジェクトが動きはじめてまもなくのこと。それまでの精神科リハビリテーションは集団で行う「精神科作業療法」がほとんどでした。患者さんの症状や状態によっては個別介入が望ましいケースもたくさんあるのですが、制度上、実施は難しい状況でした。

松本さん「精神科医療においてケアが十分に行き届かないという現状は大内病院だけの課題というよりも、日本の精神科医療の制度的な弱さに起因しています。精神科医療は、本来は人と人のコミュニケーションやケアがものすごく必要な領域であるにもかかわらず、看護師を含め、配置基準が特例的に少ないんですね。話を聞いてほしい患者さんがたくさんいるのに、話を聞く時間がなかなかとれない。困ったことがあると、本人の同意なしに入院させられる措置入院という制度もあります。それは治療のためということもあるけれど、かっこつきの【社会の安全を守る】みたいな理由でも行われているんです。つまり、最終的に患者さんが不利益を被る仕組みになってしまっているんですね」。
患者さんのことを第一に考え、“目の前の患者さんのため”に、どうしたら本当に必要な治療やケアを提供できるのか。その視点に立つと、人員不足や集団リハビリしか提供できない状況を改善していく必要がありました。そこで、疾患に合わせたリハビリで社会復帰を目指す「疾患別リハビリテーション」などの仕組みを活用。たとえば、長期入院で廃用症候群が見られる人に、機能回復やADL(日常生活動作)の改善に向けたリハビリを提供する体制をつくり、療法士の配置を増やしていくことにしたのです。
飯島さんが大内病院に異動してきたのは、まさに最初に療法士を増やそうとしたタイミング。当時、理学療法士は3名在籍しており、そこに飯島さんが新たに加わりました。
リハビリを増やしたら、患者さんの症状が改善
飯島さんは、前職で行っていた身体リハビリテーションとは勝手が違うことに、最初はかなり戸惑いを覚えたと言います。松本さんも当時の飯島さんの不安そうな様子を覚えていました。
松本さん「身体リハビリは、やればやるほど直線で回復していく感じがあるんですけど、精神疾患は良くなったり悪くなったり、でこぼこしながら最終的に良くなっていくケースが多いんですね。そういう意味では予測がつきづらいというのが、身体リハビリとの違いだったんじゃないかなと思います」。

飯島さん「まさにそうでした。数日でも変化があって、精神状態が悪くなると身体も動かなくなったり、歩容(歩き方)が崩れたりする。何が起こるかわからないので、最初はどうすればいいのか、とまどいだらけでした。だからこそ、その人の状態に合わせて行う個別リハビリの必要性はすごく感じましたね。これまでは少ないリハビリでどうしてたのかな、動けなくなった若い患者さんはいったいどうやって社会復帰していたのかなって、かえって疑問に思う部分が多かったです」。
実際に、療法士が関われば関わっただけ、患者さんには症状の改善が見られたのだそう。
飯島さん「特に大きく変わったのは認知症の方です。なるべく良い環境をつくって作業を提供すると、集中できるので患者さん自身も落ち着いたり、その後は疲れてゆっくり過ごす時間になったり。やればやるほど『精神科にもリハビリは必要だよね』という考えが現場としても強くなってきて。経営的な観点でも増やしていきたい意向があったので、その方向でどんどん進めることになりました」。
こうして少しずつ療法士を増やしていった結果、2025年9月現在、大内病院のリハビリテーション部は、理学療法士17名、作業療法士67名、言語聴覚士2名の計86名の大所帯になりました。デイケアや訪問リハビリも担当しているとはいえ、病床数228床に対し、これはかなり手厚い配置ではないでしょうか。
日常動作、余暇、有酸素運動。社会復帰の一歩をつくる

精神科リハビリテーションでは、具体的にはどのようなリハビリを実施しているのでしょうか。作業療法士が「精神科で行う作業療法」には、集団でやるものと個別でやるものがあります。
松本さん「集団リハビリは、みんなで体を動かしたり、創作活動をしたり、話をしたり、カラオケをしたりするものです。集団での日中の活動を提供し、本人の回復のペースに合わせて参加してもらい、社会復帰の第一歩にしていきます。プラスアルファとして大事なのが、やはり個別リハビリです。退院してグループホームに入る方であれば、一緒に外出してグループホームからスーパーに買い物に行ったり、デイケアに通ったり。実際に外に出て、この患者さんの今のスキルだとどんな生活になるのか、お金の管理はできるか、どのぐらいの距離なら歩けるかなどをアセスメントし、その人が希望する生活を踏まえて、必要な知識や生活スキルを獲得していくのが個別の作業療法になります」。
外出することで、病棟内ではわからなかった患者さんの様子が見えてくることもあるそうです。
松本さん「病院ってすごく保護的な環境なので、院内では元気そうに見えても、一歩外に出ると幻聴が強まってしんどかったり、10分歩いただけで息が上がって休憩しないといられなかったり。病院のなかだけではわからないことがたくさんあるので、なるべく外にも行こうというのは、部の方針としてありますね」。
地域生活に戻るためのリハビリというと、一生懸命に生活の練習をすることをイメージしがちですが、それと同じくらい大切なのが「お楽しみの時間」。
松本さん「生活のリハビリだけを真面目にやっていてもだんだんしんどくなってきます。これはエビデンスもあるんですけど、余暇活動が充実すると精神的に安定するんです。だからその患者さんが何をしたら楽しいと思うのか、何をしていると自分らしくいられるのかを聞きながら、本人の好きなものや好きな作業を提供するリハビリテーションも行っています」。

一方、理学療法士が行うリハビリは主に四つあると飯島さんは言います。
飯島さん「一つは自殺未遂や事故による骨折や脊髄損傷、頭部外傷などのリハビリです。この場合は回復期リハビリテーション病棟でのアプローチと同様であり、装具を導入することもあります。もう一つは廃用症候群に対するリハビリですね。投薬や精神症状による影響でADLが落ちてしまった患者さんにこれまでの生活に戻っていただくためのADL訓練や機能訓練を行っています。3つめは有酸素運動で、精神面の改善を狙ったアプローチとして導入しています。最後は、作業療法士とも重なるんですけど、やっぱり家に帰るための訓練なんですよね。家の環境を見たり、一緒にバスに乗る練習をしたり、自転車に乗る練習をしたりしています」。

専門性を重ね合わせてリカバリーを支援する
精神障がいや疾患のある人が、自分らしい人生を生きるための過程や活動のことを「リカバリー」と言います。そして精神科リハビリテーションには、患者さんのリカバリーを支援するための「あらゆること」が求められています。そのため、各職種の職域を円で描いたときの重なりは、とても大きくなるのだそうです。
松本さん「精神科リハビリテーションは、薬物療法と両輪をなすものです。薬物療法で症状をコントロールしつつ、精神科リハビリテーションでは、多職種でご本人が望む生活に向かえるように支援していく。なので概念としてはすごく大きいんですね。特に大内病院みたいに『その人らしさを支援します』『自分はこれでいいんだって思える生活を地域で送るために支援します』ということを目指すなら、自分の職種の枠組みだけでやることには限界がある。患者さんが不調のときにどうしたらいいかを考えることはどの職種でもやれますし、重なり合わないとやっていけないと、個人的な感覚としてはすごく思います」。
飯島さん「もちろん、専門性がなければできないことはどの職種にもあります。でも、精神科では職種の円の重なりは確かにすごく大きいんです。僕らもリハビリ中に患者さんから話を聞きますし、何かあればチームに共有します。専門性以上に、そういうことが重要だという感覚はありますね。みんなが自分の専門性のほうを向くのではなく、患者さんのほうを向いて、その人にとって何が大事なんだろうと一緒になって考えながら、必要があるときには専門性を出し合う。実際、それができたときは患者さんにもフィットして、うまくいったよねと言っているような気がします」。

ひとりの患者さんを多職種で支える場面が多いからなのでしょうか。大内病院では、職種が違うスタッフ同士がフラットに話し合える関係性があるそうです。
飯島さん「僕が大内病院に来ていちばん驚いたのが、多職種のコミュニケーションの取りやすさでした。また、役位による壁も非常に低いと思います。リハビリの一般職員が看護部長や院長と患者さんの話をしている場面をよく見かけます。これって、大きな病院ではなかなかないことなんです。あるリハビリスタッフが『バスに乗る訓練に行ってもいいですか』とある医師に確認すると『患者さんのことを知りたいから私も行きたい』と言われたそうです。普通なら『いいですよ』と言って終わりですよね。ここには、医師からも自然に歩み寄ってくれる関係性があるんです」。
松本さん「谷院長がどの職種ともフラットに話してくれるので、その影響が大きい気がします。院長は『こういうのどうですか』って提案したときにあまり否定することがなくて。考えが違っても『自分の考えとは違うけどやってみる価値はあるかもしれないね』と言ってくれる。建設的に話し合いができる雰囲気はありますね」。
研修や勉強会を充実させて、より良いチームづくりを目指す

すでに風通しの良い関係性は築けているものの「今後は意識的にチーム意識を高めていきたい」と松本さん。現在は多職種の役職者が話し合いをして、いいチームをつくるためにはどうしたらいいか、患者さんのリカバリーを多職種でサポートするために何をしていったらいいかを話し合い、研修プログラムに落とし込む作業をしているそうです。
松本さん「社会のなかの精神科の位置づけや医療政策が、この先もどんどん変わっていくことは間違いありません。だからこそ、スタッフ一人ひとりが学びたいと思ったときに学べる環境をつくっていきたいと思っています。知識を得るための勉強会もあれば、リカバリーについて体験的に学べる勉強会もある。カンファレンスももっとやりたいし、精神科の最新のニュースを題材にした研修も今年は計画しています。治療やケアに関して一定の水準が保てるよう、研修や学びの仕組みづくりに力を入れたいです」。
最近ではグループの理念「じぶんを生きる を みんなのものに」や大内病院の方針に魅力を感じ、入職する職員も増えているそう。
松本さん「いい方向に向かいたいと思っているスタッフは、昔と比べたら圧倒的に増えました。でも、もうひと声って感じです。いろいろな意見があっていいと思いますし、みんなが一色に染まるのは、むしろ怖いことだとも思います。ただ、大きな方向性はだいたい同じにしたい。そのなかでの意見の違いはあっても、ちゃんとディスカッションできるというのが目指すところで。そのためにはもう少し工夫が必要かなと思っています」。
多様な視点や持ち寄った専門性が、それぞれの色を持ったままで溶け合いながら、患者さんのリカバリーを支援していく。おふたりのお話を聞いていると、大内病院の精神科リハビリテーションは、患者さんの一歩一歩を支える、大きくてしなやかなサポート装置なのだと思われました。
次回は、大内病院と地域の関係性をつくり、退院した患者さんの暮らしをさまざまな方法でサポートする「地域精神ケア」の取り組みをご紹介します。
プロフィール

ライター
平川友紀
ひらかわ・ゆき
フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。
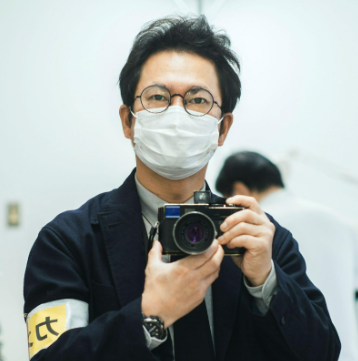
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





