入院するときよりも退院してからの生活が心配ーー実は、そう思われる高齢の患者さんやご家族は少なくありません。医療の手が届きにくい自宅に戻って大丈夫なのか。もしものときにすぐに診てもらえる医療機関はあるのか。状態が変化したときにすぐに入院できるのか……。平成医療福祉グループでは、こうした不安を解消してもらうため、患者さんの在宅生活を多職種で支える訪問サービスを充実させるとともに、地域の医療機関との連携も進めています。
今回の特集記事は、引き続き「地域と医療のあたらしい関係」をテーマにしながら「在宅医療」にフォーカス。世田谷記念病院と機能強化型の連携をしている桜新町アーバンクリニックのみなさんをお招きして、それぞれの視点から「患者さんが地域で暮らしつづけるために必要なこと」を座談会にて語り合っていただきました。
医療、介護、福祉で地域を支えるヘルスケアチーム
まずは、桜新町アーバンクリニックについて簡単にご紹介をお願いします。
村上:桜新町アーバンクリニックは、2006年に立ち上げた医療法人社団プラタナスに属するクリニックです。2008年には在宅医療部を立ち上げ、それから17年のなかで、外来と在宅医療部を中心として、訪問看護、ケアマネジャー、デイサービス、看護小規模多機能、世田谷区の委託による認知症在宅サポートセンターをつくり、半径3キロの地域を対象に、約500名の患者さんに対してワンストップで医療、介護、福祉を提供するヘルスケアチームを構築してきました。僕はこのチームの事務長をしています。

おふたりにも自己紹介していただいていいでしょうか。
五味:在宅事業部の責任者をしています。僕は世田谷生まれ世田谷育ちで、世田谷区と目黒区の境界あたりにある東京医療センターで2年間研修をした後、総合内科に5年間勤務していました。同センターは750床くらいの急性期病院ですが、うち100床を総合内科で診ているという、総合診療中心の病院として稀有な存在なんですね。ずーっと患者さんを受け入れる側だったのですが、地域の側にしっかり支えられる環境があれば、早めに患者さんを自宅に帰せるのではないかと思いはじめて。でも、在宅医療のことはほとんど知らなかったので、桜新町アーバンクリニックに見学に行ってそのまま12年が経ちました。
國居:私は介護保険制度が始まる前年、1999年から訪問看護に携わっていて、今年6月で27年目になります。訪問看護のことをもっと学びたいという思いから、2015年に聖路加国際大学の訪問看護認定看護師教育課程に入学し、2016年の卒業と同時に、こちらへ入職しました。
村上:僕は強力なふたりに守ってもらっているんです(笑)。
なぜ今、地域医療が求められているのか
さきほど、五味先生から「地域の側に支えられる環境があれば」というお話がありましたが、地域医療が求められている背景について、天辰先生に伺いたいと思います。

天辰:歴史的に見るとふたつの流れがあるなと思っていて。戦後すぐは国公立を中心として、その後は民間病院を中心に日本は病床整備に力を入れてきました。これによってベッド数は急速に増加しましたが、1990年前半をピークとしてゆるやかに減少し、約155万床(2023年度)に落ち着いています*。もうひとつは、医師の教育課程です。日本は、大学医局の専門医制度を軸にして医師を育成してきた結果、「急性期病院で臓器別専門医に診てもらうのが優れた医療だ」という価値観が根強くあります。
* 医療施設調査 令和5年医療施設(静態・動態)調査 全国編
人口増加・経済成長のフェーズともタイミングが合い、日本は低コストで質の高い医療を安定的に供給できる医療制度を実現しました。しかし、その時代は終わりました。少子化が進み、総人口に65歳以上の高齢者が占める割合は今や約3割に手が届きそうです。高齢になるにつれて複合疾患を抱えがちですし、社会的・経済的な困難など、医療の枠組みだけでは解決できない患者さんの課題に直面することも増えていて。在宅医療を含めて、地域のなかでいろんなピースを組み合わせる必要性を強く感じています。
國居さんは、27年にわたって訪問看護に関わるなかでどんな変化を感じておられますか?

國居:私がはじめた頃は「老人訪問看護」と「老人」がついていたのですが、それが取り払われたことにニーズの変化を感じています。また、最近は精神科や小児科に特化した訪問看護ステーションもできていて、できるかぎり自宅に帰そうという国の方針が診療報酬にも現れているなと思いますね。この流れを受けて、訪問看護ステーションは増えていますが、担い手となる看護師不足が課題になっています。訪問看護師の平均年齢は42〜45歳。在宅医療に興味をもつ看護学生はいるのですが、病院でも看護師が不足しているなかでは、なかなか訪問看護が選択肢に入らない現状があります。小規模の訪問看護ステーションほど、管理者の交代ができなかったり、看護師数を維持できずに閉鎖するケースが目立ちますね。
五味:この10年ほどの間に、「在宅医療」「訪問診療」というキーワードの認知度は上がり、病院側も「患者さんを在宅医療、訪問診療につなげて生活の場に戻そう」という意識をもつようになりました。近年は、医学生が地域の在宅診療所で研修するカリキュラムができたり、総合診療研修プログラムを受ける医師も少しずつ増えてはいますが、とりわけ急性期病院の医師や医療スタッフには、まだまだ在宅医療、訪問診療への興味や理解は足りていないと感じています。まだまだ、こちらから病院側に地道に働きかける必要はあると思っています。
病院と在宅医療の関わり方をどうつくるか
村上さんは、2009年から事務長という立場で在宅医療、訪問診療に関わるなかで、いろんな変化をどんなふうに受け止めてこられたのでしょうか。

村上:2010年頃のことですが、「今は政策的な誘導によって訪問診療の診療報酬が上げられているけれど、他の政策と同じくいつかはハシゴを外されるよ」という話がありました。だけど現場を横で見ていると、どう考えてもニーズは大きいし、患者さんに喜ばれている。そして、関わる医療者の方々も「本当に求められている医療を提供できている」と満足しているので、絶対に大丈夫だと思っていました。
同時に、この10数年の間、地域において在宅医療を増やさなければいけないと言われるなかで、医療業界は政策誘導によって変えるのは難しいだろうし、在宅医療の担い手の数が鍵を握るだろうと考えていました。つまり、病院と在宅医療業界による医師のリクルート合戦が、在宅医療の発展に関わるだろうと予想していたんです。だからこそ、患者さんと医療者の双方にとって一番良い環境を整えることが、僕にできるこの地域への一番の貢献だと思っていました。
そうなると、在宅医療だけでなく訪問看護も必要だし、ケアマネジャーもセットであるほうがいい。これらをミックスして提供することで、在宅医療の質が上がることを実証してきたというところでしょうか。
手老さんは世田谷記念病院の事務長として、この地域での病院と在宅医療がそれぞれの役割をもちながら関わっていくことについてどう考えていますか?

手老:世田谷記念病院、そして当グループにとって、たまたま近くに桜新町アーバンクリニックさんがあったのはすごくラッキーだったんです。もともと機能強化連携を組ませていただいたのは、患者さんの退院後の暮らしを支えるために、当院とこの地域の在宅医療、訪問診療を担う方たちと、個々の関係性を深めたいと考えたからでした。病院と在宅側の医療リソースの関わり方をもっと世の中に広めていきたいのですが、まだできていないことも多分にあります。
村上:在宅医療をしていると、患者さんが肺炎などで入院せざるを得ないことがあります。なかには、ADL(Activities of Daily Living、日常生活動作)が下がった状態で戻られる方もおられて。要は、退院後の生活が見えていない病院さんも少なくないんです。そんななかで、世田谷記念病院さんは、在宅生活を見据えたリハビリをしてくれる稀有な存在で、我々にとってもありがたいんです。

五味:急性期病院に入院された患者さんが、世田谷記念病院を経由して帰ってくると全然違いますね。リハビリスタッフの方たちは、退院前に必ず家屋調査をして必要な手すりや踏み台の設置をしてくれます。困ったときに、まずは相談してみようと思える病院が身近にあると本当に助かります。
病院以外にも、他の訪問看護ステーションやケアマネジャーさんから「訪問診療をアーバンさんにお願いしたい」と連絡いただくこともありますし、僕らの側からオファーを出すこともあります。僕らのスタッフは、患者さんやご家族のために、妥協せずに提供できるものを提供したいという熱量がすごく高くて。その熱量の部分で一緒にやれる病院さん、事業者さんとの強固なつながりの輪が10年、15年をかけて太くなってきた感じがしています。
患者さんを真ん中にして医療者が学び合う
國居:お互いの顔が見える関係性があると、すごく早くものごとを進められます。でも、地域として考えるなら、私たちには小規模の看護ステーションをすくい上げていく役割もあるんじゃないかと思っています。
村上:僕らくらいの規模になると、連携先の事業者を育てるというか、一緒に地域を考えていくスタンスを強く出さなければいけないなと思っています。そこも含めてやっていかないと、いつかは僕らが提供したい医療を提供することができなくなってしまいますから。
天辰:病院側も、入院期間中にただ検査の異常値を改善することや、体の機能を改善するということだけを目標にするのではなく、退院後に患者さんの生活に根ざしたより多面的なケアまで含めた視点をもつと、病院でできるアプローチや選択肢の幅はより広がるのではないかと思います。そういう意味でも、この世田谷記念病院とアーバンクリニックさんの連携は、患者さんのやりとりを通してグループ全体として成長できるチャンス。今のお話を伺いながら、地域の中小病院が在宅側に学ぶことで視点を広げることは、医療の質そのものを高めていけるのではないかと思いました。
病院では多職種によるカンファレンスが重要ですが、地域医療においては病院と在宅医療、訪問診療をする方達とのカンファレンスは行われているのでしょうか。

國居:ときどき、「退院前カンファレンスはあるのに、どうして入院前カンファレンスはないんだろう」と思うことがあります。在宅側から病院側に、「患者さんはご自宅でどう過ごしているのか」「どんな価値観をおもちなのか」など、ACP(Advance Care Planning)に関わるところまで伝えられたらいいのに、と。もしもそこまで踏み込めるなら、病診連携や看看連携はもっと広がっていくのではないでしょうか。やはり、書類のやりとりだけでは伝わりきらないところもあるので、直接話すのはすごく大事だと思います。
五味:入院してから何日以内に、患者さんに関わる人たちがオンラインで少し話すくらいならできそうですね。
天辰:いいアイデアですね。ACPは患者さんの人生のなかで移り変わりながら育まれていくもの。病院では診療報酬上のルール設定もあり、どうしてもその時点での意思決定を迫られる場面があり、患者さんご自身にとってもご家族にとっても、十分な準備もなく結論を押し付けられるとつらいと思うんですね。ACPに限らず、連携のなかで患者さんを診れたらよりよいケアにもつながるし、ご自宅にお戻しするときにもいい結果が生まれるのではと思います。
医療者コミュニティがより強く地域を支える力になる

村上さんは15年以上見てきた世田谷エリアに、今後どのような地域医療のかたちがあるとよいと思われますか?
村上:やはり、事業者間の関係性が重要だと思います。民間同士は経営的な問題もあり、放っておくとあまり外を向かなくなるのですが、それは良くないなと思っています。1クリニックで勉強会やイベントをするのではなく、複数の医療機関や事業所が集うコミュニティをつくるほうが、この地域のためになります。そこで、今年2月に世田谷区玉川地域を中心に機能強化型連携を組んでいる5医療機関が中心になり、今私たちがいる2Co HOUSEで「がやがやニコニコ交流会(※)。」を開きました。
そのときにも話したのですが、この連携を臨床に取り入れるとしたら、玉川地域在宅ケアアライアンスといった、医療機関や介護事業所をつなぐネットワークをつくれるといいんじゃないかと考えています。たとえば、在宅緩和ケアや在宅での肺炎治療などについて、地域の中で共通認識を作ることで均質な医療やケアを提供できるようにしたり、手技の統一やみんなで同じデバイスを使うことで医療ミスをなくせたり。一医療機関ではできないことを、複数の民間事業者が手を組むことで可能にできたら、日本の地域包括ケアシステムにおいて新しい刺激になるかもしれません。こればかりは、地域の輪に入ってくれる病院の存在がないと実現できませんが、この地域には世田谷記念病院がありますから。
※ 2025年2月14日(金)に開催された交流会。世田谷区玉川地域を中心に機能強化型の連携を組んでいる5つの事業所が中心となって開催。当日の詳細はこちら。

天辰:まさに志が同じだなと思います。社会保障費も厳しくなっていく時代ですから、これからの医療は個別の病院経営の範囲を超えて考えていかないと成り立たちません。「どんなビジョンをもって地域をデザインしていくか」という視点を共有しながら、異なる機能をもつ医療機関、地域づくりや居場所づくりをしている人たちとも関係をつくりながら、世田谷発の地域医療を育んでいけたらと思います。
病院の枠を超えて、地域のいろんなプレイヤーとともに、自分たちだけでは到底できない大きな動きをつくれるのは、めちゃくちゃ面白いですよね。1つの専門に特化するキャリアを積む生き方では見ることのできないようなワクワクする世界があります。今は、医療従事者のなり手が減っていると言われていますが、ぜひ若い方たちにこの面白さが伝わって、僕らの動きに加わってほしいと思います。
すごく熱量の高い座談会になりましたね!みなさん、ありがとうございました。
プロフィール

フリーライター
杉本恭子
すぎもと・きょうこ
京都在住のフリーライター。さまざまな媒体でインタビュー記事を執筆する。著書に『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)、『まちは暮らしでつくられる 神山に移り住んだ彼女たち』(晶文社)など。
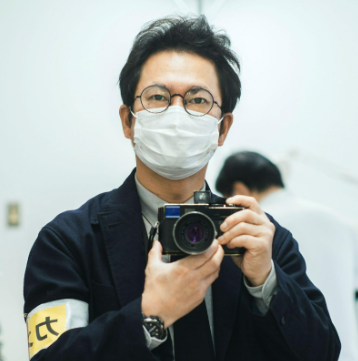
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





