「地域医療」という言葉がよく聞かれるようになりました。
地域医療とは、医療機関や介護・福祉施設、ケアマネジャーが連携して、地域の人たちの健康を守る医療体制のこと。平成医療福祉グループでは、グループを挙げてそれぞれの地域にある病院で、地域医療に取り組んでいます。
今回ご紹介するのは、徳島駅から車で約40分、清流・鮎喰川が流れる山あいのまち・神山町ではじまった、訪問診療と小児科外来のクリニック「おうち診療所 神山」。元JAだった建物を改修し、1階にはまちの人たちが集う「集会所」、カフェや図書室、コインランドリーも併設しました。リハビリや小児科外来の診察を行うスペースは、あかるい窓から周囲の山を見渡せる2階にあります。
診療所の建物が象徴するように、ここで行われているのは、いわゆる“医療だけ”ではありません。「医療者と患者」ではなく「人と人」の関係性に溶け込むように医療が行われているのです。オープンから1年を迎えた、おうち診療所 神山のいまを、スタッフのみなさんに聞かせていただきました。
*本文中では訪問診療を受けている人は「患者さん」、訪問看護を受けている人は「利用者さん」と表記しています。

<プロフィール>
武久敬洋(たけひさ・たかひろ)
平成医療福祉グループ代表。徳島県神山町在住。3人の子どもの父。2010年、平成医療福祉グループへ入職。以降、病院や施設の立ち上げなどに関わりながら、グループの医療・福祉の質向上に取り組む。2022年、グループ代表に就任。共同編集した著書に『慢性期医療のすべて』(2017 メジカルビュー社)がある。
佐々木春奈(ささき・はるな)
東京出身。急性期病院の消化器外科病棟で、主に手術や化学療法をするがん患者さんの看護を経験。ACPや終末期看護、緩和ケアへの関心を深める。2024年、おうち診療所 神山に参画するために平成医療福祉グループに入職し、神山に移住する。
森長怜実(もりなが・さとみ)
徳島・神山町出身。徳島大学病院の脳外科神経内科に7年勤務したのち、産休・育休後は外来で勤務。2024年、おうち診療所 神山に参画するために平成医療福祉グループに入職し、生まれ故郷にUターンする。
藤本優希(ふじもと・ゆうき)
京都出身。大学で看護を学んでいた頃からへき地医療や地域医療に関心をもち、「いずれは地域医療に関わりたい」と考えていた。急性期病院の小児科に勤務したのち、2024年、おうち診療所 神山に参画するために平成医療福祉グループに入職し、神山に移住する。
住み慣れたまちで最期を迎えられるように
神山町といえば、「神山アーティスト・イン・レジデンス」や、サテライト・オフィスの誘致、神山まるごと高専の開校など、何かと話題に事欠かないまち。国内外から移り住む人が多いことでも知られています。同グループの代表・武久敬洋さんもそのひとり。オルタナティブスクール「森の学校みっけ」への娘さんの転入に合わせて、家族で神山に引っ越しました。

武久さん「今まで、生まれ育った徳島も、長く暮らした東京も好きにはなれなかったんです。ところが神山に来てから、生まれて初めて住んでいる土地に対する愛着が湧きました。東京の小学校ではつらそうにしていた娘もすごく生き生きしていて、このまちのために何かしたいという気持ちが自然に生まれました」。
神山町では過疎高齢化が進み、人口は最盛期の約2万人から約4000人にまで減り、高齢化率は50%以上にものぼります。しかし、看取りのための医療体制は乏しく、町外の病院や施設で最期のときを迎えなければいけない状況がありました。
大きな医療グループの跡取りに生まれたけれど「医師としては在宅医療をやりたいタイプ」という武久さん。神山で看取りができる医療体制をつくるため「神山在宅医療プロジェクト」を立ち上げました。また、町内にすでにある医療の隙間を埋めるため、診療所には神山にはない小児科外来も設けることにしました。
「“病気だけ”ではなく“人全体”を診たい人に来てほしい」という募集メッセージに応えて、入職したのは看護師の佐々木春奈さん、森長怜実さん、藤本優希さん。3人とも在宅医療に関わるのは初めて、地元出身の森長さん以外は神山への移住を伴う転職になりました。

まちの人たちにお世話される診療所
おうち診療所 神山(以下、診療所)ができるまで、神山には「訪問診療を利用して自宅で療養する」という選択肢が想定されていなかったため、ニーズそのものが顕在化していませんでした。「診療所で何ができるか」を知ってもらう必要がありました。また、訪問診療は自宅というプライベートな空間で行われます。スタッフの顔を覚えてもらい、まちの人たちと関係をつくることも大切にしました。
武久さん「どうすれば、いわゆる医療を受けにくる人以外も、自然とこの場所に来てくれるかを意識しながら場所をつくっていきました。初めての場所でも「理由」があれば行きやすいもの。まちの人たちに需要のあるランドリーを設置したり、集会所に本や漫画を置いたり、最近はカフェもはじめています。1階は、農作業後に泥がついたままでも来やすいように、コンクリートの土間のままにしました。すごくたくさんの人が立ち寄ってくれていますね」。



診療所では、毎月のように小さなイベントも開催しています。昨年12月には、お裁縫のサークル「ちくちく笑みの会」と一緒に、集会所のクリスマスツリーを飾るオーナメントづくりをしました。
森長さん「クリスマスリースをつくっている「ちくちく笑みの会」のお母さんたちに出会って、『集会所でクリスマス向けのイベントをやりたいからつくり方を教えてください』とお願いしたら、『助けたるわ』という感じで来てくれて。最後の飾りつけまで手伝ってくれました。イベントに関わったことがきっかけで足を運ぶようになる方もいらっしゃいます」。


診療所のお世話をしてくれる人たちも増えています。伸びてきた庭木を伐ってもらったり、診療所の畑を手伝ってもらったり。その“お世話”が関わりしろになり、診療所はまちの人たちの場所として神山に根付きはじめています。また、患者さんや利用者さんとの関わりでも、まちの人たちに助けられることが多いと言います。
佐々木さん「『入院どうしますか?』と相談していたときも、向かいのおうちの人が私たちと一緒に話してくれたり。私たちの話を全然聞いてくれない人も、信頼する近所の人が声をかけてくれるとうまくいくこともあります。家族以外の人がお買い物を手伝ってくれていたり、地域で支え合っている感じはすごくあります。最初は戸惑っていたけど、だんだん私たちも『頼っていいんだな』と思えるようになりました」。
自宅では「動ける」患者さんたち
診療所のオープンからまもなく1年。「初めての訪問看護はどうでしたか?」と聞くと、「一番思うのは、めっちゃ楽しい!ということ」と佐々木さん。「めちゃくちゃ楽しい!」と藤本さん、森長さんも声を合わせます。どんなことを「楽しい」と感じているのでしょうか。

藤本さん「もちろん、プレッシャーはありますが、ご自宅でしか見えない顔があるんです。暮らしを見ているといろんな状況がわかるから、ちょっとしたできごとも自分ごととして考えられるし、寄り添える感覚があります。いい変化があるとすごくうれしいから、訪問から戻るたびに『○○さん、今日はこんなことができるようになっていたよ』とみんなに共有してしまいます」。
スタッフたちが訪問から帰ってくると、診療所はとたんに賑やかになります。体調の変化や服薬の状況など看護の申し送りに交えて、利用者さんのようすを“自分ごと”としてうれしそうに伝え合うおしゃべりに花が咲きます。

佐々木さん「病院勤務していたときは『この人こんなに動けたの?』と思ったことはほとんどなくて、完全に医療者側が患者さんの『できる範囲』を決めて、そのなかでできることをやっていた感じがします。でも、ご自宅に訪問すると、私たち医療者が想像する以上のポテンシャルを目の当たりにします。患者さん、利用者さんが私たちの枠を広げてくれる感覚があり、その可能性の大きさは在宅の魅力だなと思います」。
森長さん「好きなことをしながら治療を続けられるのは在宅の魅力。病院よりも在宅でいるときの方が笑顔もすごい素敵だし、お話もたくさんされます。私自身も、生き生きした患者さん、利用者さんとお話しできて一緒に楽しいことをできるのがうれしいです」。

最近、一人暮らしの利用者さんのご自宅に、本人の許可のもと「見守りカメラ」を導入したところ、思いもよらない姿が映っていて驚いたと言います。
武久さん「万が一の転倒などがあったとき、駆けつけられるようにカメラを4台設置したんですけど、『嘘でしょ?』って驚きました。トイレに行くのがギリギリだと思っていたのに、めちゃくちゃ動いていて。モニターからいなくなったと思ったら庭仕事をしていたりするんです。患者さんが医療者の前で見せる顔はほんの一部だと思いましたし、僕らがいないときの患者さんのことまで想像できるようになりました」。
初めてみんなで看取った患者さんのこと
いつも明るい話し声が絶えない診療所ですが、ときには真剣な議論に時間をかけることもあります。とりわけ、初めての看取りを経験したときは、「どうしたら患者さんは幸せに過ごしてもらえるのか?」を全員で考え続けたそうです。

佐々木さん「末期がんを患っておられる一人暮らしの方で、自宅にいながら通院で治療を続けたいと希望されていました。訪問を続けるなかで『抗がん剤治療がつらいからやめたい』と言われたので、意思決定のところにも関わらせていただいて。その後も食事ができなくなったり、いろんな症状が出てくるなかで、私たちに何ができるのかをすごく考えました」。
たとえば、お風呂のこと。その患者さんは、近所の神山温泉に毎日通うのが大好きだったのですが、ADL(日常生活動作)の低下により温泉に行けなくなっていました。しかし、町内の事業所の訪問入浴スタッフは、終末期で急変リスクが高い方の入浴介助に不安を感じていました。そこで、診療所の看護師が訪問入浴に同席し、入浴後に訪問看護で状態を確認。介護者も本人も安心して入浴できるようになりました。

藤本さん「お風呂に入れなくなってからは、『神山温泉の素』(入浴剤)を買ってきて足湯をしてあげていました。ご本人も毎日のように『足湯にしてくれんか』と楽しみにしてくれていて。一時期、食事がほとんど摂れなくなったとき、『ラーメンの夢を見た』って話をささ(佐々木さん)が聞いてきてたので、その翌日はかばんにカップラーメンを忍ばせて行きました。ちらっと見せたら『そんなん食べれん』って言われたんですけど、数日経ってから『あのカップラーメンが食べたい』と言ってくれて。それから少しずつ食べられるようになったんです」。
佐々木さん「食べられるなら、自分で食べたいものを選べるほうがいいよねと、ケアマネさんと連携して移動販売の車に家まで来てもらうよう手配しました。自分で買い物できるのがひさしぶりだったから、『これも、あれも食べたい』って袋いっぱいにお買い物して(笑)。自分で食べたいものを選ぶようになると、食事摂取量がすごく増えてびっくりしました。思いついたことをひたすらやっていくうちに『みんなが来てくれるなら最期まで家にいたい』と言ってくれて」。
ところが、患者さんの状態が良くなると、「もっとがんばってほしい」と思うご家族と、「がんばろうとしても身体がついていかない」とストレスを感じる患者さんとの間にギャップが生まれる場面もありました、そんなときは、患者さんと家族の架け橋となるように心を砕きました。

藤本さん「一時期は、毎日のようにご家族に電話で連絡を取り、日々のようすや今後の見立てを説明して、ご本人の気持ちを伝えさせていただいて。患者さん本人ともたくさんお話しして、ご家族にその思いを伝えることもありました。私たちのなかでも『本当にこれでいいのか』と何回も話し合いを重ねて、最終的にはみんなで同じ方向を向いてお看取りを迎えられたと思っています」。
医療者と患者さんの間に「医療」がある
診療所の実績に伴って、地域のケアマネジャーさんや事業所から、「こんな人がいるけれど在宅で過ごせるだろうか」と相談してもらえる件数が増えてきました。また、患者さんや利用者さん、集会所に来ている人たちによる口コミも広まっています。神山では、インターネットやチラシの情報よりも、口コミのほうがよほど速く広まるのです。

武久さん「地域医療って、医療者が本当に地域に根付いているかどうかだと思う。ここにいると、友だちや知り合いと話しているのか、診察しているのかわからなくなることもすごく多いけど、そういう部分がすごく大事だなと思う。これができるのは、僕が神山に住んでいて地域愛があるからです。同じことをそのまま他の地域ではできないと思います」。
あるときなど、診察を終えたあとに「ところで、先生はいつ来るんですか?」と患者さんに聞かれたこともあるそう。白衣を着けずフラットに患者さんと向き合う武久さんは、あまりにも医師のイメージからかけ離れていて、患者さんは診察されていることに気づかなかったのです。武久さんは、「神山にいるときは、いつも医療者としてのスイッチをうっすらオンしている感じ」だと言います。なにげなく過ごしているときも、医療者として「観察」をしているからです。
佐々木さん「一緒に何かすることによって見えてくることもあるんです。野球の応援をしているときに咳き込んでいるなと思ったり。お菓子を食べているときに震えているなと気づいたり。それは、話を聞いて血圧を測っているだけではわからないことです。ただ、病院にいたときは、患者さんと一緒に野球を見るなんてありえないから、『サボっているんじゃないか』という感覚はなかなか抜けませんでした。今は、元気なときは一緒に楽しい時間を過ごすことにも、すごく意味があると思えるようになりました」。
大切にしているのは「その人は今、どうしていると一番幸せなのか」。そのために、医療的なケアをするときもあれば、一緒に楽しい時間を過ごすときもあります。おそらく、医療者の生活のなかに医療があるから、患者さんや利用者さんの生活に溶け込む医療ができるのだと思います。

藤本さん「病院では、患者さんにとって私たちは『医療を提供してくれる人』です。でも、訪問看護では、利用者さんの暮らしのなかに入らせてもらうので、利用者さんは自分ごととして医療を捉えてくれる。私たちは医療行為にとどまらないいろんなケアを提供するし、利用者さんも私たちに『何かしてあげよう』と思ってくれる。そういう気持ちの連鎖があるのも在宅医療の魅力だなと思います」。
本特集で伝えてきたように、平成医療福祉グループの在宅医療は「退院後の在宅復帰を支える」部分を担うものと位置付けられてきました。しかし、神山での訪問診療・訪問看護は、グループにとって「実験と研修の場」だと武久さんは言います。
武久さん「この診療所では収益性よりも、やれることは全部やることを大事にしています。こういう医療をしていくとどうなるんだろう?という実験の場でもあります。グループの職員に研修として来てもらって学んでほしいと思っています」。
小さな診療所で積み重ねられていく確かな手応えが、いつかグループが目指す医療の礎となるのかもしれません。もし、この記事を読んで「行ってみたい」と思ったら、診療所を訪ねてみてください。集会所の「カフェ」は誰にでも開かれていますし、事前に相談しておけばスタッフから話を聞くこともできます。その一歩から、あなたが探している理想の医療が見つかるかもしれません。

プロフィール

フリーライター
杉本恭子
すぎもと・きょうこ
京都在住のフリーライター。さまざまな媒体でインタビュー記事を執筆する。著書に『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)、『まちは暮らしでつくられる 神山に移り住んだ彼女たち』(晶文社)など。
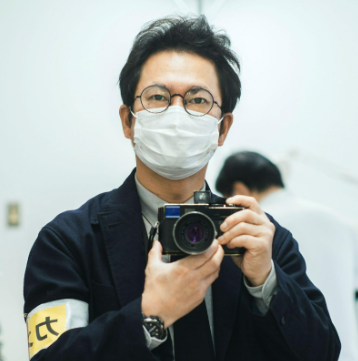
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





