離床促進による寝たきり状態の防止、身体機能回復のためのリハビリ、「口から食べる」をあきらめない栄養ケアマネジメント、できるかぎり自分でトイレに行けるようにする排泄ケア・リハビリなど。平成医療福祉グループでは、退院後の在宅復帰を視野に入れてさまざまな取り組みを行ってきました。2019年には、世田谷記念病院に在宅医療部を設立。訪問診療、訪問リハビリテーション、訪問栄養管理によって、自宅に戻った患者さんたちの生活を見守り続けています。
本記事では、慢性期・回復期医療に取り組む同グループならではの在宅医療のあり方について、同グループの経営企画医師で在宅医療部部長の佐方信夫さん、在宅医療部看護師の能勢彩子さんにお話を伺いました。
<プロフィール>
佐方 信夫(さかた・のぶお)
総合内科専門医、プライマリ・ケア認定医・指導医。2004年、神戸大学医学部卒業。手稲渓仁会病院を経て、2006年に厚生労働省入省。医系技官として診療報酬改定などに携わる。2010年から4年間、松波総合病院 総合内科に勤務したのち、ハーバード公衆衛生大学院への留学、医療経済研究機構で研究に従事しつつ、2019年から平成医療福祉グループの経営企画医師として、世田谷記念病院の在宅医療部部長に就任。筑波大学の客員准教授を兼任する。
能勢 彩子(のせ・あやこ)
世田谷記念病院在宅医療部 看護師。2019年1月、世田谷記念病院に入職。地域で暮らしている人たちの看護に興味をもち、同年10月より立ち上げ期の在宅医療部に参画する。現在は、医師とともに訪問診療に携わっている。
在宅医療には「生活の視点」が欠かせない
佐方さんがはじめて在宅医療に携わったのは、2014年。厚生労働省の医系技官、急性期病院での総合内科医を経て、大学院の博士課程に在籍しているときでした。在宅医療の現場に入ってみて、『治すとはどういうことか?』をあらためて考えさせられたと言います。

佐方さん「たとえば、腰に強い痛みがある人は『夜中にトイレに行くときに起き上がれなくて失禁してしまう』ことに困っていたりします。すると、『痛いときに飲んでください』と痛み止め薬を渡しても、トイレに行きたいときには間に合わないんです。それなら、就寝前に薬を服用してもらい、目が覚めたときに動けるようにした方がいいですよね。患者さんの生活の視点に立って細かい工夫をしないと、本当の意味で良い在宅医療ができないんです」。
あるいは、痛み止め薬が効かないなら、痛みによってできないことを補助具や介護サービスの利用でサポートするほうが、患者さんが生活しやすくなるケースもあるそうです。
佐方さん「急性期病院では、命の危険がある病気を診ることが多く、緊急で対応する必要がありました。でも、在宅医療を含めた慢性期・回復期医療では、『病気や体の障がいによって生活上の何に困っているのか』『どうすれば幸福度を上げられるのか』を考えながら取り組む医療だなと思いました」。

佐方さんが在宅医療医をしていることを知って、世田谷記念病院の在宅医療部へと招いたのは、同グループ副代表を務める坂上祐樹さん。実は、坂上さんは厚生労働省時代の佐方さんの後輩だったそう。
佐方さん「そのときは、医療経済研究機構の仕事が忙しかったので断りましたが、数年後に筑波大学とクロスアポイント契約*を結んだとき、『週2日を筑波大学、週3日を世田谷記念病院』という考えが浮かびました。坂上さんに話してみたら『佐方さんができると言うならいいですよ』とあっさりOKしてくれて。在宅事業部の立ち上げをすることになりました」。
* クロスアポイントメント契約:研究者が大学、研究機関、民間企業など複数の機関において正式な身分をもち、研究や業務に従事する雇用契約。
慢性期・回復期医療の延長線上にある在宅医療
世田谷記念病院がある世田谷区は、「日本で一番在宅クリニック数が多い」とも言われています。そこで新しく立ち上げるなら「平成医療福祉グループらしい在宅医療」であるべきだと佐方さんは考えました。
佐方さん「一般には、24時間対応が必要な終末期の患者さんにフォーカスする在宅クリニックが本流ですが、すでにそこを担うプレイヤーはたくさんいます。慢性期・回復期医療に取り組んできた当グループで立ち上げるなら、退院直後の患者さんに特化する方がいいと提案しました。世田谷記念病院で治療やリハビリを受け、退院した患者さんを見守り続けるというコンセプトです」。
もともと、世田谷記念病院には退院後の患者さんのリハビリを継続する、訪問リハビリ部門がありました。在宅医療部の立ち上げは、訪問リハビリと訪問診療をセットで行うことによって、自宅に戻ってからも回復していくプロセスを見守るというモデルで進みました。具体的に、在宅医療部ではどんな患者さんを受け持っているのでしょうか。
佐方さん「世田谷記念病院の在宅医療の強みのひとつは、バックベッド(入院できるベッド)があることです。この先も入退院が予測される人は、当院で在宅医療も受けていただくメリットが大きいと思います。また、訪問リハビリに加えてリハビリ専門医がいますので、リハビリが重要な患者さんはうちで診る方がいいですね。リハビリ専門医が評価してくれる訪問診療はなかなかないと思います」。


在宅医療部のオフィスは、医師、看護師、療法士のステーションになっています。医師による訪問診療は隔週ですが、訪問リハビリは週1〜2回。リハビリのときに患者さんについて気になることがあれば、療法士から医師・看護師に情報が共有されます。在宅医療と訪問リハビリを組み合わせることで、患者さんの状態をきめ細かく観察しながら、充実した在宅医療を提供できるというわけです。
佐方さん「世田谷記念病院では、管理栄養士による訪問栄養指導も行っていて、意外とニーズがあります。患者さんやご家族から『食生活はどうしたらいいですか?』という質問が出るのですが、管理栄養士が精緻に計算して献立を一緒に考えてくれるので、ご家族が食事の心配をしなくてよくなるんです。患者さんの栄養状態の改善だけでなく、ご家族の介護負担も減るというのは驚きでしたし、とても意味があると思いましたね」。
病棟と連携しながら在宅生活を支える
世田谷記念病院のなかに在宅医療部があることは、入院中から退院後の生活まで、シームレスに患者さんを見守れるという大きなメリットを生んでいます。看護師の能勢彩子さんは「カルテを共有しているので、介入前から詳細に情報共有できる」と言います。

能勢さん「地域連携室から依頼された段階で、一通り情報を書き出してまとめます。S情報(Subjective data、患者や家族の言葉など主観的情報)、O情報(Objective data、観察や検査による客観的情報)もすべて見られますので、患者さんがどんな話し方をするのか、ご家族の雰囲気がわかりますし、それに対するアプローチを事前に考えることもできるんです」。
地域連携室の退院支援看護師、渡辺嘉子さんは「在宅医療部が、ほぼ完璧に記録を見て情報をキャッチアップしてくれるので安心」だと言います。社会福祉士の緒方奈央子さんも「各職種が直接会って話をして、入院中の担当者と退院後の担当者が情報共有できるメリット」を感じているそうです。能勢さんたち、在宅医療部の看護師は病棟で定期的に開催されるカンファレンスにも参加しており、多職種から引き継ぎしやすい関係を作っています。

能勢さん「院内では月一回在宅支援委員会が開かれていて、地域連携室の看護師と在宅医療部の看護師、訪問看護ステーション・てとてと大岡山の訪問看護師でお話して連携をとっています。ふだんから食堂などで顔を合わせるときに『あの患者さんのことですが』と相談する関係性もありますね」。
現在、在宅医療部で診ている患者さんは約110名。そのうち60名が世田谷記念病院から退院した人たちです。次に多いのは、地域のケアマネジャーから紹介された40名。立ち上げから5年間で、地域の信頼を得てきた結果がこの数字にも現れています。
佐方さん「ここ2年ほどで、世田谷記念病院の在宅医療部が得意とすることを、地域のケアマネジャーさん、地域包括支援センターの職員さんや、急性期病院の地域連携室の人たち、あるいは医療介護従事者の人たちに認識してもらえるようになったのを感じています。『世田谷記念病院のリハビリは効果があると患者さんたちが喜んでいる』と言ってくれるケアマネジャーさんたちもいて。実績とともに、コンスタントに院外からの紹介件数も増えてきました」。
訪問診療を看護師とともに行う理由
在宅医療部を立ち上げるとき、佐方さんは「必ず看護師をつけよう」と決めていたそうです。病棟では、看護師が患者さんを見ているので、主治医がいないときにも当直医に患者さんの状態を伝えることができます。訪問診療においても、同様の体制をつくりたいと考えたからです。



佐方さん「理想は、何人かの看護師が在宅の患者さんを把握している看護体制があり、そこに医師がいるというかたちだろうと考えました。患者さんのご家族も看護師だからこそ話しやすいこともあります。実際に今、看護師にすごく助けてもらっています。うちの看護師たちは、抜群に仕事の精度が高いんです。人材に恵まれたことは非常にラッキーだったと思います」。
在宅医療部は、どの時間帯でも電話対応する「24時間オンコール」体制です。日中の電話はまず看護師が受けます。能勢さんは「どんな気持ちで電話をかけてきたのか」を想像しながら、オンコールに応えています。

能勢さん「患者さんやご家族は、『電話するほどじゃないかもしれないけど、一応かけてみよう』って悩んでから電話をかけてくれたりします。私たちからは『何かあったら小さいことでも、時間も気にせず電話してください』と伝えています。お話を聞いて解決策を一緒に考えて、医師に相談して対応のしかたをお伝えして『安心しました。お電話してよかったです』と言われると、こちらもよかったなと思います。ご家族も顔を知っている看護師と話せることが安心だと言ってくれますし、私たちも状況を知っているからこそ答えられることがあるなと感じています」。
当初は、佐方さんひとりで訪問診療を担当していたそう。患者さんの数が増えるにつれて、一人で対応しきれなくなり、病棟の先生方にサポートしてもらうようになりました。
佐方さん「消化器内科の杉本元信先生、当院院長の清水英治先生、神経内科の小倉由佳先生、リハビリテーション科の牛場直子先生、鹿沼優先生など、病棟の先生たちが手分けして患者さんを診てくださって。病棟と在宅の両方を診るのはすごく大変です。でも、それをやり続けてくれた先生たちがいたから、在宅医療部を設立できたと思っています」。
世田谷記念病院の在宅医療部は、平成医療福祉グループの在宅医療の基本モデルになりました。その後、多摩川病院に在宅医療部を開設したほか、グループに訪問事業部を新たに設け、「おうち診療所」を5カ所オープン。東京や神奈川、徳島など、それぞれの地域性に合わせた診療所づくりが進められています。
患者さんは何をしているときが幸せなのか?
平成医療福祉グループの理念は「じぶんを生きる を みんなのものに」。在宅医療部では、この理念のもと、「患者さんは何をしているときが一番幸せなのか」を日々話し合っているそうです。

能勢さん「在宅医療の現場にいると、医療者目線で『体のためにいいこと』は、必ずしもその患者さんにとっての幸せとは限らないと感じることがあります。つらいことを我慢しながら生きていくよりは、少しでも楽しいことができる人生の方がいいんじゃないか、と思いますし。たとえば、糖尿病だけど甘いものが大好きな90歳の方に、厳格な食事制限をするよりは、少しでも好きなものを食べてもらおうとお薬の調整をすることもあります」。
佐方さんは、在宅医療に関わるようになったとき、患者さんの抱える課題に向き合うほどに、「どこまでが医療なんだろうか?」と考えることもあったそうです。しかし、今は「在宅医療では病気だけではなく、生活のことまで考える必要がある。医療の枠にとどまっていては不十分」と言い切ります。
佐方さん「在宅医療部のカンファレンスでは、よく『この人はどうしたらハッピーなの?』という話をするんです。たとえば、カフェでモーニングを食べるのが好きな患者さんがいたのですが、『どうしたら彼が安全にカフェに行けるのか』を療法士や看護師と一緒に考えて、配薬を変えたりリハビリのメニューを考えてみたりしました。『この人がいかにハッピーに暮らせるか』を、医療だけではなくさまざまな角度から考えることが、まさに『じぶんを生きる』を追求することだと思います」。


おふたりのお話を聞いていて、「医療は病院のなかでするもの」という先入観がほどけていくのを感じていました。同時に、「医療は何のためにあるのか」ということも考えさせられました。私たちが病気やけがを治したいと願うのは、ささやかな日常のなかで自分らしく生きたいと望むからだと思います。もし、治療を優先するあまりその日常が壊れてしまうならーー。「じぶんを生きる」ことが難しくなってしまう可能性もあります。
もし、そのときに佐方さんや能勢さんのような医療者がそばにいて、命の安全を守ってもらいながら、同時に「あなたはどうしたいですか?」と聞いてくれるなら、どんなに安心できるでしょうか。在宅医療とは、人生を支えてくれる医療だと言えるのかもしれません。
次の記事では、徳島・神山町の「おうち診療所 神山」を訪ね、地域医療のあり方について考えたいと思います。
プロフィール

フリーライター
杉本恭子
すぎもと・きょうこ
京都在住のフリーライター。さまざまな媒体でインタビュー記事を執筆する。著書に『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)、『まちは暮らしでつくられる 神山に移り住んだ彼女たち』(晶文社)など。
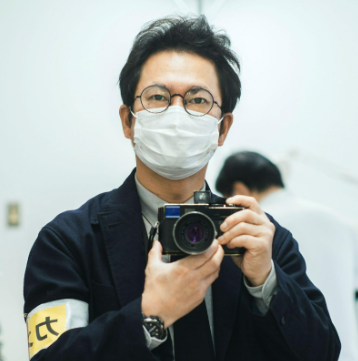
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





