病院はそもそも地域に根ざすもの。だからこそ、地域連携は重要でしっかり取り組む必要がある。そんな思いをもち、地域連携室のあるべき姿を追求してきたのが、神奈川県横浜市にある「医療法人横浜平成会 平成横浜病院」です。
特集「地域と医療のあたらしい関係:地域連携室」では、患者さんが「自分を生きる」をあきらめることなく住み慣れた地域で暮らし続けていくために、地域と医療の橋渡し役を担う「地域連携室」にフォーカス。より良い医療とケアを提供するために地域連携室が果たす役割と、平成横浜病院が目指す未来について、副看護部長の増子美佐保さんと地域連携室 主任の宮澤ゆいさん、事務長の日高正明さんにお話を伺いました。
<プロフィール>
増子 美佐保(ますこ・みさほ)
平成横浜病院 副看護部長。急性期病院などでの勤務を経て、2022年、平成横浜病院に入職し、地域連携室に配属。師長として地域連携業務の改善を手がける。2025年より現職
宮澤 ゆい(みやざわ・ゆい)
平成横浜病院 地域医療連携室 主任。社会福祉士。病棟クラークとして働いたのち、社会福祉士の資格を取得しソーシャルワーカーに。2021年に入職し、一度は退職。2023年に再入職した
日高 正明(ひだか・まさあき)
平成医療福祉グループ 病院事業部 関東エリア担当、平成横浜病院 事務長。他法人グループの急性期病院で総務経理や事務長職を経験したのち、2016年に平成医療福祉グループに事務長候補として入職。2018年、平成横浜病院の事務長に就任
素早い判断と細かな配慮で患者さんの入退院をサポート

平成横浜病院の地域連携室には、看護師6名、ソーシャルワーカー(社会福祉士)3名の計9名が配属されています。主に入院調整を行う「前方支援」は看護師が担当。退院調整とその後の暮らしのサポートを行う「後方支援」は看護師とソーシャルワーカーがともに担います。2022年に増子さんが地域連携室に参画してからは、日高さんとも相談しながらより良い入退院支援や地域連携のあり方を模索し、さまざまな取り組みを実現してきました。
増子さん「当院の地域連携室では、平均して月に200〜300件ほどの入退院支援を行っています。前方支援の主な業務は、急性期病院などから転院の相談を受け、入院調整を行うこと。当院の特徴としては、多くの病院が週1〜2回のペースで行う入院判定会議がないんですね。地域連携室の看護師がヒアリングを元にアセスメントし、その日のうちに入院の可否を判断しています」。
日高さん「以前の平成医療福祉グループの理念は『絶対に見捨てない。』でしたから、『患者さんを選ばない』という大前提があります。だったら、ベッドコントロールさえきちんとできていれば、『判定会議をする必要はないんじゃないか?』と思ったんです。病院の機能として受け入れできない患者さん以外は、基本的に受け入れる方向で調整する。最初はさまざまな意見がありましたが、今はみんなが地域連携室を信頼して、これでいけるよね、となっています」。
「入院判定会議は行うもの」という病院の常識を問い直すことで、転院までにかかる時間はぐっと短縮されました。スムーズな転院は、患者さんやご家族の不安を軽減します。また、地域の医療機関からも相談してもらいやすくなり、病棟スタッフも毎週の会議がなくなった分、患者さんのために時間を使えるようにもなりました。

後方支援でも、患者さんやご家族の不安を解消するために細かな配慮をしています。入院時面談や入院時合同調査で、患者さん、医師、看護師、ソーシャルワーカー、栄養士、薬剤師、歯科衛生士など、多職種で事前情報を共有。入院一週間後のカンファレンスで患者さんの状態を評価すると、後方支援スタッフはその情報をもとに患者さんやご家族の希望を聞いて、目標を設定します。その後は面会時に直接お話ししたり、メールや電話で連絡を取り合いながら、退院までのプロセスについてご家族への情報共有を行います。
宮澤さん「どんな情報共有の方法があるのかを最初にお伝えして、ご家族に好きな方法や頻度を選んでもらってます。メールで気兼ねなく質問できたほうがいい人もいれば、電話や面談でじっくり話がしたい人もいる。ソーシャルワーカーがほとんど必要ないケースであれば干渉しすぎないようにしますし、ご家族の心理的不安が大きい場合には、メールで頻繁に状況をお伝えするなど対応を変えていますね」。
高齢の患者さんは、病気そのものが治っても、退院後に前と同じ生活ができないケースも少なくありません。患者さん本人はもちろん、家族にとっても生活が一変する可能性があります。自宅で暮らし続けられるのか。家族は今まで通り仕事をつづけられるのか……? さまざまな不安を、ソーシャルワーカーがていねいに聞き取りながら、具体的なアドバイスをしてくれるなら、どれほど心強いことでしょう。
入院前から頼れる相談先があることの大切さ

地域連携室は、地域の医療機関、福祉施設、ケアマネジャーなどとの関係性づくりのために、広報や営業的な役割も担っています。たとえば、2カ月に1回開催されるケアプラザ主催の地域医療連携の交流会には必ず参加。顔が見える関係性をつくっておくと、何かあったときにお互いに相談しやすくなるからです。また、「平成横浜病院はどんな患者さんを受け入れられるのか」「どんな特徴があるのか」をあらかじめ伝えておけば、入院先を探す際の選択肢に加えてもらえるようになります。実際に、地道な関係性づくりのおかげで救急搬送件数が増加したのだそう。
増子さん「体制が充実して整形外科の救急搬送が受けられるようになったので、搬送に来た救急隊の方に声をかけて説明したんです。例えば『個室があるから発熱している患者さんの整形案件も受けられます』といった情報を伝えておけば、対象となる患者さんがいたときに受け入れの要請をしてくださるんですね。その結果、救急搬送の件数は、2023年度に300件だったのが、2024年度は1100件まで増えました」。
患者さんは早く治療が受けられ、救急隊も搬送先がすぐに決められる。病院としても患者さんが増えればそれだけ経営が安定することになり、三方よしの体制が築かれます。情報の共有や広報が、適切な医療の提供のためにいかに大切かがよくわかります。

また、平成横浜病院は地域連携室のなかに「患者サポート室」を設置しています。これは、地域の方々、入院中・通院中の方々が、医療や介護に関する悩みや不安があるときにいつでも相談できる窓口です。何科を受診したらいいかわからない、入所できる施設を探している、退院後の生活が不安、医療費が払えるか心配など、医療・介護にまつわることや地域で暮らし続けるための相談であればどんなことでも受け付けています。最近は家族間のモラハラや虐待についての相談が増えていて、必要に応じて適切な機関や人につなげることも。そんなところまで病院がサポートしているのかと驚きました。
宮澤さん「今は、ACP*が推奨されるようになって、医療の現場でもコミュニケーションをとって信頼関係を築いたり情報の共有をすることが、ますます大切になっています。入院してから相談に乗っているようではもう遅い。入院する前から頼れる相談先を用意しておくことは、地域連携の一環として必須ではないかなと思っています」。
*ACP アドバンス・ケア・プランニング。将来の変化に備え、医療およびケアについて、患者さんを主体に、ご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援するプロセスのこと
日高さんは「地域」を考えたときに、患者サポート室は絶対に必要だと思ったそうです。
日高さん「地域連携室には『地域』っていう言葉が入ってますよね。だったら、単なる入退院の係で終わらないで、地域の患者さんをサポートする機能をちゃんともちましょうと。実際にやるのは大変なんですけど、地域連携室のスタッフも思いは同じで、がんばってくれています」。
患者さんやご家族の「自分を生きる」を考えて取り組む退院支援

地域の医療機関から紹介される患者さんの受け入れ、患者さんが退院後に安心して暮らせるように行う在宅医療や介護サービス、施設との連携や調整、地域の医療機関などとの関係づくり、患者さんやご家族からの相談業務……ここまで見てきたように、地域連携室の仕事は非常に多岐に渡ります。
日高さん「地域連携室の仕事はすごく大変です。病院からは経営的な観点であれこれ言われるし、医師やスタッフからは入退院について意見が出される、患者さんやご家族からの要望も受け止めなくてはならない。医療について理解し、複雑な介護制度についても把握し、ときには費用に関する相談にも乗る。しかも、どうするのがベストかを見定めて提案もしないといけないんです。本当にすごい仕事だと思っています」。
この「すごい仕事」を任せられる人として、増子さんが声をかけたのが、入職から数カ月間一緒に働いた宮澤さんでした。増子さんは「この人は絶対離しちゃいけない。地域連携室を変えていくには絶対に必要な人だ」と確信していたので、一度は退職した宮澤さんに連絡を取り続けていたそうです。
増子さん「仕事や患者さんに対しての向き合い方がすごいんです。絶対に流されないし、言うべきことは医師にも看護師にもはっきり言う。患者さんの経済状況がどうであっても、社会資源を使って希望どおりにできるよう工夫したり。それこそ、グループの理念が『じぶんを生きる を みんなのものに』になる前から、患者さんやご家族の『じぶんを生きる』を考えてやってくれていました」。
宮澤さん「病院には宮澤さんのようなワーカーが必要だから戻ってきてほしい』と言っていただいて。退職した職場から戻ってきてくれと言われることは、なかなかないと思うんです。これはもう1回がんばれってことかなと思って戻ってきました。実際に、増子さんが入職されてから、地域連携室は『患者さんを中心とした医療を提供する』という意識のもと、より良い方向にどんどん変わっていきました」。
「退職した人を呼び戻すからには」と、増子さんは改善すべきところは改善しながら、より良い地域連携室づくりを行ってきました。その一端が、ここまで紹介してきた取り組みの数々です。

宮澤さん「今は、ソーシャルワーカーの仕事の範疇であれば、自分が最善だと思えるように、患者さんやご家族の意向に沿った入院調整、退院支援をさせてもらえている。本当に戻ってきてよかったと思っています。私は『じぶんを生きる』って『自分で決めていく』ことだと思っていて。たとえ、すべてのご希望を叶えることはできなくても、とにかく情報を伝えて理解してもらい、不安を軽減することはできる。そのうえで、自分はこうしたいという答えを出してもらい、その実現のためにできるだけのサポートをしています」。
日高さん「全部を一つの病院だけでやりきれるわけではありません。もちろん、地域連携室が目指す理想はあり、その実現に向けてできうる限りの改善はしていきたいと考えています。でも改善するには時間がかかるし、どうしても難しいこともある。だから、自分たちができないことが何かを知って、それを叶えられる医療機関やサービスなどにちゃんとつなげてあげることが大切だと思っています」。
つまり、患者さんの希望を叶えようと思えば、必然的に「地域連携」が必要になってくる。平成横浜病院がここまで地域連携を重視してきた理由は、患者さん一人ひとりが希望する医療やケアをどうしたら提供できるかを考えた結果でもあったのです。
地域連携室は本質的には「患者サポートセンター」である

今、地域連携室には次なる目標があります。それは、退院した患者さんの在宅訪問を実施すること。実際に生活してみると、退院時に想定していたほどうまくいかなかったり、新たな困りごとが発生している可能性もあります。次につなげたから終わり、ではなく、つないだ責任として、退院支援が適切だったかどうかまできちんと見届け、サポートしていきたいと考えているのです。その実現のために、ソーシャルワーカーを増やしていくことも検討中です。
増子さん「日高さんは本当に地域連携室のことをよくわかってくれている事務長さんで。1を伝えたら10どころか100わかってくれます(笑)。だからすごく動きやすい。在宅訪問をやりたい、ソーシャルワーカーさんを増やしたいと相談した時もすぐに理解してくれました」。
日高さん「だって、地域連携室の一連の取り組みによって、地域の中の潜在的な患者さんが平成横浜病院を信頼してくれるのであれば、その人件費は未来への投資であって、絶対無駄じゃないと思うんです」。

日高さん「そこまでできるようになったら、僕は地域連携室ではなく『患者サポートセンター』と名称を変えたほうがいいと思っています。一般的な会社で『室』って言ったら、一つの機能しか示さないじゃないですか。でも彼女たちが実際に現場でやっていることは、地域連携業務にとどまっていない。どう考えても地域連携を含めた患者サポート全般を担っているセンターなんです。とはいえ、現場にいない僕が先走って変えるのは良くないので(笑)、体制が整って、みなさんが患者サポートセンターと名乗ってもいいと思えるのを待っています」。
入退院支援だけでなく、入院前の相談や退院後のサポートまで行うことで、患者さんに、地域で安心して暮らしてもらえるようにする。地域連携室はそこまでやるべきだという強い確信が、平成横浜病院にはあるのです。
増子さん「まず、平成横浜病院が、入院する前も退院した後も話を聞いてくれて、なんでも相談できる病院だということが口コミで地域に広がってほしいです。そして最終的には、いつでも気軽に、フラっと立ち寄れる病院にしていきたいと思います!」。
病院でできる治療やリハビリは終わっても、患者さんの生活は続きます。だからこそ、いざ病気になった時に頼れる病院が近くにあることは、その地域で不安なく暮らしていくためにとても大切なことなのです。病院が日常と切り離されず、暮らしと地続きの場所になるために何ができるのか。地域連携室が問い続け、取り組み続けた先に、患者さんの「じぶんを生きる」が、本当の意味で叶えられる気がしてなりません。
プロフィール

ライター
平川友紀
ひらかわ・ゆき
フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。
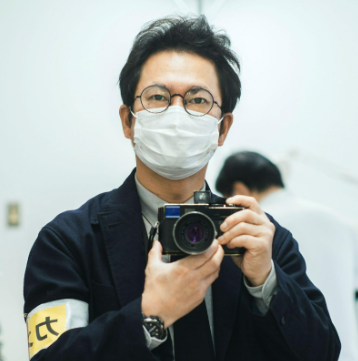
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。



