自分自身や家族が入院し、病気や障がいを抱えて介護が必要になったとき、私たちは退院後の生活をどのように考え、どう構築していけばいいのでしょうか。実際のところ、多くの人は問題に直面して初めて、この先どうしたらいいかを考え、わからないことの多さに途方に暮れるのではないかと思います。
今回の特集「地域と医療のあたらしい関係:地域連携室」では、患者さんが「自分を生きる」をあきらめることなく住み慣れた地域で暮らし続けていくために、地域と医療の橋渡し役を担う「地域連携室」にフォーカス。病院内での役割、患者さんやご家族との関わり方、地域との連携のあり方などについて、大阪府堺市の「医療法人恵泉会 堺平成病院」地域連携室のみなさんに詳しくお話を伺いました。
<プロフィール>
大谷 絵美(おおたに・えみ)
堺平成病院 地域連携室 師長。特定行為看護師。他の病院での勤務や訪問看護の経験を経て、2019年、堺平成病院設立時に入職。主に前方支援を担当
長野 和代(ながの・かずよ)
堺平成病院 地域連携室 主任。看護師。高度急性期病院に長く勤務したのち、2022年に堺平成病院に入職し、地域連携室で前方支援を受け持つ。現在は後方支援に回り、医療的観点から退院サポートを行っている
青野 沙貴(あおの・さき)
堺平成病院 地域連携室 社会福祉士。2016年、同病院合併前の浜寺中央病院に入職。回復期リハビリテーション病棟を担当したのち、現在は地域包括医療病棟の後方支援を担当している
高田 結衣(たかだ・ゆい)
堺平成病院 地域連携室 社会福祉士。大学で社会福祉について学んだのち、医療関連事業も行っている一般企業に就職。社会福祉士の資格を取得し、2020年に入職。現在は医療療養病棟の後方支援を担当する
地域医療構想を実現するための連携実務を担う「地域連携室」
地域連携室とは、地域のさまざまなステークホルダー(医療機関、福祉施設、訪問診療や訪問看護、ケアマネージャー、地域包括支援センターなど)と連携し、患者さんやご家族の希望に合わせた適切な医療や支援がスムーズに受けられるようサポートする病院内の専門部署。近年は、ますますその必要性が指摘されています。
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、2015年に厚生労働省が打ち出した「地域医療構想」。そのねらいは、地域の医療機関が施設の特色に応じて機能の分担や専門化を進めるとともに、各機関の連携により効率的な医療サービスを提供することにありました。病院においては、入退院支援を中心に、地域の医療機関との連携実務を担うのが地域連携室です。現在、地域連携室またはそれに準ずる部署は、全国の約98%の病院に設置されており、もはや病院運営には欠かせない部署だと言えるでしょう。
地域連携室の業務は大きく二つに分かれます。一つは、医療機関や救急隊、福祉施設やご家族からの要請・相談を受け、患者さんの状態を共有してもらい、医師の指示のもとで入院調整を行う「前方支援」業務。もう一つは、退院に向けて福祉施設や介護サービスと連携したり、退院後に受診する病院や診療所を紹介するなど、退院とそれ以降の生活に関わる「後方支援」業務です。
堺平成病院の地域連携室には、前方と後方を合わせて16名(社会福祉士5名、看護師9名、事務員2名)もの人員が配置されています。他の病院に比べて、人数が多いのはどうしてなのでしょうか。

大谷さん「堺平成病院は、急性期から慢性期、看取りまで一貫した医療を提供できるケアミックス型の病院です。そのため、1カ月の入退院件数が約250件と非常に多いですし、日々さまざまな入院相談が入ってきます。高度急性期病院で治療を受け、状態が安定した患者さんを回復期リハビリテーション病棟で受け入れたり、肺炎や尿路感染といった当院で対応可能な疾患の救急患者さんを搬送してもらったり。高度急性期病院が重症患者さんを受け入れることができるよう、引き受けられる患者さんはなるべく地域の病院がみるという形ですね」。

病院内外とのスムーズな連携で在宅復帰を支える
急性期病院から転院してくる患者さんは、退院後の方向性が何も決まっていない状態でやって来ることがほとんどです。そのため、患者さんやご家族の希望をヒアリングし、退院後はどうするかを一から考えていくのも地域連携室の仕事です。「みなさん状況が違うため、一人ひとりに合わせた支援をしていくのはとても大変です」と大谷さん。
大谷さん「ほとんどの患者さんは自宅に帰りたいと希望されますが、病態やご家族の状況によっては難しい場合もあります。そこで地域連携室の相談員(社会福祉士)が入って、介護保険などの社会資源を活用することで希望を叶えられる方法を検討します。施設に入ることになった場合でも、いろいろな種類の施設がありますので、どこがよいのか提案したりもしますね」。
後方支援は「どう支援するか」によって、患者さんのその後の暮らしが決まってしまうという大きな責任を伴う仕事です。社会福祉士の高田さんは、夢にまで見るほど思い悩むこともあるそうです。

高田さん「本人とご家族で、退院後に希望されることが違うこともあります。経済的な事情もさまざまです。希望されている施設への入居が難しかったり、入院費の支払いについて相談を受けることもありますね。自宅に帰れるとしても、そのためにはどのサービスをどう使えばいいのか、じっくり考えなければなりません。ああしたほうがいいかな、こうしたほうがいいかなとぐるぐる悩んでいるうちに、夢の中でもずっと考えてしまうんです(笑)」。
同じく社会福祉士の青野さんは、より良い支援のためにはコミュニケーションが非常に重要だと話します。
青野さん「福祉施設と常時連絡を取り合っていれば、必要な時にスムーズに受け入れてくれますし、ケアマネさんと何でも言い合えるようになっておけば、困った時に助け合うこともできます。普段からたくさんの人とコミュニケーションして関係性をつくっておくことはとても大切なんです」。
たとえば、地域包括医療病棟は地域の介護施設のバックベッドの役割も果たしており、六つの協力対象施設に入所している方の容体が悪くなったときは入院を受け入れています。いざというときにスムーズに調整ができるのは、月一度の情報共有を行っているからです。また、地域連携情報交換会を主催して、地域の病院や福祉施設の方々と交流する機会も設けています。こうした地道な関係性づくりの先に地域医療が育まれているのです。

堺平成病院では病院内の連携にも力を入れており、後方支援のスタッフを各病棟に配置しています。これは、病棟に常駐していたほうが、医師や看護師、セラピスト、患者さんやご家族との連携がとりやすいという考えからはじまったそうです。入退院支援では、病院と地域という外向きの連携だけでなく、院内のスムーズな連携も重要なのです。
高田さん「病棟で仕事をしていると、自然と情報が入ってきます。面会に来たご家族も相談しやすいし、私たちもリハビリの様子を見ながら『困ってることはないですか』と声掛けができて、随時支援に入ることができるんですね。あんなに歩けているから早めに退院できるのではないかということも考えられるし、逆にこのぐらいで退院を進めようと思っていたけど、もうちょっとかかるかもしれないなということも見えてくる。他の職種の方とも話し合いながら退院支援ができるので、病棟配置はすごくいいなと思います」。
地域連携室のスタッフが一緒に働くことで、病棟スタッフにも患者さんやご家族に寄り添った退院支援を一緒にやっていってもらいたいという思いもあります。
大谷さん「私は前職で訪問看護をやっていたこともあって、この患者さんは支援の仕方次第で在宅復帰できるのになと思うことがよくあるんです。病院は命を守ることが最優先なので、医師や病棟スタッフの判断が慎重になるのは当然のことです。ただ、患者さんやご家族がどういう思いをもっているかを知って、どうしたらその希望を叶えられるかを考えることも同様に大切だと思うんですね」。
患者さんの「帰りたい」を実現する方法を考え抜く

大谷さんは、在宅での看取りを選んだという、長期入院しながら透析治療を受けていた患者さんの話をしてくれました。医師は退院は許可できないという判断でしたが、長野さんが退院支援を担当し、患者さんやご家族の「自宅に帰りたい」という意思を尊重しようと説得したのだそうです。
長野さん「ご本人やご家族には、在宅復帰にどれだけのリスクがあるのかをきちんとお伝えしました。それでも帰りたいと心を決めておられたので、そこまで言っているのだからそうしましょうと説得しました。ケアマネをつけて、ベッドを用意して、訪問診療や訪問看護を手配し、おむつ交換などの家族指導も行い、無事に帰宅することができたんです。そうしたら、きっと安心されたんでしょうね。自宅に帰って3時間後に亡くなられました」。
わずかな時間であっても帰りたかった我が家に帰り、家族と過ごせたことが、患者さんにとってどれほど切実で、納得するものだったか。病院は病気や怪我を治し、命をつなぐ場所ですが、一方でどう生きたいか、どう人生を全うしたいかという患者さんの意思を尊重し、それを叶えるためのサポートができる場所でもあるのです。

青野さんは、身寄りのない一人暮らしの患者さんが在宅復帰するために、生活環境を改善するところから携わったことがあります。
青野さん「そのときは家屋調査にも行きました。玄関の段差は大きいし、トイレは和式だし、畳もボロボロだった。このままでは帰るのは難しいだろうということで、地域包括支援センターの職員とも連携し、後見人をつけました。患者さんの了解のもと費用をいただいて、畳を交換したり、エアコンの取り付けもしましたね。絶対に無理だと言われていたのに帰ってもらえたときは、本当にうれしかったです。その方は訪問診療や訪問介護を利用しながら、今でも在宅で元気に暮らしているそうです」。
在宅復帰してみた結果、社会資源を使って生活できるようになるというのは珍しい話ではありません。入院中は寝たきりだった人が歩いてトイレに行けるようになるなど、ADL(日常生活動作)が改善するケースもあるのだそうです。そういった意味でも、無理だと決めつけず、在宅復帰にチャレンジする価値はあるのです。
長野さん「そこの判断は正直難しい。帰りたいという思いはわかるけど、とはいえどうやって生活するのかな、無理だよなという患者さんもいます。それでもどうしてもと望まれるのであれば、思いきってやってみるしかない。私は、患者さんがどうしたいかを一番大事にしています」。
チーム医療の力で退院後の不安を解消する

このように、患者さんやご家族に寄り添い、その思いを叶えようと奔走する地域連携室ですが、近年、法律で定められた入院可能日数が短くなっていることもあり、退院支援には迅速さも求められるようになりました。限られたベッドを効率的に使用するためには、ときにシビアに病棟のベッドコントロール(病床管理)を考えなければなりません。
堺平成病院ではより適切なベッドコントロールを目指して、2年前に病棟の看護師も参加するベッドコントロール委員会を立ち上げました。これは、地域連携室というより、看護師のプライマリ・ナーシングの意識を高めていきたいという看護部の提案からはじまったそうです。みんなが主体的にベッドコントロールに取り組むことで、退院支援についても必然的に関わるようになりつつあります。
「そもそも退院支援はみんなでするもの」と長野さんは言います。
長野さん「ご家族に関しては地域連携室のほうが話す機会が多いんですが、患者さん本人とは、病棟の看護師やリハビリスタッフのほうがよく話をしています。だから、みんなで情報を持ち寄って、退院までに患者さんやご家族の不安を緩和していく。ケアマネさんともしっかり相談して、最後には退院前カンファレンスを開いています。帰ったらこういうところに気をつけましょう、こういうサービスが必要ですよね、これぐらいのサービスがあれば大丈夫ですかと、本人やご家族も交えて確認することで、ちょっとでも安心してもらえるのではないかと思っています。
また、多職種がそれぞれの視点から退院後の生活を考えるほうが、患者さんのためにもなります。そのときには、私たちスタッフが患者さんにどうなってほしいかという思いも大切です。そこを捉えたうえでチームとして関わっていくことが重要だと思います」。

地域の医療機関との連携がしっかりとれるようになってきた今、堺平成病院地域連携室は、いよいよ地域で暮らす人たちとの橋渡しにも取り組もうとしています。来年3月ごろには「堺平成フェスタ」というお祭りを開催しようと、地域連携室を中心に準備を進めているところです。
高田さん「本当に、何でも相談してほしいです。ご家族のみなさんは、たとえば施設を決めるときも自分たちで施設を探さなきゃ、いろいろなところに見学に行って決めなきゃとがんばるんですね。でも、私たちはいろいろな施設の情報をもっていて関係性もあるので、希望に合う施設を探すことができます。ぜひ遠慮せず、気軽に相談してもらえたらうれしいです」。
病気になったり、介護が必要になっても、最後まで住み慣れたまちで暮らし続けるには、いざというときに頼れる地域の医療機関の存在は不可欠です。この病院があるから大丈夫。そんなふうに思ってもらえるよう、堺平成病院はこれから先も、ますます地域に開かれた病院を目指します。
次回は、平成横浜病院の地域連携室の取り組みをご紹介します。
プロフィール

ライター
平川友紀
ひらかわ・ゆき
フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。
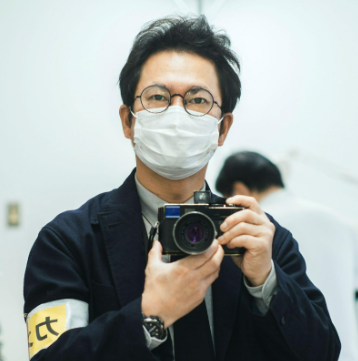
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。



