「医療法人社団 西宮回生病院」は、1907年(明治40年)7月15日に開院した、100年以上の歴史がある病院です。西洋のお城のような旧病棟は地域のシンボル的存在として親しまれ、野坂昭如氏の『火垂るの墓』や村上春樹氏の『ノルウェイの森』などの文学作品に登場したことでも知られています。
2013年には平成医療福祉グループに入り、2016年には老朽化に伴う全館建て替えを実施。そのタイミングで診療体制も一新しました。「地域のかかりつけ医」の役割と並行して、整形外科とリハビリテーションに特化した医療提供に力を入れたのです。
ふだんは裏方に徹している事務長にフォーカスする特集記事「医療の現場を支える」の第4回は、2019年7月から同病院の事務長を務めている國見祐季さんです。今回は、実際のお仕事の様子も見学させていただきました。
<プロフィール>
國見 祐季(くにみ・ゆうき)
医療法人社団 西宮回生病院 事務長。2002年、介護福祉士として介護老人保健施設「平成アメニティ」に入職。現場で働くかたわら、複数の介護施設の立ち上げや業務改善に携わる。介護福祉事業部に異動となったのち、2015年、神戸平成病院の事務長に。2016年、西宮回生病院の事務長補佐となり、2019年より現職
超過密スケジュール!事務長に密着取材

まず案内してもらったのは事務室です。普段仕事をしているデスクで見せてもらったのは、びっしりと予定が詰まったスケジュール表。赤色が國見さんのスケジュールで、朝から晩まで、分刻みで予定が入っていることがわかります。貴重な空き時間は溜まっているメールの返信などで、あっという間に終わってしまうそう。上にある青色は手術の予定です。
國見さん「西宮回生で実施しているのは、整形外科の手術です。もし手術ができる枠が埋まっていれば、そこで断るのはやむを得ません。でも、空いているのに断ったら患者さんにも迷惑をかけるし、病院の経営としても困ります。だから私のほうでも手術の予定を把握して、気になった場合はすぐ確認ができるようにしています」。

この日は1〜2カ月に1回実施しているラウンドの日。定期的に病院全体を回って、気になったことをチェックし、施設の改善や現場への指導につなげています。
國見さん「汚れているところがないか確認したり、危険なところに物が置かれていないか、物品の整理整頓ができているかなどを見ていきます。みんな忙しいので、いつの間にか煩雑になっちゃうんですよね。だから、定期的に一歩下がって見ることが大切なんです」。
ラウンドは毎回、看護部長と副部長、リハビリテーション部の部長代理も一緒に回ります。こうすることで、改善点を直接その場で伝えることができます。また、状況をすぐに確認できるメリットもあります。






「細かいところまできちんと配慮しないと、選ばれる病院にはなれない」と國見さん。事業計画を考えたり、病院の経営方針を決めたりと大きな判断をするのも事務長ですが、こうして病院の日常を見守り、細部まで整えていくのも大切な仕事なのです。
“看取りの病院”から安心して家に帰れる病院へ

2016年の病棟建て替えとともに診療体制を一新した西宮回生病院。当時、兵庫医科大学で整形外科の主任教授だった吉矢 晋一先生が退官するタイミングで、現院長の福西 成男先生と共に西宮回生病院へ来てくれることになり、整形外科とリハビリテーションに特化した病院への転換を目指したのです。そのほか、内科・小児科・脳神経外科・外科・皮膚科も新たに設置。急性期医療から外来診療、回復期医療に至るまで、「地域のかかりつけ医」として必要な機能を多面的に備えました。
現顧問の吉矢先生は膝関節、現院長の福西成男先生は股関節のスペシャリストとして、全国的に知られる医師です。そこで、大学病院と同等の設備と機能を備えた広いオペ室を用意。人工関節手術をメインに据え、半月板損傷やアキレス腱断裂などのスポーツ障害・外傷、高齢者の転倒骨折なども受け入れています。競技復帰までを包括的にサポートするスポーツ整形外科にはプロのアスリートも受診に来るほど。プロサッカークラブのガンバ大阪とはパートナー契約も結んでいます。

國見さん「西宮回生病院では、しっかりとリハビリをしてもらい、安心して家に帰っていただくことを目指しています。強みはやはり、外来に加えて、入院して手術やリハビリができ、さらに退院後も、外来リハビリや通所・訪問リハビリなどを包括的に提供できるところです。また、通常は手術とリハビリの主治医は変わるものですが、西宮回生病院では退院するまでずっと同じ医師が診ることになっています。こうした点も安心していただけるのではないかと思います」。
かつての西宮回生病院は医療療養病棟がメインで、長期入院される患者さんがほとんど。家に帰れないまま亡くなられる方も多く、地域には「看取りの病院」というイメージがありました。ところが現在では、病棟全体の在宅復帰率は9割を超えているそうです。
國見さん「病院のあり方も地域の人たちからのイメージも180度変わったと思います。整形外科とリハビリに力を入れて、在宅復帰を目指す。スタッフの比率も、看護師90名に対してセラピストは120名と数が逆転しました。やりたいことが明確だから、セラピストの入職希望者も非常に多く、やる気があって優秀なスタッフが集められるようになっていることも、提供する医療やリハビリの質の向上につながっています」。
思ったことは全部言う。やるべきことは全部やる。

おじいちゃんとおばあちゃんが大好きだったという國見さんは、2002年、徳島県にある、グループの介護老人保健施設「平成アメニティ」に介護福祉士として入職しました。2年目には、神戸市長田区にできる「ヴィラ光陽」の立ち上げを経験。入職早々に抜擢されたのは「たぶん、僕が生意気な新人だったから」と國見さんは笑います。
國見さん「僕は思ったことは全部言うし、やるべきことはちゃんとやっていきたいタイプ。1年目から効率化できることがあれば提案して、仕事のやり方をどんどん変えていきました。自分がやることに対して『なぜ?』ということを常に考えながら働いていたと思います。それは今でもそうかもしれません」。
平成アメニティにいた10年間は、複数の介護施設の立ち上げに関わったほか、施設の業務改善を依頼されるなど、現場業務と管理業務の両方を担う日々が続きました。2012年に、グループ本部の介護福祉事業部に異動すると、関西圏の介護老人保健施設9カ所を統括するエリアマネージャーに。西宮回生病院には、最初は介護のヘルプスタッフとして来ましたが、新病棟の建て替え計画がはじまるときに、介護士兼病院事務のサポートとして勤務することになったそうです。
國見さん「ずっと介護施設で働いてきたので、病院での勤務は西宮回生が初めてでしたし、もちろん病院事務も初めて。だから、最初の建て替えのときは何をどうすればいいかまったくわかりませんでした。僕は、新病棟ができるまでの間、どうやって診療を維持するかを考えることになりました」。
2015年秋からは神戸平成病院の事務長になりましたが、翌年8月には、建て替え工事が始まって多忙を極める事務長の補佐という形で、再び西宮回生病院へ。2019年には事務長に就任しました。しかし、もともと介護がやりたいと思って入職したのに、事務職に変わっていったことに違和感はなかったのでしょうか。
國見さん「僕は何でも面白がれるタイプなんです。与えられた仕事はしっかりやりたいと思ったし、事務的なことも誰かがやらないと、現場が回らなくなりますよね。そこがちゃんとしていないと間違いやリスクの元になるので、これもすごく必要な仕事だと思って取り組んできました」。
役割が変わっても、目指している場所は同じ。必要とされる場所で、國見さんは自分の力を発揮していきました。
みんなと話し合ってものごとを進めるほうが面白い

西宮回生病院の事務長に就任してから取り組んだプロジェクトで、もっとも大きかったのは、2023年に完了した南館の新築と大原病院の合併でした。同じ医療法人だった尼崎市の大原病院は老朽化が激しく、建て替えも難しい状況。残っていた旧病棟を壊して新たに南館を新築し、大原病院の患者さんを受け入れることになったのです。これを契機にますますリハビリテーションに特化していく姿勢を打ち出しました。
國見さん「建て替えは2度目だったからか、フロアの動線イメージはつきました。収納を増やしてもらったり、レイアウトを変えてもらったり、コンセントの位置まで、一つひとつこだわって決めましたね。それから、スタッフにも意見や要望を聞いて反映させました。グループの武久代表も現場から意見が出ているなら変えていいというスタンスで、自由にやらせてもらえたのはすごく大きかったです」。
「事務長という仕事の面白さは、みんなと話し合いながらものごとを進めていくところ」だと國見さん。
國見さん「僕は正直、自分でなんでもやってしまう傾向があるんですが、それだと蓋を開けたときに思っているのと違ったり、全然進んでいないことがよくあるんです。自分ひとりががんばったところで限界があるし、みんなに同じ方向を向いてもらわないと、病院が良くなっていかない。なぜそれをやらないといけないのか、各責任者がわかったうえで取り組んでくれると、ほかのスタッフにも意図が明確に伝わって成果が上がりやすいと感じます。病院の運営に参加していることが実感できると、みんなもどうしたらいいかを自分で考えてくれるようになるんです」。

より良い組織づくりの一環として、近年は職員の働きやすい環境づくりにも力を入れてきました。ユニークなところでは休憩室にトレーニングマシーンを置き、誰でも使っていいことに。これが大好評で、「みんながムキムキになって制服のサイズが上がっていくのが悩み(笑)」だそう。さらに「プロテインをつくれるようにしてほしい」という要望を受け、マシーンのすぐ横に無料のウォーターサーバーを設置予定です。
ほかにも、「制服のシワを伸ばしたい」と言われて更衣室にハンディアイロンを設置。患者さんも職員も利用できる傘の無料貸し出しも開始しました。一つ一つは小さなことですが、逆にいうと一人ひとりの小さな声に耳を傾けていなければ気づかない配慮です。
國見さん「スタッフががんばってくれているから病院が成り立っています。だからこそ、何らかの還元はしたいし、意見や要望として上がってくることには可能な限り応えたい。それは同時に、患者さんの利益にもつながると思うんですね。スタッフにしょぼーんとした顔でリハビリされてもがんばろうと思えないですよね。であれば、スタッフが明るく気持ちよく働ける環境を整えることで、患者さんにも明るく接してもらいたいと思っています」

根底にあるのは、患者さんに寄り添う「ケア」の視点

事務長は、病院運営がつつがなく進むよう、さまざまな業務を担ってます。一方で、介護福祉士だった國見さんだからこそ持っている視点が、西宮回生病院の運営には生かされています。それが、患者さんに寄り添う「ケア」の視点です。そのことがわかる一つの事件をご紹介しましょう。
介護施設では、原則禁止である身体拘束。ところが病院では、安易に身体拘束をしてしまう状況が見受けられることに、國見さんは憤りを感じていました。
國見さん「『おむつを外しちゃうから』という理由ですぐに拘束していたんです。僕からしたら、便をしたら気持ち悪いからおむつを外すのはしかたない。自分だっておむつで便をしたら履いたままではいられないから絶対脱ぐと思います。あまりにも腹が立ったから、身体拘束する用具を全部捨てたことがあるんです(笑)。『こんなものがあるからあかんねん!』って」。
通常は、現場の方針として身体拘束を減らしていくものですが、西宮回生病院では事務長である國見さんが率先してやめる流れを作り出したのです。「それぐらい本当に嫌だったんです」と國見さんは言います。
國見さん「つなぎタイプの拘束着を着せたまま車椅子に乗せて食堂やホールに連れてくるのも、僕は虐待としか思えませんでした。せめて嫌な思いをしないようにカーディガンを羽織ってもらうとかひざ掛けをしてあげるとか、それぐらいの配慮はできないのかと。患者さんは、身体拘束されることを望んでいるわけじゃない。認知症の方だって、なりたくて認知症になっているわけじゃない。そういうことを、スタッフのみんなにはわかってほしいと常々思っています」。
ちなみに現在は、看護部長とも話し合い、命に関わる場合にどうしても拘束が必要になることを踏まえ、抑制ミトンなどは用意しているそう。ただし、安易に使用することがないように、看護管理室で厳重に保管し、どうしても必要なときは師長が取りに来るルールにしています。その結果、西宮回生病院の身体拘束率は極めて低く抑えられています。
國見さんは「なぜ?」と思ったことをそのままにしません。患者さんの尊厳を守り、入院生活をストレスなく過ごしてもらうこと、そして治療に専念してもらい、安心して家に帰ってもらうことを第一に、病院のあり方を決めてきました。

國見さんの目標は「兵庫県の神戸から西宮の間で『整形外科といえば西宮回生』と、誰もが思う病院にしていく」こと。そのためにも、やることは山積みです。例えば、医療とリハビリの質の向上についてもまだまだ手を緩めることはできません。
國見さん「今、看護部長と話し合っているのは、患者さんが安心して家に帰るためには、リハビリナースが看護面からどう関わり、どのような取り組みをしたら良いかということです。看護師だけではありません。薬のコントロールによって覚醒機能が変わってくるから薬剤師さんも大切ですし、リハビリをやってもご飯の量が少なかったら筋力が落ちるから、管理栄養士さんも大切です。いろいろな職種が専門性を発揮してチームでリハビリに取り組んでいくことで、ますます質の高い医療サービスを提供していきたいと思っています」
「たくさん病院がある中で選ばれるには、現状維持で満足せず、先を見て走り続けないといけない。だからきっと、やりきったと思うことはないですね」と國見さん。介護の現場から病院の事務長へ。その紆余曲折の旅の中で得たたくさんの知見や経験が、西宮回生病院の未来を切り開いていきます。
プロフィール

ライター
平川友紀
ひらかわ・ゆき
フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。
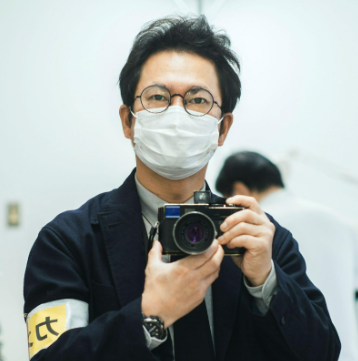
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





