病院で働く人といえば、医師や看護師をはじめとする医療従事者たちが真っ先に思い浮かびます。しかし、組織としての病院という視点で見るとどうでしょうか。病床数が100を超える病院には、数百人規模の職員が働いています。人事や広報、施設管理、職員が働きやすい環境づくりなど、病院全体の管理・運営を担う人たちがいなければ病院の経営は成り立ちません。
今回の特集記事では「医療の現場を支える」をテーマに、ふだんは裏方に徹している事務長にフォーカスすることにしました。ただ、彼らの仕事はあまりに広範囲かつ多岐にわたっているため、その全貌を紐解くべく「事務長って何をする人なんだろう会議」を開催。平成医療福祉グループ 医療事業部部長の田村大輔さんと4人の病院事務長に、事務長のやりがいと苦労、それぞれが思い描く病院の未来を語っていただきました。
事務長のお仕事、基本の「き」
一般的に、病院の事務長とは「バックオフィスの事務方トップ」とされていますが、平成医療福祉グループの事務長は「管理部門のトップ」。同グループ医療事業部部長の田村大輔さんは「病院全体をマネジメントする仕事であり、より良い病院づくりの先導役」だと言います。
田村さん「病院の管理部門のトップとして、病院長や各部門長と連携しながら、経営・運営全般に関与する役割を担います。具体的には、経営・管理業務、人事・労務管理、診療報酬・保険請求、用度品管理、建物・設備管理、患者サービス・地域連携、法務・コンプライアンス、経営改善・病院改革、プロジェクトの企画・運営、などなど。職務の範囲は広く、すべてを完璧にこなすのは至難の業です」。
たとえば、経営面にも深く関わるのが主な収入となる「診療報酬」。病院は、厚生労働大臣が診療行為ごとの点数を定める「診療報酬制度」の枠組みのなかで経営されます。言い換えれば、どれほど良いケアをしていても、診療報酬制度で認められていなければ収入にはなりません。しかし、同グループの病院では、患者さんに必要だと判断すれば、点数がつかないリハビリなどを行います。
より良いケアを続けるためにはもちろんお金も必要。事務長にはベッド稼働率を一定以上に保つという責任も課せられています。

田村さん「医療機関としては、地域のニーズに応えて困っている患者さんはできる限り受け入れたいですし、経営面から見てもベッドの稼働率を高めることは大切です。しかし、経営面を優先するあまりスタッフのキャパシティを超えてしまえば、医療の質が低下してしまい、ひいては地域のニーズにも応えられなくなります。医療の質と経営のバランスがいわば“両輪”となって、患者満足度だけでなく職員満足度を向上させて病院全体を支えるのです。そして、自分たちが目指す病院の姿を実現するには、毎日のように発生する課題を一つひとつ解決しなければいけません。なぜその課題が起きるのかを突き止め、スタッフのモチベーションを維持しながらうまく解決へ導くことこそが、経営面を担う事務長の腕の見せどころだと感じています」。
グループが目指す医療の質を保つこと、スタッフがモチベーション高く働ける環境づくり、そして病院経営に必要な収益性など、ときとして相克する目標をどのように両立させているのでしょうか。
田村さん「たとえば、『人手が足りない』という課題がある場合、単純にスタッフの配置を増やすのではなく、しくみの工夫による効率化や病棟スタッフのスキルアップなどによる解決も考えることもあります。それには、目の前の課題に対応すると同時に、組織づくりや施設や医療機器などのハード面の整備なども視野に入れて、中長期的な経営計画を練っていく必要があります」。
なんとか、事務長の仕事の基本の「き」のあたりまで理解できたような気がします。それでは、現役事務長のみなさんに、より具体的な仕事ぶりをうかがってみたいと思います。
“新宿駅”のようにタスクが同時進行する
まず、事務長は1日にこなすタスクの数が非常に多いお仕事です。関わる部署が多いため、ミーティングの数も他の追随を許さないレベルです。世田谷記念病院の事務長・手老航一さんが、複数のタスクが同時進行するようすを「16本のホームをひっきりなしに電車が出入りするJR新宿駅」にたとえると、他の事務長たちは深くうなづきました。

手老さん「どれがメインの仕事というわけでもなく、新宿駅のように1番線から16番線まですべてのタスクが同時に走っている感覚です。ときには『今、5番線はどうなってる?』とリマインドもしないといけない。そのうえでみんなの意見が出てくるように投げかけたり、吸い上げたりしながら、病院の方向性を定めていくイメージですね」。
入院している患者さんがいる限り、病院は24時間、365日休むことは許されません。患者さん一人ひとりに合わせたケアを目指すほどに、現場スタッフの仕事は複雑になりその都度判断しなければいけない課題も出てきます。「事務長の仕事はなんでも屋さん」だと言うのは、西宮回生病院の事務長・國見祐季さんと大内病院の事務長・岡師明さんです。

國見さん「病院にはたくさんの部署がありそれぞれに困りごとが起きます。部署内で解決できないときに、『ちょっと事務長、聞いてくださいよ』と言われるんですね。現場の人たちが困っていると、最終的には患者さんに迷惑をかけるので、いったん受け取ってできることはするようにしていて。対応に追われるうちに『あれ、今日は何してたっけ?』って1日が終わることもあります」。
岡さん「僕の事務長の仕事の定義は『診療に関わること以外すべて』。本来、病院全体を俯瞰して円滑に運営できる組織づくりをすべきですが、『今すぐ、ここに人手が必要だ』となれば、自分の仕事の優先順位を入れ替えてできることをやります。ちょっと極端な例ですが、大内病院で新しい建物ができたとき、厨房の人が足りなかったので皿洗いに入ったこともあります」。
事務長は、先導役としてどっしり構えるだけでなく、病院内で起きる大小の課題を解決する機動性の高さが求められる場面もあるのです。
さまざまな職種と部署をファシリテートする
病院は、さまざまな国家資格をもつ専門職が集まってくるという意味で、ちょっと特殊な場所でもあります。堺平成病院の事務長・雨松里美さんは「それぞれの職種に合わせてアプローチの方法を工夫している」と言います。

雨松さん「職種によって視点のもち方も異なりますし、スタッフそれぞれに個性があり、主張したいことや考え方があります。一人ひとりが最大限に力を発揮できるよう、事務長にはそれぞれに合うアプローチで調整する役割があります。同じことを伝えるときも看護師さんと検査技師さんではちょっとアプローチ方法を変えてみることもあります。また、事務長が直接現場の人たちに伝えるよりも、同じ部署の上長から伝えてもらう方が立場も近いし理解しやすいです。まずは看護部やリハビリテーション部の部長と納得いくまで話し合ってから、スタッフに指導してもらうようにしています」。
岡さんは、「事務長は病院全体の運営方針を決める際のファシリテーター役」でもあると言います。各部署との関わりにおいても、関わり方やコミュニケーションの取り方は状況に合わせて変えているそうです。

岡さん「明らかにうまくいっていない部署に、何度もアプローチをかけたけれども改善されないときには、トップダウンになってもいったん方向性を示すことも必要です。その一方で、こちらからの提案に対してどんどん活発に意見が上がってくる部署であれば、情報共有をしてもらうだけでいいこともあります。人に対しても、部署に対しても関わり方にはかなり濃淡があります」。
國見さん「方向性を決めて進めるときに、トップダウンで落とすと『やらされている感』が出てしまいます。やはり、現場で働く人たちに課題感を共有したうえで導いていくようなコミュニケーション力が必要だなと思います。病院は従業員数も多く、またいろんな考え方をもつ専門職が集まっています。それぞれの意見をちゃんと吸い上げて、その意見が病院の方向性にどう影響するのかまで引っ張り出していきたいと思っています」。
事務長のみなさんに共通するのは「強制はしない」という姿勢。言葉の端々から「どうすればスタッフのやる気を引き出せるのか」を常に考えているのだなと感じました。
進むべき未来をひとつずつ実現する
困っている部署のヘルプ、部署ごとの課題解決、バックオフィスのマネジメントから経営計画までーー聞けば聞くほど事務長の守備範囲の広さには驚かされます。では、「ここだけは事務長にしか担えない」と感じているのはどんな仕事なのでしょうか。
岡さん「病院の未来みたいな感じでしょうか。事務長として、病院全体がうまくいっているかどうかを見ていきつつ、これから先に病院が進んでいくべき未来を描きながら、その未来に対してどうやって今を近づけていくのか。そのためのしくみをつくり、具体的な取り組みを実行していくことが肝心なのかなと思っています」。
病院の新設や建て替えも、事務長が中心になって動かす大きな仕事です。2023年3月下旬に西宮回生病院の病棟建て替え事業を終え、同年5月に大原病院との合併を完了したばかりの國見さんは、「めったにできない経験をさせてもらえた」と話します。

國見さん「病院の建て替え事業は何十年に一度のこと。経験値もなく、誰に何を聞けばいいかもわからないなかで、事業として絶対に失敗するわけにはいかない。本当に悩み続けましたが、完成してから地域から選ばれる病院になれたと実感したときのやりがいもまた大きかったです。また、建て替え事業の経験によって身についた能力は残るので、その後はいろんな仕事の展開が早くなったのを感じています」。
雨松さんは、2024年7月に堺平成病院の地域包括ケア病棟を地域包括医療病棟へと転換する事業を終えたばかりです。
雨松さん「病棟の機能転換は初めての取組みでしたが、何度もチームで集まり、色々と不安を解消していき前向きに取り組んでいけました。結果、転換して収益もUPできました。事務長が一番責任を負うのは経営管理。収支の面だけじゃなくて、どんなことをすれば、病院はうまく運営できるのかを考えるのも経営のひとつですし、そこに向けて達成させていくのが事務長の責任だと思っています」。
未来を描くだけでなく、その未来を実現するために誰と何をするのかを考え、結果を出すところまで責任をもつ。田村さんは「事務長にはそれだけの権限が与えられている」と言います。
田村さん「たとえば、病院の体制を強化したいと思ったら、計画に基づいて論理的に説明し、決裁が通ればスタッフの採用や設備投資、備品購入など柔軟に意思決定できます。これは、病院全体の運営に携わり、地域に信頼される真に良い病院づくりの根幹から主体的に関わることができる事務長ならではの役割です。権限がある分、責任も重く、うれしいことも耳の痛いこともダイレクトにフィードバックが返ってくるため大変な面もありますが、だからこそ成果や変化を自分や組織に直接感じられるやりがいがあります」。
これからの地域と病院の関係性をつくる
高齢の患者さんのリハビリテーションや療養に取り組む同グループの病院は、訪問医療などを通じた退院後の支援や在宅医療との連携にも取り組んでいます。病院の未来を考えるとき、地域との関わりはどの病院にも共通する大きなテーマです。

田村さん「従来の病院は病院単体で成り立っていたと思うのですが、今は病院だけではなく地域で人を見ていく流れがあります。その背景には、超高齢化が進むなかで病院だけでは患者さんを見ていけないという現実があります。地域を主体とした視点をもちながら、これからどんな病院像を描いていけるのか?というテーマに向き合っています」。
すでに、それぞれの病院では地域との関係づくりが進んでいます。雨松さんは、地域で在宅医療に取り組むクリニックとの連携を進めています。
雨松さん「地域の在宅医療を担う方たちといい関係がつくれると、在宅医療で治療をしている地域の患者さんに、何かあったらすぐに病院に来られる安心感を与えられます。実際に地域のクリニックさんから、安心できると言っていただいたりもします」。
手老さんは「世田谷区の野毛地域」あるいは「東京都西南区医療圏」という地域における、世田谷記念病院の役割について考え続けています。
手老さん「日本には医師の偏在*という課題があります。地域が面になってみんなが幸せになるために、僕らは医療プレイヤーとして、病院はインフラとして何を提供できるかを考えないといけないと思っています。もしも、世田谷記念病院の地域に関わる取り組みがうまくいけば、他の地域で真似してもらえたり、『いい取り組みだから点数にしよう』と診療報酬制度に反映されたりするかもしれません。そのためには、地域のより多くの方々の顕在ニーズや、ときには〝潜在的なニーズ〟にも幅広く応えていきつつ、地域と関わることが大事なのかなと思っています」。* 地域や診療科によって医師数に偏りがあること。
田村さんは「事務長の資質として必要なのは物事を多面的に理解する柔軟な姿勢と対応力」だと言います。同グループの事務長は、それぞれに描いている病院の未来を実現するために、今日も膨大なタスクに立ち向かっています。次回以降は、本記事に登場した事務長の病院を訪問し、それぞれの取り組みについてお話を伺っていきます。
プロフィール
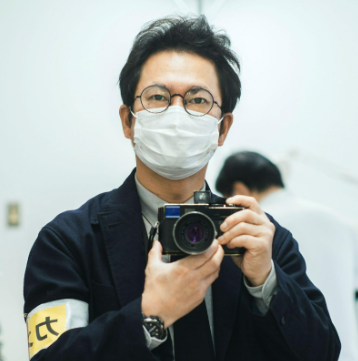
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。

フリーライター
杉本恭子
すぎもと・きょうこ
京都在住のフリーライター。さまざまな媒体でインタビュー記事を執筆する。著書に『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)、『まちは暮らしでつくられる 神山に移り住んだ彼女たち』(晶文社)など。





