大阪府堺市にある「医療法人恵泉会 堺平成病院」は、救急医療から外来診療、回復期・慢性期医療に在宅サービスまで、幅広い機能をもつ「地域密着型多機能病院」です。地域医療のハブとなり、周辺の医療・福祉事業者とも連携しながら、地域全体で患者さんをサポートしていくことを目指しています。
「医療の現場を支える」をテーマに、ふだんは裏方に徹している事務長にフォーカスする特集記事の第3回にご登場いただくのは、2020年9月から同病院の事務長を務める雨松里美さん。「堺平成病院のことが好きだから、いいところをいっぱい言いたい」と笑顔で話してくれる雨松さんに事務長として取り組んできたこと、大切にしている価値観や考え方について伺いました。
<プロフィール>
雨松 里美(あめまつ・さとみ)
医療法人恵泉会 堺平成病院 事務長。アパレルメーカー勤務を経て、医療事務の仕事に就く。2018年に堺平成病院の前身となる堺温心会病院に入職。2020年1月から事務長補佐と医事課係長を兼任。2020年9月より事務長に
地域の人々の生活を支える「地域密着型多機能病院」として
堺平成病院は、堺市内にあった「堺温心会病院」と「浜寺中央病院」が合併し、2019年4月に開院した新しい病院です。さまざまな科の外来診療や軽症・中等症の救急患者の受け入れ、各種在宅サービスのほか、堺温心会病院が力を入れてきた人工透析療法に携わり、多数の透析患者さんの治療を行ってきました。

入院病棟には、地域の急性期の病院で治療を受けたのち、社会復帰のためのリハビリを行う「回復期リハビリテーション(回リハ)病棟」のほか、入院に条件と期限がなく、中長期の療養が必要な患者さんを受け入れる「医療療養病棟」、重度障害・難病患者さんの長期療養や透析治療を行う「障害者施設等一般病棟」、そして2024年度の診療報酬改定で新設した「地域包括医療病棟」という4つの病棟があり、患者さんの状態やニーズに応じたさまざまな対応を可能としています。
このように、堺平成病院は地域医療に必要な機能を多角的に備え、地域の人々の生活を支えてきました。
雨松さん「堺市は、以前から医療機関の機能分化が進んでおり、各医療施設や福祉施設の連携がしっかり取れている地域です。そのため、病院単体ではなく『みんなで地域の健康を守っていく』という意識があります。その中でも、堺平成病院は『地域の患者さんは絶対に守る』をモットーにやってきました」。
例えば、力を入れてきたのが救急医療です。この規模の病院としては珍しく、救急の専門医を配置し、絶対に受け入れを断らない体制をつくってきました。
雨松さん「急性期病院でないと対応が難しい患者さんはそちらに行ってもらいますが、それ以外の患者さんはたらい回しにさせないという考えのもと、軽症・中等症の患者さんは可能な限り受け入れています」。
常に“患者ファースト”の精神のもと、地域の医療を支え続ける堺平成病院。その魅力を雨松さんはこう語ります。
雨松さん「すばらしいと思うのは、患者さんが早く家に帰って日常生活を送るためにどうするかを第一に考えているところです。そして、それを実現するために、しっかりとチーム医療に取り組んでいます。職員みんなが、一人ひとりの患者さんのことを真剣に考えて向き合っているんです」。
苦手分野に飛び込んだはずが、医療事務の仕事は「天職」だった
今でこそ、堺平成病院のことが大好きだと熱く語り、事務長の仕事が楽しいと話す雨松さんですが、もともとはアパレル業界で働いていたという異色の経歴の持ち主です。販売員や店舗マネージャーとして10年ほど働いたあと「ここでできることはやり尽くした」と退職し、「どうせ転職するなら一番苦手な事務の仕事をやってみよう!」と、あえて苦手な分野にチャレンジしました。医療事務を選んだのは、接客の仕事をしてきた自分に合っているのではないかと思ったから。実際に働いてみると、これが想像以上に面白かったのだそう。
雨松さん「当時はまだ紙のカルテだったので、点数計算するために医療従事者でない私もカルテを見ることができたんですね。そうすると、この患者さんはこういう病気だから先生はこういう治療をして、看護師さんはこういうケアをするということがよくわかるんです。しかもそれを点数化する。もしも私がカルテに書かれていることを見落としたら、病院はもらえるはずの診療報酬がもらえなくなります。だから、隅々までカルテを読み込んで計算しなければならなくて、1点も逃すまいとするうちに、その作業にすっかりハマってしまったんです(笑)」。
雨松さんは、いつしか医療事務は「天職」だとまで思うようになっていました。そして最初に勤めた病院からそろそろ転職しようかと検討しているとき、ちょうど募集があったのが1年後に合併と移転を控えていた堺温心会病院でした。「どうせなら移転前のしんどいときに入って一緒に頑張ったほうがみんなと仲良くなれる」と、ここでも逆の発想ですぐに転職することに。
通常業務を行いながら、平成医療福祉グループ独自の電子カルテシステム「Aloe」導入に伴う移行作業や数十年にわたる紙カルテの仕分け、さまざまな手続きのための書類作成に患者さんの移送の打ち合わせなど移転業務は多岐に渡り、想像以上の忙しさでした。

雨松さん「最初は楽しそうだと思ってワクワクしていたところもあったんですけど、結論としては、もう二度とやりたくないぐらい大変でした(笑)。患者さんを移送するときにテレビの取材が入ったんですけど、あの映像を見たら今でも当時の大変さを思い出して涙が出ます」。
しかし、その甲斐あって、ほかの職員さんともすっかり仲良くなることができました。移転後には、医事課の係長に就任。さらに2020年1月、エリアマネージャーでもあった松木泰昭さんが事務長になったとき、事務長補佐に抜擢されます。
雨松さん「松木さんはエリア全体を見ないといけないから、週3日しか堺にいられないんですね。そこで当面、事務長補佐を立てようということになって、声がかかったんです。松木さんはめちゃくちゃ賢い人で、この人の下についたらいろいろなことを学べそうだなと思いました。それと、事務長補佐をやると、地方厚生局への届出業務がやれると言われたんです。実は、以前勤めていた病院で、少しだけそのことを勉強していたんですね。それができると言われたので『それならやります!』って言いました」。
厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面などの施設基準は、一部の保険診療報酬の算定要件として定められています。規模の大きなものから細かなものまでいろいろあり、よりよい医療の提供と経営上の観点から、どの施設基準の届出をして病院を運営していくかは非常に重要になります。
雨松さん「そのときは、それが『=経営』とまでは考えていませんでした。でも、医療事務でカルテを隅々まで読み込んで点数をきっちり数えてきたことは私の強みだと思っていたので、1点でも多く取るための仕事に興味があったんです」。
地域包括医療病棟への病棟転換に取り組む
その後、松木さんが別の病院へ異動すると、雨松さんは事務長に。そして、事務長として取り組んだ大きな改革が、地域包括ケア病棟から地域包括医療病棟への病棟転換でした。これがまさに、地方厚生局への届出が必要な取り組みでした。
「地域包括医療病棟」は、急性期と回復期の間の役割を担う仕組み。急性期医療に対応しつつ、ADLの維持・向上、栄養管理、リハビリテーションなどを一体的に提供することで、退院後の在宅復帰を目指します。これまで救急医療に力を入れてきた堺平成病院にとって、これは非常にメリットの多い仕組みでした。
雨松さん「最初にこれができると知ったときは『もらった!』と思いましたね。先ほども言ったように、堺平成病院では救急の受け入れを積極的に行っていたんです。ただ地域包括ケア病棟は、救急を受け入れても特にメリットのない病棟でした。それが地域包括医療病棟になると加算がついて診療報酬が上がる。診療報酬制度が私たちがやっていることについてきてくれたという感じでした」。
もちろん、加算の対象となるにはクリアしなければならない課題もあります。例えば、入院できる期間が21日間と短くなります。また、入院している患者さんがどの程度看護を必要としているかを測る指標「看護必要度」の基準も高く設定されていました。

雨松さん「在院日数が短くなると回転が速くなるので忙しくなります。本当に運営できるのか、現場の職員からは心配する声も聞かれました。そのため、病棟でチームを組んで、毎週会議をして、シミュレーションを何度もやりましたね。病棟スタッフから質問を受けて答える会も開催しました」。
人員配置は4病棟の中でいちばん手厚くし、1病棟1人体制の事務職員を、地域包括医療病棟だけは3名体制にしたりと、看護師さんや介護士さんの負担をどれだけ減らせるか、今も考え続けているところだそう。
しかし、この病棟転換によって、病院の収益はプラスに。患者さんの状態に合わせて病棟を移すことも可能となり、治療にもいい影響が出ています。
雨松さん「地域包括ケア病棟は、ルール上、回リハへ移ることができなかったんです。でも地域包括医療病棟であれば入院直後からリハビリができるし、必要な人はその後に回リハに移ってさらにリハビリすることもできる。これは、患者さんのことを第一に考えられる仕組みでもあると思いました」。
病院に合った仕組みを活用することで、患者さんと病院、双方にメリットが生まれました。よりよい仕組みを見つけ、活用し、ときに改革を推し進めるのも、事務長の大きな役割なのです。
患者さんや地域のためになると思うと仕事が楽しい
雨松さんは「患者さんにとっても病院にとってもいいと思うことをやっていけば、収益は自然とついてくる」と言います。
雨松さん「例えばうちの病院では、少しでも早く回復して家に帰ってもらうほうがいいと考えているので、管理栄養士さんが病棟ごとについてしっかりケアするし、たくさんリハビリができるように療法士さんもたくさん配置しています。その結果、退院が早まる患者さんもいるんですね。正直、患者さんに長く入院してもらったほうが経営的には楽なんです。でも少しでも早く日常を過ごしてほしいという思いがあるから、在院日数はなるべく短くしていきたい。そうなると、空いたベッドには次の患者さんに入ってもらわないと経営的に厳しいので、急性期病院へ営業に行くんです。でもそこさえきちんとやれば、提供したい医療が提供できて、収益も上げることができる。営業も、患者さんや地域、病院のためになると思ったら、やっていて楽しいんです」。
「私が『みんなにうちのいいところを伝えたい!』という思いで行くので楽しいところもあると思います」と雨松さん。その思いが膨らんで、広報誌「さかへい」の編集やイベントのチラシの制作なども自ら手がけるようになったそう。「さかへい」を読むと、堺平成病院がどんな医療に取り組んでいるのか、堺市全体でどのような地域医療連携の仕組みが構築されているのかがよくわかります。このまちに住んでいれば医療の不安はないという安心感が広がります。

雨松さん「救急や透析、外来、それから4種類の病棟をもっているのも、地域のどんな患者さんであっても受け入れる体制をつくろうと思ってやってきたから。ここからは、それをもうちょっと発展させて、住民のみなさんと一緒にいろいろなことをやっていきたいと思っています。今は『堺フェス(仮)』という大きなイベントをやろうと計画中です。地域の人たちに私たちの取り組みを知ってもらえれば、病院がもっと気軽に来れる場所になるのではないかなと。そうしたら、在宅で療養されてる方も、何かあっても堺平成があるという安心感をもって過ごせるようになる。病院の中身が固まってきたからこそ、ここから先は、地域とのコミュニケーションがカギになると思っています」。
事務長として一人で走っているわけではない
雨松さんが事務長という職に就いてはや4年が経ちました。事務長の仕事は、やりたいことややるべきことが次々に出てきて、終わりが見えないと話します。
雨松さん「事務長は、自分が堺平成病院でこういうことをしたいとか、こういう病院にしたいと思ったら、それが実現できる仕事なんですね。というか、実現するためにいっぱい努力ができるんです。それが面白いのだと思います」。
理想を実現するために努力ができること自体を喜びとして仕事に取り組む雨松さんの姿勢は、病院全体の雰囲気にも影響を与えているように感じます。「みんなを引っ張っていくというより、みんなをまとめて一緒にやっていくのが好き」と言うとおり、堺平成病院は、何事もチーム一丸となってさまざまな取り組みを進めていく気風があるのです。

雨松さん「堺平成病院は職員同士の仲が良くて、やるとなったら一致団結してがんばるんです。だから今も『こういうことをやりたいんだけどどう思う?』と看護部長やリハビリテーション部の部長によく相談に行っています。私一人じゃ何にもできません。医療のことも看護のこともわからないのに、これをやってくださいなんて上から言うのはおこがましいです。それよりも部長さんたちと話して納得して取り組んでもらえれば、ほかの職員にも熱意をもって伝えてくれるだろうと思っているんです。 先日の座談会で、世田谷記念病院の手老さんが事務長の仕事を新宿駅のホームに例えていましたよね。私の場合は一人で16番線を全部見るというよりは、各ホームに担当の駅員がいて、みんなに助けてもらっている感じなんです。安心して任せられる人ばかりだから、私は振り分けを決めて、確認したり相談したりすればいい。事務長として一人で走ってるわけではないから、楽しみながらやれているのかなと思います」。
雨松さんの行動の根底には、常にこの病院が好きだという気持ちと職員一人一人に対する強い信頼がありました。「好き」と「信頼」を原動力にしているからこそ、多くの人にその純粋な思いが届き、理想を実現してこられたのだと思います。この先、より地域に開かれた病院になっていくための試みも、みんなで力を合わせて実現していくのでしょう。これからの堺平成病院の広がりが楽しみです。
次回は、西宮回生病院 事務長の國見祐季さんにお話を伺います。
プロフィール

ライター
平川友紀
ひらかわ・ゆき
フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。
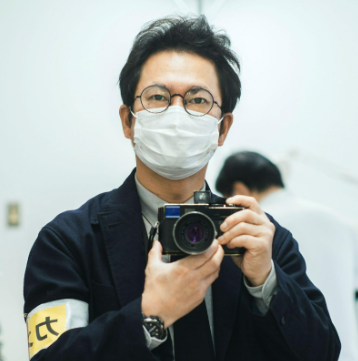
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





