2012年、東京・二子玉川で開院した医療法人平成博愛会 世田谷記念病院。
平成医療福祉グループが長きにわたり慢性期医療に取り組んできた知見を生かし、当時はまだ珍しかった回復期リハビリテーション機能を中心に据えて構想しました。地域医療のハブとなる「地域密着型多機能病院」を目指し、地域の医療・福祉事業所や行政との連携も進めています。
現在、同病院の事務長を務める手老航一さんは、製薬会社のMR、医療系人材事業会社などを経て、「医師の偏在」という課題に向き合うなかで、「地域密着型多機能病院」というコンセプトに深く共感して同グループに入職。2020年から、世田谷記念病院の事務長として活躍しています。
「医療の現場を支える」テーマに、ふだんは裏方に徹している事務長にフォーカスする特集記事、第2回は手老さんにインタビュー。これまでの4年半に取り組んできたこと、世田谷記念病院、そして世田谷という地域に思い描く未来についてお話を伺いました。
<プロフィール>
手老 航一(てろう・こういち)
世田谷記念病院事務長。製薬会社のMR、ヘルスケアメガベンチャーでのHR事業、経営支援事業などを経て、2020年に入職。
回復期・慢性期医療には、患者さんが本来あるべき姿に戻っていくことを支援する大事な役割がある
世田谷記念病院は、2011年にアメリカのLTAC(Long Term Acute Care=長期急性期医療)病院を視察した平成医療福祉グループ武久洋三会長が代表だった当時、「東京に日本版LTACをつくろう」と設立した病院です。
当時の日本では、急性期治療が終了した後も患者さんが長期にわたり急性期病院に継続入院していることが多く、救急現場は疲弊し、患者さんは必要なリハビリを充分に受けられない状態でした。アメリカでは高度急性期病床の平均入院日数は5日ほど。その後も継続治療が必要な場合はLTACで治療するという流れです。「患者さんの自宅復帰を支援するには、日本独自のポスト急性期ケア病床を充実させ早期にリハビリを始めることが必要だ」というのが会長の考えでした。
それを体現するため、2012年、回復期リハビリテーション病棟と医療療養病棟を備えた病院として開院し、ポストアキュートケア(急性期治療を終えた患者さんの受け入れ)とサブアキュートケア(在宅患者さんの緊急受け入れ)を行えるようにしたのです。

手老さん「回復期・慢性期医療は、急性期医療よりも診療報酬が低く、専門性や役割の観点から一部の専門職からは特に注目もされにくいとともに、医師も集まりにくい。でも、回復期・慢性期は、患者さんが本来望む姿に戻っていくことを支援するという、大事な役割を担っています。制度も変わるべきだし、医師のキャリアとしてももっと評価されるべきだと洋三先生は考えていたんですね。前職で医療機関の医師採用支援をしていたとき、当時グループの副代表だった武久敬洋先生からそんな話を聞く機会があり、まさに自分が考えていたこととドンピシャだと感じました」。
もともと、都市部や急性期に医師が集中し、本当に必要とされている場所に対して医師が足りていない、「医師の偏在」と呼ばれる状況に問題意識を持っていた手老さん。業界大手の医療系人材事業会社で働きながら、医師の偏在を解決する方法を探ってましたが、「この立場からは解決は難しい」と限界を感じていたといいます。いち医療機関、事業所としてあるべき姿を体現し、医療業界に働きかけていく平成医療福祉グループの姿勢に可能性を感じ入職を決意しました。
患者中心の診療方針の徹底と経営を両立する
世田谷記念病院では、2014年に診療報酬改定により地域包括ケア病棟が世の中に誕生する前から、それに近い取り組みを行ってきました。

手老さん「診療報酬で求められていることを行うのはあたりまえのことで、これから診療報酬に追加されるであろうこと、患者さんやご家族、ときにはその地域で求められていることに先んじて取り組むのが一流の病院です。ただ、診療報酬で設定されていないということは、病院の持ち出しになるということ。持ち出しになっても取り組むには、病院の経営が安定していることが欠かせません」。
そのため、平成医療福祉グループでは病床稼働なども含め、高い経営指標を掲げています。手老さんは入職後すぐに、地域連携室のスタッフや病棟の医師やセラピストと一緒に近隣の医療機関をできるだけ訪問し、病床稼働率を満床に近づける方法を考えはじめたそうです。
手老さん「当時はベッドの空きをアピールすることが多かったようなのですが、それでは世田谷記念病院の取り組みや強みが伝わりません。そこでまずは、近隣の医療機関がどんな患者さんを抱えていて、退院支援などに難渋するケースにはどんなものがあるのか、もっと言うとどんなことで困っているのかをヒアリングしました。そのうえで、世田谷記念病院だったらそういう患者さんに対し何ができるのか、排泄や嚥下のリハビリにどう取り組んでいるのかなど、僕らの病院やグループのマインドや姿勢などもお伝えしたんです。 さらに、ご紹介いただいた患者さんが、当院でリハビリされる様子などを動画を通して共有しました。急性期病院のスタッフにとって、患者さんの退院後の様子を知る機会はあまりないものです。『あの患者さんがここまで回復したんだ!こんなに食べられるようになっている!』と喜んでくれて、次第に僕らと関係医療機関の心理的な距離が近づいていくような気がしました」。
こうした取り組みを共にしたスタッフは、自分たちの日々の活動を自信を持って説明できるようになり、世田谷記念病院の姿勢や取り組みが地域に浸透していきました。手老さんが入職してから1カ月ほどで、当時なかなか上がらなかった病床稼働率は大幅に改善し、ほぼ満床になったといいます。

手老さん「日本の医療機関の7割から8割は赤字です。『正しいことをしていれば赤字でもいい』という空気感も漂っている。でも、それはやっぱり健全ではないと僕は思います。組織としてやるべきことをやっていれば、患者さんに質の良い医療を提供してそれをきちんと伝えていけば、経営状況を安定させることはそんなに難しい話ではないように思います。 ときどき現場で働く病院スタッフから『なんでそんなに数字のことばっかり言ってくるの!?』という視線を向けられますが、『患者さん中心の医療を続けるためには、経営を成り立たせる必要があるんですよね』と対話を繰り返しています」。
病院と地域のコミュニティスペース「2Co HOUSE」
入職して以降、院内外のさまざまな人とつながること、人と人をつなげることを大事にしてきた手老さん。これまでの医療の枠組みとは違った形で、本当の意味で地域と関わっていくことにも挑戦しています。
手老さん「医療・福祉に関わる人たちのコミュニティ(SHIP… *2)や各方面の勉強会などに出席するなかで、病院が医療保険や介護保険の枠にとらわれずにできること、広い意味での健康に寄与できることはたくさんあると知りました。いわゆる、ポジティヴヘルスや社会的処方*に代表されるような取り組みです。世田谷に合う形でそれを実践できればと思いました」。
*ポジティヴヘルス 2011年、オランダの医師Machteld Huberによって提唱された新しい健康の概念。健康を「状態」ではなく「能力」として捉え、患者が自身の健康を管理する能力を支援することに重点を置く。
*社会的処方 医療従事者が患者・地域住民の健康を支えるために、その問題解決として医薬品や治療を施すのではなく、コミュニティー活動や地域とのつながりを処方して問題を解決すること
2024年6月、世田谷記念病院の斜め向かいにオープンしたコミュニティスペース「2Co HOUSE(ニコハウス)」もそうした取り組みのひとつ。二子玉川の「2Co」に、Community(地域)・Communication(対話)・Connect(つながり)といった期待を組み合わせた名称で、「病院の職員だけでなく、地域のみなさんにも気軽に立ち寄ってもらいながら、集まるみんなが“ニコっと”笑顔になれる、訪れる多くの人にとってのHOUSE(家)になりたい」という願いが込められています。


手老さん「2Co HOUSEは当初、院内に不足していた“スタッフのため”の憩いの場所として建設計画が進められました。武久代表の、『スタッフが医療職、専門職としての“鎧”を脱いでひとりの人としてつながりを生んでいく、そんな場所をつくりたい』という想いから始まっています。それを体現するのが、26人がぐるりと囲める大きなテーブルです。構想を練っていたとき、武久代表が『ここにみんなが集まっている姿を思い浮かべるだけでワクワクするよね』と話していたのが印象に残っています。 その後、『2Co HOUSE』という名前が決まり、『これを自分たちだけの家にしちゃもったいない、その対象をできる限り広げていき、“みんな”が笑顔になれる家にしよう』と話が弾み、思い描く風景に地域の人が加わるようになりました」。
現在は、スタッフの休憩スペースとしてはもちろん、地域の方々が自ら主催する和綿のワークショップや、世田谷記念病院が主催する地域の医療従事者向けの勉強会・交流会など、その使用用途は多岐に渡っています。つい最近では、入院患者さん向けの芸術療法を実施。絵を描いた経験のない患者さんが「楽しくて思わず3回も参加した」と言ったり、描かれたご自身の作品を「これ持って帰っていい? 病室に飾るわ」と喜ばれたりするようすも見られたそうです。ゆくゆくは、曜日や時間を限定して地域の人が自由に出入りしたりできる場にする構想もあるそうです。
総合診療専門医プログラムを立ち上げ、回復期・慢性期で活躍する若手医師を増やす
手老さんが世田谷記念病院に入職するきっかけとなった、医師の偏在は診療科によって医師の多寡があるというかたちでも問題になっています。ここに対しても、手老さんはグループの経営企画医師のみなさんと、現在新たな取り組みをはじめようとしています。それは、複数の医療機関と連携し、総合診療専門医プログラムを立ち上げること。
総合診療専門医とは、特定の臓器や疾患を担当するのではなく、患者を全人的・総合的に診療できる専門医を指します。「内科」「外科」「産婦人科」「麻酔科」「救急科」などの基本領域に19番目に加えられました。2021年に1期生が誕生したばかりで、日本全体でもまだ人数は多くありません。

手老さん「海外の一部の国では、“医療はインフラとしての役割を担い、それぞれのリソースがきちんと求められるところに配分されるべきだ”という考えから、各専門医の数まで決められています。日本では職業選択の自由のもと、医師がそれぞれの専門を自由に選ぶことができるため、診療科の偏在・専門医の偏在が生じます。この問題を解消する施策のひとつに、日本専門医機構を中心とした総合診療専門医を育てようとという流れがあります」。
総合診療専門医は、「地域医療の強化」「患者中心の医療の実現」の可能性を高めるとともに、回復期・慢性期医療の活性化にもつながることを期待されています。しかし現状では、回復期・慢性期病院は依然として“年齢を重ね第一線を退いた医師の活躍の場”として捉えられることが多く、若く優秀な医師が積極的に選ぶフィールドとはなっていません。
この状況を変えるべく、同グループでは総合診療専門医の育成プロジェクトに着手。世田谷記念病院も研修先になる予定です。
手老さん「グループの事情はもちろん、そういった全国の各地域で共通の医療課題の打開策として、平成医療福祉グループの文化や姿勢に共感し、医療から福祉、ときにはそういった枠組みにさえとらわれない取り組みを通して地域と関わりたい、という若手医師を自分たちで育てたい。逆に言うと、そうしないと全国各地の医療提供環境や医療機関の運営はだんだん難しくなるという危機意識を抱いています」。
2024年から構想を練り始め、現在は一緒にプログラムを組む医療機関との確認を重ねている最中。専門医機構にプログラムが認定されて順調に進めば、2026年から研修医を受け入れる予定です。
手老さん「グループの経営企画医師の方々や指導医となる先生方と協力してプログラムの準備を行っています。初めてのことですし本当に大変なんですが、この病院や地域、グループのことだけでなく、日本の医療の未来にもつながることなので、やりがいがあります」。
事務長は“みんなが思い描く未来を実現するための調整係”
患者さんに必要な医療を届けたい。日本の医療をよりよいものにしていきたい。手老さんのお話を聞いていると、言葉の端々からそんな想いが根底にあることを感じます。でも、自分や家族が大きな病気にかかったり、医療に助けられたり、といった経験があるわけではないとのこと。何が原動力となっているのでしょうか。
手老さん「こどもの頃から変な正義感があるというか、道理にかなわないことがあると『おかしいじゃん! 物事をもっと本来あるべき姿にしたい』と思っていたんです。ちっちゃなアンパンマンが自分の内側にいるというか。その延長線上に、『誰もが平等に良い医療を受けられるようにしたい』という想いがあるのかもしれません」。
そんな手老さんが尊敬する人は、株式会社マザーハウス代表取締役兼チーフデザイナーの山口絵理子さん。バングラデシュの貧困問題を解決するため、現地のジュートという生地を使って世界に誇れるバッグを作りはじめた社会起業家です。
手老さん「2008年に放映された『情熱大陸』で、バングラデシュの現地責任者が話していたことが印象に残っています。バングラデシュにはそれまでもいろんな人が支援に訪れたけど、山口さんは僕らを一人の人間として見てくれて、魚を与えるのではなく、魚の取り方を教えてくれた。自ら考えて自分の足を動かして歩きはじめる光景を一緒に作り上げてくれた。そんな人が自分たちのオーナーであることにすごく誇りを持っている。そんな言葉を聞いて、僕がしたいのはこういうことだと強く感銘を受けました」。
「自分の仕事を○○係と表現するとしたら?」――前回の事務長座談会の際にそんな質問を投げかけたところ、手老さんからは「調整係」という答えが返ってきました。その背景が、少しわかった気がします。
手老さん「グループからは、事務長としてもっとリーダーシップを発揮してみんなを引っ張っていく役割を求められているのかもしれないけど、僕は自分が前に出たいとは思っていないんです。主役はあくまでこの病院で働く医療プレイヤーや、地域のみなさんであってほしい。そのために人とつながって、人と人をつなげて、何かあったら調整するのが自分の仕事だと捉えています。みんながこの地域の未来を一緒に描いて“歩きはじめる”。そんなお手伝いが自分にできたらうれしいですね」。


同じ「事務長」という職種でも、人によって大事にしていることや動機は異なります。世田谷記念病院事務長・手老航一さんがどんな人なのか、この記事で伝わっていたら幸いです。次の記事では、堺平成病院の事務長・雨松里美さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに!
*1 世田谷記念病院サイト
*2 SHIP…
*3 コミュニティスペース「2Co HOUSE」
プロフィール

ライター
飛田恵美子
ひだ・えみこ
茨城県つくば市在住。まちづくり、多様性、福祉などの分野で執筆する。著書に『復興から自立への「ものづくり」』(小学館)。
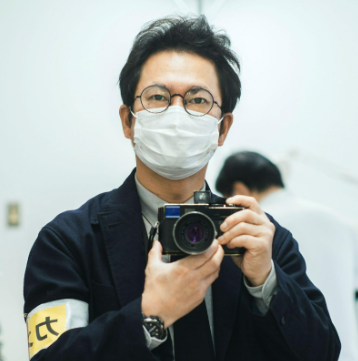
フォトグラファー
生津勝隆
なまづ・まさたか
東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。





