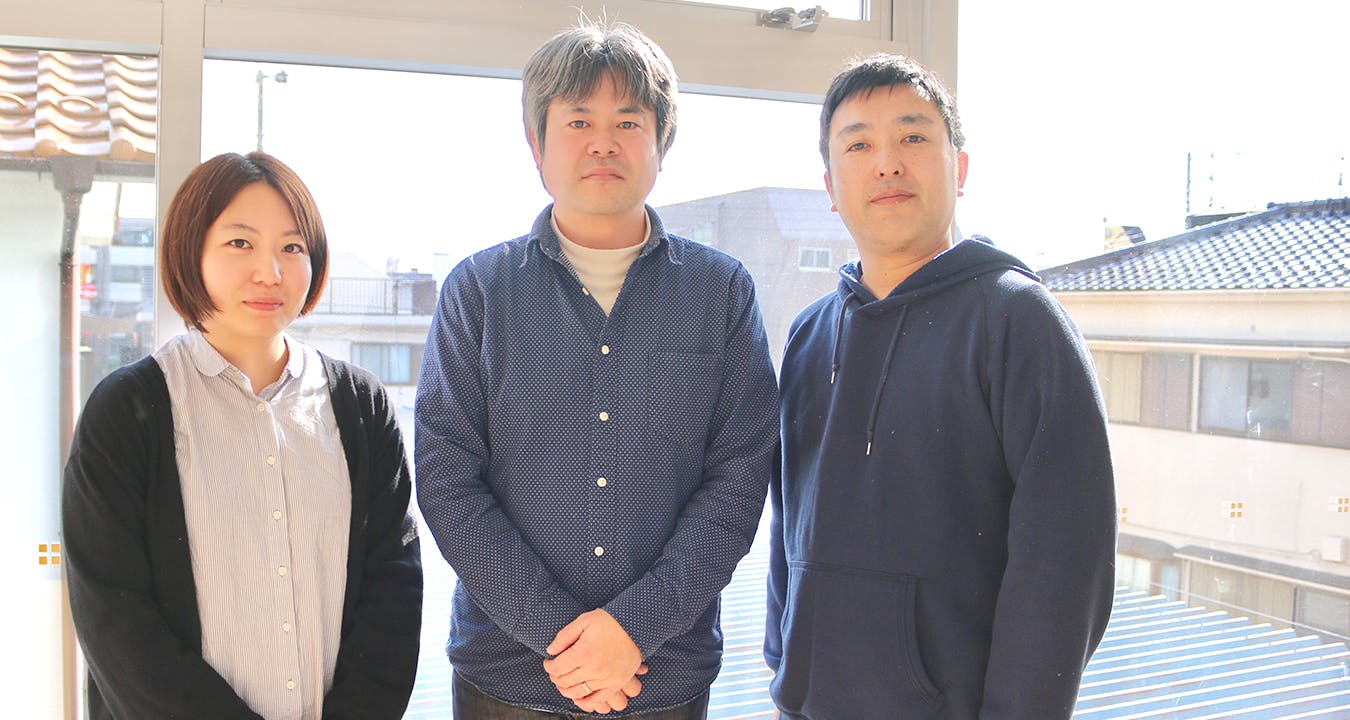社会福祉士から入職し、グループ介護部門のまとめ役に さまざまな現場を経てきた、その経歴とお仕事に迫ります!/平成医療福祉グループ 介護福祉事業部 部長/前川 沙緒里さん

社会福祉士から入職し、グループ介護部門のまとめ役に
さまざまな現場を経てきた、その経歴とお仕事に迫ります!
グループの介護福祉事業部の部長を務める前川さん。社会福祉士として入職しながら、さまざまなお仕事を歴任されてきました。今回は、まだグループの介護事業が部門として立ち上がる前の取り組みについてお聞きしています。いろいろな経験談が飛び出るインタビューは必見です!
泥を投げ、泳ぎが好きだった
出身を教えてください。
徳島県の徳島市です。
生まれ育った場所はどんなところでしたか。
田んぼに囲まれた、のどかな場所でした。
小さい時はどんなお子さんでしたか。
近所の同級生は男の子しかいませんでしたので、一緒になって田んぼとか神社で遊んでましたね。ゲームより外遊びで、木に登ったり泥を投げたり(笑)。
ヤンチャですね(笑)。学生時代は部活動は何かされていましたか。
中高生の時は、剣道と水泳をやっていました。
掛け持ちされていたんですね。
メインとして剣道部に入っていて、水泳部の方はとてもゆるかったので、大会前に合宿だけ参加して、あとはスイミングクラブで泳いでいました。
泳ぐのがお好きなんですね。ちなみに吉野川で泳いだりは…。
吉野川は流れが急で深いので、泳いじゃダメなんですよ(笑)。でもそれこそ、子どもの頃はグループの博愛記念病院の近くの川で泳いでました。
もうその頃から縁があったんですね。
同級生のおばあちゃんの家がその近くにあって、よく行っていました。岩から飛び込んだりして。
博愛記念病院のことは認識していたんですか。
いつも前を必ず通っていたので、「病院があるなあ」っていうくらいの認識でした。
阪神淡路大震災での体験がきっかけ
看護師に憧れた高校時代
福祉の道を志したのはいつからですか。
実はもともと、看護師にずっと憧れていたんです。看護体験も行って、看護学校の受験も考えていました。
看護師に憧れたのは、何かきっかけなどありましたか。
高校生の時、阪神淡路大震災のボランティアで避難所に行ったことです。大切な人を亡くされた方もいらして、家も崩れて、お風呂にも入れないような過酷な環境の中でみなさん暮らしていて。そこで、お医者さんと看護師さんのお手伝いとしてついて回っていたのですが、そんなしんどい状況のはずなのに、「ありがとう」って言ってくださるんです。自分たちが大変な時なのに、関わることで感謝の言葉をいただける仕事ってすごいなと思って、そこから興味を持ち始めたんです。
価値観が変わるような、とても大きな体験ですね。ただ、実際は看護師にはならず。
実は私、数学がとても苦手で…トラウマがあったんです。看護師の試験には数学があると聞いて、そこで諦めました(笑)。
そこがネックになったんですね(笑)。
でも「医療・福祉の仕事に関わりたい」と思って調べていたら、初めて「社会福祉士」という仕事があるということを知ったんです。

患者さん・利用者さんと社会をつなぐ
社会福祉士のお仕事
そこから社会福祉士を目指されたんですね。
こちらは試験で数学がなかったんです(笑)!
そこは大きいですね(笑)。当然、仕事としての興味もお持ちで。
もちろんありました。阪神淡路大震災のボランティアの時、思い返せば間近でその仕事を見ていたんです。それが社会福祉士さんだとその時はわからなかったんですけど。
どんな風に支援に関わっていたんですか。
高齢者の方たちのところに行って、とにかくお話を聞いていました。今悩んでること、辛いこと、なんでもお話を聞いて、何か利用できる制度があれば紹介をしたり、体調が悪いようであれば、お医者さんや看護師さんにつないだり、という関わり方ですね。
基本的な質問なのですが、社会福祉士とは具体的にどういったお仕事でしょうか。
基本的には相談役として、患者さん・利用者さんを、いろいろな機関や制度につなげるのが仕事です。例えば病院であれば地域連携室に入って、患者さんをほかの病院や、退院後のサービスにつないだり、公的な補助についての相談役をしたりということをします。その人の抱えている問題をどうやったら解決できるか、導くお仕事ですね。実際に解決をするのはあくまでご本人ですので。
患者さん・利用者さんを社会とつなぐということですね。
壁もたくさんありますし、必ずしもすぐ目に見える成果が出ないという難しさはあります。ただ、もちろん感謝していただけることもありますし、必要とされる、やりがいのある仕事なんです。
青春! 楽しかった大学時代を経て
なじみのあった地元の病院へ
社会福祉士を目指して、その後どのように進まれましたか。
大阪の柏原市というところにある福祉系の大学に進学しました。奈良に近いのどかなところで。でも大学や専門学校が集まっていたので、学生が多くて活気もありました。
大学時代は真面目に通って勉強されて。
いや、決して真面目な学生とは言えなかったですね…。どちらかと言うとアルバイトに力を入れるようになっていって、授業の取り方もそっちに合わせるように(笑)。
(笑)。どんなアルバイトをされていたんですか。
特養での夜勤、障害者施設や精神科でのお仕事とか、医療・福祉関係のアルバイトですね。それと、今までアルバイト経験がなかったのでいろいろなことをしようと思って、マクドナルドとかサブウェイなど飲食店でも働きました。
けっこうたくさんやっていたのですね。
それが楽しかったので、学校には行っても授業を受けたらすぐ帰ってましたね。
放課後サークル活動をしたりとか、学校の友達と遊んだりということもなく。
でもバイトが終わって家に帰ると、友だちが誰かしら部屋にいましたね。
えっ、勝手に部屋に入っているんですか。
そのマンションに大学の同級生が何人も住んでいて、常に誰かの部屋に集まっていたんです。大家さんがすごくいい人で、BBQとか花火を企画してくれましたし、とても楽しかったです。
卒業後、社会福祉士として就職されたんですか。
はい、うちのグループの博愛記念病院に入職しました。そもそも、その頃は社会福祉士を募集している職場自体がほとんどなかったのに、ここだけ「社会福祉士を5人募集します」っていう求人があったんです。
貴重な求人ですね!
当時介護の求人は、介護スタッフとか、介護士だけという時代だったので、とても珍しかったですね。しかも小さい頃に泳いでいた川の側の病院でしたし、すぐ受けて、内定をいただけました。

さまざまな現場を渡り歩き、経験が糧に
でも、異動は寂しい…
そこから、社会福祉士としての仕事がスタートされたのでしょうか。
最初は、社会福祉士の新人全員が介護士として現場で働きました。
まずはしっかりと現場を知るということですね。
当時「社会福祉士は全てのサービスを理解しないといけない」っていう代表の考えがあって、いろんな職場を経験していきましたね。私も最初に病院で介護士をして、そこからケアハウスに行って、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所、特養に行って老健に行って、また特養に戻って、次は地域連携室に行って…。
多くの現場を知ることが、社会福祉士としての糧になるという考えだったわけですよね。
そうだったと信じています(笑)。
社会福祉士として入職はしつつも、さまざまな経験を積まれてきたんですね。
今思えば「たくさん勉強させてもらえたな」と感じます。ただ、その当時は異動のたびに辛くはありましたね(笑)。せっかく慣れてきて楽しくなってきたところで移ることになりますし、利用者さんやスタッフさんと離れるのが寂しかったです。
先輩の社会福祉士さんも同じ様にやってこられていたんでしょうか。
私たちが入った時点では先輩はとても少なかったんですが、すでにグループ本部の仕事もされていました。きっと同じようにさまざまな職場を経たんだろうなと思います。
前川さんも本部の仕事をされるようになっていかれて。
私が施設長を務めるようになってから、徐々にですね。当時は今みたいにグループの部門や機能が確立されていなくて、本当になんでもやっていましたよ。人事部もありませんでしたから、新卒スタッフの制服の準備から、有給休暇の管理、各施設が提出する書類の管理、あとは新人研修、慰安旅行、忘年会の準備とか、何でもでしたね。
そこまでやられていたんですね!
「本部」と聞くと、全体を動かす大きい仕事をしているイメージを持たれるかもしれませんが、当時はもう少し現場に寄り添った仕事を担当していました。
早いタイミングで就いた
施設長の仕事
施設長も務められていたのですか。
グループの特別養護老人ホーム、ヴィラ勝占の施設長を務めました。オープン時に相談員として働いて、一度離れたのですが、施設長の席が空いてしまったので務めることになったんです。
施設長とはどんなお仕事でしたか。現場の職員から管理側に移るわけですよね
最初は全然わかりませんでしたね。当時まだ27、8歳ぐらいで経験も浅かったですし、しかも前任もすでにいない状況でしたので、「管理」と言われても、何を管理していいのかわからない(笑)。
やりながら覚えたような感じですか。
とにかく職員さんと一緒に何でもするところから始めました。ただ、博愛記念病院の敷地内にある施設だったので、そちらである程度の方針が決められていたのが大きかったです。それが現場に降りてきて、どう動かすかというのが私の仕事でした。
比較的若くして管理者側に立たれて、そこでの苦労はありましたか。
ヴィラ勝占については開設時から働いていて、すでに職員さんとは関係性がありましたので恵まれた状況ではありました。今の施設長さんは自分の時より遥かにたくさんの仕事があって、大変だろうなと思います。
施設長のお仕事は病院の事務長とはまた違いますか。
似た部分も多いと思います。ただ、病院は看護、リハビリテーション、介護など各職種に役職者が立って組織ができていますが、施設は病院ほど職種がいないですし、役職者もまだまだ少ないところが多いです。その点では、各職種での相談などが全て施設長に集まるということはあると思います。これからは施設も、もっとしっかり組織を作っていかなければいけないと思っています。
施設長が判断を担う部分が大きいと。グループの特長として、比較的若い施設長の方も多いですよね。
だからこそすごいなと感じています。もちろん悩むところも多いと思うんですが、その分やりがいはとてもあるし、熱意を持って仕事に当たってくれています。

施設の立ち上げをサポート!
グループの方法を伝える難しさ
介護福祉事業部として部門が立ち上がったのはここ何年かのことだったと思うんですが、それ以前は本部にいてどのように動いていたのですか。
明確に誰が何をという決まったことはなく、病院・施設の立ち上げや、新たにグループ加入する施設などがあれば、本部から何人かのメンバーが入り込んで、そのサポートをするという感じでしたね。
新たに介護施設がグループに加入する場合、以前から働いているスタッフさんの中に入ることになるわけですよね。
すでに利用者さんもスタッフさんもいるところに入っていって、うちのグループとしての仕事のやり方を研修しました。ただ、形としてはうちのグループに加入、ではあるけれど、現場からすると、いきなり外部から人が入ってくるように印象になってしまうので、大変なことも多かったです。
やっぱり、グループのやり方に合わせられない、ということも当然ありましたか。
グループとしては、今も言われている「患者さんのために良いことは、損をしてでもする」というような姿勢は一貫してありました。ただ、実際現場に入ってみると、職員さんにとってはやりやすいんだけれど、利用者さんにとっては良くない、という事例がたくさんあるんです。それを変えてもらうのは難しいので、大変ではありましたね。離れてしまう人も多いですし。
以前からのやり方に慣れていると、変化するのは難しいのですね。
ただ「合わなくて辞める人は追わない」というのは、当時から代表が言っていました。去る人ではなく、残ってがんばってくれる人たちを大切にして、現場を託していけるように、必要なことを伝えていくわけです。
どのくらいの期間、常駐されるんですか。
3カ月〜半年くらいです。ほぼ同時に2施設が立ち上がった時期もありました。その頃のことは、何をどうやっていたのかをもう思い出せないくらい、大変でした(笑)。
介護福祉事業部の立ち上げで受けた衝撃!
介護福祉事業部の立ち上げについてはどのような想いでしたか。
衝撃でした。やはり病院からスタートしたグループですので、どうしても病院に軸足を置いて進んできたところはあったわけです。ただ私自身は介護保健施設に多く関わってきましたので、だからこそ介護も部門化して取り組めることになったのが本当に嬉しかったです。
確立されることでより本腰を入れられるようになりますからね。
これを主導した副代表が「医療には限界があるけど、福祉には限界がない」と言っていたんですね。福祉は医療のように傷を治せるわけではないけれど、気持ちの部分が作用することなので、限界がないんです。「もっと良くしたい」と思えば、やれることがたくさんある、と。それを聞いてなお衝撃を受けて!
長らく携わってきた身からすると、大きなことですよね。事業部としてのお仕事は実際どういったことになるのでしょうか。
大きくは高齢者介護施設や障害者支援施設の運営サポートです。新施設の開設時や、グループ加入時は立ち上げに関わりますし、運営にまつわる細かい相談や採用計画、また、各施設の収支を確認して、経営についても施設長に提案を行います。
数学が苦手とおっしゃっていましたが、経営分析で数字を見ることも今はされて。
数字は好きではないけど見ないといけなくなりました(笑)。いつも本当に経理の方にお世話になって取り組んでいます。
日常的に全国の施設を回られているのですか。
今はケアホーム板橋の立ち上げがあるので東京にいることが多いですが、基本的には徳島の博愛記念病院にいて、その都度、必要に応じて各施設を回っています。
立ち上げの時はやはり集中的にそこに行くことが多いのですね。
それでも以前よりは減りました。川口さん(※)のように、各エリアに任せられる人ができたので。それと、テレビ会議のシステムが進化したのが大きいです。遠隔での仕事が飛躍的にやりやすくなったので、少ない負担で仕事の幅を広げることができました。
介護福祉事業部としての目標を教えてください。
もっとみんなが楽しく利用者さんのことを考えながら働ける環境を作っていきたいと思っています。果てしないですけど、それを考えて仕事をするのがまた楽しいです。そのためには一緒に手伝ってくれる仲間がもっと必要ですね。

介護職への想い
よりクローズアップされる仕事へ
介護職の教育や研修についてはどのように取り組んでいますか。
成長の段階に応じて受けるラダー別研修や、資格取得に向けた研修、さらに部内の職種ごとによる研修などを行って、スタッフを支援しています。e-ラーニングも全病院・施設に導入されて、より取り組みやすくなりました。
段々と教育体制が充実してきているのですね。
初めは抵抗があるスタッフさんもいたのですが、段々と慣れてくるうちに「こんな研修をやってみたい」という声が現場からも出てくるようになって、いい作用が生まれています。
より前向きに取り組めるようになるのですね。
介護はクローズアップされにくい職種ではあると思うのですが、少しでも良い環境で働いてもらえるように動いている人もいるんだ、ということがわかってもらえるといいですね。
介護業界全体の問題として、介護従事者が少ないということがあると思います。なり手を増やす、また離職者を減らすというのは大きな課題ですよね。
やっぱりすごく大切な仕事をしているわけですから、自信を持って自分たちの仕事をアピールするっていうことがあっていいかなと思います。誰よりも利用者さんと関わる時間が長く、寄り添える仕事ですので、そういう自信をもっと感じてもらえるようにするのが課題です。ただ、それには国に変わってもらわないといけない部分もあるので「私たちもがんばるから、国もがんばってよ!」と思っています。
(笑)。しっかりと研修やステップアップの機会があるのが大事なことですね。
キャリアアップについても、もっと目に見える形にしたいなと考えています。「こうなりたい」と目指せる場所を作れるのが理想ですね。
ノウハウを徐々に掴んでいった
障害者福祉への取り組み
介護福祉事業部は、高齢者介護とともに、障害者福祉についても取り組んでいますが、こちらはどういった経緯があったのでしょうか。
大阪にある淀川暖気の苑という施設がグループに加入してからですね。高齢者介護とともに障害者支援も行っている施設ですが、当時グループでは障害者の施設に携わるのが初めてだったので、もともと働いていた方たち以外には詳しいスタッフがいませんでした。
介護福祉事業部を立ち上げていくなかで、障害者支援事業にも力を入れていこうということになったのですか。
副代表が主導して始めていきましたね。暖気の苑のスタッフは当時「こっちに目を向けてくれたことが驚きだった」と言っていました。ただ、目が向いた分、変えないといけないことも多かったので大変だったとは思います。
今とはどういう点が違っていましたか。
「スタッフと利用者さんが一緒に」という傾向が強かったです。寄り添い方が少し違うというか、「障害があるからこれはできない」「みんなで同じことをするのが、良いことだ」というように、変に解釈していた部分もありました。
前川さんご自身は障害者福祉への取り組みについてはどのように考えていたのですか。
もともと大学では児童・障害専攻でしたので、いずれは障害や児童の分野に取り組んでみたいという気持ちがあったんです。だから副代表から話があった時、それがバーッとあふれ出て(笑)。
実際どういったことから手をつけましたか。
私も障害の分野から長く離れていましたので、まずは副代表と、しょうぶ学園(※1)に行ったり、べてるの家(※2)に行ったり、さまざまな障害者支援の取り組みを見学させてもらいました。
※1:鹿児島県鹿児島市にある、知的障害者支援施設。2016年には学園を題材にしたドキュメンタリー映画「幸福は日々の中に。」が公開。工芸・芸術活動や、創作・表現活動の支援のほか、レストランなどを地域に開放、活動に取り組んでいる。 ※2:1984年に設立された、北海道浦河町にある精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点。生活共同体、働く場としての共同体、ケアの共同体という3つの性格を持ち、100名以上のメンバーが地域で生活する。
それぞれどんな取り組みをされているかを見て、吸収して。
環境も違いますし、同じことをしようとしても、簡単にできるわけではないので、考え方を感じに行くという意味合いでした。実際、障害者福祉への考えが大きく変わりましたね。

その人らしく
楽しいこと、好きなことに取り組む
そこから現場をどのように変えていかれたのでしょうか。
現場スタッフにも、しょうぶ学園を見学してもらいましたが、やはり考え方の違いを感じられたと思います。それから、一つひとつの細かい業務を見直して、これが本当に利用者さんにとって良いことなのかを整理して。さらに建物自体も、より自由に安全に過ごしてもらえるように手を入れていきました。
淀川暖気の苑で取り組んでいる「くるむプロジェクト(※)」では利用者さんが描かれた絵などを素敵なグッズにされていますよね。これはどういった想いで取り組まれているのですか。
一般社会のものさしで考えると、仕事をしてお金をもらうことは当たり前ですが、そこに合わせるのが、障害者の方にとっては必ずしも幸せにつながることではないと思うんです。でも利用者さんも、好きなこと、楽しいことは続けられるわけです。だから、お金をもらうためにやるのではなく、あくまで自分たちがやりたいこと、楽しいと思うことに取り組んでもらう。そこにスタッフの力が加わることで、作品が商品となり、結果的にそれが収入になって、社会とつながれるんです。取り組みとしてはまだこれからではありますが。
※障害者支援施設の創作活動で生まれた個性豊かな表現を、さまざまな「カタチ」や「方法」で社会に発信するプロジェクト。
くるむプロジェクト
素朴な疑問なのですが、利用者さんにとっての「好きなこと」は、どうやって見つけるのですか。
最初はわからないので、一通りやってもらいます。ネジを作るのが向いてる人もいますし、粘土をこねるのが好きな人もいる。そのなかから、これがいいんじゃないかっていうのを考えて、取り組んでもらいます。
選択肢がたくさんあるのが良いということでしょうか。
必ずしも選択肢に全ての人が当てはまるわけではないので、今ある選択肢に無ければ新しく作ることも考えます。その方の生活を見ながら「こんなことが楽しめそう」ということを話し合いながらですね。
現在グループでは、暖気の苑以外にも、こうした障害者支援に取り組んでいますが、医療グループとして取り組む強みはどういったところにありますか。
各地に展開するグループならではですね。障害者福祉への取り組みについては今後どう進めていかれますか。
現在、大阪のほかに、兵庫県淡路市の「ココロネ」、東京都足立区の「OUCHI」、さらに東京都小平市の「緑成会整育園」と、内容はそれぞれ異なりますが、障害者福祉に取り組んでいます。今後は、施設をどんどん増やすのではなく、まずそれぞれの地域でしっかりと根を下ろして活動していきたいです。そこから少しずつ広げていけたらいいのかなと思っています。
地域の介護需要に応える大規模施設
より安心して過ごせるようにスタートを切る
今日の取材場所であるケアホーム板橋が、いよいよ6月にオープンですね! 現在はどのような状況ですか。
先日までは、先行して入職したスタッフが準備に当たっていましたが、4月の後半からは新入職のスタッフが130名ほど入っての研修が始まっています。
130名! 規模が大きい施設なだけはありますね。
200床の特別養護老人ホームのほか、ショートステイ、グループホーム、ケアハウス、地域包括ケアセンターがひとつの施設に入りますし、当グループとしても初となる規模ですね。
どんな特長がありますか。
多様な機能を持ちますので、高齢者の方の暮らしについて幅広く相談を受けられるのが強みです。規模も大きいので、広々とした設計がされているのもポイントですね。「特養の施設っぽくない」という言い方が正しいかわかりませんが、スタイリッシュな雰囲気になっています。
明るくて開放感がありますよね!
屋上には自由に行ける庭園がありますし、見晴らしもとてもいいです。近隣のみなさんも使える、広い地域交流スペースも設けていますので、ぜひ活用していただきたいと考えています。
利用者さんについてはどのような状況ですか。
ありがたいことに大変ご好評をいただいて、入居についてはほぼ決まっています。ただ、この大きさの施設を動かせるようになるには、ある程度時間が必要と考えています。そのために、オープンしてからは段階的に利用者さんを受け入れながら進めていく予定です。やはり事故やけがなどがあってはいけないので、慎重に進めていければと思います。

仕事の後に飲み会
まるで夢のよう
お休みはどう過ごされていますか。
いちばんの楽しみは洗濯をすることですね。気分が一新されるようで、とても気持ちがいいです。以前は休日となると出かけないと損した気持ちになっていましたけど、最近はボーッとできる時間がないと、逆に損した気持ちになるようになりました。
何も考えずに過ごす時間も大事ですよね。ちなみに趣味はありますか。
趣味という趣味はないんですけど、最近折り畳み自転車を買ったんですよ。
いいですね!
でもまだ乗れていないんです(笑)。本当は、折り畳み自転車を車に積んで、行った先でサイクリングしたいんです。今は買ったまま家に置いてあるので。徳島に神山町っていう、のどかでいいところがあるんですね。そこに行って乗りたいと思っています。
ちなみにスタッフとお酒を飲みに行くことはありますか。
たまに行きますよ。でも徳島や関西だと年に1、2回くらいですね。車通勤のスタッフが多いので、仕事帰りにフラッとっていうのができなくて。逆に関東に出張に行く時には車ではないので、飲みに行けるのが楽しくて、夢のようです。仕事帰りっていちばんお酒を飲みたいじゃないですか(笑)。
(笑)。開放感がありますよね。
だから声をかけてもらえるとものすごく嬉しいです。施設長さんたちとも、最近は行けるようになりましたね。以前は「仕事で来ているのに」っていう意識があったんですが。最近では、そういう機会も、とても大切な時間だなと感じています。徳島・関西の施設長さんたちとも、もっと行ければなあと思っています。
以前よりも気持ちの余裕ができたんでしょうか。
そうやって話せる関係ができたのかなとは思います。でも立場的に怖がられているかも、とは思うんですよ(笑)。
施設長さんとお話しされている様子を見ると、そんなこともなさそうに思います(笑)。
自分から言わなくても、企画して誘っていただけるので、とても嬉しいですね。あんまり自分からは言わない人間なので(笑)。
プロフィール

平成医療福祉グループ 介護福祉事業部 部長
前川 沙緒里
まえかわ さおり
【出身】徳島県徳島市
【職種】社会福祉士
【好きな食べ物】カレー(バーモントカレーみたいなおうちのカレー)
病院情報

東京都板橋区向原3丁目7-8
https://itabashi.tokuyou.jp/
ケアホーム板橋
2019年6月に開設。特別養護老人ホーム(ユニット型、従来型)、ショートステイ、グループホーム、ケアハウス、地域包括支援センター等の介護保険サービスを提供する高齢者施設です。