強く興味を持った、医療政策の仕組み 厚生労働省で医師として積んだ数々の経験が、大きな財産に/平成横浜病院/天辰 優太先生

強く興味を持った、医療政策の仕組み
厚生労働省で医師として積んだ数々の経験が、大きな財産に
平成横浜病院で医師を務める天辰優太先生にインタビューしました。現在は外来や訪問診療を担当しながら、主には病院運営について携わる天辰先生。グループに着任する以前は、医療機関ではなく、厚生労働省で医系技官(※)として働いたというキャリアを有しています。なぜ医系技官として働くに至ったのか、また、どのような仕事に携わってきたのか、ルーツを紐解きながら、その経歴を中心に伺いました。ぜひご覧ください!
※医系技官:医師として保健医療に関する制度作りに携わる技術系の行政官。
進路希望は当日の朝まで迷った…
医師のほかに目指した意外な職業
平成横浜病院へ入職されたのはいつですか。
昨年の11月なので、半年経ったくらいですね。
まだ割と日が浅いんですね。ちなみにご出身はどちらですか。
大分県の大分市に生まれました。食事がおいしいくていいところです。
鶏肉の消費が多いことで有名ですよね。
そうですね、あとは関アジ、関サバとか、魚介類もおいしいことで有名です。
今は横浜の病院で働いていらっしゃいますが、いつまで大分で暮らしていたのですか。
小学校を卒業してからは鹿児島県にあるラ・サール学園に入ったので、中学・高校時代は鹿児島県で暮らしていました。
おおっ、名門校ですね。地元を離れて進学する、というのはご自身の希望でしたか。
自分で希望しました。父親が歯科医で、祖父も医師というのもあって、親も理解があったというか。自分の周りにも同じように進んだ人がいたので、そういったところに進学して、医学部を目指す、という選択に自然となりましたね。
小学生の頃から勉強が好きだったのですか。
それよりは、野球が好きでした。小学生の時は自分でも野球をやっていましたし、プロ野球の選手名鑑を親に買ってもらって、それをずっと読み込んで、出身校とか年俸を覚えてプロ野球博士みたいになってましたね(笑)。
(笑)。かなりくわしくなっていたんですね。進学については、地元を離れるよりも、もっと野球をやりたいとか、地元の友だちと遊びたいという気持ちはなかったのですか。
プロを目指していたわけではなかったので、野球をそのままやっていくという気持ちはそこまでなくて、それより、医学部に行きたいという気持ちがありました。
そこで、よりチャレンジできる環境を求めて、地元を離れたわけですか。
そうですね、九州では有名な学校ですから、面白そうでしたし、せっかくなら高め合える環境に進んでみたいなと。
実際進学してみていかがでしたか。いきなり親元を離れるとなると、戸惑うことも多そうですね。
最初の1年半くらいは寮生活で、その後は姉が鹿児島の大学に進学したので、一緒に暮らしていました。寮生活は楽しいこともありましたけど、1年生から3年生まで一緒に暮らす8人部屋だったので、小学校を卒業したばかりだと、環境やルールになれるまでは大変でしたね。
やっぱり厳しい縦社会なんですか。
むちゃくちゃに厳しいというわけではないですけど、それなりには厳しかったです。「1年生は鏡がある風呂場を使っちゃだめだ」みたいなルールがあって。でも、今考えるとそういう経験があって良かったというか、勉強にはなりました。
礼儀とか社会性を身につける、というか。
あとは、寮内で自習をしないといけない時間も決まっているので、勉強には集中できる環境でしたね。
当時からもうずっと「医学を学びたい」という気持ちで勉強に励んでいたんですか。
もちろん医学部っていうのは希望としてあったんですけど、実は当時「証券マンになりたいな」っていう気持ちもあって。経済にも、もともと興味がありましたし、そういう仕事がやりたかったんです。なので医学部ではなく経済学部に進学するという道も考えて、悩んだことがありました。
金融の仕事は、どういうところに魅力を感じたんですか。
ある意味ダイナミックな世界ですし、そういうところで活躍するのは、楽しそうだしかっこいいなっていうことは学生ながらに思っていましたね。昔は証券取引所で、手でサインを出して取り引きをしていたじゃないですか。あれがかっこいいなって(笑)。
(笑)。確かに印象的な姿ですよね。
でももちろん、もともと医学部を目指していましたから、最終的には捨てきれずに、そちらを選びました。高校2年生の時、進路希望を文系か理系か選ぶじゃないですか。希望を提出する期限の当時の朝までずっと、どっちにするか悩みましたから。
かなりギリギリまで悩まれたんですね!
親も心配したと思うんですが、最後はやっぱり医学部を目指して理系を選びました。
その瀬戸際で決断した決め手はなんだったんですか。
いやあ、でも今もしまた自分が同じ状況にいたとしたら、またどっちにするかで悩むと思います。本当に、その日の朝の気分だったというか、明確にこれがあったから、ということではないんです。
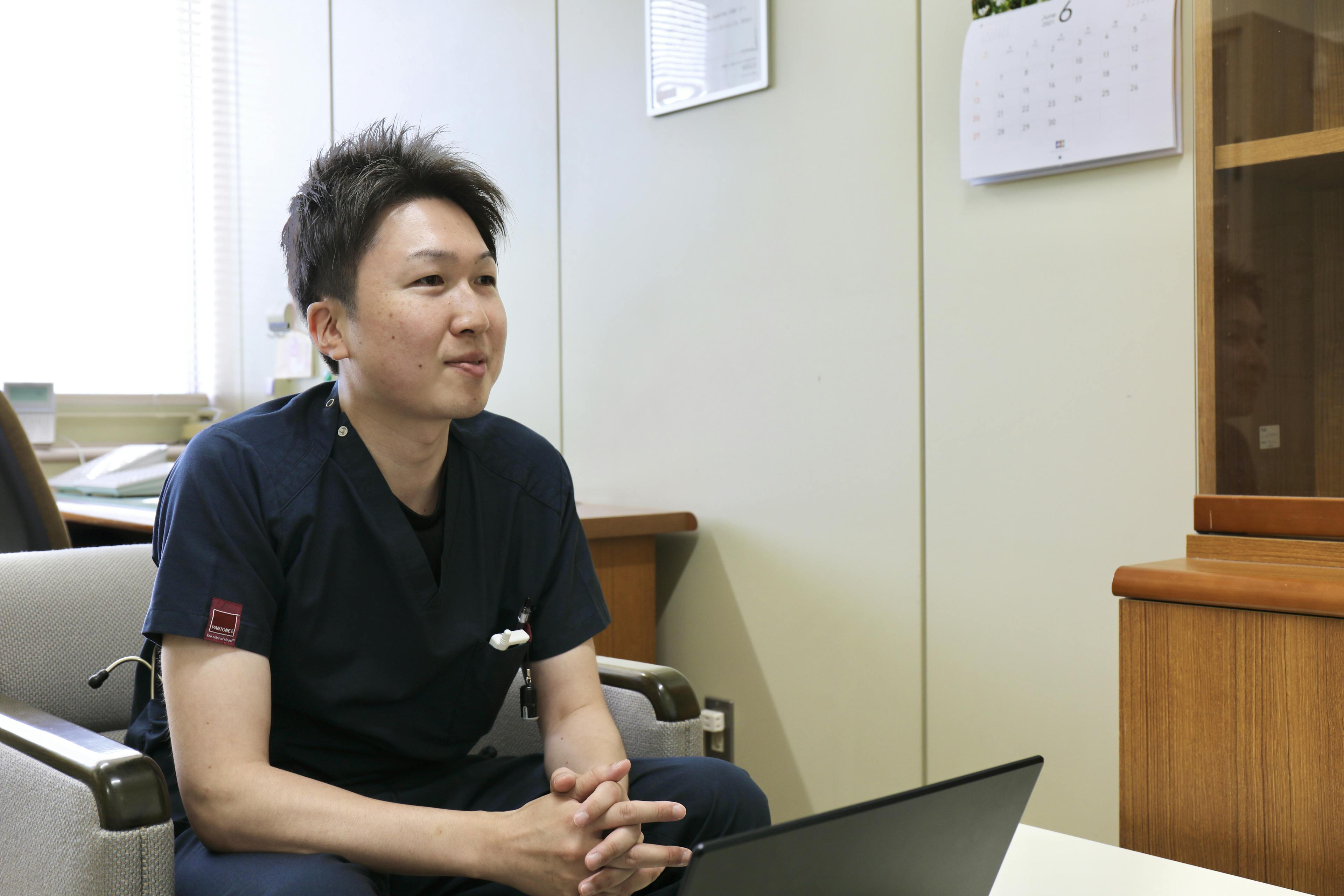
弱くても勝てます
選手兼監督として弱小チームを強化
いざ医学部を目指すと決めて、どのような選択をされたのですか。
ある程度自分が入れそうなところで、なおかつ一人暮らしをしたかったので、九州から離れたところに入ろうと思って、岐阜の大学に入ることができました。
岐阜での生活はいかがでしたか。
大学は岐阜市内ではあったんですけど、思いっきり郊外にあって、周りが田んぼだらけで思ってた以上にのどかだったんですよ。中学高校と男子校に通っていましたから、大学というと華やかなキャンパスライフを想像してましたけど…実際は田んぼの畦道を自転車で通学するような日々で(笑)。
それはだいぶ想像とは違いましたね(笑)。
それはそれでのんびりして良かったんですけどね。
大学生活で印象的なことはありましたか。
小学校、中学校と野球をやっていて、高校では離れていたんですけど、大学に医学部の準硬式野球部があったので、そこに入ってまたやり始めました。
また野球熱が復活したと。けっこう熱心にやっていたんですか。
そうですね、決して上手ではなかったですけど。医学部の野球部なんで、もちろん監督なんていませんから、各学年持ち回りでプレイングマネジャーとして監督もやっていて、僕の学年は僕1人だけだったので、やらざるを得なかったんですね。
選手兼監督もやっていたんですね。
それがけっこう面白くて、どうやったら勝てるかなっていうのをずっと考えてました。当時、東海地区の大学が集まった東海リーグっていうっていうのが、一部から四部まで入れ替え制であって。うちの部はそれまで基本ずっと四部にいました。ほかの大学のチームは元高校球児も在籍していて、体格が良い選手もけっこういるけど、うちは医学部生だけのチームで半分くらいが初心者でしたし、僕と同じくらいの小さい人も多くて、なかなか勝てなかったんですよ。
リーグ内でかなりチーム力に差があったわけですね。
ただ、よく見てみると、四部とか三部のチームって、そんなに練習してないところも多いんですよ。高校の時は良い選手だったんだろうけど、大学生になった今は、みんなバイトとか飲み会をして、半分二日酔いみたいな感じで試合に来たり、お腹もたるんできてたりして。
昔取った杵柄(きねづか)じゃないけど、高校球児の頃のように真剣に練習せずに臨んでいたと。
そこで、うちのチームはたまたま足が速い人が多かったので、機動力でかき回したら勝てるんじゃないかって思ったんですね。かなり真剣に練習して、自分がプレイングマネジャーだった時に、四部リーグで優勝して三部に昇格して、さらにそこでも優勝して、一気に二部まで上がれたんです。
おおっ、すごい快挙ですね!
医学部のチームが二部に上がったのは初めてだったみたいです。大変ではあったけど、当時はすごく面白くて、良い経験をしたなと思います。初心者ばっかりのチームでしたけど、一生懸命やって勝てたのは、達成感がありましたし、結束が強まって良かったですね。
プレーすることも好きだったとは思うんですけど、マネジメントする面白さ、みたいなことはそこで気が付いたんですか。
僕自身、足がめっちゃ遅かったんで、そこを基準にすると絶対ベンチなんですよ(笑)。でも、ベンチにいて采配を振るうっていうのも、めちゃくちゃ面白かったですね。
ご自身はそんなに出場しなかったんですか。
一度、代打で出場して、バントだけして。それくらいですね(笑)。

臨床よりも強く興味を持った
医療政策の仕組み
医学部の学生としては、どんなことに興味を持ったのですか。
一般的には臨床をやっていくのが普通なんですけど、正直に言うと、もともと金融経済にも興味があったとお話した通り、どうやって今後進んでいこうかと迷ったところがありました。
臨床の道に進むことに迷いがあったと。そこからどのように決断されたのでしょう
大学6年生で岐阜県内の病院に実習に行った時に、現在はグループの世田谷記念病院で在宅医療部部長を務める佐方先生と出会って、僕の上級医として1カ月間一緒に働く機会がありました。佐方先生はその前まで厚生労働省で医系技官として働かれていたので、公衆衛生に関わることの面白さ、みたいなことを教えてくれたんです。
その出会いが、その後の選択に大きく関わったと。
その話を聞いて、厚生労働省の道に進むのが面白いんじゃないかと思ったんですね。臨床は、またタイミングが合えばできる機会もあるかなと考えて、なかなかできない経験ができる、医系技官の道に進んでみようと。その後、臨床研修をやって、そのまま厚労省に入りました。
周りは臨床医を選ぶ人の方が多かったと思うんですが、ご自身は周りと違う道を選ぶことに、心の揺れはありませんでしたか。
もちろん、臨床が面白いっていうことは思いましたし、患者さんの状態が良くなって感謝していただけた時に、やっぱりいいなって思うこともあったんですけど。当時は厚労省で「自分の能力を試してみたい」という気持ちが強かったので、そこに迷いはなかったですね。
その時は、実際どういうことをしたいと思って厚労省に入ろうと考えられたのですか。
医療行政の仕組みはどうなってるのかとか、医療行政を決定しているのはどういった人たちなのかとか、興味本位の方が強かったですね。自分が働いていたような病院の、行政ルールがどう決まっているのか知りたい、っていう気持ちです。
仕組みの方に興味があったと。
もともと、経済学部を目指すっていうことも選択肢にありましたし、官僚っていう仕事についても昔考えたことがあったので、自分に合っているかもしれないと思ったんです。それと大学の野球部での経験にもつながるんですけど、みんなで力を合わせてやるっていうところで、自分の力を発揮できるかなと思ったので、そういう観点で行政に携わったら面白いんじゃないかと思ったところもありましたね。
目の前にいる患者さんに向き合うのとはまた違った視点を持って仕事をしていくと言いますか。
そういう新しいチャレンジみたいなことは僕に性格としては合ってると思ったので、面白そうだなと思って進みました。
同級生でもなかなか進む人が少なそうなチョイスですよね。
都内の大学であれば、まだ多かったかもしれません。今も当時の同期と飲んでも、共通の話題が少ないんです(笑)。みんな手術や患者さんの話をするところで、僕がこういう仕事をしたっていう話をしても、なかなか理解はしづらいでしょうし、自分の親にしてもそうなんですけど、当然僕が臨床医になると思っていましたから。これは課題だと思うんですが、厚労省内で大変な仕事をしていても、なかなか理解されにくい部分なんです。
大きな財産になった
診療報酬改定での経験
厚労省ではまずどういったところに配属されたのですか。
最初は介護報酬に関わりました。介護報酬の中でもリハビリの分野を担当したのですが、作業療法士の方とチームを組んで「介護においてリハビリはどうあるべきか」ということを、議論しながら進めていきました。当時はリハビリについてくわしくなかったので、その方に教えてもらいながら、けっこう大変だったんですけど、それで報酬改定に初めて携わりましたね。
当然それまではリハビリについてもそこまで知識はなかったと。
研修医としてもそこまでリハビリについては関わらなかったので、そこでリハビリのあり方、みたいなことを教わったのはとても勉強になりました。
経験にもなりますけど、最初は大変そうですね。担当する分野についての知識を入れながら、同時にアウトプットしてという感じですか。
そうですね。最終的には法律として通知できる文章にしないといけないので、いわゆる法令のプロである、本当のキャリア官僚の人たちと、正確な表現や解釈の揺れが起こらないようにしていく作業もあって、それはものすごい大変でしたね。
細かい調整が求められそうですね。
僕らが書いたものをそのまま出せるわけではないので、赤ペンをめちゃくちゃ入れられて。その分すごく勉強にはなりましたけどね。その次には、診療報酬改定も担当したんですけど、改定って本当に大変な業務のひとつで、それなりに労働時間も長かったですし、肉体的にも大変でした。
介護報酬と診療報酬と、どちらも担当してみて、関わり方は違いはありますか。
当然、制度や歴史が違いますが、基本的には同じですね。担当する分野によって、一緒に仕事をする人も変わって、診療報酬の時は看護師さんと一緒になって取り組んでいましたね。
その頃のお仕事のやりがいや醍醐味は、どういうところにありましたか。
改定で変わった部分によって、現場が良くなったというお声をいただいた時は「大変だけどやって良かった」と思えましたね。診療報酬を改定するということは、全国的にその変更されたルールに沿って動くことになるので、インパクトが大きいですから。
確かに、大きく報道もされますし、現場への影響も大きいものがありますよね。
なので、慎重に行わないと間違ったメッセージを伝えることになってしまうので、手が震えながらと言うと大袈裟かもしれないですけど、日々自問自答しながら、各分野の専門家にも意見を聞いて、慎重にステップを踏んでいました。
時には耳の痛い指摘を受けることもありましたか。
当然そういうこともありました。でもそれも必要なことですし、問題が生じていることは確かなので、そこから改善点を見出して、できることは取り組んでいくというのが大事だと思いました。仕事としては肉体的に大変なこともありましたけど、やりがいはすごくありました。
やはり大変は大変だったのですね。
僕は入省する面接の時に、アピールポイントがそんなになかったので「部活もやっていたし体力には自身あります」って言ってしまったので、それでいきなり体力枠として、介護報酬改定の担当になったんだと思ってます(笑)。だから、その後も2回診療報酬改定に関わらせてもらえたのかなと。ただ、そのおかげで財産になるような経験はできましたね。
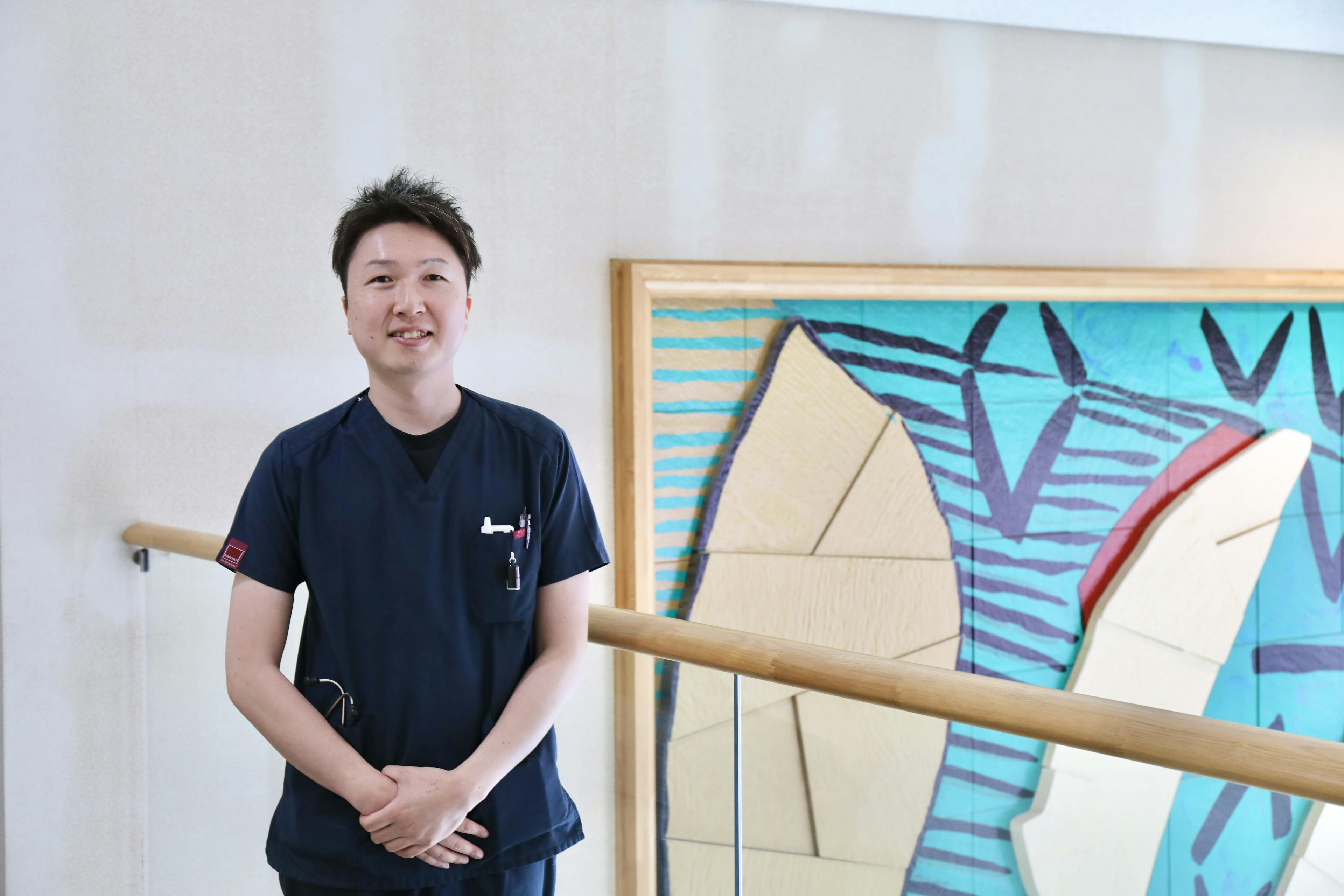
厚労省は常に新しいチャレンジができる環境
その後はどのようなお仕事に関わったのですか。
国立ハンセン病療養所の医師確保に関わったり、医師の働き方改革について関わったりしました。
ハンセン病療養所は、なかなか医師のなり手がいなかったと。
全国に十数箇所あるんですが、なかなか知ってもらうこと自体が難しかったんですね。刑務所で働く矯正医官もそうですが、行政に関わる医師の仕事はいろいろあっても、普通に働いているだけではなかなか目にする機会がないんです。
求人サイトに出るようなお仕事ではないわけですよね。
なので、例えば大学を回ったりとか、各都道府県庁にお願いをしに行ったりなどして、知ってもらう工夫もしていました。
医師の働き方改革については、最近もよく報道で目にしますし、引き続き話題になっているテーマです。
政府として、医師に限らず働き方改革を推進するという流れがもともとありましたが、医師は当直をやらないといけないですし、長時間の労働がベースにはなっているという特殊な労働ですから。医師が患者さんを守るためには、まず医師自身の健康や働き方も守らないといけない。そのため、ある程度地域の医療を維持できながらも、働き方のルールを作るっていうことをやっていました。
地域によっては医師の数が足りていない状況で、働き方も改善するとなると、難しいバランスと言えそうです。
まさに、救急体制を維持しながら、必要な医療を地域のみなさんに提供できるっていうことが大切なポイントですから。そことのバランスや、ルールをどうしていくかとか、これはかなり苦労したことで、検討会も何度も開いて調整していましたね。
医師の需給とも絡んでくるわけですね。
それと同時に、地域医療構想ともセットで考える必要があります。ほかにも考えないといけないことがたくさんあって、単純に医師の労働時間を制限するっていうことだけでは地域の医療に影響が出てしまいますから、大学病院や自治体と、うまくセットになっていけるようなパッケージを組めるように取り組んでいました。
ここまで聞いたお仕事については、やはりその時その時でのやりがいがあったのでしょうか。
厚労省の仕事は、2年に1回周期で人事異動があるので、長くは関われないんですけど、それぞれ課題があって、常に新しいチャレンジができるっていうのが面白かったですし、自分には向いていると思いましたね。
厚労省でのキャリアを通して特に印象的だったお仕事はどんなことですか。
特に印象に残っているのは、診療報酬改定ですね。診療報酬と一口に言っても、いろいろな職種の方が関わるような点数がたくさんあるので。看護師の方やリハビリスタッフの方、薬剤師の方とか、さまざまな方と話をしたり聞いたりして「こういう仕組みにできたらいいよね」と話しながら進められたのは、やりがいもありましたし、楽しかったですね。
大変だった分、印象にも残っているんですね。
臨床医だと、治療に携わっているその瞬間瞬間で反応が見えることも多いと思うんですけど、厚労省で関わってきた仕事は、効果が見えるまでの期間も長いんです。良い反応をいただけたときはかなり嬉しいんですけど、忍耐力は必要ですし、種まきみたいなところはありましたね。

グループの取り組みに強い興味
厚労省を離れることを決断
厚労省から、平成医療福祉グループに入職することになった経緯を教えてください。
厚労省でいくつかのポストを経験させてもらって、もちろんそれで全部わかったというわけではないですが、行政の仕組みを多少なりとも見ることができたので、新しい分野に移って仕事をしてみたいという気持ちが漫然と出てきたんです。
ある程度の経験を積めたので、今度はそれを別の場所で生かそうと。
そこで厚労省を離れたんですが、次に何かチャレンジできることはないかなと思った時に、もともと知り合いだった厚労省OBの坂上先生(※)や佐方先生(世田谷記念病院 在宅医療部 部長)が、このグループで活躍されていて、話を聞いてみると、面白そうな仕事をしているなと思ったんですね。
※平成医療福祉グループ 医療政策マネジャー/坂上 祐樹先生 インタビュー記事
同じく元医系技官のお2人から話を聞いて興味を持たれたと。ほかの企業や医療機関からのお誘いもありそうですね。
病院を経営されている方や、医療系のベンチャー企業を経営されている方、ほかにもいろいろとお声がけはしてもらったんですが、ここがグループとしての規模もあるうえに、挑戦的な取り組みをしているなと思ったので、そこに魅力を感じて、移ってみようと決めたんです。
もともとグループのことはご存知でしたか。
グループの武久代表は、日本慢性期医療協会の会長ですし、診療報酬や介護報酬の改定のときに委員をされていたので。直接話したことはなかったですが、講演などを聞く機会もあって、その時から面白そうなグループだなと思っていました。
主にどんなところに興味を持ったのですか。
自分が診療報酬改定を担当している時に、栄養やリハビリの大事さを知ったんですが、グループとしてそこに対して積極的な取り組みをしているという話を聞いて、興味を持ちました。それと、このグループには地域密着多機能型病院(※)を目指す、というメッセージもあると思うんですけど、病院があって介護施設があって、地域で患者さんをサポートしていく、ということの重要性も、診療報酬の仕事を通じて理解していたんですね。単体の病院だとそれを実践するのはなかなか難しいんですが、大きなグループだからこそ、そういうことに関われるというところが、面白そうだなと感じました。
興味を持った取り組みに、包括的に関わることが、このグループならできるんじゃないかと。
それが決め手としては大きかったですね。そこで、坂上先生に連絡をして、話を聞かせてもらいました。

まずは臨床の勘を取り戻す
経験を生かしながら病院運営に
そこで、平成横浜病院に着任することになったわけですね。
坂上先生もインタビューで同様の話をしていたと思うんですが、医系技官として働いている間は臨床からずっと離れていましたから、まずは半年間、臨床を鍛え直してほしいということで、この病院であらためて臨床に携わりました。病棟を担当して、そこで森岡先生(※)に研修医のようにつかせてもらいました。
※平成横浜病院 診療統括部長/森岡 研介先生 インタビュー記事
平成横浜病院
久しぶりの病院の現場はいかがでしたか。
最初はやっぱり難しかったですね。ブランクがあるので薬の名前がすぐ出てこなかったり、どういう選択をしたらいいのかっていうことで悩みましたけど、その都度、森岡先生や看護師さんに相談をして。毎回丁寧に教えていただいたので、乗り切ることができました。
訪問診療も担当されたそうですが、それまで経験はありましたか。
初めての経験でしたけど、興味深かったです。グループ介護施設への訪問にもついて行かせてもらって、医学的な面はもちろん大事にしながらも、生活の場でもありますから。どういう治療を望まれているのかを伺って、スタッフさんともどんな形がいいのかを話し合って進めていきました。介護の仕組みを前職で学んできたので、経験も生きたのかなと思いますし、やりがいを感じましたね。
半年経った現在はどんなお仕事をされていますか。
今も訪問診療と外来診療は担当させてもらいながら、事務長の日高さん(※)と一緒になって、病院の運営に携わっています。
※平成横浜病院 事務長/日高 正明さん インタビュー記事
運営には具体的にどのように関わっているのでしょう。
院内でうまく運用ができていないケースとか、ルールが明確になっていないケースについて、各部署のスタッフさんと話し合いながら、決めていっています。それと、前職での経験を生かして、例えば感染症対策で、国のこのルールを利用して補助金を活用して、この戦略で進めていこうとか、そういうことも話し合って進めていますね。
そこは厚労省出身であることが生きていますね。話し合う機会も多くありそうです。
そうですね、勝手に決めるわけにはいきませんから、日高さん含め、各部署の方と話して、うまく解決策や折り合えるポイントを見出していっています。
厚労省時代に、いろいろな職種の人と話し合ってきたことも生かせていそうですね。
そういう意味では、運営の仕事はある程度自分の経験を生かしてやれているかなと思いますね。
平成横浜病院は風通しの良い環境
実際に平成横浜病院に入ってみて、現状と今後についてはどうお考えですか。
もともとここは企業経営の病院としての歴史がありますけど、時代の変化とともに求められるニーズや患者さんの層も変わってきますので、病院としても変わっていく必要がありますよね。ただ、それは簡単ではないというか、単純にこれをやればいい、ということではないので。日々の診療からそれを感じ取っていって、積み重ねて改善していけたらと思っています。
今後変わっていくには、変化を肌で感じながら積み重ねていくと。そういうなかでも、この病院でどういったところが良いと思われますか。
もともと急性期の病院機能を有しているところにに回復期リハビリテーション病棟もあって、グループの介護施設とも連携ができて、さらに訪問診療も始まっている、まさに多機能を提供できる状態にあるので、そこは大きな強みだと思います。あとは、そこをどういうバランスでやるとより良くなるか、というところです。
まだまだ企業経営時代のイメージを持たれている方も多そうです。
外来の患者さんは、その頃からずっと来てくださっている方も多くて「この病院が好きなんです」と言ってくださることもありますね。ただこれからは、そこからさらに今のグループの強みであるリハビリとか栄養のことや、多機能のことについても認知が高まって、それを実際に求められる病院になるといいなと思いますね。
地域からしっかり求められる病院になっていくと。
そのなかで、平成横浜病院で特にいいと思ったのは、風通しがすごくいいところです。僕が入る前から、問題があっても、すぐバッと集まって話し合って決めよう、っていう風潮があったので、そういう意味ではやりやすいなって思います。柔軟に変化に対応できる環境が整っているので、うまくいくんじゃないかなと思っています。
より良くするために進めていきやすい環境が整っているわけですね。
ただ、医療の経営で難しいのが、好事例はたくさんあって、そういうケースが載った本もいっぱいあるんですけど、それを真似するだけではうまくいかないわけです。
やはりシチュエーションが違うと、こう事例を参考にしてもなかなかうまくいかない。
その通りで、患者さんや地域の状況も違いますし、自分たちの病院の持っているノウハウも違うので、やっぱり正解がないんですよね。だから、自分たちのなかでは「これがいいんじゃないか」っていうのを、常に話し合っているんです。

自分は便利屋でもいい
病院運営の困りごと解決に見出す喜び
今後はどういう動き方になっていくのでしょうか。
あまり先のことは僕自身わかりませんが(笑)、運営では、先ほどお話ししたように経験を生かせますし、なにより自分自身もすごく好きな仕事なんで、それで病院を良くしていけるようなお手伝いができたらいいですね。
医療現場のことも把握しながら、運営・経営にも携われる人材というのは、まだまだ少ない。
最近は多少増えているかもしれないですね。ただ、やっぱり臨床をやるということが医師のキャリアパスとしてはもともとあって、その年次が上がっていくと、管理職や経営に携わることになる、というケースが多かったと思います。とは言え、経営について学ぶ機会というのは多くないですから、みなさん独自に苦労しながら、模索してやってこられたんだと思います。
まさにグループでは病院運営や経営に携われる方を求めています。
いわゆる経営に携わりたいと希望する医師はなかなかいないんですが、医療もこれだけ制度が複雑になって、考えないといけないことが多いですから。今後はある程度そのスキルも求められてくるのかなと思っていますし、自分もその道でキャリアを積んでいければと思っています。
周りにもそういう志向の方は増えてきましたか。
最近の医学部の若い学生さんと話してても、経営に興味があるんですっていう話も聞きますし、起業されて医療系のベンチャーをやっている方からも、そういった話を聞きますね。ただ、医療の世界は理想だけでは動かなくて、実際の臨床と、医療政策、さらに経営や技術革新がうまく合致しないといけないので。そのバランスをうまく取れるとか、バランス良くそういった経験をしている、ということは大事になってくると思います。
どれかひとつに偏ることなくと。
そういう意味では、ここに入職した時に、いきなり運営ということではなくて「まず最初は臨床をやってほしい」と言われたことは、自分としてはとてもありがたかったです。
今はどんなモチベーションでお仕事をしていますか。
課題はいろいろあったとしても、これをやったら病院が良くなるんじゃないかっていうアイデアもありますから、それで病院がよくなると本当にいいなって思うと、やっていて面白いですね。さっき医師のキャリアパスの話もしましたけど、なかなか僕ぐらいの年齢でこういう経験をさせてもらえることも少ないですから。それをやらせてもらえる環境はありがたいですし、本当に楽しいですね。
ご自身としては今後グループでどういうことをしていきたいですか。
病院の運営には携わっていきたい、ということはあるんですが、結局は求められるものをやっていきたいです。厚労省時代も僕はそうだったんですけど、課題があってそれを解決するっていうのはどちらかというと得意だし、喜びを感じるので、ある意味便利屋でもいいかなと思っています。運営面でお手伝いできることがあって、それでグループが良くなっていけばいいですね。

一年休んでも読んでいたいくらい
とにかく本当に本が好き
ではプライベートのお話を伺います。お休みの日はどのように過ごしていますか。
僕は読書がめっちゃ好きなので、ずっと本を読んでいます。
仕事に関する本が多いですか。
そこはもうあまり境目がないですね。半分趣味じゃないですけど、例えば経済学とか経営に関してはもともと興味がありましたから。
そういうジャンルの本が多いのですか。
あとは哲学とか歴史も多いですし、今は知識を業務にも生かせる立場になっているので、読んでいても、楽しくてしょうがないですね。本当は一年くらいずっと休みをもらって読んでいたいです(笑)。
(笑)。本当に読書がお好きなんですね。
新しいものとか知らないものに対して、すごく興味を持つので、例えば理系の本を読んでいても、歴史のことが触れられていると、今度はそこを勉強してみよう、となりますし、飽きが来ないですね。
ちなみに本は紙派と電子書籍派、どちらですか。
最近は、電子書籍がけっこう多いですね。あとは、車に乗る時もオーディオブックを流して、読書しながら移動していますよ。
筋金入りですね…! ほかに趣味は何かありますか。
最近は行けてないんですけど、キャンプが好きですね。少し前に子どもが生まれたので、もうちょっと大きくなったら、一緒にファミリーキャンプがしたいです。
いいですね〜! 初めてのお子さんですか。
1人目です。もうめちゃくちゃかわいいですね。ここで働き始めてからは、まだ子どもが起きてる時間に家に帰れるので、毎日それが楽しみで仕方ないです。
ご家庭の時間も増えたんですね。
そうですね、子どもができるくらいのタイミングでちょうど前職から離れたこともあって、やっぱり家族とそういう触れ合える時間が圧倒的に増えたのは、本当に良かったと思います。

プロフィール
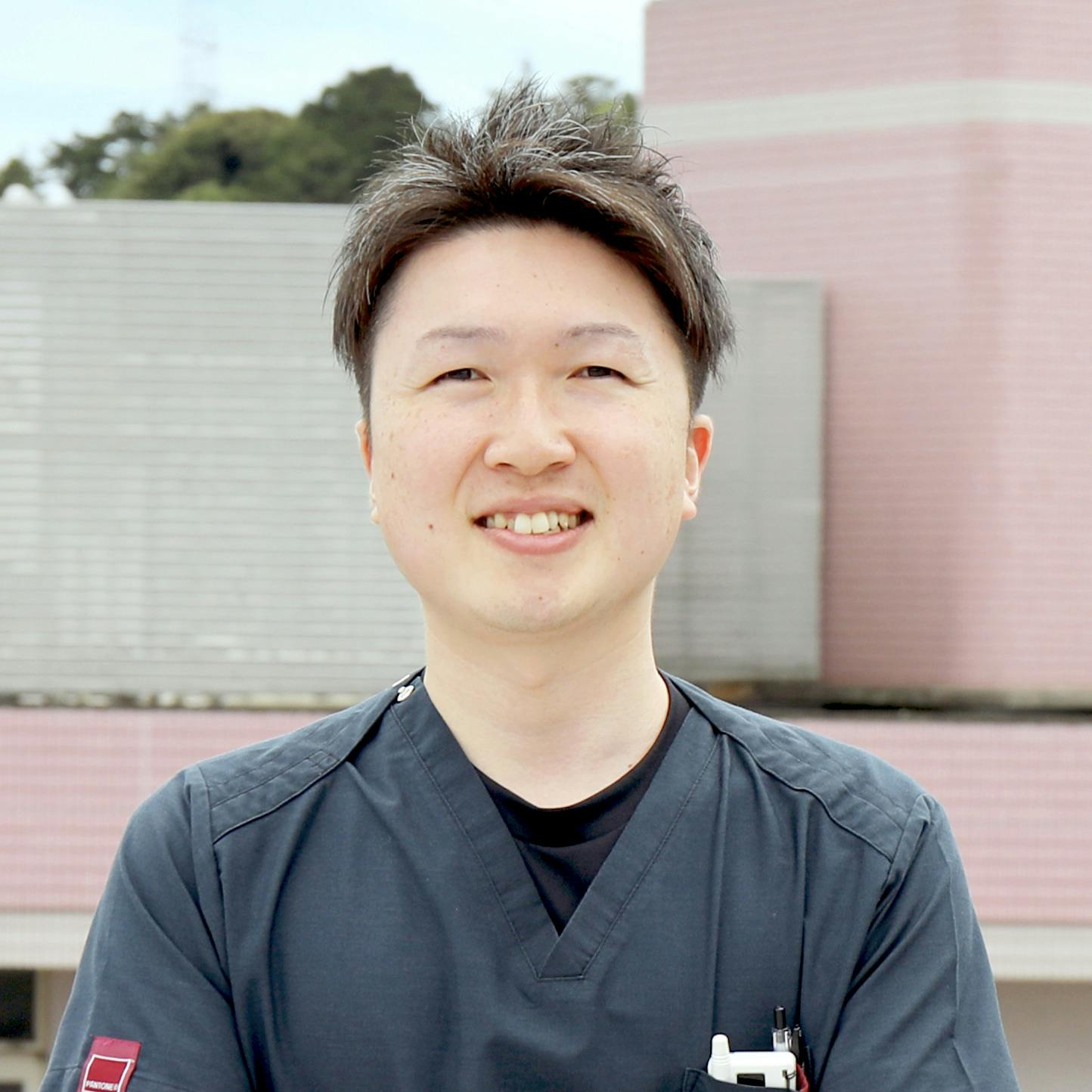
平成横浜病院
天辰 優太先生
あまたつ ゆうた
【出身】大分県大分市
【専門】内科
【趣味】読書、キャンプ
【好きな食べ物】ラーメン(岐阜の麺屋白神がおいしい)
病院情報

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550番地
https://yokohamahp.jp/
医療法人横浜 平成会
平成横浜病院
内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・外科・泌尿器科・皮膚科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科・脳神経外科
地域に根ざした病院として、一般病棟、地域包括病棟を備え、回復期リハビリテーション病棟を新設しました。さらに救急告示病院として24時間365日、患者さんの受け入れを行っています。2018年6月には、総合健診センターがリニューアル。地域の健康を支えていけるよう努めています。





