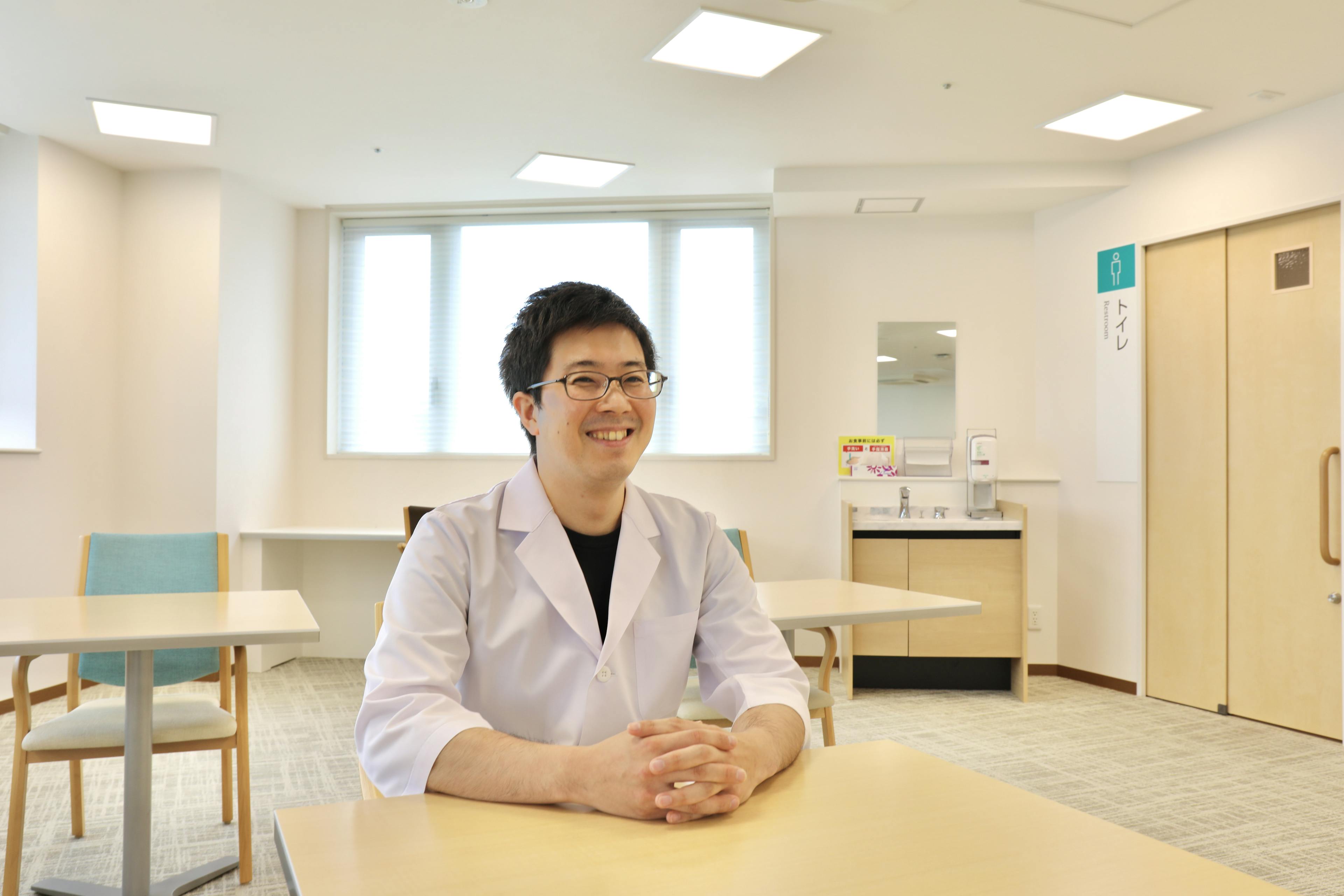薬大好きな文学少女が病院薬剤師として活躍するまで/平成医療福祉グループ 薬剤部 部長/秋田 美樹さん
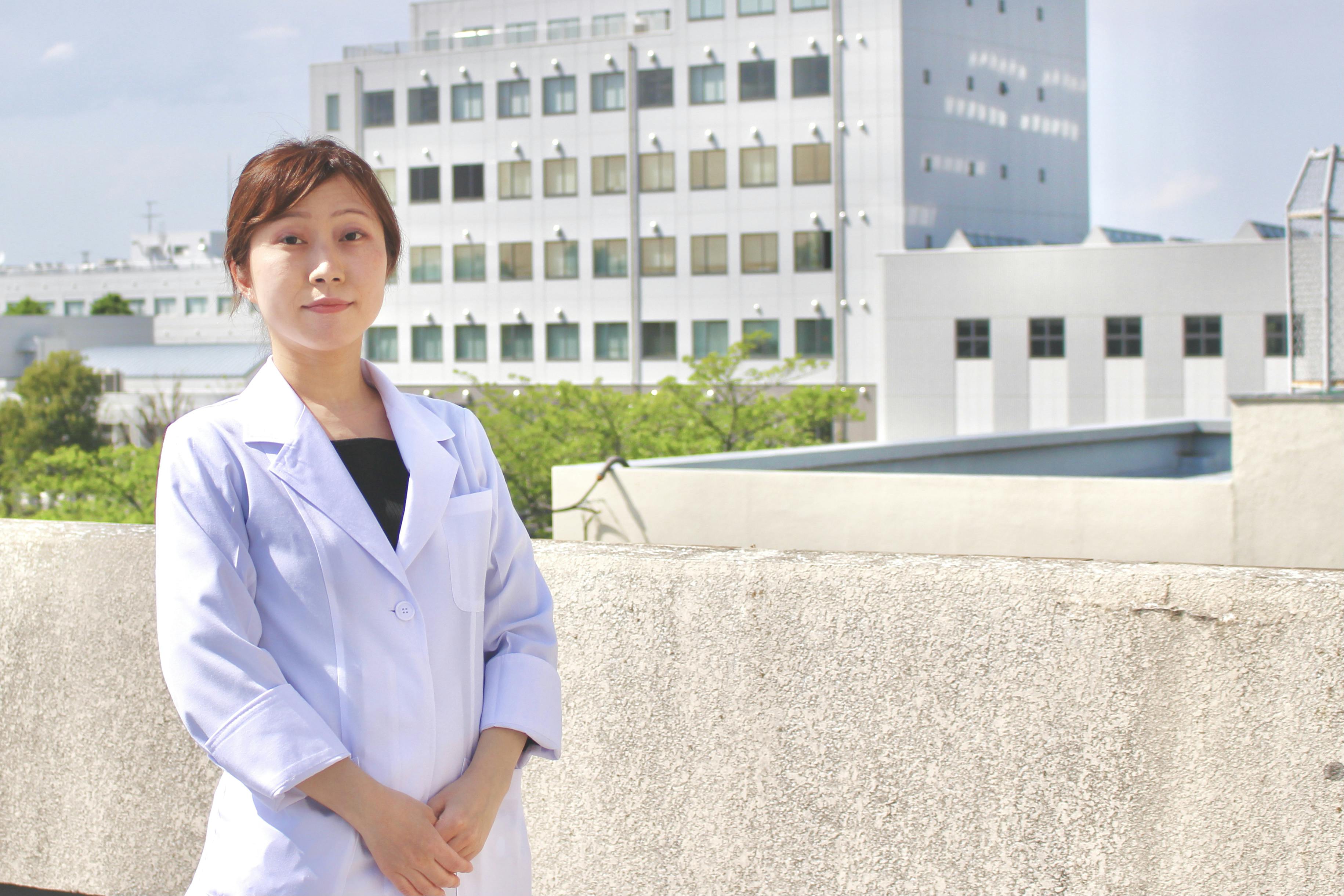
薬大好きな文学少女が
病院薬剤師として活躍するまで
グループの薬剤部で部長を務める秋田美樹さん。小学生の頃は「良くも悪くも目立っていた」と語る秋田さんは子どもの頃から多趣味で、文学や芸術、合唱などさまざまな分野に興味を持つなかで、当時からすでに「薬が好き」だったと話します。そんな秋田さんの小学生時代のエピソードや、子どもながらに薬を好きになった理由、「もともと良くないイメージを持っていた」という病院薬剤師になるまでの経緯について、伺いました。
ぜひご覧ください!
周囲との違いを感じた小学生時代
今日はよろしくお願いします!
ここ最近のひとプロジェクトって、出ている方の空気感が近く感じませんか? 良い意味でAB型系というか、オタク気質というか、職人気質の人が多かったような気がして。
言われてみたら職人タイプの方も多かったかもしれないですね。ご自身についてはどう思われるんですか。
私もそのタイプというか、自分ではわかんないですけど、よく「変わっている」って言われるので、「そうなのかなあ」って。まあ褒め言葉だと思ってますけど(笑)。
(笑)。では早速、ご出身から伺っていきます。
東京都の東村山市です。残念ながら亡くなってしまいましたけど、志村けんさんで有名なところです。
「東村山出身の有名人と言えば」という感じですよね。東村山市はどんなところですか。
本当に「志村けんの街」です。お祭りも必ず『東村山音頭』ですしね。意外と踊れないけど。あとは何があるかっていうと、トトロの森ですかね。
『となりのトトロ』の舞台のひとつになったとされているところがあると。
緑が多くて空気が良くて。昔は結核の療養地みたいなところだったんですよ。今は転用されてますけど、もともと療養のための病院が多くて、トトロでも、主人公のお母さんが入院していた病院のモデルになったところが、東村山にありますから。
環境の良さが伺えますね。小さい頃はどんなお子さんでしたか。
う〜ん…昔から、良くも悪くも目立つんですよ。良く言えば、面白いとか個性的とか、元気とか、人からは言われるんですけど。小学校高学年になって思春期を迎えた時に、「ヤベッ」て思いましたね(笑)。
どういうことですか(笑)。
小学生って高学年にもなると、周りに合わせる同調圧力みたいなのが出てくるじゃないですか。そこから飛び出る感じはあったんじゃないですかね。それで、目立っちゃうなって思って、ちょっとセーブして。
「飛び出ない方がいいな」という意識を持ったんですね。
それで悩んだこともあったんですけど、周りの勧めもあって、中学校は地域の学校ではないところに入ったんです。そうしたら今度は周りに、良い意味で個性的な、天才タイプの人が多くて、むしろ私が地味なくらいでした。
ドラッグストアで
薬を眺めるのが好きだった
では中学時代にはだいぶ環境が変わって過ごしやすくなって。その頃はどんなことに興味がありましたか。
多趣味というか、いろんなことに興味がありまして。まず小中学校の頃は特に本が好きで、真面目な本を読んでたんです。宗田理とか、群ようことか読んでいましたね。
小学生で群ようこは珍しいかもしれないですね。
それが高校生くらいになると、小野不由美とか須賀しのぶとか、時雨沢恵一とか、だんだんコバルト文庫とか電撃文庫に寄っていくんですよね(笑)。
趣向が純文学からライトノベルの方に移っていったと。文学好きだったのですね。
でも、それと同時に薬も好きだったんですよ。
えっと「薬も好き」というのはどういう意味で…(笑)。
家族とか親戚で薬を飲んでる人がいて、薬自体が身近だったのと、「なんでこれが効くんだろう」っていうことに小さい頃から興味があったんです。中学生になって電車通学になったので、地元にはない大きなドラッグストアにも行ける機会ができて「すごい! 楽しい!」って思って。
薬が並んでるのを見るだけで楽しかった。
だから学校帰りに、1時間とか2時間とかドラッグストアで薬をずーっと見てました。今から思えば、すげー変な子なんですけど(笑)。
中学生だと同じ趣味の人は少ないかもしれないですね(笑)。
友だちと一緒に行くこともあったんですけど、みんなは「早くプリクラ行こうぜ」って感じで。
文学も好きで、薬に興味もありつつと、文系理系にとらわれないタイプだったのですね。
どちらも面白いなと思っていましたし、美術系のことにも興味がありましたし、いろいろ興味がありましたね。
ちなみに部活動などはされていたのですか。
中学・高校と合唱部でした。歌うのも好きでしたね。ハモると気持ちいいんですよ〜。

薬剤師と臨床心理士との
2択で迷う
それだけいろいろと興味を持つなかで、薬学を選ばれたのですね。
実は、臨床心理士と薬剤師の2つで悩んだんです。進路を選ぶ時は本当に迷いました。
臨床心理士にも興味があったのですか。
高校の倫理の授業がすごく面白くて、そこで臨床心理士という仕事があると知ったんです。薬剤師も臨床心理士も、どっちも医療系という点では同じベクトルなんですけど、アプローチの仕方が全然違うので。
その2択から薬剤師を選んだのはどんな理由ですか。
高校2年生の時の担任が化学の先生だったんですけど、私が迷ってるのを知ってか知らずか、すごくいろいろ教えてもらったり良くしてもらったりして。「化学って楽しいな」とあらためて思うことで迷いも吹っ切れたんです。それで薬学部を目指すことにしました。
薬学の基本となる化学の楽しさに気付かされて、背中を押されたのですね。
あと、当時はまだ薬学部が4年制だったんですけど、ゆくゆく6年制になるっていう話も出てたんですね。臨床心理士の方は、こないだの「ひとプロジェクト(※)」でも話題にありましたけど、資格を取るには大学に4年行って、さらに大学院で2年学ぶ必要があると。でも薬剤師は「今なら4年で取れるな」と思ったというのもありました。
※世田谷記念病院 臨床心理士・公認心理師/岡崎美帆さん インタビュー記事
4年で学べるうちに学んでおこうと。やはり4年制と6年制ではだいぶ様子が違うのでしょうか。
授業がギュッとしてましたね。大学ってバイトをするとか、余裕のあるイメージだったんですけど、みっちりで。さらに研究室に配属されてからは、夜10時とか11時までは研究していましたし。
いわゆる「キャンパスライフ」という感じではなかったんですね。以前にインタビュー出ていただいた薬剤部課長の入間川さん(※)は、学生時代のバイトやパチンコの話もされていました(笑)。
きっと上手いことやってたんじゃないかな(笑)。
※平成扇病院/薬剤部 課長 入間川 寿々可さん インタビュー記事
(笑)。どんな講義が興味深かったですか。
「薬理学」ですね。薬がどの受容体にどのように作用して、どう効くかっていうことを学ぶんですね。ちなみに最近、グループの聖和看護学校で薬理学の授業を担当させてもらっているんですよ。教える側は難しいですけど、化学の楽しさを少しでも感じてもらいたいなと思っています。
ご自身が最初に薬に興味を持った時のように、興味を持ってもらえるといいですよね。どの職種でも、学校で学んだうえで「いざ現場に出たら全然違った」ということはよくあると思うんですが、いかがでしたか。
それはもう全然違いますね。基礎知識を詰めておくことは大事なんですけど、ほとんどは現場に出てからの勉強ですから。基本的な授業の内容は、電子がどう移動してここの結合が切れて、この反応がどうこう、とか、もちろんそれはそれで大事なんですけど、実際にほかの職種のスタッフとか患者さんにはその情報を噛み砕いて話さないといけないですから。
知識をどう使うかは、実践が大きいと。忙しく過ごしていたのでは、サークルなども特に入らず。
でも、生薬研究会に入ってましたね。薬用酒を作ったり、軟膏を作ったり、生薬を入手して漬けたり加工したりとか。東大和に東京都の薬用植物園があるんでみんなで行きましたよ。檻の中で麻薬も栽培しているんですよ(笑)。
(笑)。なるほど、なかなか専門的な植物園があるんですね。

生意気だった新人時代
気がついた「聞く技術」の重要性
就職はどのように考えられたんですか。
あんまり考えてなかったです(笑)。ただ、当時は病院で働くというのは考えのなかにありませんでした。
どういった意図でそう思ったのでしょう。
実習で行った急性期の病院で、上下関係が厳しいなか、仕事もずっと同じことをやり続ける、っていう経験をして、すっかりそのイメージがついてしまったんですね。
なるほど。もちろんそれは一例だったとしても、秋田さんのなかでは病院にそういったイメージがついてしまっていたと。
1日中地下室にこもる作業を半年以上毎日やり続ける様子を見て、これは私には向いてないなと。で、学校に就職説明会とかでいろんな企業が来るんで、そのなかから決めちゃったという感じですね。
どんなところに入ったのですか。
調剤薬局併設のドラッグストアを運営している会社でしたね。ただ、今思うとその時は本当に世間知らずだったので、すごく嫌な新卒だったなと思って、穴掘りたいですね…。
思い返しても、穴があったら入りたいくらいの生意気さだったのですね。
本当に何もわかってなかったので、生意気なことをたくさん言って迷惑かけたなって、今は反省しています。「なんでこうじゃないんですか」とか、いろいろ言って協調性がなかったですね。上の人の苦労も理解せず、自分の主張ばっかり言ってた気がしますし…ああどうしよう!
過去の話なのできっともう大丈夫です(笑)。
でも、そんな生意気な新卒にも、薬局主催の健康相談会とかイベントを任せてくれたんですよ。血圧とか糖尿とかをテーマに企画して、実際来てくれた人の血圧を測ってアドバイスをしていましたね。あとは薬の説明書きを一生懸命作ったり、そういうことも早期に割と目覚めていました。
そうやって患者さんと接するとか、わかりやすく伝えるとか、まさに授業だけでは学べない部分ですね。
特にドラッグストアや調剤薬局に来られる患者さんって、どちらかと言うと、話を聞いてほしい方も多いんですね。これは「聞く技術」がいるなと思いました。後々、地元の調剤薬局に転職したんですけど、そこでも聞く技術の大切さを学びましたね。
どんな調剤薬局だったんですか。
60歳を超すベテランの薬局長さんが切り盛りしている地域密着の調剤薬局でした。その方がもうカリスマ的で、聞く技術が本当にすごかったんです。みんな「カリスマと話したい」って、処方せんを持って来ていましたね。
じゃあ、その薬局長さんと話したくて、わざわざ来る人がいて。
ほとんどがそうだったんじゃないですかね。薬の説明がわかりやすいのはもちろんなんですけど「息子さんは最近どうですか?」「お嬢さん大学合格されたんですね」とか、患者さんのことをちゃんと覚えて話をしていて、みなさん気分良く帰って行かれるんですよ。
まさに地域のみなさんに愛される薬局になっていたんですね。
そこまでなるには何十年とかかりそうですけど、本当にすごい話術だなと思いましたよ。

一度は病院で働こうと決意
緑成会病院リニューアルのタイミングで入職
このグループで働くようになったのはどんな経緯がありましたか。
ちょうどその調剤薬局で働いていた頃が、近所の緑成会病院の運営が平成医療福祉グループに変わってリニューアルオープンになるタイミングで、たまたま求人募集のチラシが入っていたんです。
求人チラシを見たところで、いざ移ろうと思ったのはどうしてですか。
先ほどもお話ししたように、学生時代から病院で働くこと自体に抵抗がありましたし、仕事も職人的にカッチリしていて厳しいというイメージを持っていたんですね。
そもそもは進んで病院を職場にしようとは思っていなかったと。
しかも病院に入ること自体、とても難しいというイメージがあったんですね。でも、そのうち6年制の薬学部を卒業する学生も出てくるというタイミングで、病院で勤務したことのない私が、もし病院の仕事を経験するとしたら、挑戦するのはもう今しかないんじゃないかと思ったんです。
なるほど、つまり一度は病院の仕事も経験してみようと思って、それにはこのタイミングしかないと判断したのですね。
調剤薬局のみんなには「ちょっと修行に行ってきます」って言って転職しました。みんなも「行ってらっしゃい」って送り出してくれたし、だから本当は今も修行の身なんですよ(笑)。ただ、その薬局も途中で経営が変わってしまいましたし、いざ緑成会病院に入ったらそれどころじゃなくなってしまい…。
今や部長ですからね。実際に緑成会病院に入職してみて、どんな印象でしたか。
実習の時から、病院は怖いとか硬いっていう印象だったんですけど、いざ入ってみたら、ヘルプで来てくれていたグループ病院の人たちが、淡路弁や阿波弁でホワーッと話していて。
言葉が柔らかい印象がありますからね。淡路島や徳島のグループ病院からヘルプで薬剤師さんが来てくれていたわけですか。
そうです。それが、私が思っていた病院のイメージと全然違って。しかも、けっこう臨機応変にいろいろものごとも決められていて、そこもギャップがあったところですね。
もともとグループ病院の仕事の仕方がそうだったと。
グループ病院の特長でもあると思いますし、慢性期医療だからこそというところもあるかもしれないですね。
これを私が決めるの?!
病院の仕事で感じたカルチャーショック
病院でのお仕事はどのように掴んでいったのですか。
当初は、さっきお話ししたヘルプの薬剤師がいて、その方がまたすごくいい人で、ほとんどすべてを教えてくれて、そのやり方を吸収しましたね。
実際に病院の仕事自体は、調剤薬局でのお仕事と比べて、どう違いを感じましたか。
全然違いましたね。調剤薬局って、処方せんをもらって、処方された薬の量とかはもちろんチェックするんですけど、患者さんがどうしてこの薬を飲んでいるかとか、どうして処方量が増えたとか減ったとかっていうことは、患者さんに聞くしかないんですよね。逆に病院では、むしろ処方理由を医師から聞かれるんです。「これはもういらないんじゃない?」とか、「これどう思う?」とか。それがカルチャーショックで。「えっ、私決めるの!?」って(笑)。
その判断に入り込むのは大変そうですね。
処方せんを出す前に相談をもらうんですけど、最初は聞かれても答えられなくて「ごめんなさい!」って感じでした。なのでめちゃくちゃ勉強しましたし、勉強するうちに聞かれたことにも答えられるようになっていきました。「この量でいけますよ」とか「減らしてもいいと思いますよ」とか、そう言えるようになるまでに何年もかかりましたね。
先ほど、急性期と慢性期の違いというような話もされていましたが、どういった違いがあるのですか。
まず慢性期病院では急性期病院と比べて、入院期間が2カ月、3カ月と長いので、検査値を追っていきやすいということがあります。それと、1人の医師に対して患者さんの受け持ちが多いので、薬については薬剤師が任せられる部分も大きいです。さっき言ったような判断とか、副作用の疑いとか、血液中の薬の濃度を確認したりとかは、薬剤師の役割にもなってくるんですよね。
任せられる範囲も大きいと、それは相当鍛えられそうですね。
鍛えられましたね〜。いい意味でなんでも任せてもらえましたし、すごく感謝してます。任せられると無責任なことも言えないので勉強もたくさんしました。
院内での立場も変わっていかれたのですか。
主任になりましたね。と言ってもその時は人が足りてなくて、薬剤師は私しかいなかったんですけど(笑)。

思いがけず薬剤部の部長として立つことに
ポリファーマシー対策に取り組む
今のようにグループの仕事をするようになったのは、どんなきっかけがあったのですか。
入職して5、6年した頃、グループの代表と副代表に呼ばれたんですね。しばらく雑談をした後に「仕事ぶりを見込んで、関東エリアの病院を任せたい」と。
秋田さんが入職した頃は、関東のグループ病院は緑成会病院と緑成会整育園だけだったと思いますが、その頃はまた病院が増えていて。
そうですね。ほかにも、世田谷記念病院、多摩川病院、大内病院と、関東でも病院が増えていました。ただ、私の担当はいつの間にか関東だけじゃなくて全国の病院になっていたんですけどね(笑)。
ではもう、すぐに関東エリアの担当から、今の役職である薬剤部の部長に。
そうですね。全国と聞いて「ギョギョッ」とは思ったんですけど、自分としては関東を担当するだけでもかなり大きなことだったのが、さらに大きな話が来たところで、もうサイズ感がよくわかんなくなってて(笑)。
関東も全国も一緒だと(笑)。では緑成会病院の仕事も手放して、グループの仕事に移っていかれて。
最初は病院の仕事も並行していましたが、そこから私以外の常勤スタッフや非常勤のスタッフが増えていったので、徐々に任せていきました。本当にみなさんに助けられましたね。
当時はグループ内で薬剤師同士の横のつながりはあったのですか。
ほとんどなくて、年に1回講演会で顔を合わせる程度でしたね。部門の研修会もその時はまだありませんでした。
その状況で、どんなお仕事から始まっていったのでしょう。
最初はポリファーマシー(※)対策のマニュアルを作るところと、自動分包機を導入するところからでしたね。
ポリファーマシーの取り組み自体は、もう始まっていたのですか。
私が緑成会病院に入職した時からグループの理念としてはあって、当時は「5剤制限申請書」と言って、内服薬が5剤を超える場合は申請書を書くという制度がありました。
処方する薬がむやみに増えないようにと。
そういう考えは根底にあったんですけど、じゃあ実際どう取り組んでいくのか、どの薬に気をつけるか、どういった薬を提案するのか、医師や看護師さんとどう協力していくか、っていうフローはまだこれからの状態だったんです。
ちなみに、ポリファーマシーの概念自体はいつ頃から始まったものなんですか。
日本老年医学会が、2000年代前半には提唱はしていました。あとアメリカの方では既に「ビアーズクライテリア(Beers Criteria)」っていう、高齢者に使用するのに注意が必要だとされる薬剤の基準と一覧が提唱されていましたから。そういった概念はあったんで、グループでも割と早くに取り入れてたんだと思います。
もうひとつ取り組んだ、自動分包機の導入というのは。
当時は薬を手で調剤していたんですけど、そのことで業務の時間が取られてしまっていたので、自動でできる機械を導入しようと。その分、薬剤室にいる時間を減らして、できるだけ病棟に出ていこうということだったんです。そこで部長になりたての私が、機械とともに「どうも初めまして〜」って全国を回って導入をサポートして(笑)。
(笑)。なるほど、挨拶回りも兼ねて各病院を回られて行って。
関西や徳島の病院もそれまで行ったことがなかったですから。ただ、ニューフェイスがそうやって回っていっても、やっぱり最初は「ん?」と戸惑われることもありましたね。なので、まずは意識統一が必要だと思って、関東と関西で薬剤部の研修会を開きました。関西はエリア長さんもいましたから一緒に企画して。飲み会もして仲良くなって、というところから初めていきました。
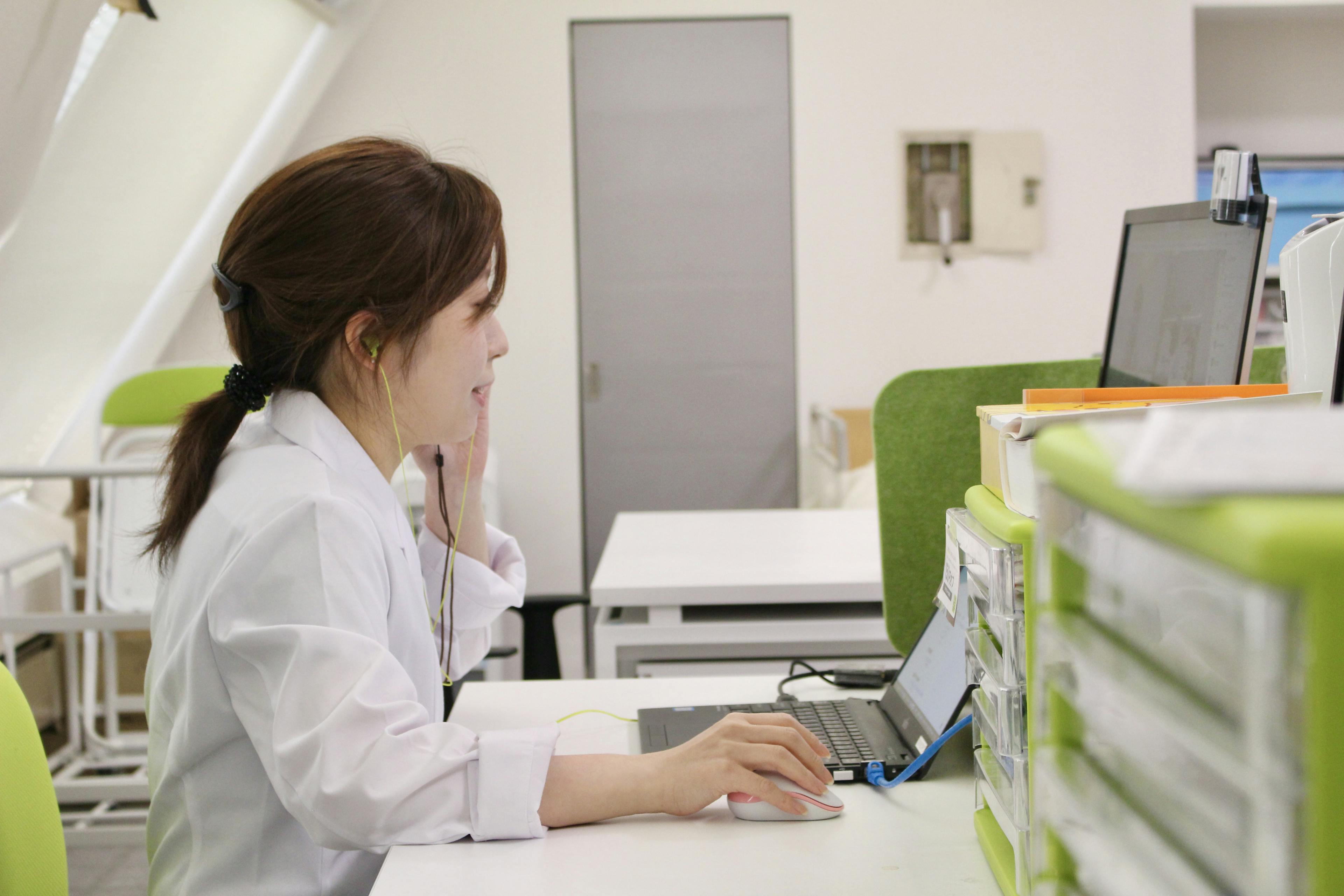
部門の体制づくりに力を入れる
学生のみなさんに慢性期の魅力をアピール
部長になってからは、部門の形や取り組みも変えていかれましたか。
例えば部門会にしても、最初は私が喋ることがメインだったんですけど、テーマを決めてみなさんに担当を振って、いろんな人に参加してもらう形に変えていきました。部門会自体が、年に何回もできるわけではないので、さらに意志統一や意識共有を進めるためにも、チームを作ることにしたんですね。
具体的にどういったことを進めたのですか。
業務支援チームや薬品情報チームといったチームを作って、ある程度の役職やリーダーシップのある方に参加してもらい、定期的にオンライン会議を開催していきました。そこでいろんなマニュアルや業務フローを作ったり、意見をもらって統一薬を追加したり。
積極的に部門内で意識を共有していったわけですね。
リクルートチームも立ち上げて、グループの人事部さんと一緒に学校訪問をしたり。そうこうしているうちに、6年制になった薬学部を卒業した若い力もたくさん入ってきました。
以前と比べて、グループ内の薬剤師の数も増えてきましたか。
だいぶ増えましたね。以前は、ひとつの病院に薬剤師が2人いれば御の字なところもありましたけど、今は病院によっては10名以上いるところもあります。そのおかげで、病棟での業務とか、いろいろできることも増えました。
部長に就任した当初は、そういった取り組みを進めたくても、人が足りなくて苦労されて。
今より全然いなかったですからね。当時は学生のみなさんに、グループ薬剤部の広報を全然できていなかったので、広報部さんと一緒にパンフレットを作って、人事部さんと一緒に学校に行って説明させてもらうと、だんだんと入職を希望する学生さんも増えていったんですね。
慢性期医療の病院を希望する方も増えてきたと。
くわしく聞いてみないとわからないですが、そうなっていたらいいなあと思いますね。新卒で入ってくれた人のなかには「最初から慢性期病院で仕事をしたくて入りました」とか「ポリファーマシー対策に取り組みたくて入りました」って言ってくれる人もいるので、慢性期病院の人気が高まっていると信じたいです(笑)。
リクルートではどういった点をアピールされていますか。
最近はコロナ禍で、直接ではなく、すっかりオンライン説明会が主流になってしまったのですが、その際にお伝えしているのは「調剤をすることプラスアルファで、どんどん提案とか、他職種と連携してチーム医療に関わりたい」っていう方を求めていますということですね。
基本業務としての調剤があって、プラスして病棟での業務などにも積極的に取り組んでもらうと。
薬剤師としては、病棟業務に出るより前に、まず調剤業務を間違いなく完璧にする、っていうことが第一ラインにはなりますから。そのうえで病棟業務もあって、両方大事ということですね。ただ、最近6年制を卒業して入職したスタッフは、病棟に出ていきたいと言ってくれる人が多いです。
なぜ飲むのかわからない薬を飲み続けているケースも
グループで力を入れるポリファーマシー対策とは
薬剤師が増えてきて、特に以前と変わったのはどういうところですか。
以前は、とにかくいかに調剤業務を行っていくか、ということがテーマだったんですけども、今だともう、ポリファーマシー対策も、病棟業務も配薬業務も当たり前といった感じで、どんどん変わってきていますね。
ポリファーマシー対策には、実際薬剤師がどう関わっているのですか。
まずは患者さんが入院してきた段階で持参薬について聞き取りをするんです。そのうえでわかりやすいように表を作って検査結果と照らし合わせて、どの薬を継続するかを医師と相談していきます。
「継続しない」と判断されるのはどういったケースなのでしょう。
聞き取りをしてみると、患者さん自身「この薬はなんで飲んでるのかわからない」とか「胃薬を10年以上飲んでいるけど、胃に症状は何もない」ということがよくあります。入院中は薬を減らした後の経過が見やすいので、薬を減らせる一番のチャンスなんです。もちろん、薬剤師だけでなく医師や看護師の協力あっての取り組みですね。
例えば10年以上飲み続けているということは、実際は不必要なのに、ずっとその処方が出ているわけですか。
血圧を下げる薬が処方されているけど、そもそも血圧が低いとか。90歳を超えて、血液をサラサラにする抗血小板薬や抗凝固薬を飲んでいて、もし転んだら大出血になっちゃうとか。抗精神病薬や睡眠薬とか、作用時間が長いものを処方されて、意識がドロドロになって食事やリハビリができないとか。そういう謎の処方があるんです。
取り組みは患者さんにご理解いただけていますか。
入院時に説明をすると、ほとんどの方にはご理解いただけます。むしろ「家で薬を飲むのが大変だったから、ぜひ減らしてください」っていう声が多いですね。
薬が多くなって、飲むタイミングがそれぞれ違う場合などは大変ですよね。
もう「エイッ」って嫌になっちゃいそうじゃないですか。それで、本当に大切な薬を「エイッ」としてしまって、再発や再梗塞とか、発作が起きてしまうっていうことが一番良くないので。「この薬は大事なので飲んでくださいね」とお伝えしていきたいですね。
病棟業務というのは具体的にどういったことを行っているんですか。
お薬が変わった時の服薬指導や薬の説明、それと先ほども話が出ましたけど、入院時の初回聞き取りもそうですね。あとは回診に同行して患者さんの不安や要望を聞いたり、リハビリスタッフさんと合同でカンファレンスを行って、薬についての相談を受けたりですね。あとは配薬の業務とか。まだ人数が揃っていない病院もあるので、全病院で均等にできているというわけではないのですが。
とは言え、人数が増えたことで取り組みの幅は広がったと。
そうですね、その点は本当に感謝ですね。入ってくれたスタッフにも、理解いただいて多く薬剤師を配置させてもらっていることにも感謝ですね。

目指すのは患者さんとスタッフの幸せ
少しでも仕事がしやすくなることがモチベーション
今に至るまで、部長として進めてきた仕事を振り返っていかがですか。
ここ5、6年は「薬剤部をいかにひとつにまとめていくか」ということが割と自分の中でのテーマだったんですけど、そこは割とできてきたかなと思っています。チームも立ち上げたし、関西でも関東でも、リーダーとして立ってくれるスタッフがいて、すごくありがたいことだなと。あとは、グループ統一薬の取り組みを進めていたんですが、昨年に医薬品管理センターを立ち上げて、より進めやすくなりました。
グループで使う薬品を統一するという取り組みですね。以前は各病院の薬剤部がそれぞれで交渉して購入していたと。
そうですね。統一することで、コストや価格交渉の面でのプラスが大きいですから。今までは各病院の担当者に苦労をかけていたんですけど、それを医薬品管理センターで一括してやれるようになって、必要な薬やいらなそうな薬について、情報共有できる体制も整いましたね。
今後の薬剤部について、展望はありますか。
今は、組織としてやっと形になってきましたし、リーダーシップを発揮してくれる人にも助けられ、新しい人も入ってきてくれて、すごくいい感じになってきているんです。今後はさらに、みんなの考える仕事のポリシーと、グループの方針を融合できたらいいなと。もし不安や不満があったとしても、それをチームや私に共有して、より解消できるようにしたいなと思っています。
熱意を持って仕事をする人にとって、働きやすさにつながりますね。
それと、今はエリア勉強会でも、みんな知識や技術をどんどん上げているので、いかにコミュニケーションをとって、それを他職種のスタッフに伝えていけるかっていうことも考えています。せっかくレベルが上がってきたところなので、それをどうアウトプットして、どう他職種と協働していくかっていうのが、今から数年のテーマだと思ってます。
病院内でも、もっと薬剤師の存在感が増していくような取り組みですね。
「薬剤師さんが病棟にいてくれて良かった」って、今も言ってもらえることもあるんですが、これを全部の病院で言われるようになるのが目標ですね。
個人的にこういうことをやっていきたいとか、もしくはこれをモチベーションにしている、ということはありますか。
う〜んなんだろう。薬剤部のみんなが幸せに働けたら、患者さんもほかの職種も幸せになれると思うので、まずはみんなを幸せにしようと思ってます。そうだ、グループにいた上長に以前言われた言葉を、唐突に思い出したんですけど。
どんな言葉ですか?
「薬剤師に必要なのは、薬の知識よりも、人の心を動かす力なんです。その点で、秋田さんは大丈夫だよ」って言ってもらえて、あれはありがたかったですね。
それは嬉しい言葉ですね〜。
私が部長になってから「仕事がよりやりやすくなった」って言ってくれる人もいて、それも嬉しいですね。まだまだな部分もあっていろいろ整備中ではあるんですけど、みんなが少しでも仕事がしやすくなって、病棟でたくさん活躍してくれることが、私にとってのモチベーションかな、って思ってます。

最近夢中なのは
癒しの存在「ベタ」
では最後にプライベートについて伺います。お休みの日はどう過ごしていますか。
最近はコロナの影響で出かけられなくなって悲しいので、去年の暮れから魚を飼い始めたんですよ。
おおっ、どういう魚ですか。
ベタっていう熱帯魚なんですけど、かわいいんですよ〜。最初1匹だったんですけど、今は4匹になりました。(ベタの画像を見せてくれる)

きれいですね〜。もともと熱帯魚が好きだったんですか。
そんなに興味があったというわけじゃなかったんですけど、家にいる時間が長くなったので、何かペットが飼いたいなって思って。この魚が人懐っこくて、ちゃんと私のことを認識してくれてますよ。本当かはわからないですけど(笑)。
今はそれが日々の癒しですか。
そうです〜。ご飯をあげるとパリポリ音をたてて食べるんですよ。あと、この魚がまた特殊で、エラとは別に「ラビリンス器官」っていうものを持っていて、空気呼吸ができるんですよ。
へーっ、変わってますね!
だからたまに水槽の上に来て空気呼吸してて。だからそれをボヤ〜ッと眺めてます。
ベタには名前をつけているんですか。
つけてますよ。みんな「ベッティー」です(笑)。
みんな同じなんですね(笑)。今後やりたいことはありますか。
コロナ禍が明けたら、御朱印集めをしたいんですよね。
新しい趣味ですか。
そうですね。そんなに密にもならないので、タイミングを見て去年くらいからちょこちょこはやっているんですけど。
歴史好きということもあっての趣味ですか。それともパワースポット巡り的なことですか。
両方ありますね。神社仏閣はもともと好きでしたし。
冒頭では、小説をよく読まれていたとお話がありましたけど、最近はいかがでしょう。
だんだん活字を読むのが辛くなってきていて、漫画は読みますけど小説は読まなくなってますね。今でも歴史ものは興味があるので、そういった題材の漫画は好きですよ。『進撃の巨人』とか『ゴールデンカムイ』とか。
『進撃の巨人』は少し前に連載が終了したばかりでしたね。
作者の諫山先生は天才ですね! 本当に全部、セリフとか話数とかにまで意味込めてるじゃないですか。読み返しても「こんなところにこんなことが描いてある!」っていうのがあるんですよ。テーマも、人種差別とか歴史とか、あとは帝王学とまではいかないまでも、リーダーシップについてとかも描かれていて面白いですよね!
緻密に描かれているところが魅力ですよね〜。今まで見てきたものや読んできたもので、強く影響が残ってるものはありますか。
う〜ん、なんでしょうね…いろいろ読んだ本とか漫画とか、満遍なく取り入れて自分になったんじゃないですかね。そのなかで言うと…小野不由美の『十二国記』はけっこう残ってるのかもしれないです。いやでもこれちょっとすごいオタクな話になってきたな(笑)。
(笑)。
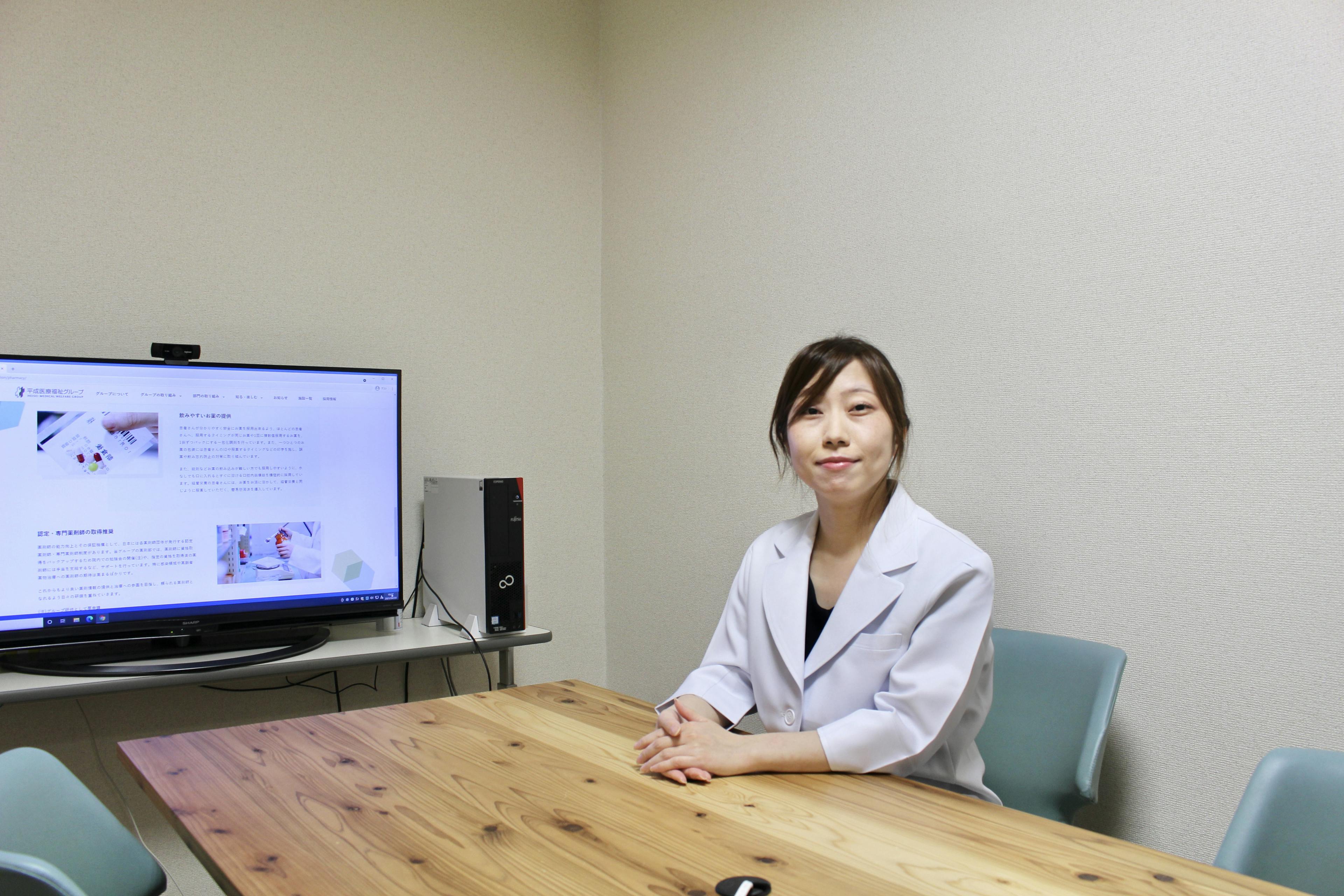
プロフィール
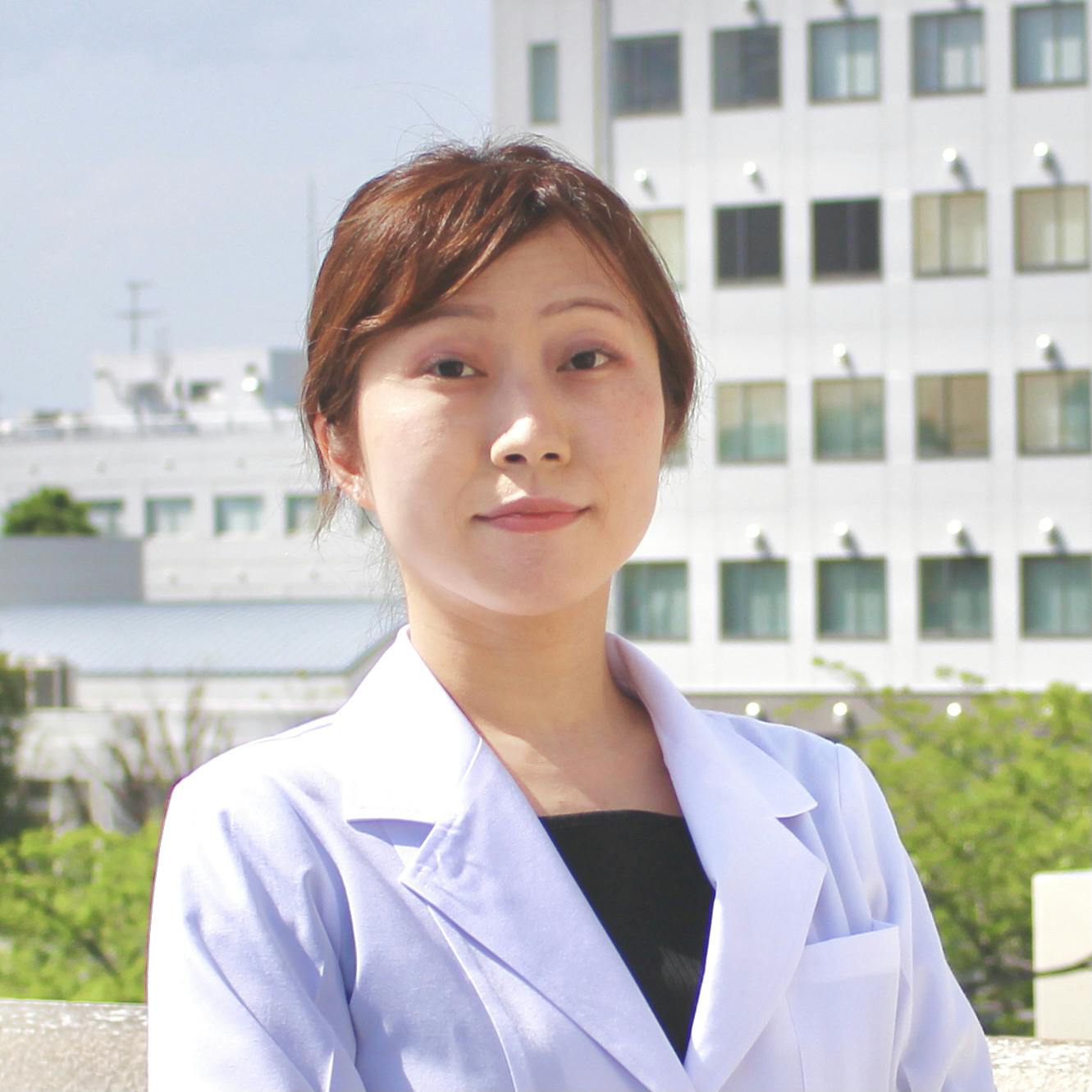
平成医療福祉グループ 薬剤部 部長
秋田 美樹
あきた みき
【出身】東京都東村山市
【資格】薬剤師
【趣味】読書、音楽鑑賞、ベタ鑑賞、御朱印集め
【好きな食べ物】今時じゃないタピオカ(フニャッとしたやつ)