喋ること、食べることが難しい方の助けになりたい!紆余曲折の末に目指した言語聴覚士の仕事/多摩川病院/言語聴覚士/長山 素世子さん

喋ること、食べることが難しい方の助けになりたい!
紆余曲折の末に目指した言語聴覚士の仕事
多摩川病院に言語聴覚士(ST)として勤める長山素世子さん。もともと医療職を目指していたわけではなかった長山さんには、STというお仕事の基本を聞きながら、ここに至るまでのバラエティ豊かなキャリアについてお聞きしています。高い売り上げをあげていたアパレル時代、意外な理由で勤めた院長秘書など、さまざまな過去も飛び出す前編、ぜひご覧ください!
名前の由来は、あの「親鸞聖人」
STの方がこの記事に単独で出られるのは初めてなのですが、長山さんは「STってどんな仕事ですか」と聞かれた時は、何と答えていますか。
簡単に説明するときは「主に首から上に関わるリハビリをする仕事だよ」とお話しています。さらに「嗅覚と視覚以外の機能に関わるリハビリ」ということもお伝えして。下から順に、呼吸、発声、嚥下、構音、聴覚、高次脳機能の障害に関わりますので。
どういった患者さんが多いですか。
多摩川病院だと、嚥下障害、高次脳機能障害が多いですね。患者さんの状態をしっかり評価して、一人ひとりに合わせてリハビリを提供しています。
では長山さん個人のことをお聞きしていきます。「素世子」さんというのは珍しいお名前だと思うんですが、どんな由来があるんですか。
母方の先祖を辿ると、有名な親鸞というお坊さんがいるらしくて。
えっ! 日本史の教科書にも載っている、あの有名な?
そうらしいです。私が第一子だったので、せっかくならそれにちなんだ名前にしようと考えたそうで。親鸞聖人の本を読んでみると「そよ吹く」っていう一節があって、その音の響きから取って「素世子」にしたみたいです。
なかなか一回で「そよこ」とは読んでもらえなさそうですね。
まず正解の読み方で読まれないです(笑)。
ベランダで毎日歌う幼少期
転校続きで人見知りを克服
ご出身を教えてください。
石川県の金沢市です。今は金沢駅の近くに実家が移ったんですが、当時は駅から少し離れた住宅街でした。
小さいときはどんなお子さんでしたか。
ずっと家の中にいて、絵を描くか、歌を歌っていたらしいです。おもむろにベランダに出て、外に向かって必ず毎日歌っていたらしくて(笑)。
大胆ですね(笑)。何を歌っていたんでしょうか。
何か当時のポップスとかだったんだと思うんですが。近所の人が、「あの子が歌い出したからそろそろ夕飯の買い物に行こう」って話していたと聞きました。
時計代わりに(笑)。家で遊ぶのが好きだったんですね。
幼稚園では友だちとも遊んでいましたけど、それ以外はほとんど家で1人で遊んでいましたね。でも小学校にあがって以降は、父の仕事の関係で北陸のなかで転校することが多くなって、人見知りしている場合じゃなくなったので、無理やりがんばるようになりましたね。
転校続きで鍛えられたんですね。
それと、親とか祖母が転校初日に学校に来て、同級生を何人か見つくろってきて「うちの娘をよろしく」って(笑)。それでどうにか友だちを作っていましたね。
豪快な作り方ですね(笑)。

英語科に進んだ高校時代
5弦で低音を奏でた大学時代のこと
ちなみに学生時代の部活動などは。
絵を描くのが好きで、ずっと美術部でした。でも高校では、英語を喋れるからという理由でESS(English speaking society)に入れられましたね。
では、英語はお得意なのですか。
祖父が大学の英文科の教授だったこともあって、「英語はできた方がいい」という方針が昔からあったんです。今はそんなに喋ってはいないんですけど、旅行先での日常会話くらいはできます。
それがSTの仕事に生きるというようなことは。
全くないです(笑)。でも一度、日本語がわからない海外の患者さんが病院にいらしたことがあって、その通訳をしたことはありました。英語力はともかく、発音だけは割といい気はします。耳がもともとよかったので、それがSTになる動機のひとつにもなりましたから。
耳が大事なんですね。ちなみに高校は普通科だったんですか。
私立の英語科に通いました。英語の授業の割合が多くて、英語でスピーチができるようになる、文章を書けるようになる、字幕なしで映画を見られるようになるとか、そういうことは授業でできるようになりましたね。
大学も英語関係に進んだのですか。
東京の私立大学の英文学科に入りました。
その時は、英語にまつわる仕事をしようという気持ちがあったんですか。
国際政経系の学部に受かったら、そういう仕事をしようかなと思っていたんですが、そちらには入れなかったので、もうやりたいことをやるために大学に行こうと思って進みましたね。
思い切りましたね! どんなことがやりたかったのですか。
とにかくベースを弾きたかったので音楽サークルにすぐ入りました(笑)。
ちなみにどんな音楽をやられていたんですか。
小さい時からもともと音楽が好きだったんですけど、大学のサークルで音楽のジャンルが決まっていたんですね。ソウルとか、当時でいうアシッドジャズとか。有名なところだとジャミロクワイとか。
あーなるほど、じゃあネックが幅広い5弦とか6弦のベースを弾かれて。
そんなすごいものではなかったです(笑)。でも5弦ベースは買いました。
かっこいいですね〜!
インカレサークル(※)で、7つの大学が一緒になってやっていました。みんなで大きい会場を借りて、ライブをやって、楽しかったですね〜。単位はギリギリ落とさなければいい、っていう感じでした(笑)。
※インターカレッジサークルの略。複数の大学の学生が合同で活動するサークル。
アパレルの販売員に!
全国的な売り上げをあげながら退職
大学卒業後すぐにSTになられたわけではないんですか。
そうですね。卒業後はアパレル業界に進みました。
また医療とは全然違った世界ですね。
販売員になりたかったんです。もちろん、洋服が好きだったのと、パッと見てどんなことをやるのかわかる仕事に就きたいなと思ったのもありました。販売員ならイメージしやすかったので。
どんなところで働かれていたんですか。
最初に、新宿の百貨店に配属になりました。
最初の配属にしてはなかなか大変そうな場所ですね。
まさに、すっごい大変でした。当時、そのブランドが、その百貨店のファッション部門で1位か2位の売り上げだったんです。私はなぜか最初にそこに配属になってしまい。先輩たちがたくさん売り上げをあげるなか、私は全然売れないので、毎日毎日怒られてましたね。
それはきついですね…! ただ、実際そうやっているうちに、売れるようになってくるんですか。
なりました(笑)。なぜなのかいまだにわからないですけど。
ほかの店舗でも働かれたんですか。
今度は、同じ新宿の別店舗に行きました。そこがお店の広さの割に売上が低かったので、テコ入れが必要とのことで配属になって。
実際それでそのお店の売り上げは…。
(間髪入れず)上がりました(笑)。
おお〜っすごい! いざテコ入れのために配属されて、何をどうすればいいというのは、わかるものなんですか。
何となくはわかります。一緒に移って来た先輩たちも、ものすごい売り上げる人だったので、場所だけで売り上げは決まらないんだな、と思いましたね。
のちにアパレルを辞められたのは、どういう理由だったのですか。
日々販売をしているうちに、毎月のノルマがどんどん上がっていくんですね。「ノルマを達成できた!」と思っても、すぐ次の日ゼロに戻るっていう生活を1年に12回繰り返して。個人の売り上げもお店の売り上げも上がりましたが、「私はこの仕事をいつまでできるだろう」と考えた時、少なくとも私にとっては、ずっと続けることは難しいなと思ったんです。
長山さんご自身としては、厳しいという判断だったんですね。
でも中途半端では辞めたくないと思ったので、自分の中で「今日から1年間、お店の売り上げトップを守って、かつ全国の販売員の10位以内に入り続けることを継続できたら辞めよう」と決めたんです。
ちゃんとやり切ってから辞めようと。
そもそも、そんなことはできるはずないと思っていました。でも、それを1年続けられたんです! 気持ちよく「辞めます!」って言えましたね。周りからは止められましたけど、私としては、服はもう気が済むくらい売ったなと(笑)。

意外な動機で就いた院長秘書
次につながる貴重な経験
STにはどうやって辿り着いたんですか。
それがすぐ辿り着かないんですよ(笑)。アパレルをやめてから、全く違う仕事をしようと思って。そこから病院で仕事をし始めました。
医療系にはなったんですね。どういうお仕事でしたか。
院長の秘書を務めました。都内にある、割と長く続いている病院でした。
どういった動機で院長秘書になられたのでしょうか。
これが、少し腹黒い話なんですが…(笑)。その頃、私の地元の友だちが、だんだん結婚し始めるんですよ。それで親からも地元でのお見合い話が来まして。私としてはそれが嫌だったので、どうにかして東京に残る理由が欲しかったんです。
なるほど、意外な事情ですね…(笑)。
父が耳鼻科の開業医をしていたので、耳鼻科じゃないにしても、父の先輩のような人と近いところで仕事をすれば、地元に呼び戻すようなことはしないはず、と考えて(笑)。そこに、耳鼻科の専門病院で院長秘書の募集が出ていたので、「これだ!」と思ってすぐ応募しました。
渡りに船だったと! でも未経験でいきなり院長の秘書とは、お仕事がガラッと変わりましたね。
とても戸惑いました。パソコンもそんなにできませんでしたので。
どんなお仕事が主になってくるんですか。
院長のスケジュール管理や、週に3回ある院長回診時の受付業務やカルテチェック。さらに、外部の方とのやり取りは基本的に秘書を通してからになるので、全部の連絡が来ます。朝は、同じ時間に同じ濃さのミルクティーを入れて持って行っていましたよ。
お仕事が幅広くて、やることも多そうですね。
多かったですね。会合が特に多くて、どこどこのレストランとかホテルを予約するとか、たくさんありました。ただ、8年ほど働いた頃、院長が亡くなられてしまい、離れることになりました。忙しい仕事ではありましたけど、いい経験はさせていただきましたね。
それだけ年月を共にしていたら、亡くなられた時は寂しかったでしょうね。
寂しかったですね…。お別れの会や葬儀も秘書の仕事だったので気を張っていたのですけど、終わった時にフッと悲しくなりました。
食べること、喋ることが困難な方のため
厳しい先生のもと、STを目指す!
STを目指されたのはそこからですか。
秘書職を離れることになった時、いわゆる手に職を持って、長く働けるということの大切さを思ったんです。
確かに資格を持った専門職は、長く働きやすいですね。
その頃、実家の耳鼻科で「STが欲しいから、資格を取らないか」という話が出たんです。私はとにかく勉強がしたくなかったので、嫌だと思っていたんですけど。当時、30代前半で独身、職も無いタイミングで、親が「STが欲しい」と言っている…。いろいろと考えたら「なるしかない」という結論に至りました(笑)。
ご実家で働くことを視野に入れながらだったのですか。
半分は親孝行のつもりで、力になろうかなって思いながらでしたね。ただ、多分病院で欲しいっていうのは口実で、「この先心配だから手に職をつけろ」っていうアドバイスだったんだと思います。その後も特に「帰って来て」とは言われなかったですし。
実際、興味があって目指したことではあったのでしょうか。
きっかけは親の勧めでしたけど、実際に目指そうと思ったのは、私自身が食べることが好きで、人と喋るのも好きというのも大きくて。食べるのは生きることに直結してますし、喋るのは人とつながることで、生活で大事な部分じゃないですか。
生きていくのに必要なことですし、楽しみでもありますね。
STはその2つができない方の助けになれる仕事ですので、私が少しでも力になれたらなっていうことがありました。また、院長秘書の頃、病院で仕事自体は目にしていたことも大きかったですね。
それから専門学校に行って学ばれて。
学校のSTの先生たちがまあ怖かったですね(笑)。特にベテランの先生は、高次脳機能学会で有名な方とか、それぞれの部門でプロフェッショナルがいて、怖かったですね〜。挫折する同級生もいましたからね。
それはその学校が特別厳しかったんですか。
そうだったのかもしれないです。でも今はだいぶ優しいらしいですよ。今年の2月に学校へ伺ったら「もう今は優しくしてる」って言ってました(笑)。
実際授業が始まってみて、いかがでしたか。
全てが未知の世界すぎて「失敗した!」って思いました。基本的に授業は理系の勉強ですし、暗記することも多くて、本当に大変でしたね。
なんとかやり抜けたのはどうしてですか。
ここで踏ん張ってSTにならないと、これから先どんなことも中途半端になってしまうなと思ったんです。自分が決めた道だし、これは試練だと思ったので。

病棟を横断し、デイケアでもリハビリテーションを行う
多岐に渡るSTの仕事
最初に入職したのはどちらの病院ですか。
この多摩川病院です。学校の同期の子が、このグループの緑成会病院に入っていたんですが、当時多摩川病院にSTが1人しかいなかったのでヘルプでも来ていて。私がちょうど職場を探していたので、「募集しているよ」と誘ってくれたんです。そこで迷わずに面接に行きました。
自分の中では決まってたんですか。
「ここだ!」って思っていたので、採用していただけて良かったです。
入ってからはどのような感じでしたか。
最初はグループの世田谷記念病院で研修を受けまして。多摩川病院に戻ってからは地域包括ケア病棟に配属されました。
現在はどのようなお仕事をされていますか。
回復期リハビリテーション病棟を担当しています。病棟の患者さんにリハビリテーションに入るほかに、医療療養病棟や地域包括ケア病棟にも入院患者さんの初期評価をしに行きます。他病棟のスタッフがお休みの日はフォローにも入りますし、できる人で全病棟を回しているような感じですね。あとはデイケアでもリハビリをしているのと、月に2回、グループのヴィラ町田にもリハビリをしに行っています。
施設の方にも行かれるんですね。
隔週で、利用者さんの食形態が適切かどうかの確認をしに行ったり、もう少し機能が良くできそうな方がいたら、良くするために行ったりもしています。
STさん同士はもちろん、PT・OTさん(※)とも協働して仕事されているわけですか。
もちろんです。1人の患者さんを、PTさんOTさんと一緒に見ているので。
※PT:理学療法士/OT:作業療法士
各リハビリの進行状況はみんなで共有されて。
そうです。どういうことをやっていこうかっていうのも話し合って進めていますね。

患者さん一人ひとりを注意深く観察しながら進める
STのリハビリテーション
今いらっしゃる病棟はどんな患者さんが多いですか。
高次脳機能障害、嚥下障害、構音障害の順で患者さんがいますね。
高次脳機能障害とは、どういったことですか。
けがや病気で脳に損傷を負って、記憶力や注意力に障害が残っている状態です。リハビリ時には、どういう障害かカテゴリにまず分けて、さらにどういった症状を呈しているかを注意深く調べて、患者さん一人ひとりの症状に合わせたリハビリを行っています。
具体的にどんなことをやるんでしょうか。
例えば、記憶に障害をお持ちの方だと、教材を使ったリハビリをしたり、会話をするなかで回想してもらったりっていうことをしますね。
やり方はそれぞれで変わるんですね。
特に失語症の方だと、どういう症状を呈しているかをしっかり見ないと、負荷の高すぎることを行っても効果が見られませんし、かなり気は使います。
どの程度喋れなくなられているかで、やることがかなり違うわけですね。
音声言語であれば「話す/聞く」、文字言語であれば「読む/書く」この4つがどのくらいのレベルでできるかという仮説をきっちり立てないと、全く違うアプローチをすることになってしまいますので。
嚥下障害ではどんなことをするんですか。
訓練できる方であれば、訓練して機能を上げていって3食とも口から食べられることを目指していくんですが、これに関しては運動療法なので、とにかく、嚥下に使うところを動かします。そこが高次脳と全然リハビリのアプローチが違うところですね。
PTさんがリハビリ時に、患者さんに足を動かしてもらうような要領で、舌を動かしてもらうようなイメージですか。
そうです、実際に使うところを動かしてもらいます。舌の準備運動として、舌を動かしたり口を動かしたりしながら、実際に安全性の確保ができるものを飲んだり食べたりしていただきます。
とろみのついたものなどですか。
それと、角度を変えることも大事です。
角度というのはどういったことですか。
体幹の角度です。普通に座っている時の角度というのが、実は一番むせやすくて。体を正面から見て、気道が手前にあって、その奥に食道があるんですね。そこで、角度を少し後ろに傾けると、気道が上、食道が下、っていう位置関係を作れるので、重力で食べ物が食道に落ちやすくなります。
飲み込む力が落ちていると、物理的にそういう状況を作ることが大事なんですね。
簡単にはいかないこともありますが、機能を向上させるために鍛え続けるしかないわけです。
少しずつでも前進することが嬉しい
安全を確保しながらも、攻めのリハビリテーション
STとしてのやりがいはどういったことでしょうか。
例えば嚥下が一番わかりやすいんですが、マーゲンチューブ(※)が入って経管栄養の状態で入院された患者さんが、リハビリに取り組んだ結果、3食ご自分の口から、ご自分の手を使って食べられるようになったら、それはもう掛け値無しに嬉しいことですね。
※主に経管栄養などのために、鼻から胃に通すチューブ。
リハビリの結果が目に見えるわけですからね。
それと、失語症で世界が周りと断絶されていた方が、「いや」とか「トイレ」とか、少しでも言えるようになったり、喋ることが怖くなくなったりとかした時も嬉しいですね。
少しでも前進できたっていうのが、やっぱりやりがいになると。
ご家族からの期待もかなり大きいと思います。もし歩くのが難しくても「せめて少しだけでも喋ってほしい」「口から食べられるようになってほしい」っていうご希望をいただくこともありますし。
コミュニケーションが取れるとか、自分の口で食べるって大きなことですよね。
QOL(※)の最後の砦とも言うべきところなのかもしれないですね。ただ、嚥下障害の訓練をした時、間違えて誤嚥させてしまわないか、かなり慎重になります。せっかく良くなりうる方に誤嚥性肺炎を起こさせてしまったら、それまでのリハビリで築き上げたものもゼロになってしまいます。
※患者さんの「生活の質」を意味する言葉。Quality of Lifeの略。
どのお仕事もそうですが、責任が重大ですね。
なので、かなり慎重に取り組んでいます。安全性を最大限に確保した状態で、どれだけ攻めたリハビリが実施できるか。ご家族ともしっかり信頼関係を築けるように努めながら進めていますね。

STは変わった人が多い?!
ちなみにSTさんはどういう方が多いですか。
よく「変わった人が多い」と言われます(笑)。
(笑)。実際どうなんでしょうか。
実際そうですね(笑)。
ご自身についてはどうですか?
どうなんでしょう、変わってるのかな…。
PTさんOTさんは、運動に関わってきて志す方が多いイメージがありますけど、STさんはどういった経緯で志されたかがイメージしづらいために、そう思われやすいのかもしれません。
「どうしてSTになったの?」っていうのはよく聞かれますね。
どういう方が向いているというのはありますか。
理論的に物事を考えたい人には向いているかもしれません。特に高次脳機能障害って目には見えないので、仮説に基づいて検証していかないといけないわけです。立てた仮説を「これは理論的じゃないから違う」って排除する作業を繰り返していく。そういうことをたくさんやるから変わってるのかもしれないですね(笑)。
(笑)。STになるにあたって大事なことはありますか。
全部に使えるわけじゃないんですけど、耳が良いことは大事ですね。患者さんの喋り方がおかしいときに「ベロがここの筋力が弱くてこうなってるんだろうな」っていうのがわかりやすいんです。構音評価ってとても細かくやるんですけど、耳の良さは役立ちます。これを活かせる仕事があるとは思っていませんでした(笑)。
予測がつきやすいんですね。耳がいいっていうのは今までどう生かしていたんですか。
英語を聞いて、どう発音してるかっていうのはすぐわかりましたね。舌がどういう風に動いているかっていうのがわかりましたので。それと、転校が多かったのですが、転校した翌日には、すぐそこの方言を喋れました。
すごい便利ですね!
リーダーとして思う
後輩たちは「守るべき存在」
新人のスタッフさんに仕事を教える時にはどのようなことを伝えますか。
まず第一に患者さんの安全確保ですね。その点については大事なので、特にしっかり教えています。
先ほど、誤嚥のお話もありましたしね。
それと、自分でしっかりと理屈を考えるようにしてほしいと伝えています。患者さんと接しながら、学校で勉強してきた知識を、点と点をつなげていくように実感した方が絶対に理解が進んでいくので。
あの時、授業で習ったのがこれだったのか、と気づけるわけですね。
知識については勉強すればカバーできることなので、とにかく目の前の患者さんを限られた時間内で精一杯みてほしいと伝えています。客観的事実を集めて記録して、考察として残す。そこができないと、全てのベクトルが外れていきますから。ただ、なるべく自分で考えてほしいと思っていますけど、求められればアドバイスもしますよ。意地悪な質問をするようなことはないです(笑)。
(笑)。今はSTのリーダーとして働かれているとお聞きしましたけど、どういう風な動き方をされていますか。
1年ほど前に任命いただきましたが、仕事としては、要は伝言係じゃないですけど、ほかの職種からSTに伝えたいことがあった場合に、まずは私が窓口として立って、伝えてもらうっていうのがあります。あとは会議に出たり、プリセプター(※)として後輩を担当しているので指導したり、STを全体的に見たり。シフトも作りますよ。
※新人スタッフに一定期間先輩スタッフがつき、マンツーマンで指導を行うこと。
リーダーになってみて、どんなところが変わりましたか。
スタッフのことを「守るべき存在」って感じるようになりました。ほかの職種のスタッフさんとの調整が難しい時は私が間に入ることも多くなりましたし。それと、仕事を続けていくには、やりがいとともに、自分の生活を守ることも重要だと思っていて、体調管理とか家庭のことも大事にしてほしいと伝えています。最近、お子さんが生まれたばかりの男性スタッフもいるので、退勤時間になると「早く帰ってあげて」って言ってます(笑)。
いいことですね! 頼られそうです。
う〜ん、果たして私がリーダーでいいのか、っていう葛藤もすごくあります。でも頼ってもらえた時は良かったと思いますし、私で良ければ、やれることは全部やろうって思っています。
やっぱり長く働いてもらいたいですよね。
楽しく長く働いてもらえることが一番ですね。「この病院に入職して良かった」って思ってもらえたらいいなと。
長山さんのこれからの目標を教えてください。
どの職種もそうだと思いますが、STも一生勉強なので、これからも自分の仕事をブラッシュアップし続けていくしかないです。それと、学んだことをスタッフにも教えていきたいと。身につけたことを自分だけのものにしないで、お互いに共有できればと思っています。職業の垣根も超えて共有していけたらいいですね。
多摩川病院自体の底上げにもつながりますね。
そうですね。「これってこういうことだったんだ!」っていうことが増えると楽しいですし、やりがいもさらに出てくると思うので。自分のやってくることの意味もわかってきますしね。

ゆったり過ごす優雅な休日
炊飯器はなくても大丈夫
お休みの日はどう過ごしていますか。
午前中は家事をして、午後からゆっくりします。早い時間から料理をし始めて、夕方ちょっと前くらいからお酒を飲みつつ、だらだらとずっと食べています。でも、必ず夜の7時までには食べ終わるようにしていますね。
ゆったりした休みの過ごし方ですね。夜の7時までというのは何かあるんですか。
消化のことと、次の日の仕事にお酒を残さないようにと考えてですね(笑)。
お酒はけっこう飲まれるのですか。
飲むのは好きではありますね。ただ、弱くなったと自分では思っているんですが、周りからは「それで弱いって言っちゃダメだよ」って言われるだろうなって思います(笑)。
まだまだ強いんですね(笑)。リハビリに限らず、病院スタッフで飲みに行くことは。
ありますよ! ソーシャルワーカーさんとかとも行きます。うちに来てくださったこともありますし。その時はラムチョップを焼いて振る舞いました。お店っぽいメニューを作るのが好きなんです。
いいですね〜。趣味はなんですか。
食べること飲むこと、あと排水溝の掃除です(笑)。ほっときがちなところを、常に掃除してキレイに保つのが好きです。
どんな食べ物が好きですか。
鮎ですかね。買ってきて家でも焼くんですよ。あとパクチーとかルッコラとか、クセのある香味野菜です。クセのあるチーズも好きです。
お酒に合うものがお好きなんですかね。
そうかもしれないです(笑)。
ご飯よりお酒が中心ですか。
確かにそうかもしれないです。うちには炊飯器がありませんから。
なるほど! 全然炊かないんですね。
どうしても食べたくなったら、お鍋で炊きます。それよりもたんぱく質と野菜が大事です。
健康的に聞こえますね。
その分お酒を飲みますし、どうでしょうかね…そっちで糖質を取っているのかもしれないです(笑)。
プロフィール

言語聴覚士
長山 素世子
ながやま そよこ
【出身】石川県金沢市
【職種】言語聴覚士
【好きな食べ物】鮎、香味野菜、チーズ(クセの強いタイプ)
病院情報
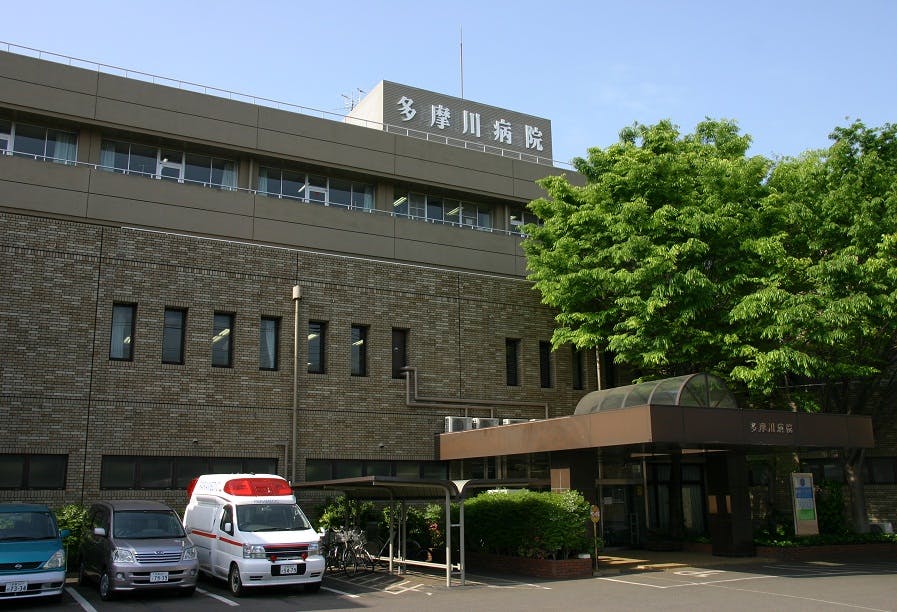
東京都調布市国領町5-31-1
https://www.tamagawahp.jp/
医療法人社団 大和会
多摩川病院
内科・循環器内科・整形外科・リハビリテーション科
回復期リハビリテーション病棟、医療療養病棟、地域包括ケア病棟に機能分化し、慢性期疾患の患者さんの治療、早期在宅復帰を目的とした機能訓練を行います。 また、内科、整形外科、循環器内科の外来治療をご提供するほか、居宅サービス、訪問看護や、日常の機能回復訓練のためのデイサービス、デイケアを設置し、地域の患者さんの幸福な日常生活の維持・増進のために努力しています。


