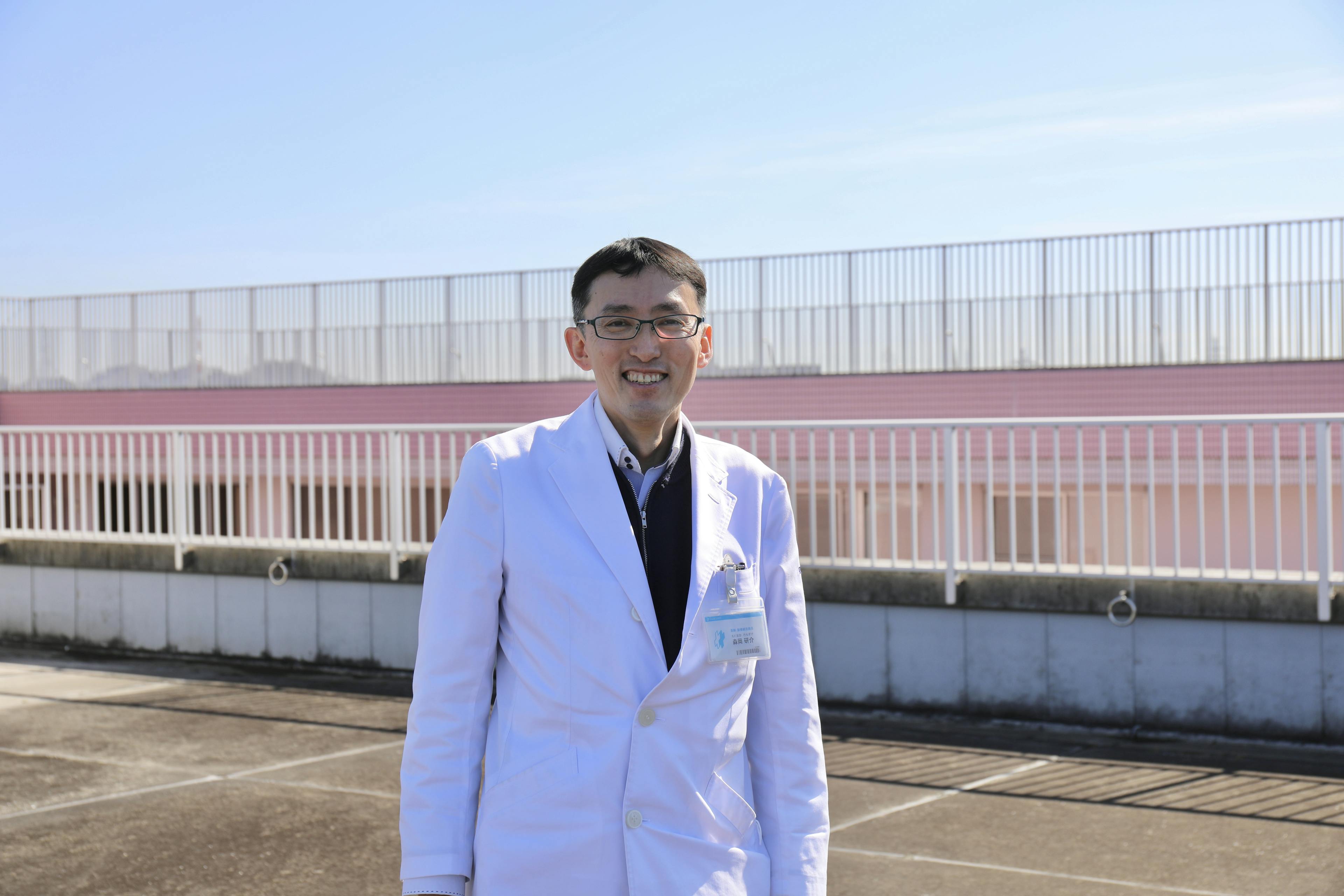長く携わってきた「がん」の治療 原点は学生時代「目の前の患者さんを助けたい」という想い/平成扇病院 副院長/児玉 圭司先生
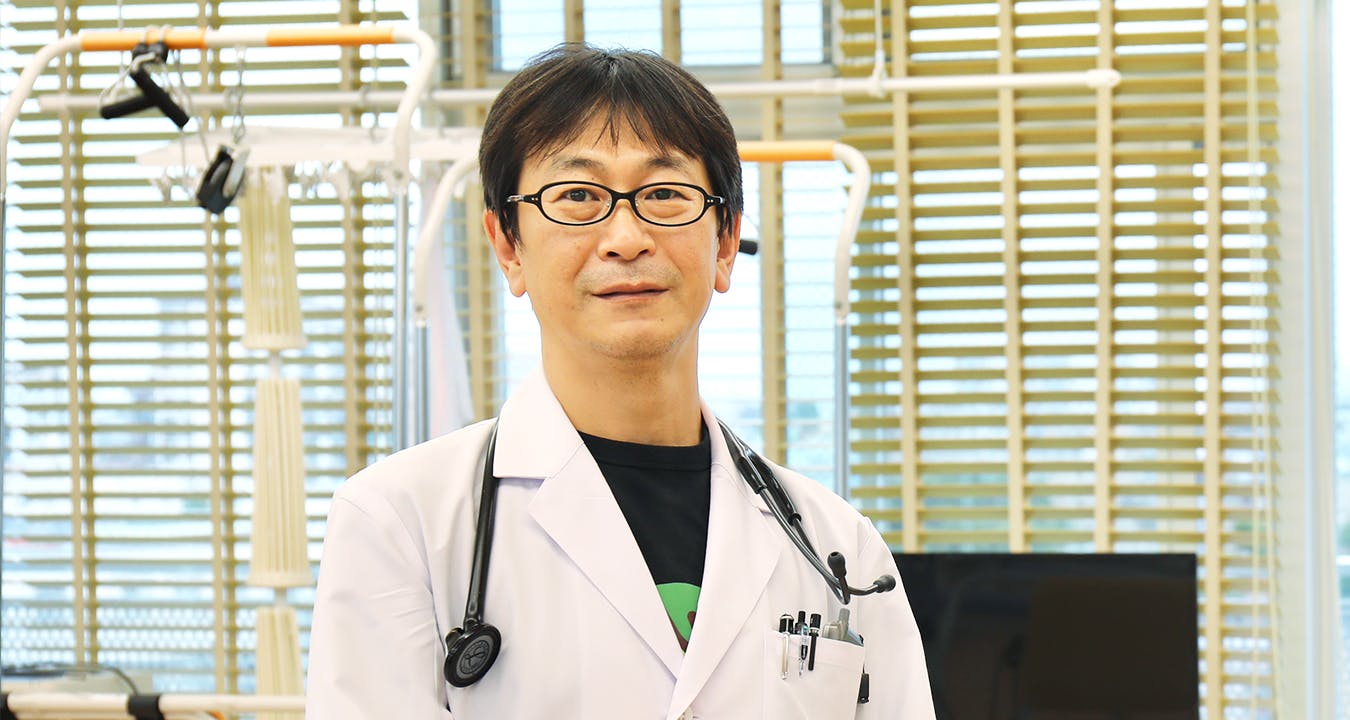
長く携わってきた「がん」の治療
原点は学生時代「目の前の患者さんを助けたい」という想い
平成扇病院の副院長、児玉 圭司先生にお話を伺いました。グループの世田谷記念病院入職以降、慢性期医療に携わってきた児玉先生ですが、実はキャリアを通して長く携わってこられたのは、がん治療だったそうです。キャリアの原点と、ハードに働かれた医療現場のお話を中心にお聞きしています。ぜひご覧ください!
最初に興味を持ったのは
実はIT業界
ご出身はどちらですか。
徳島県の羽ノ浦町というところです。
グループでいうとヴィラ羽ノ浦がある阿南市の羽ノ浦町ですね。どんなところですか。
のどかなところですよ。田んぼと畑と、あとはヴィラ羽ノ浦かというくらいの(笑)。
(笑)。のんびりしたところだったと。部活や勉強など何か打ち込まれていましたか。
小学生の頃はサッカー部だった気はするんですけど、記憶にはそんなにないです。命をかけてやる、みたいな感じではなかったです。
徳島にはどのくらいまでいらっしゃったんですか。
大学までいました。
医学部に進もうというのはいつから思い始めたのですか。
本当に行こうと思ったのは、高校3年生の夏くらいですね。
ずっと前から考えていたというわけではなかったんですね。
それまでは理工学部に行きたいと思ってました。今では当たり前のことですけど、当時「これからはITの時代が来る」と思って、そっちに進もうとしてたんです。
当初はIT分野に興味があったところから、医学の道を選ばれたのはどんな理由ですか。
ITの道に進むなら、その分野のトップにならないとダメで、2番手じゃダメなんだと、何となく思ったんですよ。そう考えたら、トップになるのは多分無理かなと思って(笑)。
例えば、ビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズみたいな存在にならないと意味がないと考えられていたと。
あくまで何となくですけどね。医師だったら、一番じゃないといけないっていうことはないかなと思って、医学部を選んだんです。
ご家族やご親戚で医師の方などはいましたか。
父が産婦人科医として開業していました。
では、医師の仕事へのイメージがあったというのも影響があって。
漠然と雰囲気がわかっていた程度ではありましたけどね。
ITの分野でないなら、医学の道に進んでみようという。
熱い野望はなかったですけど、興味はありましたし、医師なら活躍の場所は幅広いだろうとは思っていました。
講義には興味が持てなかった
現場に立って初めて湧いた実感
医学部に進まれて、勉強が始まってみていかがでしたか。
大学時代は、あんまり楽しくなかったですね(笑)。
えっ、どんな理由ですか。
講義を受けてみて、そんなにピンと来るものがなかったんですよね。
そこまで興味を持てずに。
ただ、臨床の実習が始まると、具体的にやることがわかってきて興味も出てきました。
患者さんを目の前にして感じるものがありましたか。
実際に困っている患者さんがいる、ということがわかったのは大きかったですね。病気の病理とか理論はもちろん大事なことなんですけど、それだけ学んでいても、患者さんがどう困っているかっていうのが実感できなかったので。
それよりは、目の前の患者さんをどう良くできるかということの方が。
そうですね、患者さんの困っていることをどうやったら解決できるかっていうことで、あらためて興味を持ち出して。それまで勉強してなかったもんだから、その患者さんの病気をもう一回自分で勉強しましたよ。
現場を見てからの方が、腑に落ちることも多そうですね。
教科書に書いてある内容が「ああこういうことだったのか」ってわかってきて。文字が意味持って現れたということですね。
よく、実習は辛いとも聞きますが、先生はいかがでしたか。
大変だったんだろうとは思うんですけど、辛かったという記憶は無いです。それより「こんなに困っている人がいるんだ」と実感できた方が強かったんでしょうね。

この時代があるから今の自分がある
がんと向き合って蓄積した知識と経験
大学卒業後はどんなキャリアを歩まれてきましたか。
千葉県の柏市にある、国立がんセンター東病院(※)で初期研修をやって、抗がん剤の開発に関わりながら腫瘍について学びました。その後、近畿大学に誘われて、そこでも抗がん剤の開発を続けました。
では長くがんに携わってこられたのですね。興味を持たれたのはどういうきっかけがありましたか。
さっきお話しした大学時代の実習で、肺がんの患者さんと接したのがきっかけですね。「これからどうなっていくのか」と不安になっていた様子が印象に残っていました。
実際かなり悪い状態の方だったのですか。
今思うと、多分そんなに悪くはなかったんですけど、なぜかその時興味を持ったんです。担当してくれた外科の先生が熱心に教えてくれたのもあって、自分もやってみようと思ったのがスタートですね。
国立がんセンターでは、具体的に当時どんなことをされていたんですか。
抗がん剤の臨床試験をひたすらやっていました。投与した薬が効くかどうかとか、まだ認証されていない薬の投与量決定とか、そういう開発に携わっていました。
実際お仕事されていかがでしたか。
まあ辛かった、大変でしたね(笑)。ものすごく忙しかったです。ただ、今考えればそこがとっかかりになって今の自分があると思うので、良かったなとは思うんですけど。
今のご自身にどうつながっていると思いますか。
新規の開発にたくさん取り組んでいましたから、今も新しいことを始めるのには何の抵抗もないですね。だからこそ、今こうして医療療養病棟で働いているわけですし。
今聞いている当時の話からすると、だいぶ分野が違いますもんね。その頃が大変だったっていうのは、とにかく担当する件数が多かったということですか。
今は違うと思いますけど、当時は休みがなかったですね。3年くらい勤めたんですが、ほとんど病院に住み込みでしたね。ただ、忙しい代わりに、本当にがんだけを追っかけていて、得るものは山ほどあって。
忙しさはあったけど、蓄積されるものもあったんですね。体は大丈夫でしたか。
若かったから大丈夫だったんだと思います。今は無理ですね(笑)。ハードワークでしたけど、みんな口を開いたらがんのことしか話していませんでした。
その後、近畿大学からのお誘いがあって移られたということですが、興味深いお誘いだったんですか。
その当時のがん研究の中心は、東が国立がんセンター、西が近畿大学でしたから、もう誘われたら行くしかないですよね。
そちらではどんなことをやられたのですか。
センターと大学の違いはありましたけど、基本的には明けても暮れてもがんのこと。また抗がん剤の臨床試験でしたし、仕事としては近い内容ではありました。
そこまでずっと、がん治療に対してはどのようなモチベーションで取り組んでいらっしゃいましたか。
もう、ただただ治したい。新しい治療法を開発して、がんが治るようにしたいという、それだけでしたね。
がん治療薬の研究に転身
結果を求められる、厳しい研究の世界
そこからのキャリアはどのようなものでしたか。
近畿大学で2年働いてから、今度は自分で薬を作る方に興味を持ち始めました。そこで、大学受験の時くらい軽い気持ちで思い立って、がんセンターの研究所に移ることにしました。
では、そこでは薬の研究開発に取り組まれたと。
そこで取り組んだのが「分子標的治療薬」の開発ですね。普通の抗がん剤は、全身に効いてしまうので、髪が抜けるとか、吐き気を催すとか副作用もあるわけですね。分子標的治療薬は、がん細胞から特有に出ている分子をターゲットにするから副作用が少ないので効率が良いだろう、と言われているものですね。
研究の仕事ということで、働き方も大きく変わりそうですね。
当然患者さんは診ないですからね。日々、顕微鏡と試験管に向き合って、実験ばっかりしてました。初めてやることだし、忙しくて精神的にも体力的にも大変でしたけど、楽しかったですね。
締め切りがあるわけじゃないけど、やることもたくさんあって忙しいという感じでしたか。
締め切りがないからこそ、追われるんですよね。基礎研究の世界って、結果出せなかったらクビなんで。
厳しいですけど、1日でも早く結果を出さないといけない世界なんですね。
だから追われるわけです。結果は出ないで、夢はいっぱい見ました(笑)。
(笑)。実際どういう結果になりましたか。
論文の発表はもちろんできたんですが、残念ながら実際に薬の開発まではいかなかったですね。それでも、得るものは山のようにありましたね。
先生のなかには、どんなことが今も残っていますか。
ディスカッション能力とか、物事を整理して考えられるようになるとか、そういう力は圧倒的につきますね。考え方がスマートになりますし、今もそれを生かして仕事をしてるつもりです。

腫瘍内科、総合診療内科、救急センター
一番ハードだった日々を振り返る
そこから離れて、また臨床に戻られたのですか。
埼玉医科大学で腫瘍内科を立ち上げるということで、声をかけていただきました。
またがんについては継続して関わっていかれたのですね。立ち上げと聞くとまた大変そうですが、いかがでしたか。
それはもう凄まじく大変でしたよ(笑)。
ハードな環境が続きますね…(笑)。研究から、臨床の現場に戻ることに抵抗はなかったですか。
一旦現場から離れてしまうと、臨床に戻るのはちょっと躊躇しましたね。ただ、がんセンターでお世話になった先生からのお誘いでしたから、行くしかないなと。その方は腫瘍の分野ではすごく有名な先生で、海外の学会でその先生の弟子だと言うと、みんなが握手を求めてくるくらい名のある方でした。
腫瘍内科では、がんセンターや近畿大学での取り組みとは違いはありましたか。
以前は新薬開発の取り組みが使命だったので薬物療法に特化していましたが、こちらでは薬による制限がない診療が行えましたね。
そこでのお仕事はいかがでしたか。
今までいたなかで一番辛かったです。
ここまでもかなりご苦労がありそうでしたけど、まだ辛い現場があったのですね。精神的、体力的に、どんな理由ですか。
全てですね。忙しさもありましたし。その頃にはそれなりの年齢になってるから、実績も出さないといけない、立ち上げなので失敗できない、という精神的なプレッシャーもありましたし。
数字も残していかないと続かないと。実際いかがでしたか。
うまくはいってたと思います。無事に立ち上がって、今に至ってますから。腫瘍内科が軌道に乗り初めたあたりで、そろそろほかのことをやりたいなと思い始めましたね。それで、一般内科に近いこともやろうと。
それまで長く、がん治療にまつわることに携わられてきて、どういう心境の変化でしたか。
がんセンターでは、割と合併症が少ない方を診ることが多かったんですけど、埼玉医科大学ではそうではなく、高血圧や糖尿病や、たくさん病気を持った患者さんが多くて。そういうものも、もっとしっかり診られるようになりたいなと思ったんです。それで、同じ大学内でお世話になった呼吸器内科の先生のところに移りました。
新たにまた学び直すようなことになるんですか。
追加くらいではありますけど、勉強はしなきゃいけませんでした。でも、知らないことなんでそれは面白いですよね。そのうち、今度は総合診療内科を立ち上げることになって、そちらにも関わることになりました。
総合診療内科ということは、より横断的な知識が求められると。
内科系は全部診ますし、自分はこれだけが専門だから、っていう言い訳は通用しないところです。自分ではそれなりの知識があるんだなと思っていましたけど、知らないことが本当に多いなとわかりましたね。その後は救急センターでも働きました。
またやることがガラッと変わりましたね。体力的にはとてもハードそうな印象があります。
ただ、ほかの科の先生が当直を手伝ってくれて、かなり助けてもらいましたね。
さらに幅広い患者さんを診ることになりますよね。
重い方から軽い方まで、なんでもやりましたね。2次救急とは言ってたんですけど、実際3次救急の方まで来てはいましたね。かかりつけの患者さんの心臓止まったと聞いて「よそでお願いします」とは言えないですから。
場所は変わっても、ずっとハードな現場を経験されてきていますね。
楽だと思ったことは、今に至るまで一度もないですね(笑)。

世田谷記念病院で
リハビリテーションの重要性を認識
このグループに移ってこられたのはどんな経緯でしたか。
今までずっと、大学かセンターで働いてきたので、そうではない街中にある、いわゆる市中病院も経験してみよう、と思いました。とりあえず街の病院に出てみようっていう感じでしたね。そこで、ご縁があって、世田谷記念病院に入職することになりました。
特に「急性期医療から慢性期医療に」という意識ではなかったと。
「環境を変えてみよう」という風にしか考えてなかったですね。自分としてはずっと新しいことしかやってなかったので、よっぽどの変化でなければ対応できるだろうと。結局、患者さんを良くしよう、という原則は一緒ですから。
実際に移ってみてどのような印象でしたか。
担当した地域包括ケア病棟は穏やかでしたね。システムもできあがっていましたし、患者さんも症状が落ち着いている人が多くて、割とゆったりしていた気がします。
では、じっくり診て対応できていた環境だったと。
そこで、もうちょっと忙しい病棟に変えようと思ったんですね。
忙しいというのはどんなニュアンスですか。
以前は診ていなかった、重症の患者さんも受け入れるようになりました。さらに、近隣の開業医の先生たちから、在宅療養中に状態が悪化した患者さんの受け入れもなるべく行うようにしていきました。
より間口を広げていかれたわけですね。
その結果、忙しい病棟になったと(笑)。くわしく確認してみないとわかりませんが、稼働状況は良くなったのではないかなと思います。都内全体であってもベッド数は限られているので、早く治さないと次の方が待っているわけです。そこで、本来2カ月かかるところを1カ月で治したら、倍の数の患者さんを良くできるわけですから。そうしたことも意識して取り組みましたね。
ベッドの回転を良くしようと。
もちろん、ただ早くするということではなくて、しっかり良くして、決められた目標まで早く到達できるようにということですね。そこは常に意識していました。
このグループに移って、リハビリ職種との関わりも増えたのではないかと思いますが、実際どのように感じましたか。
一般的な大学病院と比べて、リハビリ職種が活躍する機会が圧倒的に多いですね。最初はどんな効果があるかわかっていなかったんですが、やっぱりリハビリが介入した方が、良くなる可能性が高いなと思いました。あるのとないのでは全然違うと思いますね。
地域包括ケア病棟でのリハビリテーションはどんなものになるんですか。
多かったのは、移動、排泄などADL(日常生活動作)の改善ですね。トイレに行って、自分でご飯を食べるとか。そこを目標に行うことが多いですね。実際それで改善も早かったと思います。それは、このグループに移ってみないとわからないことでした。

いよいよ平成扇病院へ
地域のニーズに応える病棟に
現在在籍している、平成扇病院に移られたのはどういった経緯でしたか。
世田谷記念病院が全面改修することになって、一旦こちらに出向という形で移っていました。もともとここには精神科の病床があったんですが、それが機能転換して医療療養病棟になるということで、立ち上げをやってほしいと、依頼を受けたんです。
立ち上げの依頼についてはどう思われましたか。
ここに至るまでいろいろ立ち上げに携わってきましたし、とにかく1から仕事しやすく作れるっていうことは思いましたね。
立ち上げには慣れていたと。精神科病棟がなくなったったのは、全国的に精神科の病床を減らすという背景があってのことでしょうか。
僕が移ってきた時には既に精神科の病床がなくなっていたので、実はくわしい経緯は知らなかったんですが、実際に医療療養病棟がスタートしてみると、コロナ禍の時期でも早い段階でベッドが埋まったので、そう考えると療養に対する地域のニーズはあったんでしょうね。
実際に入院される方は、どういったところから来られることが多いのですか。
圧倒的に急性期病院からが多いですね。
みなさん、ある程度治療を終えられた状態で来られると。
終わっている方もいますけど、あまり終わってない状態の方もいらっしゃいますね。できる限り受け入れるようにして、もし治療の途中であっても「あとはこっちで仕上げます」ということで。
では世田谷記念病院でやられていたように、ある程度重めの方も受け入れて。やはり同じ足立区内の病院からの受け入れが多いですか。
足立区はもちろん、渋谷区や埼玉県の病院からも来られて、意外と範囲が広いですね。
広範囲に渡るのはどんな理由があるのでしょうか。
医療療養病棟だけど、重症の方を受け入れているというところですね。意外とほかにないのかもしれません。
やはりそういう状態の患者さんは、受け入れ先が少なくなってしまうんですか。
絞られてしまうことも多いようです。この近辺に限らず求められていると思いますし、だからこそ、続けていきたいですね。
ちなみに現在、医師も募集されていると伺いました(※)。
一緒に取り組んでいただける方をお待ちしています。募集については太字にしておいてほしいです(笑)。
求人についてもアピールしていきたいと(笑)。どんな方が活躍できる場所だと思いますか。
例えば、総合診療内科を経験されているとか、幅広い分野に知見があると活躍しやすいですね。あとは、新しいことをするのに興味ある人ですね。見たことがない病気はたくさんありますから、それを怖がらずに、どういう病態かしっかり考えられる方がいいと思います。
よく、慢性期医療や療養と聞くと、言葉のイメージとしてのんびりしているという印象を持つ方も多そうですが。
それはここには当てはまらないと思いますね(笑)。
目指すのは「家に帰れる医療療養病棟」
ちなみに副院長としてはどういった業務をされていますか。
実際今は医療療養病棟60床を担当していますので、運営よりも臨床業務に携わる時間が長いですね。運営や管理は、佐野院長にお任せしている部分が大きいです。
がん治療や救急などに携わってきた先生ですが、今はどんなことをモチベーションにお仕事されていますか。
食べられなかった方が食べられるようになる、歩けなかった方が歩けるようになる、医療療養病棟であっても、状態を良くして帰すっていうことは常に目標にしています。患者さんが、なるべくご自身でできる範囲のことができて、足りない分だけ手伝ってもらうくらいで済むくらいの状態ですね。それを実現させようとすると、いろいろ忙しくはなるんだけど、やっぱり必要なことですから。
良くなって帰ってもらおうと思うと、当然時間や手はかける必要があると。
そうしたことで必ず良くなる、とは限らないですが、少なくとも、そうしないと良くなるものもなりません。入院しているご本人もご家族も、家に帰れるなら帰りたいと思う方が多いですし、それは叶えられるように努力しないといけないですよね。
今後、病院としてはどういう役割を担っていくのが責務だと思いますか。
難しい話ですね(笑)。でも、できるだけエッジが効いた病院にできたらいいなとは思っています。「これならここしかない」っていう、独自性を持った病院です。今はその独自性を作っている最中なんだと思います。
それを医療療養病棟と回復期リハビリテーション病棟の2つで実現させると。
それぞれ性格は変わってくるだろうけど、独自色を強くしていって。それが医療療養病棟で言うと、家に帰れる病棟に、ということですね。
先ほどもお話がありましたけど、そういった性格の医療療養病棟がなかなかないと。
まだ目立たないけど、いずれは増えていくと思います。その前に、先陣を切って取り組んでいるところです。動き出して半年程度ですので、まだまだ途中ですね。
実際に形になるまでは、まだ時間が必要ですか。
それは何年もかかることかと思います。この先もきっと良い時、悪い時どちらもあるでしょうし、それを繰り返して形になっていくのかな。評価は周りがすることですし、目標を立てたら、こちらはひたすら走るだけでしょう。そのうち結果が後からついてくると思うので。

スタッフのみんなに感謝
患者さんには敬意を
新たに医療療養病棟がスタートして半年経って、今はどんな感想ですか。
スタッフがすごいがんばってくれています。それはもう感謝ですね。和気あいあいとした雰囲気ができていますし、仕事も進めやすいです。
みなさんの努力のおかげもあって満床にもなっている。
ちゃんと退院できる患者さんも増えていますし。ここまでいい感じには来ていると思います。
先生が目指す病棟の実現には、どんなことが大事だと思われますか。
いろいろあると思いますが、患者さんに尊敬の念を持って接することですね。認知症の患者さんも多いですが、しっかり敬意を払うことが大切です。忙しいとつい疎かにしがちなところなので、大事にしています。
スタッフのみなさんにもそういうお話をされますか。
実際は忙しくてそういうことを話す余裕はなくて…(笑)。
先生がそういった対応を続けていけば、みなさんに自然と伝わっていくかもしれないですね。
自慢のワンちゃんと過ごす休日
では、プライベートのお話を伺います。お休みは取れていますか。
今はちゃんと休めています。昔のように病院に住み込むようなことはないです(笑)。
休日はどんなことをして過ごされていますか。
犬のお世話ですね。トイプードルが2匹いるんです。
ちなみにお子さんと出かけたりなどは。
いえ、あまりなくて。高校生の娘が2人いるんですけど、そんなに言うこと聞いてくれないです(笑)。
そういう時期なのかもしれないですね(笑)。では休みの日は犬と過ごされて。
今は新型コロナウイルスの影響で遠出できないので、ひたすら近所で散歩していますね。
趣味はありますか。
それも犬のお世話ですね。ひたすらお世話。明日もトリミングに連れて行きますよ。
それも犬のお世話ですね。ひたすらお世話。明日もトリミングに連れて行きますよ。
そうですね。うちの犬はね、以前『25ans(ヴァンサンカン)』っていう女性ファッション誌に載ったことがあるんですよ。もう何年も前ですけど。
すごいですね!
エレガントなドッグで「エレdog」っていう特集があって、セレブ犬として扱ってもらいました。それは嬉しかったですね〜。このインタビューで一番言いたかったことはそれかもしれない(笑)。

プロフィール

平成扇病院 副院長
児玉 圭司
こだま けいじ
【出身】徳島県羽ノ浦町
【専門】内科
【趣味】犬のお世話
【好きな食べ物】蒙古タンメン中本(北極ラーメン)、フォー
病院情報

東京都足立区扇3-26-5
http://www.ougihp.jp/
医療法人社団 大和会
平成扇病院
内科・リハビリテーション科・精神科
2016年4月に開院。内科病床と精神科病床を有していましたが、地域の医療ニーズに応えるため、2020年4月に内科病床を中心とした、医療療養病棟60床、回復期リハビリテーション病棟60床の病院機能にリニューアル。積極的なリハビリテーションはもちろん、脳血管疾患後の高次能機能障害の神経学的な鑑別など、引き続き『こころとからだ』の両面に対して幅広いアプローチを実践、地域のみなさんが安心して在宅で生活できる後方支援病院を目指します。