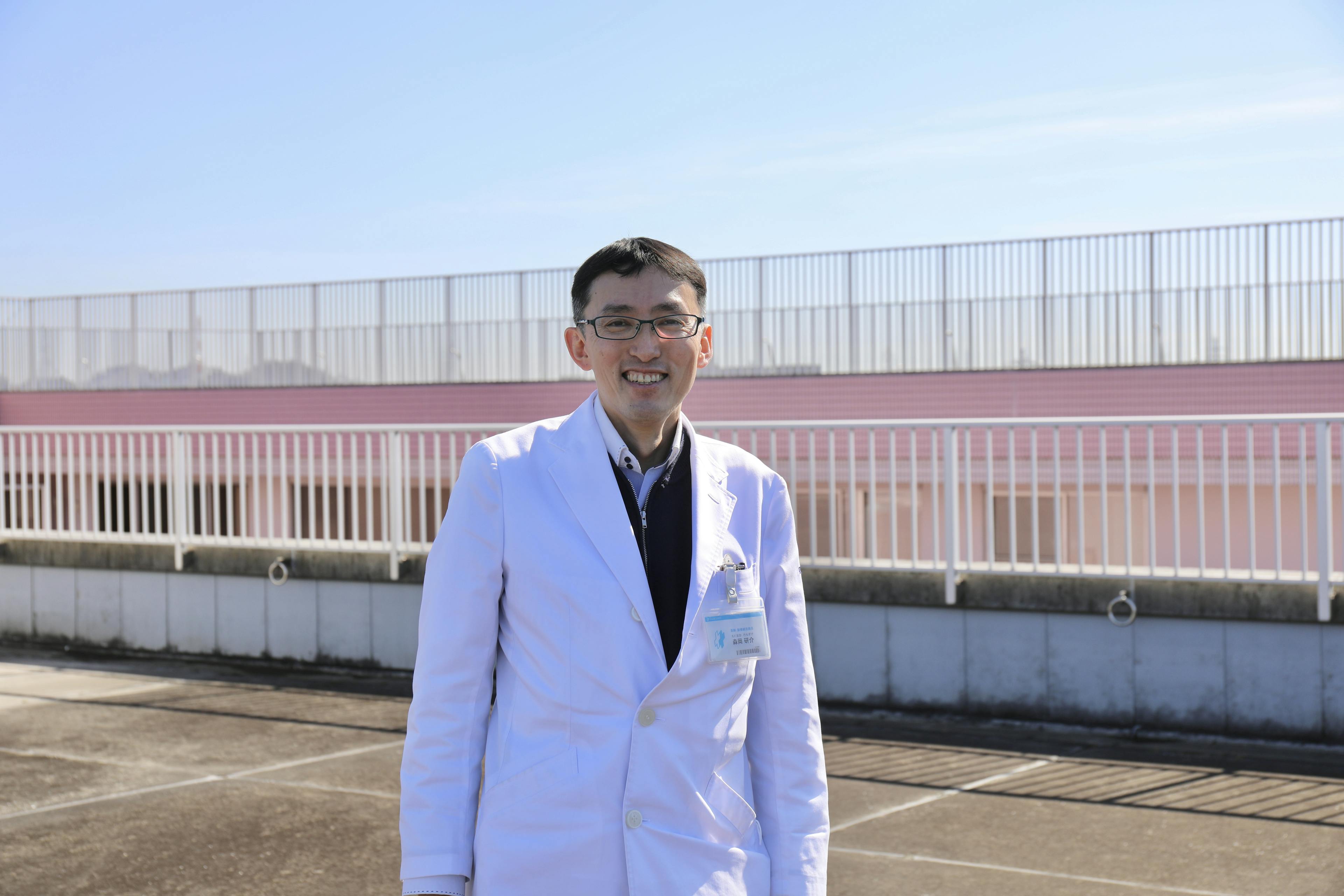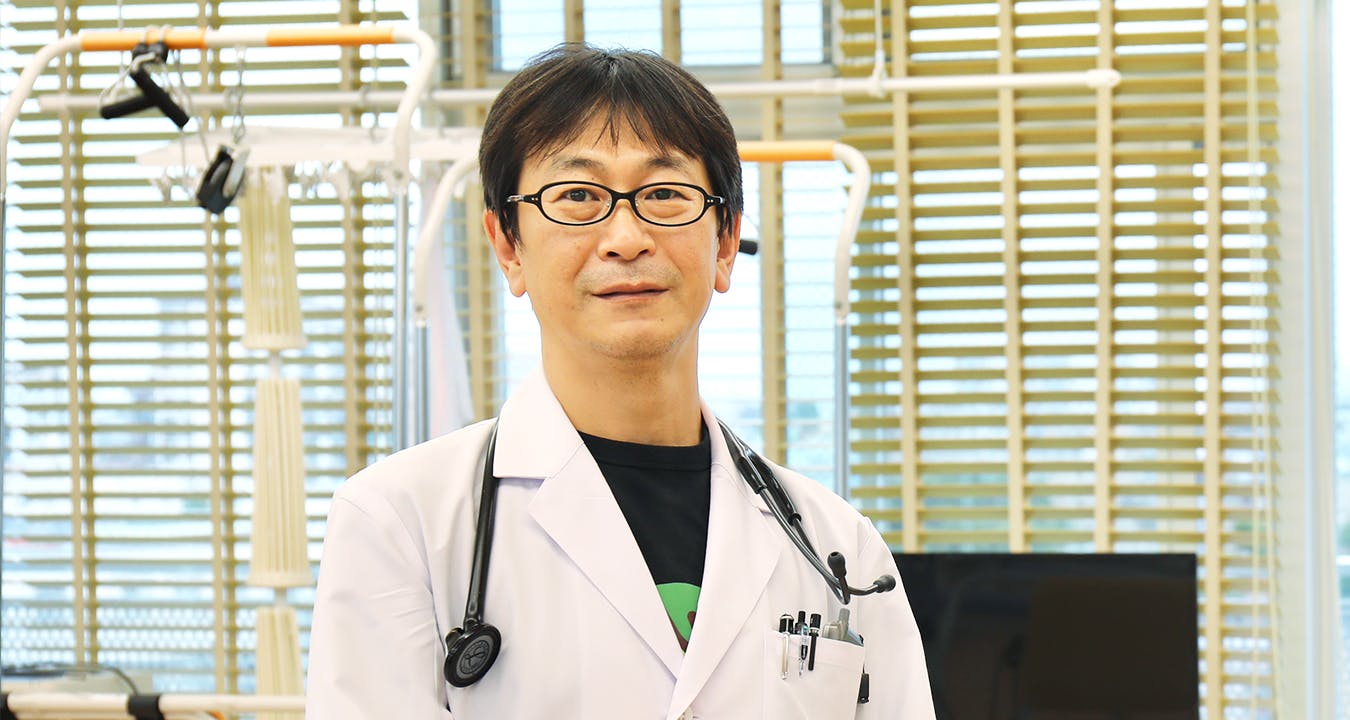長く歩んだ救急医療の道 最前線を経て、堺市の医療へ/堺平成病院 救急センター長/定光 大海先生

長く歩んだ救急医療の道 最前線を経て、堺市の医療へ
堺平成病院の救急センター長を務める、定光大海先生。定光先生は、山口大学や大阪大学で救急医療の最前線を経験され、当グループの堺温心会病院へと移られました。今回は、そこに至るまでの数々の経歴に迫ります! バリケードに阻まれた高校時代のお話などは必見です。ぜひご覧ください!
気づけば目指していた医師の道
ご出身はどちらですか。
広島県の庄原市です。
幼い頃は、どんなお子さんでしたか。
野球がとても好きで、野球選手になろうと思っていましたね。
部活にも入られて。
小学生の頃は草野球を仲間でやっていました。ただ、中学校に入った時には背が小さいということで、野球は諦めてテニスを始めました(笑)。テニスは中学〜高校〜大学と続けましたね。
医師になろうと思ったのはいつだったんですか。
そもそも記憶にあるのは、小学生の低学年の時に受けた耳鼻科の手術ですね。アデノイドだったかな。
その時の医師がとても印象に残られて。
いや、全く顔も覚えてないんですよ。ただ、手術を受けた時に「自分もなりたい」と思った記憶はあります。
そこで漠然と思われたんですね。
野球の選手になろうという気持ちもないこともなかったんですけど、中学校に入って野球を辞めてからは、もう自分は医師になるんだと思って、ほかの選択肢はなぜか頭の中にはありませんでしたね。
強い志があって、というよりは、いつの間にかそうなった。
大層な意志はなかったんです。ただ、自分はそういう道に進むんだって、決めていましたね。
学校にはバリケード!?
通学できなかった高校時代
高校は医師になることを考えて進学されたんですか。
必ずしもそういうことでもなかったんですが、地元の庄原からは離れた広島市内にある、修道高校という私立高校に進んで、下宿生活をしていました。
親元から離れて進学をされたんですね。入ってみていかがでしたか。
進学校だったんですが、高校1年生で高校2年生くらいまでの内容に進むんです。しかも中等部から進学してきている人は、中学3年生の時に高校1年目くらいまでを終えている。「これは大変だぞ」って思いましたね。
やっぱりできる人ばかりが周りにいて。
それと同時に、当時は70年安保(※)の時代ですから学園紛争が盛んな時期で、私の行っていた高校も学園閉鎖になりましたね。
※日米安全保障条約の自動延長に反対する大規模デモ運動。各地で盛んに学生運動が展開された。
70年代を感じるエピソードですね! 学校に入れないんですか。
学校にはバリケードが張られて、中に入れなかったです。2年間くらいは普通に通えたんですが、紛争が激しくなって、あとは休校でした。
先生ご自身はそういう運動はやられてはなかったけど。
テニスは続けてましたけどね(笑)。本格的な受験勉強は、高校時代にはやった記憶がないです。
高校の上級生が学生運動に関わっていたんですか。
学内の生徒だけではなくて、近くの大学の学生も入り込んでいたみたいですね。自分はバリケードの向こう側(内側)にいたことはないんですけど、特に悪くは見ていませんでした。田舎からそういう市街地の学校に来て「勉強もがんばらんといかんな」と思いながら、「こういう世界もあるんやな」と。
やっぱり当時の時代の雰囲気というか。
生徒が意見して制服もなくしていたような学校でしたし、校則でガチガチに固めるような時代は終わってましたね。でもグジャグジャの高校時代。卒業式すら行かなかったです。いつやるのかもよくわからなかったですから。
休校になってしまうと、もう単純に何も授業がないんですか。
なくなっちゃう。結局高校卒業時には高校3年までのカリキュラムが全て終わってない、そういう状況でした(笑)。

京都で卓球しすぎて不合格!
学校に入れないような状態で受験されるのは、なかなか大変そうです。
だから僕たちの学年っていうのは、あんまり現役で進学できた人は少なかったですね。僕も2年間浪人して、山口大学に進みました。
山口大学を選ばれたのは何か理由があったんですか。
本当は京都大学に行きたくて3回受けたんですが、落ちてしまったんです。最初の年は、京大に進んで吉田寮(※)に住んでいた先輩がいましたので、泊まらせてもらって。
※1913年から続く、日本最古の学生自治寮と言われる、京都大学の学生寮。
当時の吉田寮なんて、今よりも混沌としていそうですね。
そうそう、行ってみたらやたら汚くて、学生がわんさかいましたよ。そこで試験の前の晩に、卓球をして遊んでたら、ちょっとやり過ぎてしまって、疲れ果てて寝込んだんです(笑)。次の日試験会場に行って「これは試験どころではないな」と思って、やっぱり落ちましたね。
(笑)。そこから山口大学へと。
3年目に京大は落ちたけど山口大学が受かったので、親にあまり負担をかけるのも、ということもあって、医師の道に進むために山口に進学しました。
大学時代を経て
救急医療の道へ
大学を経て専攻を絞っていかれたと思うんですが、どのように決めたんですか。
臨床実習では各診療科を回って、どの科を選ぶか決めていくわけですけど、とても迷いましたね。そのなかで、血液内科をやってみようと思って、広島の原医研(原爆放射線医科学研究所)で研修させてもらうことになりました。
地元に魅力ある研究所があったのですね。
ただ、その前に救急やICUの仕事を経験したかったので、「大阪に1年間行かせてください」とお願いして、大阪大学の特殊救急部(現 高度救命救急センター)に行かせてもらったんです。
救急医療を経験したいと思ったのはなぜだったんですか。
と言うより、全身管理を学びたかったんです。重症患者を診るために、そういう症例を診ている施設で経験を積まないとダメだなと。
そういう症例を数多く経験できるとなると、救急だったと。大阪大学を選んだのは理由があったんですか。
その頃、1979年当時はオープンスペースのICUがまだほとんどなかったんですが、大阪大学にはあったんです。それがすごく進んで見えました。
そこで救急を1年経験をして、広島に戻ろうと。
それが甘い考えでしたね(笑)。救急に携わってすぐに「これは外科のトレーニングをしないといけないな」と思い至ったんです。
それはなぜですか。
本来は1年間研修してから、さらにそこから整形外科に行ったり、脳外科に行ったり、研修に出るんです。ここで中途半端に帰ってしまうと収まりがつかないなと思って、広島の血液内科の方にはお断りを入れました。先のことは外科を経験してから考えようって。
まず初めに「これがやりたい」と決めていたわけではなかったんですね。
今思えば、その時はもう救急医としての道の中にいたんでしょう。とにかく外科的修行を終えないと、医師として一本立ちできないだろうなと当時は思ったんです。で、静岡県の国立東静病院(現 静岡医療センター)に腕の立つ外科医がいるということで、そこを勧めてもらって研修に行きました。
そこからは大阪大学に戻ったんですか。
その後、大阪大学に戻って勤めながら、大阪市内の病院に出向もしたんですけど、山口大学の医学部付属病院が1982年に救急部を立ち上げて、人が足りないからとお声がけをもらいました。母校に義理を果たす気持ちで、3年くらい働いたら戻ってこようと思っていたんですが、結局15年勤めました(笑)。

山口大学で没頭した救急部の仕事
オン・オフを切り替えられることの大切さ
山口大学ではどんなことをされていたんですか。
麻酔学講座から、集中治療部のポストで講師などを務めたほかに、後に救急医学講座ができた際には准教授を務めました。
いろいろと携わることが多かったのですね。
救急医学講座ができた時に、教授と僕を含めて3人でのスタートでした。最終的には当直を全て救急医で回せるようにするため、医局員が増えるのを待っていたんですが、最初の10年は、集中治療室のスタッフなどに手伝ってもらいながら、ほぼ二人で現場をやっていました。
じゃあその間はけっこう大変だったんですね。
ほとんど病院に住んでいたような感じで大変でしたが、そこで経験を積んでいって、救急医として自信を持てるくらいにはなりました。
忙しかったけれど、それだけのことをやったと。
そう言えますね。72時間寝ずに働いたこともあって。
ええっ…72時間目にはどうなってるんですか?
自分では大丈夫だと思っていても、周りから見るとヨレヨレらしいんですよ。で、帰ったら24時間寝てしまうんです。平均すると4日間で1日6時間ずつ寝たことになるんで、帳尻は合ったような気持ちにはなるんですが(笑)。
計算上だけですけども(笑)。
でもそういう働き方はやっぱり無駄ですし、良くないですよ。人員がいて、ちゃんと二交代で回せれば、オン・オフも切り替えられますから。
山口大学で立ち上げに関わった
国立大学で初の救命救急センター
医師の業務以外にもいろいろと尽力されたと思うのですが、どんなことをされましたか。
当時、国立大学付属病院では初となる、救命救急センター(※)の設立に関わりました。当時は文科省の人ともやりとりもしていました。
※山口大学 医学部附属病院 先進救急医療センター(AMEC3)。1999年に設立。
国立大学でそうした救命センターができるというのは珍しいことだったんですか。
救急医療は大阪大学が当時イニシアチブを取っていましたけど、国立大学の病院で救命センターを作る、という発想自体はありませんでしたね。救急というのは、専門科目のなかでも、主流とは言えませんでしたから。
位置付けが多少今とは違ったと。
重要な医学的ポストとして認められるまでに時間がかかったんです。そのうち、救急医療が医療のなかの基本だっていう話になっていったんですよ。
その前までは、そういう空気っていうのは。
無かったですね。救急医という標榜ができるのはずいぶん後のことなので。だから「救急医って何科ですか」って聞かれても、外科でもあるし麻酔科でもあるし、なかなか表現しづらかったですし、社会に理解してもらいづらかった。そういう時代が長く続きましたが、そのなかで、ずっと現場を作ってきたんです。
先生がいた以外の現場では、どうやって対応されていたんですか。
みんな各科救急です。2、3人の救急医と、あとは各科の先生がいて、救急の患者さんが来たら、各科へと振り分ける。今でもそうですけど、救命救急センターといっても、救急の専門医が、全部カバーしているようなところって、限られていますからね。
以前と比べて変わった点もあるけれど、変わってない現状も多いと。
医師の数は限られてますから。だから当直医が一人しかいないと、急性期病院と言えども大変ですよね。けがをしたと言っても、「今日は内科医しかいませんから、ダメです」ということにつながります。病院が救急患者さんを断る大きな理由です。
問題が根深いですね。
ずっと言われていることではあります。救急医を育てて救急救命センターに配置して、24時間365日見れるようにしよう、と。それと、ER(総合診療医)を育てよう、というのが今の流れですよね。

福島原発でも活動
災害医療に携わる
当グループに移る直前のことをお伺いします。
山口大学から、今度は大阪大学の関連病院で国立病院機構 大阪医療センターに16年勤めていました。
そこではどんなことをされていたんですか。
救命救急センターのセンター長をずっと担当していましたね。
管理者として仕事をされていたんですね。
最初は当直もやっていましたけども、ちょっと働きすぎて体を壊しまして。当直からは離れて、それからは管理職に徹しました。
管理業務に携わるということは、ご自身としてはいかがでしたか。
救急の現場は若い人に任せて、役割分担だなと思っていました。やっぱり救急医をハードにフルタイムでやる歳ではなくなっ
病院だけにとどまらず、救急医療に関する活動をされていたと。
全国のDMAT(※)訓練にも行っていました。そもそも事務局は東京にできたんですけど、首都直下型地震が起きたら対応できないので、各地に分散させようということで大阪にもできまして。
※Disaster Medical Assistance Teamの略。大規模災害や事故の発生時に活動する、専門的な訓練を受けた、医師・看護師・業務調整員からなる医療チーム。日本DMATは2005年、厚労省により発足。
東日本大震災の際にはどのような活動に関わったんですか。
DMATでは管理職として、チームを編成してスタッフを送り出していました。初期は現場入りしてなかったんですが、福島原発での被ばく医療の対応のため、私もその後福島県には何度も行きました。私は原子力安全研究協会で被ばく医療の講師も務めていましたので。
実際に原発まで行かれたんですか。
津波で建物が根こそぎ流されているところを通り、人のいない街を抜け、防護マスクをつけて、原発の敷地内まで実際に行っていました。
どういったことを行われたんですか。
原発で働いている人たちの健康管理や、けがをした人への対応などをしていました。全国から医療班的な役割として、交代で人が派遣されていたんですね。
そういった活動にも携われたんですね。
そういったこともあったので、救命センターでの現場の診療は主に部下に任せていました。大阪医療センターにいた時は、病院の活動というよりはそういったDMATに関わることや、講演とか学会の座長とか、普及活動などに力を入れてましたね。
再び臨床の現場
堺温心会病院へ
そこから当グループの堺温心会病院に移られるのはどういった経緯がありましたか。
やはり臨床の現場を一度離れてしまうと、現場の細かいことが自分にフィットしなくなってしまう。そこで、もう一度臨床をやりたいと思ったんです。
そう思ったのに理由はあったんですか。
いずれ、どこか地方に移り住んで、小さい病院規模で地域医療の担い手になりたいなと思っていたというのがまずあったんです。人口密集地ではなくて、高齢者がいるけど、病院にはちょっと行きづらいよね、っていう場所で。
そこで医療を提供したいと。
やっぱり地域にちゃんと医療があれば、そこに住んでいけるわけです。実際に移住して医療を提供しながら、ゆくゆくは自分も面倒を見てもらえるようにしたいなと。
そのために臨床の現場にまた戻るというのがまずあったのですね。
臨床医としてまた現場を経験しようと思っていたところで、ちょうどこの病院に声をかけてもらったんです。ここは慢性期医療の病院ですけど、救急は断らないということを標榜していますので、それならば救急医が総合診療的な仕事をする場があるなと思って、来させてもらいました。
実際声をかけられてみて、いかがでしたか。
グループの武久代表は日本慢性期医療協会の会長ですし、そういう研究会に誘われたこともあって面識はありました。それと、大阪緊急連携ネットワークができて、このグループの診療本部長である井川先生(※)とも一緒にやらせてもらっていましたので、関係性があるところでお声がけをいただいて、ありがたいことです。
堺温心会病院の印象については。
古い病院だとは思いました(笑)。でも、ここの外来は急性期の機能を持っていて、病棟では高齢者の方も多いですけど、透析医療もやっていて、一般病床もあってと、さまざまなことができるなと考えました。

急性期病院と慢性期病院
連携がとても大事
超急性期から慢性期の病院に移られたわけですよね。
患者さんと十分時間をかけて接することができるという良さがありますね。急性期は、どんどんと患者さんがいらして、その分どんどんと出てもいくわけです。それと、慢性期の病院に移って、急性期で治療をした後の患者さんがどうやって家に帰れるかっていうところまで見られるというのは大きいですね。やっぱり自分の専門分野だけ治ったら終わりというわけにはいきませんからね。私はそういうやり方はしたくなかったので。
急性期と慢性期とどちらからも見ることで得られる視点もありそうです。
それぞれがそれぞれでやることがありますので、そこの連携をうまくやる必要がありますよね。お互いのことをちゃんとわかっておかなければいけないので、急性期を経験して、慢性期をに取り組むというのは意味のあることだと思います。
ひとつのキャリアモデルとも言えるのでしょうか。
救急医は、体力的にずっと続けていくというのが厳しいですからね。管理職の仕事をやるのもそうですし、その次の道をどうするかっていうのは、先に行く人間が「こういう道があるよ」って作らないといけないなと。
道を示しているわけですね。
示すというか、身をもって苦心していると(笑)。でも救命センターと慢性期病院で、患者さんも違うと思うでしょう。
違うような印象があります。
でも外来にいらっしゃる患者さんは、やっぱり「お腹が痛い」とか「けがをした」とか、基本的なところでは変わらない。重症度の違いで、救命センターに行く必要がないというだけで。だからこそ、救急医の総合診療的な見地が生かせるわけです。
堺平成病院は重要なモデルケース
堺平成病院が開院してからの先生の仕事内容に変化はあるんでしょうか。
大きくは変わらないですが、対外的な堺市の会合などにも出る機会も増えると思います。救急の受け入れを行うには、地域との関係を築いていくことがとても大切ですので。
堺平成病院では、救急体制はどのようになりますか。
基本的には堺温心会病院と変わらず、「断らない」ことが前提です。依頼があればすべて受け入れを行えるよう、救急医療体制を整えています。1次・2次の救急(※)の治療のほかに、初期応急治療後に、3次救急への転送も行います。
※1次救急:軽症患者に対する救急医療/2次救急:中等症患者に対する救急医療/3次救急:重症患者に対する救急医療
堺市自体の救急医療は、どういう現状ですか。
急性期の拠点病院があって、2次救急の受け入れ病院も増えて、形は整ったと思うんですね。もともとは救命救急センターもありませんでしたから。以前はみんな大阪市に搬送されていたんです。
受け入れ先はできたわけですね。
体制そのものは整ったんですが、各病院で連携していくマネジメントについては、さらにこれから進めていくことだと思っています。
もうちょっと進めていける余地があると。
そうですね、そこは課題と言えると思います。堺平成病院として大事なのは急性期での治療後の受け入れですね。治療後、自宅へ帰るまでの病院として、という意味で大きな病院になると思っています。
特にその点においては大きな役割が果たせればということでしょうか。
そうです。加えて、一部救急患者さんを引き受けて、さらに外来で、地域でちょっと具合が悪くなった患者さんも診ていく。
堺市も高齢化は進んでいると思うのですが、この病院の役割はいかがでしょうか。
大きいと思います。回復期リハビリテーション病棟の病床も多いですからね。そのために地域のみなさんとの信頼関係を築いていくことが重要です。そうした患者さんを、ちゃんと診られる体制をつくっていく。その気持ちでスタッフみんながいないといけませんね。
そのためには、どういったことが必要ですか。
看護師さんとかソーシャルワーカーさんとか地域連携室のスタッフとか、実際にたくさん動いてもらっていますので、しっかりコミュニケーションを取って連携することが必要ですよ。仕事の仕方として、「俺に話を全部持ってこい」みたいなことでは難しいわけです(笑)。
まさにチーム医療ですね。
今後どうなるかわかりませんけど、ひとつのモデルケースに近い病院と言えますね。注目している方も多いと思いますので、がんばっていきたいです。

院内外での連携で
患者さんを受け入れる
今は開院直前ですが、どんな準備をされていますか。
これから、実際に救急患者さんの受け入れの流れをどうするかっていうのを作るのと、病院のすぐ隣が消防署(堺市 中消防署)ですから、相談して軽傷救急の受け入れネットワークを作れたらと思っています。
地域との連携ですね。
うちだけで完結することではなく、他の病院とどう分けて、シェアをどうしていくか。それと地域として、この病院がある深井周辺の住人や人口、バックグラウンドを調べて、どういう世代の方がどれくらいいらっしゃるとか、そういったことを整理していきたいですね。
なるほど、実際にどういった方が患者さんとして病院に来るのかと。
このエリアの救急を、100%は無理にしても大部分診ることができる病院にしないといけないと思っています。難しさはあるにしても、患者さんを受け入れる流れは、阻害ない方法を考えていきたい。すぐには無理にしても、取り組んでいきます。
定光先生としては、どういった目標を持っていますか。
まずは、日々患者さんがいらっしゃるのを、できるだけ断らないように診ていく、その積み重ねでしょうね。大風呂敷を広げず、地道に続けていきたいです。
踊り食いの果ての悲劇!
お休みはどう過ごされているんですか。
基本的に土日はお休みです。だいたいどちらかには研究会や勉強会がありますね。
熱心ですね。そういう研究会などが入ることが多いですか。
学会や委員会は土曜日が多いですから、2日間とも丸々休みは少ないかもしれませんね。でもできるだけ休むようにしてます。ウィークデーは時間内にできるだけたくさんの患者さんを診て、週末はしっかり休んで。
ほかにお休みの過ごし方はいかがですか。
僕ほとんど趣味ないんですよ、仕事一本で来ましたので。休みも女房と買い物いったりするくらいで。旅行は時々行ったりはしますけどね。以前は車で長野県に日帰りで行ってましたよ。今はしんどいから行きませんけど(笑)。山口にいた時には、山口から鹿児島の指宿まで行って帰ってきましたね。
日帰りで九州を縦断したようなことですよね。すごい距離ですね!
朝出て、夜中の22、23時に帰ってくるような。最近もたまには温泉に行きますよ。
ちなみに好きな食べ物は。
食べ物……(しばし考える)。と、いうくらい、僕は何でも好き嫌いなく食べてしまうんですよね。ただ、ほとんど何でも食べられるなか、ひとつ食べられないものがあって。
なんでしょうか。
昔大阪に出て来た頃、大阪駅の地下の第三ビルとかあの辺で、魚のおいしいお店がたくさんあって、エビの踊り食いとかをよくやってて、生でたくさん食べてたんですよ。
ああいいですねえ〜。
そしたら食べ過ぎたのか、アレルギーになっちゃったんですね(笑)。
わっ、それは残念ですね。
以後、生の甲殻類は食べてないですね。火を通せば大丈夫です。
好きだったのにちょっと寂しいですね(笑)。

プロフィール

堺平成病院 救急センター長
定光 大海
さだみつ だいかい
【出身】広島県庄原市
【専門分野】救急医学
【好きな食べ物】好き嫌いなく何でも食べる(生エビ以外)
病院情報

大阪府堺市中区深井沢町6番地13
https://sakaiheisei.jp
医療法人 恵泉会
堺平成病院
内科・循環器内科・消化器内科・リウマチ科・放射線科・眼科・整形外科・泌尿器科・歯科・リハビリテーション科・脳神経外科・皮膚科・外科・糖尿病内科(代謝内科)・人工透析内科・心療内科・麻酔科
2019年、長らく堺市でご愛顧いただいた堺温心会病院と浜寺中央病院が合併して誕生した病院です。救急医療から回復期医療、慢性期医療、そして在宅サービスまでの幅広い機能を持つ「地域密着多機能病院」として、地域にあるさまざまな事業者と遠慮なく無駄なく連携できる関係を作れるよう、地域医療のハブになり、地域全体で患者さんをサポートできるよう、努力を重ねてまいります。