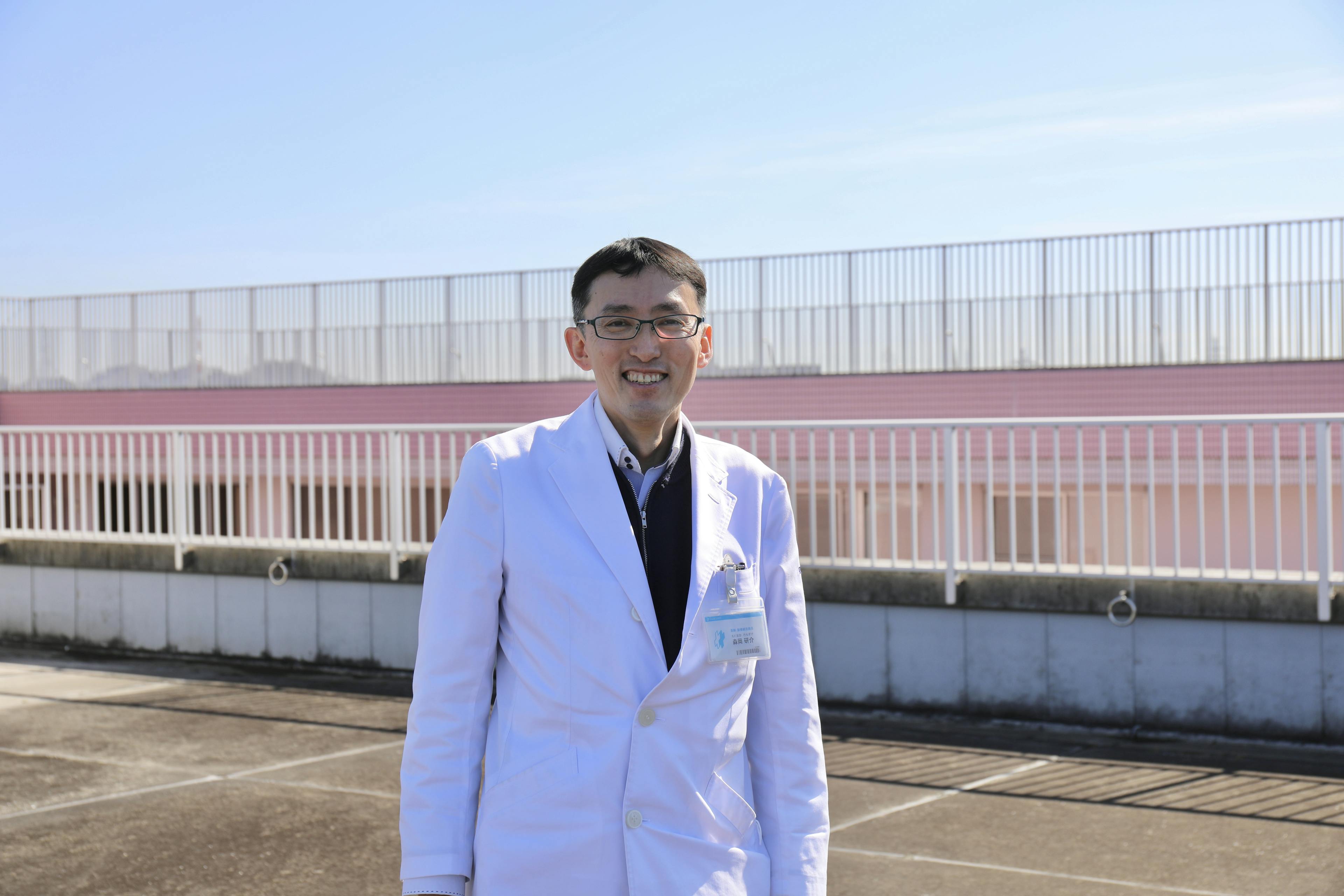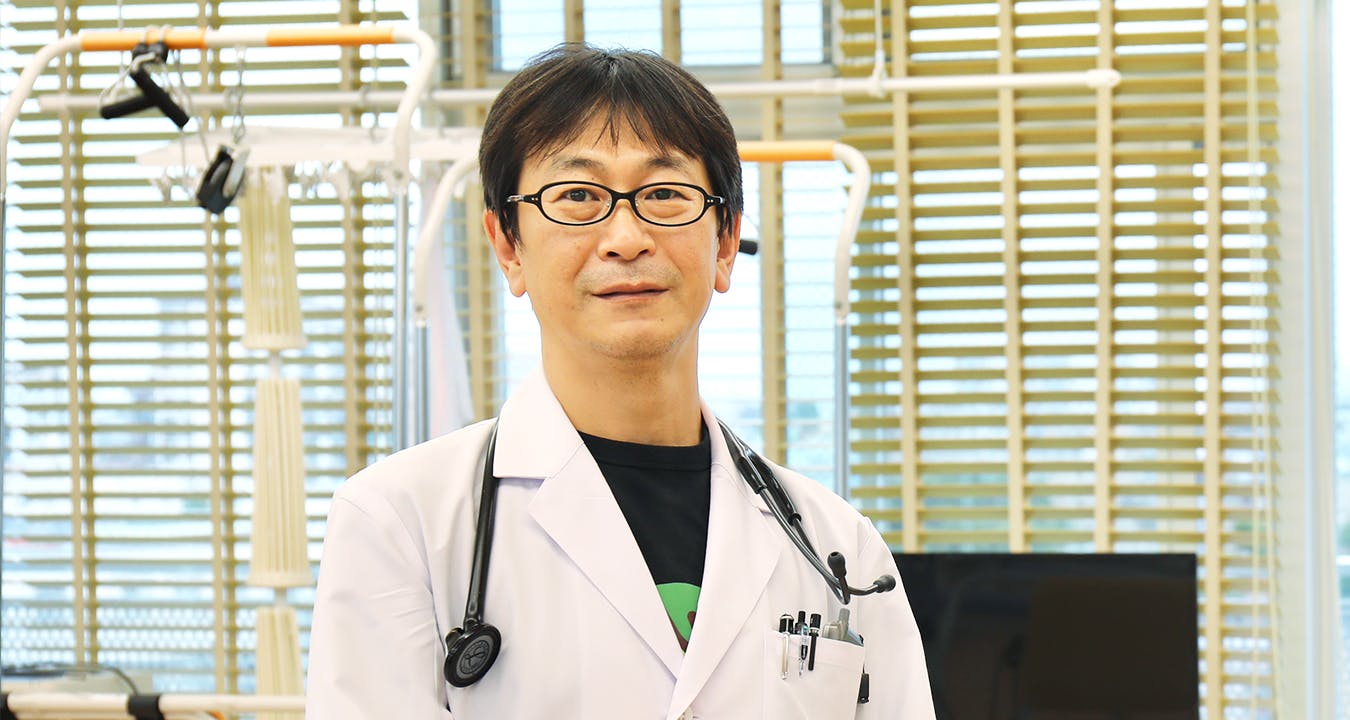医師を目指したきっかけは、命を救ってくれた医療への「恩返し」 脳神経外科と在宅医療に深く関わってきた、その経歴に迫ります/平成横浜病院 院長/程塚 明先生

医師を目指したきっかけは、命を救ってくれた医療への「恩返し」
脳神経外科と在宅医療に深く関わってきた、その経歴に迫ります
平成横浜病院で院長を務める、程塚明先生にお話を伺いました。2021年4月に院長として立たれた程塚先生。長らく北海道の急性期病院を拠点に、脳神経外科医として多くの手術を手掛けてきたほか、近年では神奈川県内で在宅医療にも携わってこられたという経歴を持ちます。そんな先生の経歴を中心に、医師を目指したきっかけや、学生時代のお話などを伺いました。ぜひご覧ください!
病魔で一時は死の淵に…
そこから目指した医師の道
長い期間北海道で働かれていたと伺いましたが、ご出身はどちらですか。
出身は埼玉県のさいたま市です。旧大宮市と言われるあたりですね。北海道には、大学時代から旭川に行って、そのまま居着いちゃった、って言ったら変ですけど、30年以上過ごしてました。
生まれ育ったところはどんな場所でしたか。
うちは大宮と言っても郊外の方で、周りは畑ばっかりでした。我が家は違いましたけど、親戚は全部農家で。
ちなみに周りに医師をしていた方はいらっしゃいましたか。
それが全くいないんですね。うちの父は工場で働いてましたし、母は事務の仕事をしていましたから。でも、うちの一族を辿ると1人だけいたらしいです。元を正せば、平将門の家来だったとか。
えっ、そんな前に! そもそもそれだけ家系図が遡れるというのもすごいですね。
うちは分家なんですけど、本家に家系図があると聞いたことがあります。
医学の道はどんなきっかけで志したのですか。
1番のインパクトは、小学3年生の時です。私がちょっと病気をしましてですね。今じゃ医学の教科書にも載ってますけど、当時はよくわかってない「紫斑病」っていう病気で。
どういった症状の病気なのでしょう。
あちこち出血して、体中に紫斑が出るんです。私の場合は最初に風邪みたいな症状が出て「なんか治んないね」って言っているうちにどんどんひどくなって、鼻血が出たり、歯から血が出たりして、こりゃ変だっていうんで入院したんですけどね。
最初は風邪をこじらせたくらいのつもりでいたのに。
紫斑病にもいろいろ種類があって、私がかかったのはアレルギー性のもので、それが地元の病院じゃわからなかった、というかその頃はまだ病名がなかったんです。それで、地域のそこそこ大きい病院に行ったんですけどやっぱりわからなくて。そのうちどんどん悪くなって、全身がむくんじゃったんですね。今思うと肺水腫みたいになってて、ぜこぜこ息が苦しくなりました。
判明する間も無く、どんどん悪い状態になっていって。
もう死ぬかと思いました。うちの親も、このままでは死んでしまうと思ったんでしょうね。その病院の先生に泣きついたんですけど、その方がたまたま都内の大きな病院の先生で、なんとかそこに運んでもらって。でもそこでも最初はよくわからなくて、白血病じゃないかとかいろいろ言われて、あらゆる検査をしましたね。腰椎穿刺って言って髄液を抜くんですけど、腰だけじゃ足らずに、首の後ろからも抜かれて。
その検査をするだけでも辛そうですね。どうやって快方に向かったんですか。
今思えば、ステロイドとかを使ったんだと思うんですね。要はアレルギー性のものでしたから、そういう薬を使ううちに徐々に良くなって。ただ、後遺症で不整脈が残って「大人になるまで気をつけないと、不整脈で死んじゃうよ」って随分脅かされて、定期的に病院にはかかってました。結局不整脈も出ずに治っちゃいましたが。
その経験が、医師を目指すひとつのきっかけとなったわけですか。
その時の担当医の先生との出会いが大きいですね。その先生に出会って、私は命を助けてもらったと思っています。理由としては、それが一番じゃないかな。今はもう80歳を超えていますけど、いまだに交流があるんです。
自分が医療に命を救われたという想いが、今度は医療の道を目指すきっかけに。
でも、その頃くらいですかね、医療の道に行こうと思い始めたんです。このことがあってからは「将来医者になるんだ」って言うようになりましたね。「助けてもらった」っていう気持ちがあるので、恩返しじゃないけど、そんな気持ちがありました。

「医師になる」ではなく
「脳神経外科医になる」ことを目指した
その後は医師を目指して猛勉強されて。
いえ、中学からテニスを始めたんですね。中学が軟式で高校が硬式だったんですけど。それでもう中高はテニス漬けの生活で。
どちらかというと勉強よりテニスと。
中学までは勉強もそこそこやってたんですけど、高校はもう。今も付き合いがありますけど、みんなで部室にたむろしているような感じで。あまりうるさいことを言わない学校だったので、体育会の連中は進学も4年計画なんですよ。3年間はスポーツをやって、1年間浪人して、大学に行くと。
そこで進まれたのが旭川の大学だったわけですか。どんな生活でしたか。
大学でもテニス部に入って、もうずっとテニスばっかりやってましたね。だから試験はいつもギリギリで。でもだいたい100人学生が入って、卒業の時は60何人くらいしかいないんですよ。それくらい、かなり落とされる学校でした。
入ってからが厳しいんですね。
鬼のように厳しいんですよ。だからたくさん勉強させられましたけど、それ以外はテニスばっかやってました。5、6年になって臨床に入ってからは面白くなって、そこからちょっとは真面目になったけどね。
先生の専門は脳神経外科と伺っていますが、当時、臨床の授業ではどんなことに興味がありましたか。
割と興味があったのは消化器外科だったんですよ。ダイナミックで面白いなと思って実習に参加してました。逆に一番苦手だったのは神経(笑)。
神経が一番苦手なのに、脳神経外科を選ばれたのですか(笑)。
これは、自分が医師になろうと決めた理由の、もうひとつのインパクトに関係しているんです。中学3年生の時のことなんですが、学校に新人の先生が入ってきたんですよ。新卒なんで多分当時22、3歳で、こっちは14、5歳ですから、お兄さんみたいな感じですよね。その先生もテニスをやってたので、顧問ではないけど仲良くなって、お家に遊びに行ったりもしてたんですね。
ずいぶん仲良くなられたんですね。
卒業してからも仲良くしていたんですけど、ある時家に遊びに行こうとしたら「今日はちょっと」と言われて。どうもお母さんがくも膜下出血で倒れたらしいんですよ。その頃のくも膜下出血って言ったら、亡くなる確率や、助かったとしても寝たきりになってしまう確率が今以上に高かったんですね。
今以上に深刻であったと。
それが、1ヵ月くらいしたら「遊びに来い」って呼ばれたので、みんなで恐る恐る行ってみたら、「いらっしゃい」ってお母さんがご飯作って待っててくれて、ビックリしたんです。その先生の同級生がたまたま大学病院の脳神経外科にいたので、そこまで連れて行って手術してもらったそうなんですけど、ひと月前に死の危険があった人が、こんなに元気になって戻ってきたのかと。
確かにそれは驚きますね。
医師になるためのひとつめのインパクトは僕自身の病気だけど、2つめは、そのお母さんのことなんですよね。そこで初めて「脳神経外科」っていう名前を知って、「脳の手術をする外科がいるんだ」と。当時、高校1年生でしたけど、医学部に入る、っていうことを目指すところから転換して、「脳神経外科医になる、そのために医学部に入ろう」と思うようになりました。
見知った方が死の淵から戻ってこられたことを目の当たりにして、衝撃を受けられたわけですね。
ところが大学に入ったら、神経の勉強が全くできなくて、カーッとなりました(笑)。
(笑)。そこで路線転換は考えなかったんですか。
さっき言ったような消化器には興味がありましたし、いろいろお誘いも受けましたね。でも、たまたま誘われて、ある病院の脳神経外科に実習見学に行ったら、そこではもうバンバン手術をやってるわけですよ。細かいことは細かいんですけど、すごいダイナミックにやってるし、それ見て「すごいなあ」と思って。そこで「やっぱり脳神経外科だな」と思って決めました。

悔しい思いもしたからこそ
手術の技術を必死で磨いた
そこからは北海道で長く仕事をされて。
これもテニス部の縁なんですけど、大学病院の脳神経外科の教授が、もともと国体に出るくらい強い選手で、テニス部の顧問をやってくれていて、何かとお世話になってたんですよ。それで「歴代のテニス部主将は脳神経外科に入る」っていう不文律がありまして(笑)。
(笑)。テニスが縁で北海道に残られたのですか。
「まあ脳神経外科ができるからいいかな」って思って(笑)。昔の大学って、教授が絶対的に威張ってるんですよ。でもその教授はそんなことなかったんで、それは良かったですね。そこから30数年は北海道で脳神経外科医として仕事をしました。
それだけ長い期間やられているなかで、働き方も徐々に変わっていきましたか。
最初は旭川の大学で研修して、その後はドサ回りっていうかね、道内の人手が少ない関連病院を回って行きました。決まったローテーションはないんですけど、あそこの病院が大変そうだから行ってくれと。患者さんも大きな病院がある旭川に集まるんですけど、それでも地域ごとに拠点病院がないとやっていけないので、北見とか根室とか、遠軽、名寄とか留萌とかそういったところをあちこち回って。
やはりそういった地域ごとにある病院が大事なわけですね。
特に私たち脳神経外科が見る病気は、その場でなんとかしないといけない、何時間も救急車にいたらとてももたないわけです。今みたいにドクターヘリもない時代ですし。とはいえ、人員も環境も、旭川とは違いましたね。
整っているものも違うと。
もちろん大学病院とは全く違いますよ。しかも今みたいに、患者さんの画像を送ってWebで確認する、なんてできませんので。当時はフィルムを見ながら電話で説明するしかないですし、極端な場合、レントゲンのフィルムを持って、車で走ったことがありますよ。車で旭川まで行って、フィルムを出して説明して。
もう行って直接見せるしかないわけですね。手術は地域の拠点病院でもやられて。
その病院で手術できるものだったらしましたし、待てる時間があれば、旭川まで搬送して。まあでも、それはほとんどなかったですけどね。当時は私たちではできないんで、旭川から応援が来て手術をしてもらうと。それが悔しくてね。「自分でできたら、こういう想いをしなくてもいいのにな」って。
本来なら、この場で自分たちでどうにかしたいわけですよね。
教育も足りてなかったですよね。今みたいに人がいないから、びっちりついて指導をする、なんてできないですから。だから当時はみんな、基本はあるんだけど、かなり我流でしたね。そのなかで、テレビにも出るような有名になった先生もいますし、当然そうでない人もいますし。
当時は全体的に人が少ないから、それが当たり前と言うか。
そうせざるを得なかったですね。ただ自分としては早く腕をつけたいと思っていました。そこで、たまたま旭川の病院に異動してくれと医局の人事で言われまして。そこは別の大学の関連病院だったんですけど、手術を見てみると、うちの教授の技術とそこまで変わらないんですよ。基本はみんな一緒なんだなと思いましたね。
基本をあらためてそこで確認されたわけですか。
そこに1年ちょっとくらい行ったのかな。今もそうだと思いますけど、その病院は手術件数がすごく多いところで、年間800〜1000件くらいやっていました。それがすごく勉強になりましたね。
数を重ねることで経験値がついていって。
やっぱりたくさん見るだけじゃなく、ある程度やらせてもらわないとできるようにならないので、そこでの経験は大きかったです。
期間としてはそこまで長いものではなかったけど、経験としては大きかったのですね。
大事なことは
「患者さんに教われ」
脳神経外科というと、微妙な違いで予後にも大きな影響が出そうな、繊細なイメージがあります。
すごくありますね。うちの教授によく言われたのは「患者さんに教われ」っていうことですね。
具体的にどういうことですか。
ある時、八百屋のおかみさんの動脈瘤の手術をしたことがあったんですが、歩けるようになり、すっかり良くなって退院されたんです。で、それからしばらくしたら外来に来られたので、どうしたのかと尋ねたら、八百屋の店先に立ったんですが、いつもはできていたそろばんの勘定が、うまくできなかったそうなんですよ。
そこで、何かおかしいと気づいた。
実は、軽いんですけど高次機能が落ちてたんですよね。それでもう一回入院してもらって調べたら、水頭症の傾向があって。くも膜下出血の後とかになる合併症のひとつなんですが、頭に水が溜まるんです。それでシャント手術というものをしたら、無事に回復して、そろばんをはじけるようになりました。
無事、元のようにお店に立てたのですね。
私たちは医師としての視点で見ていますけど、大事なのは患者さん本人の満足度ですよね。その意味で、患者さんから教わることが大きいと思います。
確かに、何をもって回復かということは、患者さんに教わらないとわからないことですね。
やっぱり治療としては、あくまでも患者さんやご家族にどれだけ満足してもらえるか、が大事なんですが、残念ながら救うことができなかった時にも、ご家族から後々お礼を伝えられることがあって、本当に驚きました。
ご家族はどういったお気持ちだったのでしょう。
「残念ながら病気には勝てなかったけど、病院のみなさんが一生懸命やってくれた」ということへの感謝でした。普通であれば、病院にかかるということは、元気になって帰ることが目的で、そうでなければ行く必要はないわけです。痛い思いをしたうえで命を落としてしまって、ご家族からすると「許せない」と思われても仕方ないのに、感謝までされてしまうと、ありがたいというか申し訳ないというか…。
どうお応えしていいのか難しいところではありますね。
助けられなかったことについては「残念です」とお伝えするしかないですし、謝罪もするんです。よく「謝ったらダメだ」ということも言われますが、結果的に助けられなかった、ということについては、謝罪をお伝えしていいと思いますね。ただ、やるべきことはやったというのであれば、そこまで最善を尽くしたことに関しては、胸を張っていい、と思っています。
そこまで尽くしたことが伝わったからこそ、ご家族からの感謝につながったわけですね。

一大決心!
新天地で在宅医療の道へ進む
先生は前職で、神奈川県内で在宅医療に携わられていたと伺ったのですが、北海道で脳神経外科をされていたところから、どういった変遷があったのでしょうか。
これもまたインパクトとなった出来事があって、まあここまでそういうことが多いですけど(笑)。
(笑)。そういった出来事が先生の行動の後押しになっていますよね。
在宅医療への転換について、一番直接的に影響があったのは、北海道で関連病院にいた時に受け持った、脳梗塞の後遺症で認知症が残った患者さんですね。入院中、いろいろとやったんですがなかなか良くならなくて。私たちとしては、もう少し薬物治療やリハビリを続けることをお伝えしたんですが、ご本人とご家族がもう嫌だと言って、自宅に帰ることを決めてしまわれたんです。
これ以上入院を続けることを拒否されたと。
でもそうは言っても、その状況で放っておいてしまってはどうなるかわからないので、どうしようかと悩んでいたら、その病院でたまたま内科の先生が在宅医療を行っていて。相談したら「ついでに回っておくよ」と、定期的に診てくれることになったんです。
退院に同意する代わりに、在宅医療を受けることになったのですね。
それから何カ月かして、その患者さんが、外来に定期のMRIの検査をしにいらしたんですけど、見たらビックリしたんですよ。
どんな変化があったのでしょう。
数値や画像で見ても、特別良くなったというわけではないんですけど、見た目がすごく良くなっていたんです。病院では暴れてしまうこともあったのが、脳の構造機能は変わってないけど、家に帰ったらいいおじいちゃんになっていて、ちゃんと生活できるようになっていました。
特別なことをしたわけではないのに、すごいですね。
それがすごいショックでね〜。病院にいる人間からすると「病院で行う治療が一番良い」と自負してますから。今だから言えますけど、在宅医療のことは当時「安否確認代わり」くらいにしか思ってなかったです。
やっぱりそれは、ご自宅で生活しているということ自体が良かったわけですか。
そう、その患者さんにとっては、病院っていう異質なところにいるよりは、慣れ親しんだお家にいた方が安心できるし、脳にとっても良かったんでしょうね。僕としては、病院が最高だと思ってたのが打ち砕かれたことで「じゃあ在宅医療ってなんだろう?」って思うようになったんです。
なるほど、その出来事はインパクトとして大きいですね。
それでいろいろ調べているうちに、都内にいる脳神経外科の仲間の、知り合いの知り合いくらいのつながりで、在宅医療所を運営している方とご縁があって、お誘いを受けたわけです。
それにしても、だいぶ環境も立場も一気に変わるわけですから、かなりの決断にはなりますよね。
実はそのちょっと前に、うちの父親が亡くなったんですね。その時はちょうど病院で手術をやっていて、会えたのはもう亡くなった翌日だったんですが、家族も僕がこういう仕事をもう何十年とやっていますから、文句も言いませんし、フーテンの寅さんみたいなもんだと思われているんですけど(笑)。
(笑)。いつ帰ってくるかわからないと。
自分としては患者さんのためとはいえ、自分の親の死に目に会えなくていいのかなっていうことをちょっと思って。いずれは関東で仕事をしたいということは少し考えていました。そこで、たまたまその診療所の方と出会いがあって、しかもその方が若くて目がキラキラしていたので、すごく惹かれてしまって、思い切ってやってみようかなと。
いろいろと重なったタイミングにご縁があったわけですね。
当時は北海道で院長をやってましたけど、60歳手前で最後のチャンスというか、面白そうなことをやってみようと思って決断しました。

在宅医療を通じて
患者さん個人個人の人生に触れる
長く携わってきた脳神経外科の道から、いざ新たに在宅医療に触れてみていかがでしたか。
法人の本部がある東北で3週間くらい研修をさせてもらったんですが、当初は、けっこう大変そうだなと思いました。今まではずっと病院にいて、手術となったら夜中でもやりますし、当直の時は48時間くらい勤務はしますけど、割とオンオフがあったんですよ。
今度は家にいたとしても、呼ばれることがあると。
それから、研修を終えていざ仕事を始めようという時に、それまでいた看護師さんやソーシャルワーカーさんが、タイミング悪く辞めることになってしまって。僕を含めて在宅医療の未経験者ばかりが残って、スタートすることになりました(笑)。
新しい門出としてはちょっと不安ですね。
時々本部から応援部隊は来てくれるんですけど、当然普段は私たちだけでやらないといけませんから。3週間の研修で見たことを思い出しながらやって、わからないところは地域のケアマネジャーさんや訪問看護師さんに教わりながら。最初は怒られ怒られやってました(笑)。
怒られることもあるんですね(笑)。
そうやっているうちに、私たちなりのスタイルができていきましたね。近くに何年もやってる先輩方もいますし、研究会もありますので、そこでお話を伺って、どういう気持ちでやっているとかもお聞きしながら。
どういった患者さんが多かったですか。
大学病院や大きい病院が多い地域だったので、7割くらいはがん患者さん、特に末期の方、お看取りが多かったです。
実際に取り組んでみてどのように感じましたか。
大学病院や関連病院にいた時は、手術してから退院までが早いですから。その後どうなっているんだろう、っていうのはもともとずっと気になっていたんです。
そういった病院では、多くの患者さんを手術して救うことが、まず大事な役割ですからね。
在宅医療では、患者さんがご自宅に帰ってからもずっと密着して関われますし、お話もじっくり聞けますから。それまでの関わり方とは違って、患者さん個人個人の人生を間近でみることができていい経験になりましたし、医師として良かったなと思っています。

「絶対に見捨てない。」医療に関わるため
平成横浜病院へ
この平成横浜病院にはどういう経緯で移られたのでしょうか。
6年くらい在宅医療に携わってきたんですが、ひとつは、ある程度仕事が確立できてきたっていうことと、訪問の仕事にちょっと疲れたところもありました。そこに後任が入って来て、落ち着いて来たんですね。
ご自身のなかで、ひと段落というタイミングがあったと。
そこで、知り合いの方を通じて、このグループから「病院のマネジメントに関わりませんか」と声をかけてもらったわけです。
平成医療福祉グループについてはご存知でしたか。
グループの世田谷記念病院は、その診療所と患者さんの行き来もありましたし、退院前カンファレンスのために行ったこともありました。世田谷記念病院が在宅医療部を立ち上げる時に、私がいた診療所に見学に来られたこともあったんですよ。
そこで縁もあったわけですね。病院の仕事にまた戻ることについて、どのような気持ちで決断されたのでしょう。
最初はお受けするか迷ってたんですけど、グループの「絶対に見捨てない。」という理念を見て、気持ちがガラッと変わりましたね。
どういった意識でしょうか。
以前病院で仕事をしていた時も、見捨てるということは当然ないんですが、在院日数やベッドの都合で、別の病院に移ってもらわざるを得ない、ということはあったわけです。
もう少し手をかけたいという気持ちがあっても、状況がそれを許さなかったと。
だからこそ「絶対に見捨てない。」ということを掲げる医療ってどんなものなんだろうと、見てみたい気持ちになりました。あとは、私の今までのキャリアからすると、慢性期病院というのが経験がないところだったので、これをやると全部のピースが埋まる、というか(笑)。でも実際に関心があったんですね。それで、やってみようと思ってお受けしました。

グループ理念を具現化したい
もっとリハビリテーションを病院の柱に
平成横浜病院は、今まで程塚先生が働いてきた急性期の病院とは違うタイプの病院だと思うのですが、実際働かれて印象はいかがですか。
面白いですね。それなりに歴史もあるところなので、その良し悪しもありますし、グループとしてのやり方もありますし。それをどう調整していくかっていうのが、興味深いです。
リハビリの職種と関わることもそこまで多くなかったのではないでしょうか。
ほとんどなかったですね。大きい病院だと、リハビリカンファレンスがあって、リハビリスタッフと話す機会はありましたけど、それでも月に1回くらいでしたから。ここみたいに密着して話すことはなかったですね。
関わり方もだいぶ変わってきたと。
個々の患者さんについて、個々の療法士と話す。カンファレンスにしても、一人ひとりの患者さんについてやっていくっていうのもあまりなかったですね。その点では今までと密着度が違いますよね。
実際に院長として立たれたのは着任から半年ほど経って、今年(2021年)の4月からと伺いましたが、院長となって変わったことはありますか。
そんなに大きくは変わってないかもしれないですね。でも、院長と名が付くのは今回が3回目なんですけど、やりがいは特に今まで以上に大きいかもしれません。実績がすごく見えてもきますので、それはプレッシャーでもあるけど、同時に励みにもなっています。
現在はどのようなルーティンでお仕事をされていますか。
総合内科の外来を週に2回、あとは発熱外来も2回担当しています。内科の方は、神経系の患者さんはよく担当しますよ。それに加えて、在宅医療も週に2回。そういった診療に関わりながら、院長として会議や委員会に出席したり、事務系の仕事をやったりしています。
先生として、現在のやりがいはどんなところにありますか。
グループの理念でもあるし、自分も関わりたいと思った「絶対に見捨てない。」医療を、どこまで具現化できるか、ということです。まだ全部はできてないと思いますけど、もっと具現化して、職員みんなで共有できたらいいですよね。全員が同じ方向を向くって大変だと思いますけど、そういう流れを作っていくのが、自分の仕事かなって思ってます。
今後の展望はいかがですか。
病院の機能として、リハビリをひとつの大きな柱に、もっとうまく連携していきたいですね。そのために私は環境を整備しないといけないですし、人材なり設備なり、考えないといけないなと思います。

医療や福祉の網から漏れ出る人を
1人でも減らしたい
もともとマネジメントを依頼されて着任されましたが、2020年には程塚先生が中心となって、在宅医療部門をスタートさせたそうですね。
病院の運営会議の時に、「外来に通っていたけど、来るのが難しくなって、そのままになっている患者さんがいる」という話が出たんですね。なかなかそのフォローができていなかったそうなんですが、病気によってはそのままにしておくと危険なものもありますから。
そこで、経験のある程塚先生が担当するということに。
「そういう患者さんは、訪問したらいいですよ」って僕が言ったら、「そういえば先生、在宅医療やってましたよね」って言われて、「あっしまった!」って思ったんですけど(笑)。経験があるのが僕だけだったので「じゃあやりましょう」と。もともとは、一般的な在宅医療とは違って、うちの外来に通っていたけど来れなくなってしまった患者さんをフォローします、っていうことで始まりました。
基本となるのは、平成横浜病院の患者さんへのフォローアップということですね。今後は拡充もお考えですか。
今は私ができる範囲でやっていますが、もちろん今後スタッフが増えればそれも考えています。専任できる人が増えれば、より回る頻度が増やせますから。時々、地域のクリニックからも患者さんを診てほしいとお願いされることがあるんですが、そういったこともより対応しやすくなります。
地域の在宅医療の診療所との棲み分けについてはいかがですか。
よく、こういう話になった時に「パイの取り合い」っていう言い方をされる時がありますけど、取り合うのではなくて「いかにパイを広げるか」ということを考えるのが大事だと思うんです。
医療において「パイを広げる」とはどういう意味ですか。
先ほども、病院に来れなくて困っている方がたくさんいるという話が出ましたけど、それは、平成横浜病院に限らないわけです。今は独居とか老老介護が増えてますから、人手の問題であったり金銭的な問題もあるかもしれない。福祉はそういった方にも働きかけてますけど、医療は病院で待っているだけでいいのかと。福祉と同じように、医療も手を差し伸べていかないといけないんじゃないかと思っています。
実は見えにくいところに医療を求める声があると。
そこに福祉のサービスは届いているけど、そのなかに実は医療を必要としているという方がたくさんいるんですよ。
今は向こうから働きかけがないと、病院側からはそれが見えない。
来れるのであれば、きっと病院に来てくれていますからね。そういった方については、地域のケアマネジャーさんや介護士さんが情報を持っていることが多いので、それがもっと把握できるようになれば、私たちがそういうところに訪問できると。ご自宅で療養している人のなかには、医療がちゃんと手を差し伸べて治療すれば、症状が良くなるとか、仕事に戻れるとか、ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を改善できるっていう人がいるんです。だからみんなでパイを奪い合うのではなくて、広げていかないといけません。
行きたくても病院に行けない人や、実は医療が必要だけど届いていない、という人を、地域の医療機関でカバーしていくわけですね。
今までは空き地があちこち多かったので、いかにその空き地を埋めていくか。そのために医療として何ができるかを考えていった方がいいんじゃないかなと思います。院内も充実しないといけないですけど、外とのつながりの充実も大事ですよね。網の目状に全ての人をカバーできるように、病院同士もみんなくっついていけば良いなと思います。
地域のなかで、医療も福祉も連携していくことが大切ですね。
医療や福祉から漏れ出る人を1人でも減らすっていうことが大事じゃないですかね。この病院で全てはできないにしても、そういう風を起こしたいっていうことは思いますね。その時に「絶対に見捨てない。」という理念は大事だと思うんです。

大好きなのは
横浜が地元の、あのバンド
ではプライベートの話をお聞きします。最近、お休みの日はどうお過ごしですか。
疲れて寝ていることが多いですね(笑)。でも運動不足になっちゃいけないんで、とは言えそこまでできないので、奥さんと散歩したり、あとはジムにも行ったり。営業時間が今は短くなっちゃっているので、週1回でも2回でも、行ける時は行っています。
コロナ禍になって、やはり過ごし方は変わりましたか。
以前よりは外に出なくなりましたね。前は奥さんの買い物に付き合うとか、たまに、コンサートとか映画とか、お芝居も見に行ってましたよ。
コンサートは、どういうものが特にお好きですか。
クラシックも聞きますし、あとはクレイジーケンバンドが好きですね〜。もともとクールスとか、矢沢永吉とかキャロルからくるんですけど。
やはり矢沢永吉やキャロルは当時大流行していましたか。
当時はああいうワルっぽいっていうのが良かったんだろうね、ちょっとアウトローというか。
コロナ禍以前はそういったコンサートもよく見に行かれていたと。
それが、北海道にいた時はクレイジーケンバンドのチケットも割と取りやすかったんだけど、神奈川に来たら全然取れなくて(笑)。北海道では1、2列目で見れてましたから。
横浜が地元ですし、競争率が高いのかもしれません。今後やりたいことはありますか。
高校の時の友達と、テニス部の仲間とテニスやろうとは言ってますね。あとは、年に一回、みんなで集まってのキャンプ。「今年こそ」って言ってて、先々週に予定はしてたんですけど、残念ながら。
あっ、今回キャンセルになってしまったんですね、残念…。
それに行きたいっていうのがひとつですね。あと、ちょっと無理かもしれないけど、山登り。やったことはないんですけど、今後は行ってみたいなって。
では最後、みなさんに、好きな食べ物をいつも聞いているんですけど。
食べ物、なんだろうな…。好きだけど全然食べれてないのがカレー。
どうして食べられないんですか。
なぜかいつも食べたい時に当たらないんです。病院の食堂でも、カレーが出る日はなぜかいつも忙しくて食べられない(笑)。
(笑)。求めているのに得られないと。
ただ、カレー食べると太っちゃうからね、食べすぎちゃって(笑)。
プロフィール

平成横浜病院 院長
程塚 明
ほどづか あきら
【出身】埼玉県さいたま市
【専門】脳神経外科
【趣味】音楽鑑賞、舞台鑑賞など
【好きな食べ物】カレー(食べたいのになかなか巡り会えない)
病院情報

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550番地
https://yokohamahp.jp/
医療法人横浜 平成会
平成横浜病院
内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・外科・泌尿器科・皮膚科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科・脳神経外科
地域に根ざした病院として、一般病棟、地域包括病棟を備え、回復期リハビリテーション病棟を新設しました。さらに救急告示病院として24時間365日、患者さんの受け入れを行っています。2018年6月には、総合健診センターがリニューアル。地域の健康を支えていけるよう努めています。