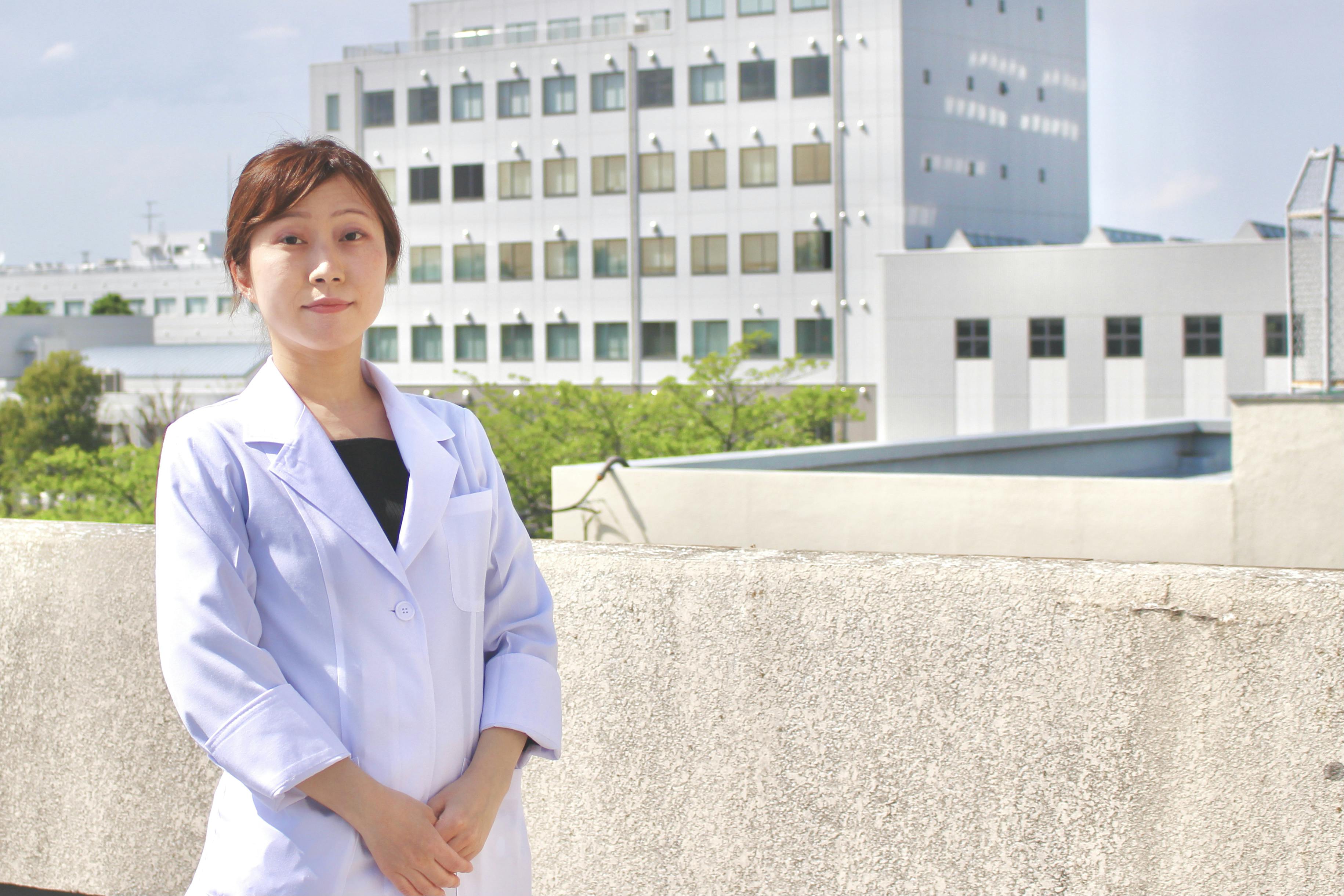挫折をきっかけに目指した医療の道 多くの職種と関わりながら働くことが楽しい/平成横浜病院 薬剤部 係長/瀧田大輔さん
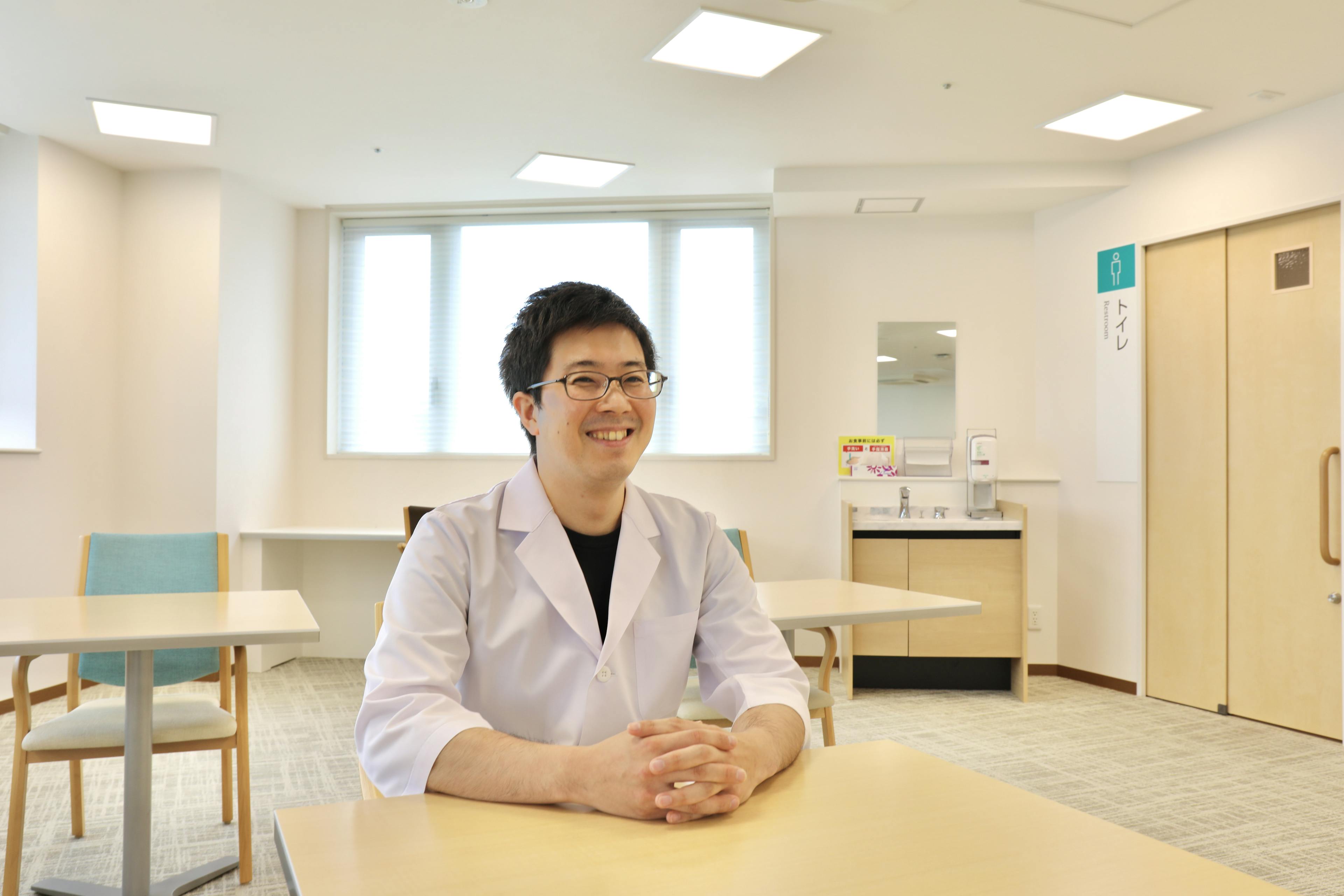
挫折をきっかけに目指した医療の道
多くの職種と関わりながら働くことが楽しい
平成横浜病院の薬剤部で係長を務める、瀧田大輔さんにお話を伺いました。薬剤師を目指す以前、プロを目指すほど熱心に野球に打ち込んでいた瀧田さん。しかし、悲劇に見舞われて挫折を経験、その後、薬剤師を目指すこととなります。薬剤師として歩んできたキャリアを中心に、急性期病院での経験と、そこから考える慢性期病院で働く醍醐味などを伺いました。ぜひご覧ください!
高校野球に打ち込むも
膝の故障で散る…
もともとはこの平成横浜病院にお勤めではなかったと伺いましたが、こちらで働き始めてどのくらい経ちましたか。
この4月でもう3年が経ちました。もともとはグループの緑成会病院に勤めていました。
そちらはどのくらい在籍していたのですか。
5、6年はいたと思いますね。
ではグループでのキャリアは10年弱ぐらいになるんですね。ご出身はどちらですか。
東京都の清瀬市です。東京都の天狗の鼻みたいなところです。
埼玉県に接しているところですね。清瀬市はどんなところですか。
病院がたくさんあって、田んぼが多いところです。観光地も大きい建物もないんですが、あとはひまわり畑が有名ですね。
東京都内でものどかな土地なんですね。どんな少年時代を過ごしましたか。
小学校5、6年生くらいから、ずっと野球をやってましたね。小学生、中学生とやって、高校2年生まで。
ということは、高校3年生の最後の夏を待たず、2年生で辞められたのですか。
当時ピッチャーだったんですけど、高校2年生で膝を悪くしたので、退部したんです。そこからフラフラしていました。
野球を続けられないレベルの故障だったのですか。
膝の半月板がすり減っちゃいましたから。病院では「使いすぎだ」って言われましたね。
ピッチャーといえば肘の故障のイメージが強いです。
私はアンダースローだったんですよ。低いところからスッと投げるので、足にすごい負荷がかかっていたみたいで。それに耐えられない体だったんでしょうね。本当はプロ野球選手になりたかったんです。
そのぐらい本格的に打ち込んでいたと。野球部が強い高校だったのですか。
当時は選手層は良かったんですけど、そんなに良いところまでは進めなかったですね。でも甲子園経験のある監督が指導者として入っていて、部員も1学年100人もいるくらい人数が多くて。
公立の高校としてはなかなかの部員数ですね。膝を故障した後も、そのまま野球部に残るという選択肢はなかった。
今でこそ野球を見るのは好きなんですけど、その頃はやるのが好きだったので「もう野球ができないなら辞める」という気持ちでした。
みんなと一緒に3年の夏までやりきろうという気持ちにはなれずに。
その頃はそう思えなかったです。挫折でした。引退して半年くらいは何もしてませんでしたね。不登校になった時期もありました。
おおっ…そこまで落ち込まれていたのですね。
でも、その頃くらいですかね、医療の道に行こうと思い始めたんです。

野球の挫折から
辿り着いた薬剤師への道
野球を諦めたところで、医療への道を見つけたと。何かきっかけがありましたか。
ちょうど同じ頃に祖父が倒れるということがあって、自分に何かできることはないかなと思ったんです。なので、最初は医師になりたかったんです。でも、血を見るのが苦手で(笑)。
その理由で医師は難しそうだと。
そこで、何かないかなと思って調べた時に、薬剤師を見つけたんです。薬を通じて支えようと思って、薬学部に進もうと決めました。でも、ちゃんと受験勉強を始めたのは高校3年くらいの時ですね。
野球への挫折感はあったけど、そこからは切り替えて勉強に打ち込まれて。
真面目ですね(笑)。
(笑)。もともと理系だったんですか。
理系ですね。化学は嫌いでしたけど(笑)。このインタビューに出ていた薬剤部の秋田部長(※)は、むしろ化学が大好きと話していましたが、僕は生物系が好きなんです。体の構造や機能を学ぶ授業の方が楽しかったです。
※平成医療福祉グループ 薬剤部 部長/秋田 美樹さん インタビュー記事
受験勉強はいかがでしたか。
ずっと野球ばかりやっていましたし、それこそ勉強自体を高校3年生から始めたようなものだったので1年浪人させてもらって、そこから薬学部入学しました。
ちなみに、当時薬学部はもう6年制の頃でしたか。
浪人したことで、6年制の第1号になったんです(笑)。
(笑)。なるほど、1年ずれたことで2年間学生生活が長くなったと。授業で教わること自体は、4年制と一緒なんでしょうか。
同じだと思います。ただ6年制は、現場ですぐに活躍できるようにということで、最後の2年間は実習が多くあるんです。
即戦力となるための2年間なんですね。いざ大学で薬学の勉強をしてみて、どう思いましたか。
勉強する分野がすごく幅広いんですよ。直接薬学と結びつかない勉強もやる必要があって「こういうこともやらなきゃいけないんだなあ」って思いました(笑)。
大学時代はどんなことが楽しかったですか。
在学中はほぼ実験ばっかりでしたね。薬学部って少し変わった人も多いんですね。みんなで飲みに行く、というのもあまりなかったですね。
みなさん職人タイプというか。
そうですね。授業が終わったらみんなすぐ帰って。授業もだいたい朝から夜までみっちり入っているので、ちょっと遊んで帰るくらいでしたね。でもアルバイトは大手ドラッグストアでやっていました。
6年制になって実習期間が充実したとのことでしたが、いかがでしたか。
調剤薬局と病院にそれぞれ行くんですけど、特に薬局では指導の薬剤師さんがとても熱心で人が良くて、それが印象に残っています。地域密着の調剤薬局だったんですけど、指導薬剤師の方が、いろいろとやらせてくれて、とても楽しかったです。その方とはいまだに交流があって、いずれ恩を返したいなと思っています。
当時の縁がまだ続いているというのは素敵ですね! 就職先としては調剤薬局と病院とで迷いはありましたか。
調剤薬局も魅力はあったんですが、もともと薬剤師を志した時から病院で働きたいという気持ちがあったので、病院に進もうと決めていました。ただ、当時は本当に募集が少なくて。
病院で薬剤師の募集枠が少なかったと。
今でこそ薬剤師も病棟に出ていこうということが言われるようになっていますが、その頃はまだそういった概念が広く浸透していなかった時期でした。なので、薬剤師の人数もそこまでたくさん必要なかったんです。
病棟での業務行わないのであれば、そこまでたくさん募集することもないと。
その頃はまだ病棟薬剤師が出始めの頃で、業務としてはあったんですけど、人数が揃っている病院でしかできなかったんです。その頃くらいから徐々に認識が変わり始めてきて「薬剤師も人数が必要だよね」ってことで枠が増えてはいくんですが。
瀧田さんが就活している当時だと、まだ一般的になっていない時期で。
そうなんです。私は病棟で働きたいという気持ちがあったので、そういう病院を探していたんですけど、なかなか枠がなくて。そのなかで、都立の急性期病院が、非常勤なら入れるということで、入職することになったんです。

薬剤師のスタートは急性期病院
常勤の誘いをかわしながらキャリアを積む
キャリアのスタートは急性期病院での非常勤勤務だったのですね。お仕事はいかがでしたか。
楽しかったですね。同期が4人いたんですけど、常勤非常勤の隔たりもなく、ちゃんと教育もしてくれました。先輩たちも年齢層が若くて、すごい楽しくやれましたね。一通り全てのこともやらせてもらいましたし、「病院薬剤師なんぞや」というのは、そこで働いた2年間で学ばせてもらえたんです。
良い経験ができたと。そこでは、まだ病棟業務はされずに。
それが、すぐに携わらせてもらえました。薬剤師の活躍の場を広げていこうという考えの病院で、それを事前に知っていたからこそ、そこに入ったんですね。すごく忙しかったんですけど、すごい良い病院でした。
どんなタイプの忙しさだったのですか。
急性期病院ならではの忙しさでした。急性期病院では患者さんが入院している間隔がすごい短くて、10日とか2週間で病棟の患者さんがガラッと変わってしまうんですね。
今働いていような慢性期病院とはサイクルが違うわけですね。2年間働いたとのことですが、どうしてそこから離れたのですか。
その病院で1年ぐらい仕事をした時に「退院してからの患者さんってどうなってるんだろう」っていうことに興味が湧いてきたんです。
早いサイクルで仕事をしていると、なかなか患者さんの退院後まで追ってはいけないと。
そこで、慢性期病院も見てみたいなと思った時に、たまたまそこで一緒に働いている同僚に、グループの緑成会整育園で働いた経験がある薬剤師がいたんです。その人は今、平成横浜病院にいるんですけどね(笑)。
グループに戻ってまた一緒に働かれているんですね!
その薬剤師から緑成会病院を教えてもらって求人に応募して、今度は緑成会病院で非常勤として働くことになったんです。
当時は緑成会病院でも、非常勤での募集しか出していなかったのですか。
いえ、常勤でも募集していたんですが、しばらく働いて様子を見てからと思っていたので、まずは非常勤として入りました。当時はグループ薬剤部の秋田部長が、まだ現場で主任か課長として働いていた頃でしたね。
最初は、必ずしも長く働こうという気持ちではなかったと。
ここで経験を積んで、ゆくゆくは急性期病院に戻ろうという気持ちが当初はあったんです。入ってすぐに「常勤にならないか」とも言っていただけたんですけど、「急性期病院に戻るつもりなんで」と言いながら(笑)。少しだけですけど、どちらの病院でも非常勤で働いていた時期もありましたよ。
どちらも重なっていた時期があったんですね。それこそ、元いた急性期病院で常勤になるという道もあったのではないですか。
実はそちらでも常勤に誘っていただけました。楽しい職場だったんですが、若いうちでないと、いろいろな職場を見ることができないんじゃないかと思ってお断りしたんです。その職場のみなさんにはとてもお世話になって、今でも交流があります。ちなみに調剤薬局も気になっていたので、一時期は調剤薬局でも非常勤で働いていました。
なるほど、急性期病院も調剤薬局も経験したうえで、緑成会病院で常勤として働くことになったと。
緑成会病院で働いて
人と話すことがさらに楽しくなった
緑成会病院で常勤で働くことにした決め手はどんなことでしたか。
このグループで働いて一番良いと思ったのは、いろいろな職種の人と話せるというところでした。もともといた急性期の病院だと、薬剤部ではよく話していましたし、病棟に行けば医師や看護師とも話す機会が多かったんですけど、あまりほかの職種と話したことはなかったんですね。
直接的に薬剤師と関わる職種の人とのやりとりはあったけれど。
本当に薬にフォーカスして仕事をしていたという印象でした。緑成会病院に来たら、リハビリスタッフや管理栄養士、医事課のスタッフとも話す機会があって「あ、こんなにいろんな人が働いているんだな」って気づいたんです。
そこが決め手となって、緑成会病院で働いていこうと。
ほかの職種の人と話すことで面白くなっていったところも多かったので、そこが良かったです。その時も働いていて楽しかったですし、これから常勤になって働いたとしても、きっと楽しいことがありそうだなと。もともと私は暗くて内気な性格なんですけど、薬剤師になってから人とよく話せるようになっていったんですね。
今話していただいている印象からすると、ちょっと意外な気もします。
今も明るいかわからないんですけど(笑)。それが特に、緑成会病院に来てさらに変わった感じがして。とにかく働き始めてから、人と話すのが楽しくなりました。あと緑成会病院で働く理由として、当時は常勤スタッフが秋田さんしかいなくて、とにかく忙しそうにされていたというのもあって。
なるほど、それをお手伝いしていこうという気持ちが。
秋田さんの仕事を尊敬していたので、着いていこうという気持ちがありましたね。

病院現場をサポートする
グループ薬剤部の業務
常勤スタッフとして緑成会病院で働き始めて、仕事の変化はいかがでしたか。
今思えば、非常勤で働いていた頃から仕事自体はほとんど常勤の薬剤師と変わらなかったかもしれないです。それこそ、印西総合病院の立ち上げ時の応援に行ったこともありましたし。
薬剤師としての仕事内容にはそこまで大きな変化はなかったと。
ただ、その後に役職をつけてもらって、グループの仕事に関わるようになったんですけど、そこからは今につながるような仕事が増えていきましたね。
病院内だけでなく、グループ薬剤部としての仕事にも携わるようになられて。
グループのリハビリテーション部にならって、チーム制というものを薬剤部でもスタートさせたんですね。業務支援を行うチーム、就活をサポートするチーム、薬品情報に特化したチーム、病棟業務をサポートするチーム、この4つからスタートしました。今も所属する業務支援チームには、この時から携わっています。
なるほど、長く関わってきているのですね。
でも、当時はまだ人数が少なかったので、むしろ全部のチームに入ってましたね(笑)。
全掛け持ちですか(笑)。グループの仕事はいかがでしたか。
忙しくはなりましたけど、楽しかったですね。業務支援チームだと、担当エリアの病院を回るので、いろいろな病院も見ることができて、さらに楽しいなと思いました。今もほとんど同じことをやっていますけど。
業務支援というのはどういうことをされるんですか。
現場でうまくいかないことや、ミスが発生しやすい状況があった時に、改善できるようにアドバイスをしたり、ほかの病院の事例を紹介したり、いろいろとサポートさせてもらっています。当初はエリアの各病院を月1で訪問して、聞き取りをしていましたけど、コロナ禍になってからは、オンラインでつないでヒアリングをして、困っていることに対して支援を行っています。
いろいろな症状を持った患者さんに関われることが
慢性期病院で働く醍醐味
先ほど、他職種のスタッフと話す機会があることが楽しいと話されていましたが、例えばリハビリテーション部と薬剤部は、どう連携していますか。
リハビリに薬が影響することってけっこう多いので、リハビリの進みが良くない時、実は薬が関わっているかもしれない、という視点で常に見ているんですね。例えば、飲むとフラフラしやすい薬というのがあるので、それを飲まれている患者さんに関しては、リハビリの様子をリハビリスタッフさんに確認して、影響が出ているようであれば、医師と相談して調整をするとか。
なるほど、リハビリにおいて薬の影響が出る可能性があるから、常に連携が欠かせないわけですね。
ほかの部署とも同様ですよ。薬と食事が合わないこともあるので、管理栄養士さんとも相談しますし。医事課や地域連携室からは、患者さんが直前に入院していた病院で服用されていた薬が、こっちに移ってきた時はどうなりますか、とか、そういう相談ももらいます。
急性期病院で働いていた時と、関わり方の違いはいかがですか。
私個人の印象なんですが、急性期病院では、もし体に複数の問題があったとしても、まずはそのうちの1つの問題解決に集中すると。まず一番やらないといけないことをやって、そのほかの問題については、また次の病院でやってもらう、というのがイメージとしてあるんですね。
決められた入院期間のうちに、一番大きな問題の解決に注力すると。
そうやっていかないと、次々と患者さんの治療をしていけませんからね。そういう前提がありますから、患者さんが慢性期病院に移ってくる時に、全体の状態が良い、ということはあまりないわけです。
一番悪いという状態を脱したところで移って来られて。
なので、こちらに移ってからもいろいろとやることがありますし、とにかく見ないといけない範囲が広いですから、聞かれて答えに困ることも多かったです。
いろいろな疾患を抱えた状態の患者さんが入ってくるということで、薬剤師としての仕事にも違いが出るわけですね。
新人スタッフや、学生さんに説明する時によく言うのが、専門に特化して集中してできるのが急性期、幅広く全般的な知識をつけられるのが慢性期、ということですね。
慢性期というと、急性期と比較して、のんびりしたイメージを持つ方も多いと思うんですが。
今お話ししたように、全般的な知識を求められますし、そのなかで、前いた病院に確認をするとか、なるべく薬を減らしてあげるとか、やることは決して少なくないです。多職種で連携しながら、いろいろな症状を持った患者さんを良くしていけるところが、慢性期病院で働く醍醐味だと思います。

採用活動、業務改善に力を入れながら
スタッフみんなで薬剤部を立て直す
もともとグループの緑成会病院で働かれていた瀧田さんですが、この平成横浜病院にはどんな経緯で移ってきたのですか。
今でこそ10人以上薬剤師がいるんですが、一時期は本当に薬剤師が少なくて。なかなかスタッフが定着しない時期が続いていて、業務もうまく回っていなかったんです。
ではグループ薬剤部の業務支援チームとして仕事をするなかで、平成横浜病院 薬剤部の立て直しに動いたと。
業務を改善したいけど、人が少ないからなかなか手が付けられない、という状態でしたから、自分が入った方がいいなということで、移ることになりました。
当初からいた緑成会病院を離れる寂しさみたいなことは。
それはありましたよ! 家からも近かったですし、楽しさもありましたから。最初は1年くらいで立て直して戻ろうと思っていましたけど。
ある程度軌道に載せたらまた戻ろうと。
そうですそうです。それで今3年目に入りました(笑)。でもこちらの仕事はこちらの仕事で楽しんで取り組んでいます。
実際移られて、どんなことから取り掛かったのですか。
まずは新しいスタッフを入れながら、さらに業務を改善して、そのスタッフたちに定着してもらう、っていうことを1、2年でやろうと。
新しく立ち上げるような感覚でしたか。
そうですね。しかも、私がというよりは、みんなで一緒に立ち上げていこうという形で、変えていきました。
そこで実際にスタッフさんを増やすことができたわけですか。
非常勤も、常勤の方も入ってくれるようになりました。一昨年は新卒のスタッフが3人も入りました。
新卒の方も入られたんですね。学生のみなさんに対しても積極的にリクルート活動を展開したんですか。
はい、学校訪問をして、説明会をやらせてもらって。今まではスタッフが個々で動いていたんですが、ここ何年かで、リクルートチームがしっかり機能するようになったので、グループとしてリクルート活動ができるようになって、大学とのやりとりもかなりスムーズになりました。
学生のみなさんにもアピールできる土壌ができたのですね。

状況が整ったことで
今後は中身を充実させていく
取り組みの結果、現在は平成横浜病院も人員が充足してきたと。
今はだいぶ人が揃ってきたので、次は中身の問題ですね。今度はさらに質を高めていこうと思っています。
外枠ができたところで、今度は中身を充足させていくわけですね。
患者さんへの服薬指導や、ポリファーマシー(※)対策をもっと積極的に、ということや、今は薬剤部から他部署への発信というのがまだ少ないので、今後1年かけて増やしていけたらなと。
※薬物の相互作用を減らすため、6種類以上の服薬を「多剤内服」として減らす取り組み。くわしくは下記ページおよびインタビューををご覧ください。
・平成医療福祉グループ 薬剤部の取り組み
・平成医療福祉グループ 薬剤部 部長/秋田 美樹さん インタビュー記事
どういった発信ですか。
「こんな薬を飲んでいる時はこういうことに注意してください」とか「この症状がなければこの薬は止めても大丈夫ですよ」とか、薬剤師が持っている情報を、他職種が見てもすぐわかるように、カンファレンスなどで伝えていきたいと思っています。
発信については、瀧田さんが薬剤師さんの背中を押しているというような感じですか。
そうです。今もやってくれているので、さらにそのレベルを一定に揃えていけたら良いなと。
瀧田さんは、人に物事を教えることや、人事的な管理の仕事については、どういう意識で携わっていますか。
親が教師だったこともあって、教師になりたいという気持ちも実はあったんですよ。それもあって、教えること自体は嫌いじゃないですね。教えられる側がどう思っているのかはわからないですけど(笑)。ただ、指導や人の管理と言っても、キャリアとしては私より上の方もいますし、こちらが教えてもらうとか、一緒にやっていくということを意識しながらやっています。実際、私が知らないことも多いですから。
立場上は管理者ですけど、管理者然としてドンと立つというよりは。
もうフラットな目線でやっているイメージです。その分、みんなからは言われたい放題ですけど(笑)。
(笑)。もちろんそれは責められているという意味ではなく、和気藹々ということですよね。
そうですそうです。小さい問題は日々あったとしても、それも解決しながら進めていると思います。
新人スタッフとも一緒に進める
ポリファーマシー対策
グループ薬剤部の特長として、ポリファーマシー対策があると思うのですが、新卒の薬剤師さんにはどのように指導を進めているんですか。
最初から「この薬を減らしてください」と、医師に意見を伝えるのはなかなか難しいので「まずは病棟に溶け込んでいって、そこからこういう話をしてみよう」と伝えることが多いですね。だんだんと「こういう症状があるので、この薬は必要ないかもしれません」と、提案できるようになっていきます。
やはり慣れていくまでは提案するのは難しいものですか。
特に1年目では、まだ知識も少ないですので、「こういう時にはこう減らせるよ」と、先輩たちが教えてあげたり、逆に「こんなに薬を飲んでるんですけど」って相談に来てくれたり。経験しながら徐々にやっていってもらってますね。
新卒の方もみなさん興味を持って取り組まれているのですか。
興味はみんなあります。ただ、自信がないんです。
経験を積んだ医師に対して、新人の立場で発信するのは、最初は勇気が要りそうですね。
6年間みっちり薬について学んできているのは薬剤師だけなんで、私たちの方がくわしいはずではあるんです。なので、必要があれば積極的にお伝えしていかないといけないと思っています。もちろん、減らすことだけが目的ではなく、足りないものは足していくこともありますし、あくまで適正化っていうことで進めていってますね。適切な処方につなげることを目的にしています。
ただ減らすだけを目的化するのではなく、あくまで適切な処方を目指していくと。
そこがメインですね。そのなかで、あわよくば処方する薬が6剤以内になればいいよね、ということで取り組んでいます。
瀧田さん自身は、たとえばポリファーマシーのことは、グループに入る前から知っていたのですか。
いえ、急性期病院にいる時は、薬を減らすという概念を持っていませんでしたね。緑成会病院に入ったら、6剤以上は処方しないように、っていうルールがあって、「そうなんだ」って(笑)。だから最初は減らすことに違和感がありました。
ポリファーマシー対策についてもだんだんと浸透してきて。
ここ5年くらいで、薬を減らすことに対して、診療報酬の加算がつくようになったんですね。そこからさらにいろいろな病院で取り組みが広がったようですし、大学の講義でも、ポリファーマシーという言葉が出ることが増えたみたいです。
加算も後押しとなって、より広がってきているのですね。
ただ、実際に取り組むとすると、急性期病院ではなかなか時間がないので慢性期で取り組むことが多いと思うんですが、しっかり取り組めている病院は今でもまだ少ないと思います。
徹底した取り組みはこれからになっていくと。グループ内ではいかがですか。
やはり病院ごとで実施状況に多少の差はありますね。そのなかで、グループ内では博愛記念病院は取り組みが早かったので、かなり浸透しています。もう20年くらいはやっているんじゃないですかね。博愛記念病院の薬剤師さんから教えてもらうことも多いですね。横のつながりで薬剤師どうしで相談することもよくあります。

仕事への姿勢はいつも前向き
「嫌なことも良いこと」に
病院の薬剤部としてはどんな目標がありますか。
薬剤師が、病院のなかで「薬のことは、薬剤師にまず相談」という存在になってほしいです。いろんな職種から話や情報を収集して、それをまた返すという役割ですね。薬局にいるだけではなくて、薬で困ったら薬剤師に聞くことができるっていう体制を、病院のなかで作っていきたいですね。
そのためには、先ほどお話しされたような発信も大切になってくるわけですね。
そうなんです。病棟に行くと、看護師さんが薬のことを調べる時に、処方薬についてのハンドブックを読んでいるのを見かけることがあるんですね。もちろんご自身で調べることも大事なんですけど、そう言う時に気軽に聞いてくれたら嬉しいなって。
せっかくならもっと気軽に薬剤師に聞ける環境にしていきたいと。ほかにやりたいことはありますか。
グループの介護施設との連携ですね。現在、3つのグループ介護施設について、平成横浜病院が往診を担当しているんですけど、そこに薬剤師は特に関わっていなかったので、今後は医師のラウンドに着いていってもいいんじゃないかな、とも思っています。
利用者さんとしても安心ではありますね。
医師と一緒に行って、薬の見直しをするのも良いのかなと思います。施設に関わりたいというスタッフもいるので、ぜひ橋渡し役になってもらって。せっかく同じグループですし、それでこそ本当の意味で、長く見守ることや、地域密着ということにもつながりますから。まずはやってみて、効果が出てきたらいいのかなと。まだ妄想の段階ですけどね(笑)。
平成横浜病院から、そういった施設へ移られる方もいるでしょうし、新しい取り組みとして良いかもしれないですね。グループ薬剤部の仕事については、今後の展望はいかがですか。
コミュニケーションについての研修を進められたらいいなと思っています。薬剤師は、薬剤部内はもちろん、薬剤部の外ととのやりとりも多いですから、そこを円滑に進めていくための取り組みを増やしていけたらと思っています。
業務をよりスムーズに進めるための取り組みですね。
薬剤師が患者さんのために1人だけでできる仕事ってほとんどないんですよ。患者さんに触ることはできませんし、医師からの処方がなければ薬を出すこともできない。作った薬は看護師さんがいなければ飲ませることもできない。何にするにも、薬剤部以外の人が関わりますから、そこをさらにスムーズに進められる薬剤師を、どんどん増やしていきたいです。
仕事を回すためには大事な取り組みですね。瀧田さんが、仕事で大切にしていることはありますか。
よく「自分が作った薬を飲んでいる患者さんを、必ず見に行こう」ということはスタッフに伝えています。いくらカルテをいじっても、どんな人が薬を飲んでいるかはわからないですし。例えば、全然口が開かなくて、処方された錠剤が飲めない、とか。逆に、飲みやすく粉状にしたけど、口内に張り付いちゃって飲みづらい、とか。そういうことは、現場に行かないとわからないことなんです。「とにかくどんどん現場に出て見に行こう」ということは大事にしています。
そういった考えはいつから持つようになりましたか。
実は、最初に勤めた急性期病院で病棟に出させてもらった時、初めは何をやっていいのかわからなかったんですよ。でも、患者さんのところに行って話を聞くと、薬以外のこともお話ししてくれて、薬を作るだけでは知ることができないこともたくさんあったんです。もちろん、そうやってお話できるようになるまでは、失敗を何度も重ねましたけど。
最初の急性期病院での体験が、今につながっているのですね。
私の薬剤師としての土台はそこで作られましたし、今も経験が生きていますね。
ここまでお話を聞いて、瀧田さんはずっと楽しんで仕事に取り組んでいる印象があります。キャリアを通して、辛かった時期はなかったのですか。
この病院に移ってきた当初は、人がいないなかで業務と採用を同時に進めていったので、体力的には大変でしたね。でも、ほかにはそこまで辛いことはなかったかもしれないです。
前向きに取り組めているんですね。
問題が起きた時は、嫌だなと思いますけど、結果として良い方向に転がっていけばそれでいいので「嫌なことも良いこと」だな、と思いながらやっています。
素晴らしい思考ですね!
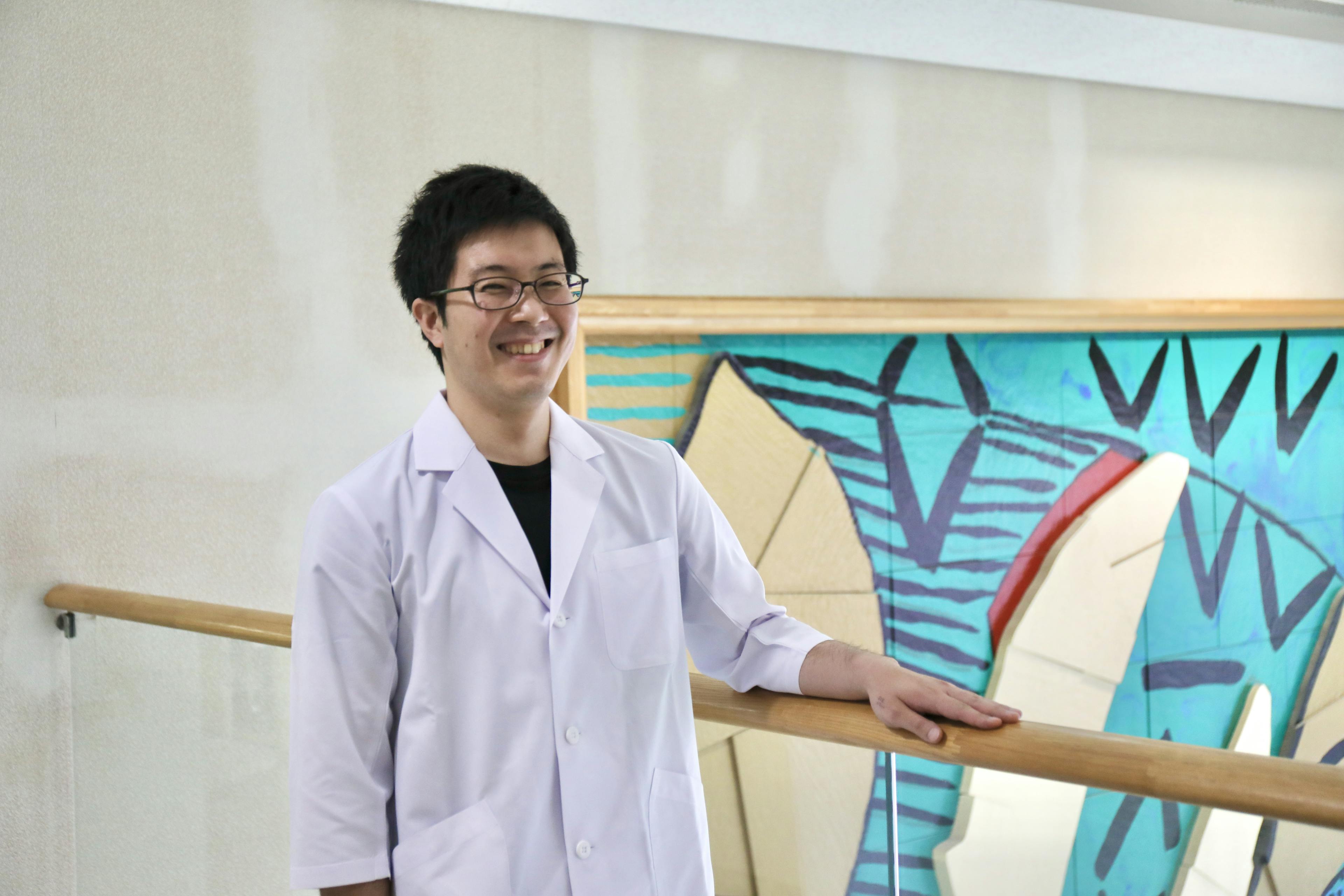
本当はアクティブに出かけたい
そしてあふれ出るタケノコへの愛情
冒頭で野球経験の話を伺いましたが、最近は野球をやることはありますか。
それができてないんですよ〜。緑成会整育園が参加している施設交流の大会が毎年あって、そこにいつも誘ってもらっていたんですけど、それも実施できていないので。
故障した膝はもう問題ないんですか。
毎日野球をやらなければ大丈夫です(笑)。
(笑)。お休みの日はどう過ごしていますか。
本当はドライブとかバーベキューをしたいんですけど、今は全然できてなくて。車もそれ用に大きめの四駆があるんですが、全然乗れていないです。
維持費だけがかかっていくと…(笑)。本当はいろいろやりたいこともあるわけですね。
本当は飲み会も大好きなんですよ。あんまり知らない人たちの飲み会にも参加するんです。
えっ、どういうことですか。
他部署の飲み会がある、と聞いたら「行って良いですか?」って言って、シュッと参加してました。
すごいスキルですね(笑)。
平成横浜病院にきてからは割とすぐコロナ禍になってしまったので、あまり行けていないんですが、緑成会病院は飲み会も多かったんですよ。
今まで出ていただいた緑成会病院関連の方も、みなさん飲み会の話はしていましたね(笑)。
それが楽しかったですね。僕は趣味が全然ないんですけど、あえて言うなら、人と話すことかもしれないですね。
今後やりたいことはありますか。
バーベキューとか、キャンプをやりたいです。あとはスノーボードにも行きたいです。行ったことはないけど、ずっと前から行きたいって行っているので、周りからは趣味は「スノボ(予定)」って書けって言われてます。
外堀を埋められていますね。
ボード以外は準備できてるんです。早く行きたいなあ。
では最後に、好きな食べ物は。
タケノコです。特に青椒肉絲が好きです。SNSのアイコンも青椒肉絲の写真にしてるくらいですから。
ものすごいタケノコ愛ですね(笑)。
ひとプロジェクト今回からしばらくお休み。
次回の公開をお楽しみに!
プロフィール
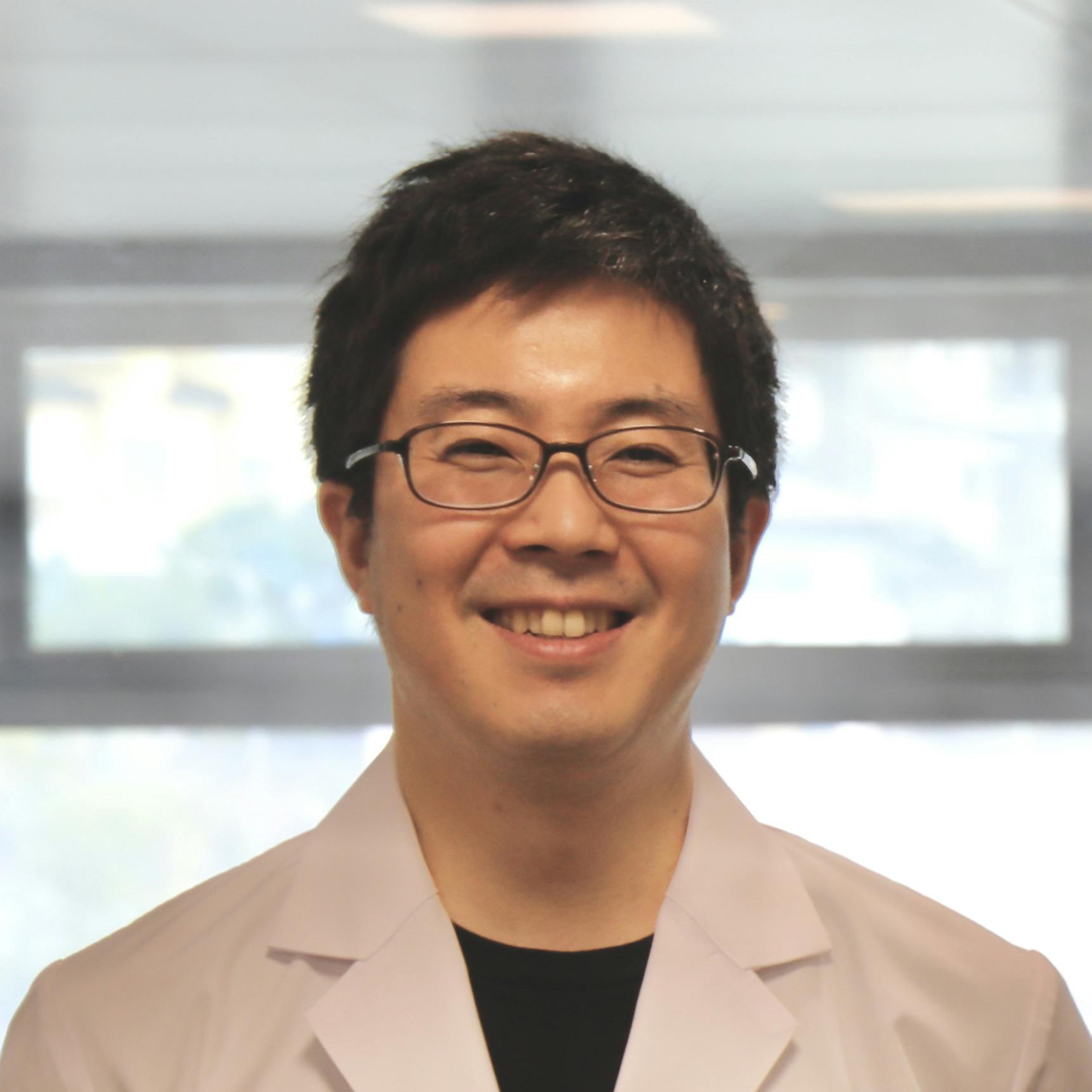
平成横浜病院 薬剤部 係長
瀧田 大輔
たきた だいすけ
【出身】東京都清瀬市
【資格】薬剤師
【趣味】人と話すこと、スノーボード(予定)
【好きな食べ物】タケノコ、鶏肉(パサパサした方が好き)
病院情報

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550番地
https://yokohamahp.jp/
医療法人横浜 平成会
平成横浜病院
内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・外科・泌尿器科・皮膚科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科・脳神経外科
地域に根ざした病院として、一般病棟、地域包括病棟を備え、回復期リハビリテーション病棟を新設しました。さらに救急告示病院として24時間365日、患者さんの受け入れを行っています。2018年6月には、総合健診センターがリニューアル。地域の健康を支えていけるよう努めています。