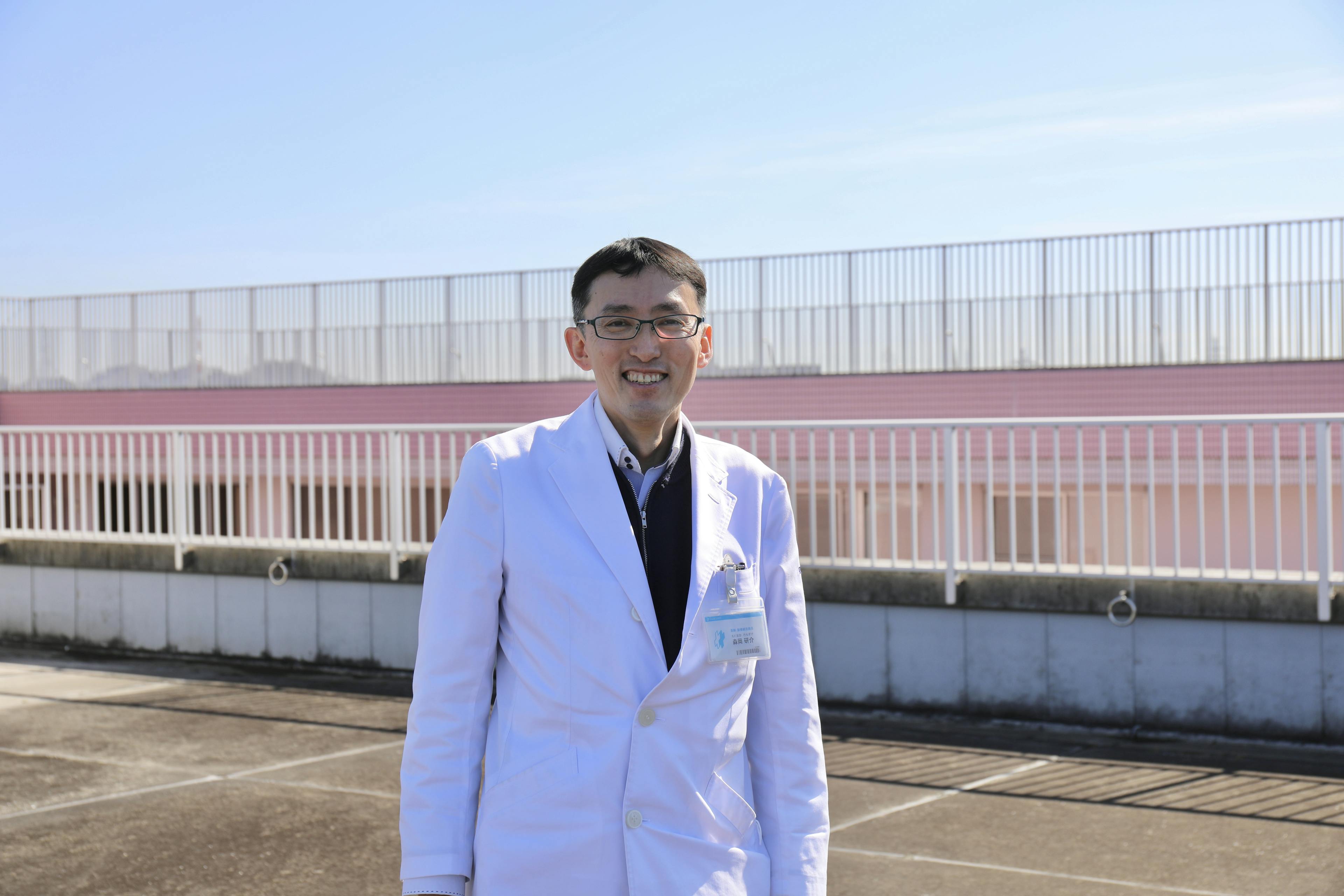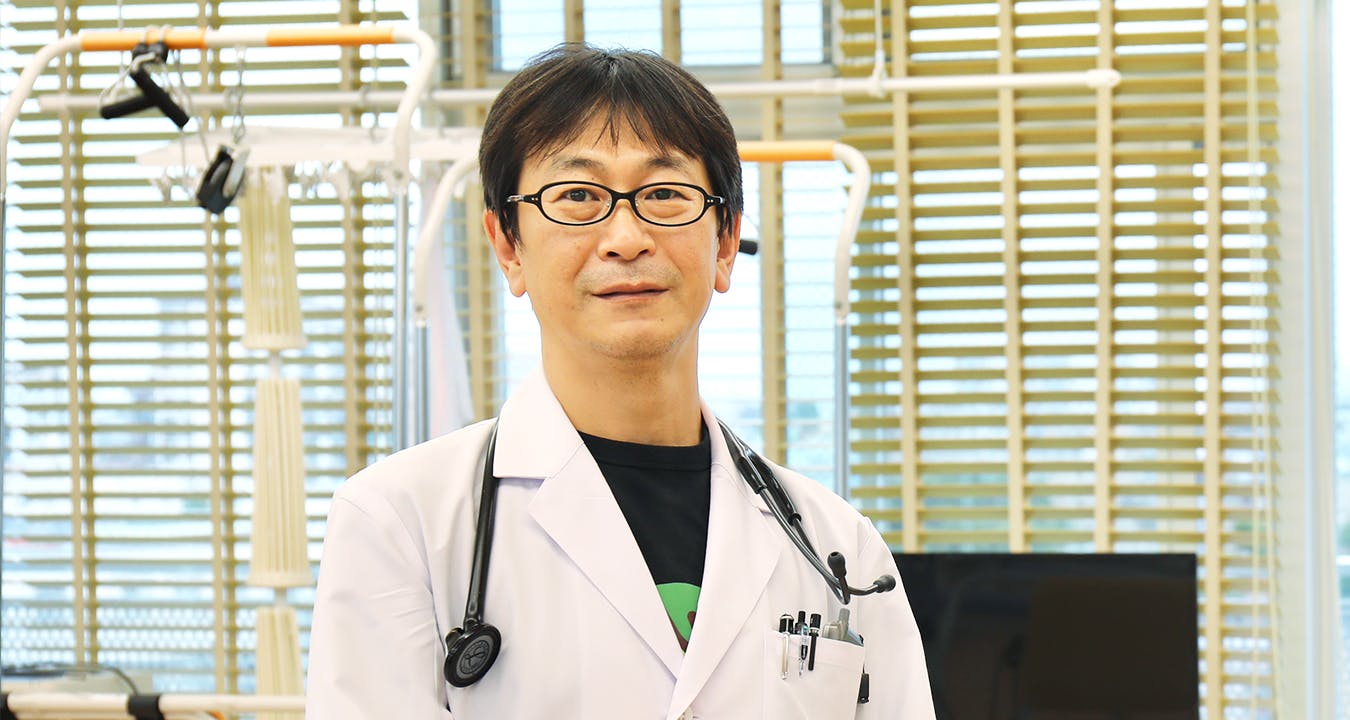「人のために尽くしたい」 その一心で医師となった、新院長に迫ります。/堺平成病院 院長/正木 浩喜先生
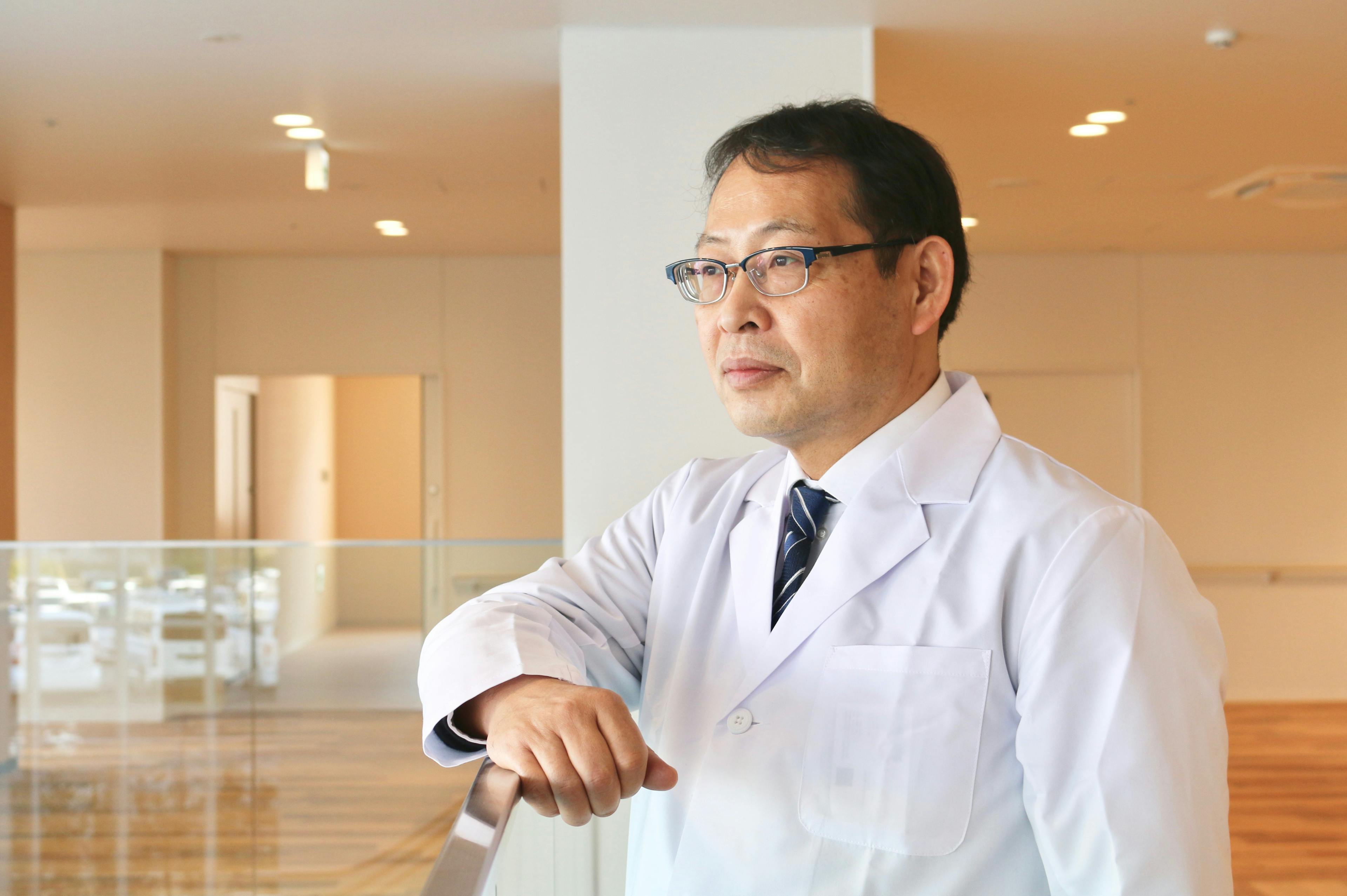
「人のために尽くしたい」 その一心で医師となった、新院長に迫り
堺温心会病院で院長を務め、堺平成病院でも院長となる正木浩喜先生。「インタビューは苦手で…」と話される正木院長ですが、医療に携わる動機となったある想いや、堺平成病院開院に向けた意気込みなどを、まっすぐに語ってくださいました。「ちょっとビクビクしていた」と言う研修医時代のお話も。
ぜひご覧ください!
自転車、水泳、登山
アクティブに過ごした学生時代
ご出身はどちらですか。
大阪府の泉大津市ですね。
泉大津市はどんなところですか。
「だんじり祭(※)」で有名な岸和田市の少し北側に位置するんですが、繊維産業が盛んで、毛布の製造シェアが全国で約90%、それとニットの製造でも有名ですね。ただ、今は地場産業よりもベッドタウンの性格が色濃いと思います。ちなみに泉大津にもだんじり祭があるんです。
※毎年9月に岸和田市北西部で行われる。重さ4tを超えるだんじり(山車)を引いて街中を駆け回る勇壮な祭り。
そうなんですね。やっぱり当時も今もお祭りは楽しみですか。
今もちょっと見に行くことはありますよ。泉大津市のだんじり祭りは岸和田と違って、だんじりをぶつけ合うんですね。だからさらに荒っぽいです。
迫力が凄そうです! 先生は参加されたことは。
いやあ、もう全然(笑)。せいぜい小中学生の頃くらいですかね。
幼い時はどんなお子さんでしたか。
近所のコミュニティっていうんですかね、隣近所に年長の人や小さい子もいて、学校終われば、一緒にみんなで野球したり、川でザリガニを釣ったりとか。そういう昭和の遊びをしていましたね(笑)。
活発にみんなで遊ぶ方だったんですね。
どちらかというと外向きだったと思います。
では学生時代にスポーツとか部活動は。
中学時代は水泳部にいて、主に自由形を泳いでいました。
高校では続けられなかったんですか。
高校では水泳部がなかったので、部活はしてなかったんです。ただ、趣味であちらこちらとサイクリングに行ってまして。今も流行っているような競技用の自転車で、友人と遠出しましたね。
アクティブですね! どんなところに行かれたんですか。
高校時代は大阪近辺ですけど、大学生の頃は、四国一周をしましたね。八十八ヶ所めぐりじゃないですけど、海岸線沿いをグルッと周りましたが非常に広くて。昔はユースホステルが多くありましたから、そこを点々と泊まりながら一周しました。
大学時代ならではのエピソードですね。
そうですね(笑)。10日から2週間くらいかけて行きましたけど、一周してスタート地点の徳島県庁に戻ってきた時は、やはり達成感がありましたね。
体を動かすことが好きだったんですね。
自転車以外にも、大学時代はワンダーフォーゲル部に入って山歩きもしていました。関西近郊の山だけでなく、夏は北アルプスに登ったりね。
本格的にやられていたんですね。最近は山登りや自転車はいかがですか。
この仕事を始めてからはなかなか趣味の時間がなかなか取れていなくて。家族もできましたし、残念ながら最近はやっていないんですよ。

「人のために尽くしたい」
父の影響を感じながら医療の道へ
医師の道を志したきっかけを教えてください。
父親が開業医をしていまして、産婦人科医だったんですけど。母が一緒に手伝っていて。
じゃあもう幼い時から医療が身近にあったと。
そうです。自宅の隣に診療所があったので、そこで診察や分娩、入院もみなさんされていましたからね。
やはりそれがご自身にとって影響として大きかったのでしょうか。
中学生までは医師を志すっていうことは考えてなかったんですよ。ただ、高校生になると、大学を選ぶことがこの先の進路に関わってくるので、職業のことを考え始めて。高校2年生の夏休みの間にいろんな書物を読んだり、考えたりした結果、医療系の大学を受験することにしたんですね。
お父様からは特に医師を勧められたというわけではなかったんですか。
それは特になくて、進路については本人の意思に任せるという形でした。
どういう点で医師という仕事に憧れましたか。
いろいろな職業がありますけど、医療に関わる仕事っていうのは、特に人に対して尽くす仕事ですよね。最近では医療もサービス業的な見方もありますけど、やはりその側面だけではなく、どれだけ相手を想って治療に生かすかっていうことがあると思います。その中でも医師となると、自分の判断や選択で進めていける仕事なわけで、「自分の責任で人に尽くす」というところが「素晴らしい仕事だな」と思ったんです。
それは、高校2年生の時に「医師を目指そう」と思った時にはもう考えられていたんですか。
実際に近畿大学に進学して医大生になり、それから医師国家試験に通って、という中で、さらに実感を持って思うようになりましたね。
どの科もそれぞれ大変さが違うと思いますが、産婦人科医のお父様を身近で見ていて、「医師になるのは厳しそうだな」と諦めそうになったことはありませんでしたか。
もちろん大変な仕事だと思っていました。夜中でも電話があれば医院を開けて患者さんを診ますし、24時間、日曜・祝日も関係ないわけです。逆にそれを見ていたので「医師になったら、違う働き方をしよう」と、医師は目指すけど科目は変えようと思い、内科を選びました。同じように考えた先生もおられるかと思いますね(笑)。
医療という道は共通していたけれど、ということですね。
選択の方向は違いましたけれど、同じ医療をしているからこそ、父親のことは尊敬しますね。大変さがとてもわかりますので。
実際、医師になるということを伝えて、産婦人科を勧められることはなかったのでしょうか。
内科や産婦人科以外の科を勧められましたね(笑)。
(笑)。それはどういう意図で。
なるべく生死に関わる確率が少ない診療科を勧めたい、という親心でしょうね。
ご自身が一番よくわかっていたからこそですね。
気持ちはありがたかったですけど、私なりにどういう道に進むかと考えたうえで、内分泌代謝内科に入局をしましたね。
紙とペンがあれば仕事はできる
内科医としてのモットーとは
先生が専門とする「内分泌代謝内科」とは、内科の中でもどういった疾患を診る科目なのでしょうか。
「内分泌内科」と「代謝内科」が合わさった科目なのですが、「代謝内科」の方は体内の糖とかタンパク質とか脂肪の代謝に関わる臓器の疾患です。糖尿病が一番有名ですね。
なるほど、では「内分泌内科」の方は。
主にホルモンですね。甲状腺とか、ホルモン分泌に関わるもので、バセドウ病などが有名です。
先生にとってこの内科のやりがいはどういったところにありますか。
一番は、患者さんを一対一で目の前にして、全身像を見て訴えを聞いて、そこから病気を絞り込んで診断していくところです。
推理すると言いますか。
患者さんの訴えに対して、どういう病気でその症状が出ているのか、っていうのを医学的知識を持って突き詰めて治療につなげるということですよね。
そこにやりがいがあるわけですね。
だから本当は大きな器具もいらなくて、僻地の診療所だって診療スタイルは変わりません。基本的には机とペンと椅子と、聴診器があれば、ある程度のところまで類推して絞り込んでいきながらということになりますね。
もちろん内科に限らないと思いますが、知識と経験が問われますね。
最初の5年、10年は、なかなか経験値が上がらないなかで苦労します。いろいろな患者さんの診察をしながら知識を増やしていくというか。もちろん国家試験を受けているわけですから、いろんな知識が入ってからのスタートではありますが、結局はその都度考えながら判断しなければならないので、内科の一般的な知識をちゃんと網羅しておくことが重要ですね。
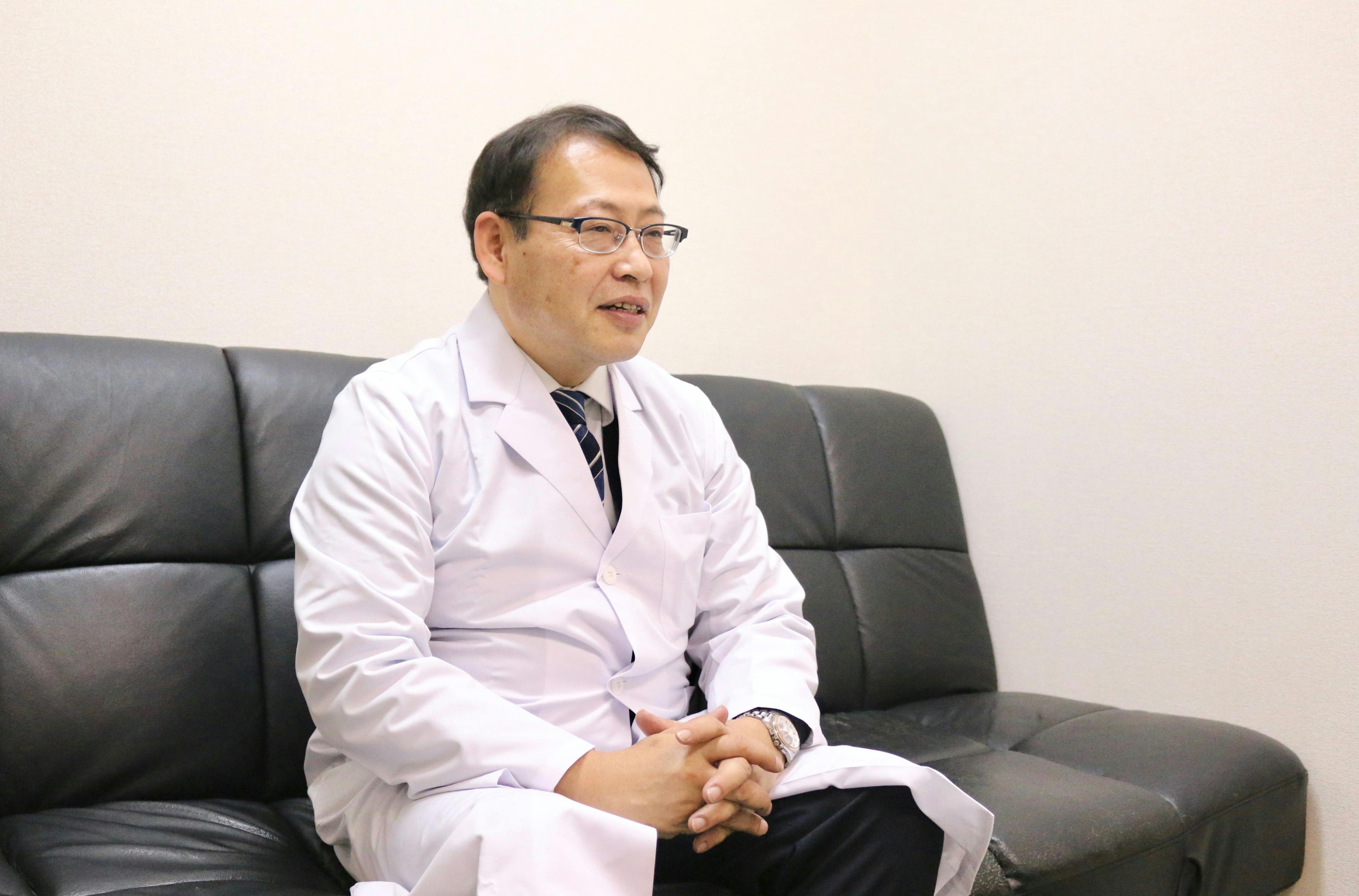
大変だった研修医時代
厳しい指導医の先生…
それこそ大変なこともあったと思うんですけど、研修医時代などはいかがでしたか。
まず検査値が全部英語で苦労しました。GOT、GPTとかね。それと特定の患者さんを持つ担当医になっても、その患者さんの検査値と検査項目が把握できない。あとその頃は指導医が厳しく指導し、まさにスパルタでしたね。
ああ、やっぱり今よりも…。
今がどうなのかはわからないですけど、当時は師匠と弟子みたいな関係がまだあって、指導医の指示は絶対でしたので、そういう意味では非常にビクビクしてました(笑)。
かなり鍛えられてきたんですね。
ただ、指導医の先生たちも、一人の医者をしっかりと育てるという責任を持っておられ、その気持ちが強い形で現れて、指導してもらっていた時代だったと思いますね。
くじけそうになったことはなかったですか。
大学の診療だけでなく、当直業務がついてくるんで、さすがに3日続けて病院で当直した時は倒れそうになりました。昼間は大学、夜は当直っていうのを繰り返すわけですから、4日目は持たなかったです(笑)。
寝る間がないですもんね。
それとやはり、病院で宿直してるっていうのは常に緊張していますので、睡眠ではなく仮眠ですよね。実際のところは神経が張り詰めていて、次にどんな患者さんが来るかわかりませんし。特に自分の知識や経験が十分じゃない時なので、非常に緊張します。
当直中だと、周りに助けてくれる人も日中より少ないわけですよね。
そうなんです。最初に言ったように、自分の責任でもって人に尽くす仕事だとわかっていたわけですけど、実際に自分の責任で進めるとなると…、当時はやっぱり大変でしたね。
こちらの想いだけで
医療を提供してはいけない
先生が診察の時に気をつけていることを教えてください。
どんなに小さいことでも、患者さんの変化に気づくっていうことですね。それと、相手の訴えをよく聞くことです。患者さんは医師に伝えたいことが必ずありますので、まずはそれを聞くという姿勢が大事。それを最初にしないと診療は始まらないですし、患者さんとの関係がうまくいきません。
常にそういう姿勢を大事にされていると。
患者さんはたくさんいらっしゃいますので、そこでブレないことを続けていかないと、患者さんごとに不公平が生まれてしまう。診療自体も、かかる時間の違いはあるかもしれないけど、やはり平等に診る姿勢っていうのは大事だと思います。
それはやはり先生が経験を積まれて、そのようなブレない芯が出来上がったんでしょうか。
やはり自分の診療技術が不十分な時は、自分のことでいっぱいいっぱいでしたね。経験を積んで視野が広がることで、患者さんの目線に立つことができるようになるんです。
医師と患者という立場はもちろん違うんですけど、目線は合わせて。
医師の側からだけで物を見ないことが大切です。こちらの想いだけで医療を提供することが、必ずしも患者さんのためになる、満足につながる、というわけではないんです。説明することだってそうですよね。本当は時間をかけてゆっくりとお話をしたいんですけど、ともすると一方的なものになりがちです。患者さんにとってわかりやすい言葉で伝えられているかは、患者さんの目線で見てみないとわかりません。
常にその視点を大事にされながら診療をされてきたと
人生の中で病気っていうのは非常に大きな障害ですから、そういう状況で、支える場所が病院です。私たち医師だけでなく、専門職の人たちがチーム医療で合わさって、ケアしていく。その連携で、入院している患者さんやご家族が安心できたらいいですよね。

赴任当時の堺温心会病院
堺温心会病院に入られたのはどういった経緯でしたか。
研修が終わってから、この堺温心会病院に内科医として赴任することになり、1996〜2001年まで在籍していました。
その当時はまだ平成医療福祉グループの所属ではなかったと思うのですが、どんな状況でしたか。
建物の大きさは一緒なんですけど、そのころは245床ありました。ベッド数も科目も多く、小児科、産婦人科、眼科、外科、泌尿器科、皮膚科、透析などを通して、急性期病院として地域の医療に携わっていた病院でした。
今とは病院の性格が違ったんですね。
堺温心会病院の前身が松井病院っていうんですけど、そこで出産された方が、今もかかりつけとして来院してます。そういう意味では、ずっと地域に根ざしている病院と言えますね。
院長である前に
一人の医者として
その後、堺温心会病院の院長になられたわけですね。
2010年にこの病院に戻り、平成医療福祉グループに加入し、2014年から院長になりました。
院長になって、仕事は具体的にどのように変わりましたか。
私自身はその前の副院長時代も診療部長時代も、一医師として実診療を軸として仕事していた時と変わっていないんです。もちろん、病院を責任持って管理していくっていうことと、病院の経営を安定させ、診療実績を維持していくのは院長として重要な仕事として取り組んでいます。
まずしっかりと医師としての軸があってという意識があるのですね。
経営的なことは当然ですが、医師である限りは人に尽くすっていうことがあるので、やはりそれを一番に考えています。
院長になられてから病院として変わった点はありますか。
救急医療に関しても、一般診療に関しても、患者さんの受け入れについて、以前から努力はしていましたが、甘い部分もありました。平成医療福祉グループへの加入後は「絶対に見捨てない」というグループの理念の元、診療をさらに広く深く担っていくということで、患者さんを受け入れることが多くなりました。地域医療は救急体制も大変な面はありますが、少しでも地域の部分をカバーするための努力を続けていますし、実際に診療する機会も増えたと言えますね。

いよいよ開院!
堺平成病院は地域における、こんな病院
4月にはいよいよ堺平成病院が開院となります。同じく堺市にある浜寺中央病院と合併ということですが、あらためてその経緯を教えてください。
堺温心会病院と、同じくグループ病院として堺市にある浜寺中央病院は、どちらも堺市で長らく地域のみなさんのために医療を提供してまいりました。しかし、両院とも建物が老朽化し、建て直しの必要性が発生したことを機に、合併して場所も移転し、新たな病院としてスタートを切ることとなったわけです。
この2つの病院が一緒になる強みはどういうものだとお考えですか。
回復期リハビリテーション病棟や療養病床を持つ浜寺中央病院と、急性期一般病棟、障害者病棟や医療療養病棟を持つ堺温心会病院がひとつになる。そこでのコンセプトというのは、地域医療、特に急性期病院での治療以降の医療、いわゆるPAC(※)をさらに進めていくことにあります。医療費削減の流れで急性期病院ではどんどん在院日数が短くなっていきますので、そのあとの機能回復のための受け皿として、機能を充実させるのがひとつの目的です。
※Post Acute Careの略。急性期病院での治療を終えたのち、まだ自宅や介護施設に戻るまでには不安がある患者さんの継続的治療やリハビリテーションを中心に行うこと。
ほかにはどのようなことがありますか。
地域医療を担う病院として、地域の方の救急医療や外来受診、また入院に関わるさまざまな問題を解決するために、対応できる病床を組み合わせて診療していくことになります。これがSAC(※)という機能ですね。この地域は高齢者が多く、一人では動けず救急車などで搬送されないと病院に来られないという方も増えています。しかし救急患者として救急救命センターのような高度急性期病院に行くことになると患者さん自身も大変ですから、自宅から近い病院で診てもらえるっていうのは、安心につながるわけです。
※Sub Acute Careの略。自宅や介護施設で療養している患者さんが急激に悪化した際に受け入れること。
地域医療のハブとなるような位置付けですよね。
そうです、地域の中に高度急性期病院やクリニックがあり、介護施設や居宅介護があり、その中の基幹病院として当院が機能するわけです。例えばクリニックなら、当院に入院依頼をしてもらったり、逆に退院後の外来として紹介させてもらったり。
なるほど、連携をするということですね。
はい、病院で長期入院になるということではなくて、治療が終了すれば自宅や介護施設に移行していく、あるいは在宅診療に移行していくわけです。あくまでも、当院だけで完結するわけではない、ということ。それが「地域包括ケア」ですね。
現状、堺市の医療というのはどういう状況なんでしょうか。大阪府内では人口が2番目に多い大都市ですよね。
病院ごとに徐々に住み分けて、機能分担をしていかなければいけないのですが、今はまだその途上です。この堺平成病院は、回復期リハビリテーション病床が120床と、とても多いのですが、堺市全体では、まだまだ病床が足りていない。ということは、高度急性期病院で手術・治療された方が機能回復する場所が不足しているのが現状です。
その中で大きな役割の一端を担う病院ということですね。
そうですね。近隣にはそういう高度急性期の病院がいくつもありますので、そういった病院からの患者さんの機能回復ができるような、後方支援をさせていただければと思っています。

より大きな規模で
さらに地域のために尽くしていく
あらためて、開院への意気込みをお聞かせください。
現状、堺温心会病院で地域医療に根ざした取り組みを行っていますが、堺平成病院で行うことも延長線上にあるということは間違いありません。そこからブレずに、さらに地域のみなさんに関わって医療を提供していきたいです。
正木先生がずっと持っている「人に尽くす」という想いが、さらに広く地域の方に向けられると言いますか。
堺平成病院ではより病床数も増えますから、その範囲が、今まで私たちが考えていた以上に、もっと広いものしていかなければいけないと思っています。
現在、開院に向けてはどのような取り組みをされていますか。
病院全体で取り組んでいることとしては、病院の運用システムの最終的な詰めと、移転の準備ですね。ほかには、広報活動として地域住民の方や他病院に関しての説明会を随時行っていく予定です。
開院ということで、新たなスタッフを募集されていますが、どんな想いを持った方からの応募をお待ちしていますか。
応募いただくのは、現在医療に携わっている方や医療を学んできた方だと思うんですが、自分だけでなくて、いろんな職種の方と協力して、チーム医療を実施していくという姿勢が大事です。
多職種連携を実践できる方ということですね。
今の医療の中では一般的なことですけど、自分と同じ職種の人だけでなく、院内で横のつながりで連携しながら患者さんを治していく、広い視野を持って働けることが理想ですね。
堺平成病院として将来的な目標や目指すところはありますか。
一番は、地域の中で「受診したい」「入院したい」と選ばれる病院になっていきたいです。地域の患者さんに信頼していただけるよう努力していきます。

ご褒美として
いつか行きたい場所がある
お忙しいなかだとは思いますが、お休みはどのように過ごしていますか。
買い物に出かけたりとか、近場の温泉に行ったりもします。
温泉、いいですね〜。この辺だとどこの温泉に行かれますか。
有馬温泉とか、いろいろ行きますよ。温泉に入ると息抜きになります。
「こういうことがしたい」というような、個人的な目標はありますか。
長い休みが取れたら、海外旅行に行きたいですね。イタリア、フランス辺りがいいです。
―素敵ですね。今は開院間近で大変かとは思いますが、落ち着いた頃に行けるといいですね!
そうですね、ご褒美としていずれ行けたらいいなと期待しています(笑)。
プロフィール
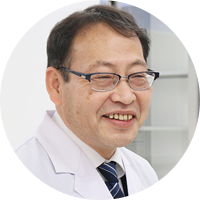
堺平成病院 院長
正木 浩喜
まさき ひろき
【出身】大阪府泉大津市
【専門】内分泌代謝内科
【好きな食べ物】ブリ、タイ、マグロ(大好き)
病院情報

大阪府堺市中区深井沢町6番地13
https://sakaiheisei.jp
医療法人 恵泉会
堺平成病院
内科・循環器内科・消化器内科・リウマチ科・放射線科・眼科・整形外科・泌尿器科・歯科・リハビリテーション科・脳神経外科・皮膚科・外科・糖尿病内科(代謝内科)・人工透析内科・心療内科・麻酔科
2019年、長らく堺市でご愛顧いただいた堺温心会病院と浜寺中央病院が合併して誕生した病院です。救急医療から回復期医療、慢性期医療、そして在宅サービスまでの幅広い機能を持つ「地域密着多機能病院」として、地域にあるさまざまな事業者と遠慮なく無駄なく連携できる関係を作れるよう、地域医療のハブになり、地域全体で患者さんをサポートできるよう、努力を重ねてまいります。